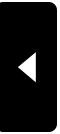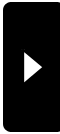PR
2013年11月19日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 200 『(根)抵当権債務の承継』
本日は、(根)抵当権の承継について、お話させていただきます。
債務者の抵当権付不動産を相続により承継する場合、まず、その目的不動産について相続を登記原因とする所有権移転登記を行い、次に抵当権債務者の変更登記を行うこととなります。
債務者の根抵当権付不動産を相続により承継する場合も、同様となります。
さらに、根抵当の場合、相続開始時にその根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当関係を継続させる場合には、根抵当債権者と根抵当設定者の間で指定債務者(相続人)の合意をして、根抵当権変更登記を行う必要があります。
以上、(根)抵当権の承継について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の必要書類や添付資料について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
債務者の抵当権付不動産を相続により承継する場合、まず、その目的不動産について相続を登記原因とする所有権移転登記を行い、次に抵当権債務者の変更登記を行うこととなります。
債務者の根抵当権付不動産を相続により承継する場合も、同様となります。
さらに、根抵当の場合、相続開始時にその根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当関係を継続させる場合には、根抵当債権者と根抵当設定者の間で指定債務者(相続人)の合意をして、根抵当権変更登記を行う必要があります。
以上、(根)抵当権の承継について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の必要書類や添付資料について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年11月18日
相続の事が少しずつ分かるいいお話199 『保証債務の承継のポイント』
本日は、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきます。
◇保証債務の相続性の有無
保証債務のうち、普通の保証債務、連帯債務、連帯保証、賃貸借における賃料債務の保証および、損害発生後で賠償額決定の身元保証などについては相続性が認められています。
一方、連帯保証のうち、継続的取引の将来債務で責任の限度・期間の定めのないもの、身元保証・信用保証については相続性が認められていません。
なお、平成17年4月1日から施行された改正民法では、保証金額や保証期限の定めがない包括根保証は禁止されました。また、根保証規約は口頭では無効となり、書面で行わなければ効力を生じないことになりました。
貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、主たる債務者または保証人が死亡したときに確定するとされました。
◇被相続人が会社代表者であった場合
被相続人が非公開会社の代表取締役をしていた場合には、会社の債務については、殆どのケースで金融機関から保証人となることを求められています。相続により代表取締役が変更になった場合、保証人の変更も同時に求められることが多くあります。
◇保証債務を承継しない場合
なお、保証債務を承継しない方法としては、限定承認、または相続の放棄をする方法があります。
◇相続税の課税価格計算上の取扱い
相続税法上、保証債務は、通常の確定債務と認められず、相続税の対象となる財産から控除することができません。これは、相続税法では『控除対象となる債務は確実と認められるものに限る』とされているためです。
したがって、保証債務が保証債務者である被相続人の債務として控除できるのは、相続開始時点で、主たる債務者が弁済不能状態であり、被相続人である保証債務者がその保証債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがない場合に限ります。
その場合、その保証債務者である被相続人の債務として相続税の対象となる財産から控除できる金額は、主たる債務者の弁済不能部分の金額に限られます。
以上、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきました。
次回は、抵当権債務の継承について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
◇保証債務の相続性の有無
保証債務のうち、普通の保証債務、連帯債務、連帯保証、賃貸借における賃料債務の保証および、損害発生後で賠償額決定の身元保証などについては相続性が認められています。
一方、連帯保証のうち、継続的取引の将来債務で責任の限度・期間の定めのないもの、身元保証・信用保証については相続性が認められていません。
なお、平成17年4月1日から施行された改正民法では、保証金額や保証期限の定めがない包括根保証は禁止されました。また、根保証規約は口頭では無効となり、書面で行わなければ効力を生じないことになりました。
貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、主たる債務者または保証人が死亡したときに確定するとされました。
◇被相続人が会社代表者であった場合
被相続人が非公開会社の代表取締役をしていた場合には、会社の債務については、殆どのケースで金融機関から保証人となることを求められています。相続により代表取締役が変更になった場合、保証人の変更も同時に求められることが多くあります。
◇保証債務を承継しない場合
なお、保証債務を承継しない方法としては、限定承認、または相続の放棄をする方法があります。
◇相続税の課税価格計算上の取扱い
相続税法上、保証債務は、通常の確定債務と認められず、相続税の対象となる財産から控除することができません。これは、相続税法では『控除対象となる債務は確実と認められるものに限る』とされているためです。
したがって、保証債務が保証債務者である被相続人の債務として控除できるのは、相続開始時点で、主たる債務者が弁済不能状態であり、被相続人である保証債務者がその保証債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがない場合に限ります。
その場合、その保証債務者である被相続人の債務として相続税の対象となる財産から控除できる金額は、主たる債務者の弁済不能部分の金額に限られます。
以上、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきました。
次回は、抵当権債務の継承について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年11月16日
相続の事が少しずつ分かるいいお話198『保証債務の承継』
本日は、保証債務の承継について、お話させていただきます。
保証債務には相続性が認められているものと、そうでないものがあります。
相続性が認められているものは以下の手続をとることとなります。
【提出書類関連】
提出書類:保証書
提出人 :保証債務を承継した相続人
提出先 :その債務の債権者(銀行など)
提出時期:その遺産の分割協議成立以後
提出費用:特になし
【添付資料チェックリスト】
◇保証人変更契約書など
◇被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍記載事項証明書または全戸籍(除籍記載事項証明書または除籍・改製原戸籍謄本を含む。)
◇被相続人の住民票の除籍または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の住民票抄本
◇代理権限証書
【概要】
◇保証債務とは
保証債務とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、保証人が主たる債務者に代わってその履行をする旨の債務を負担するときの相続人の債務です。
主たる債務を担保することによってその保証人の債務が生じます。
本日は、保証債務の承継について、お話させていたざきました。
次回は、保証債務承継のポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
保証債務には相続性が認められているものと、そうでないものがあります。
相続性が認められているものは以下の手続をとることとなります。
【提出書類関連】
提出書類:保証書
提出人 :保証債務を承継した相続人
提出先 :その債務の債権者(銀行など)
提出時期:その遺産の分割協議成立以後
提出費用:特になし
【添付資料チェックリスト】
◇保証人変更契約書など
◇被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍記載事項証明書または全戸籍(除籍記載事項証明書または除籍・改製原戸籍謄本を含む。)
◇被相続人の住民票の除籍または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の住民票抄本
◇代理権限証書
【概要】
◇保証債務とは
保証債務とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、保証人が主たる債務者に代わってその履行をする旨の債務を負担するときの相続人の債務です。
主たる債務を担保することによってその保証人の債務が生じます。
本日は、保証債務の承継について、お話させていたざきました。
次回は、保証債務承継のポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年11月14日
相続の事が少しずつ分かるいいお話188 『不動産の遺産分割協議がある場合の所有権移転登記
本日は、遺産分割協議がある場合の不動産の所有権移転登記について、お話させていただきます。
不動産を法定相続分ではなく、任意に分割して相続登記するには、それを証する遺産分割協議書等の添付が必要となります。
【申請書類関係】
申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
申請時期:特になし
申請費用:所有権移転登録免許税 相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4 司法書士報酬
【添付資料一覧】
ケース① 遺産分割協議がある場合
◇登記原因証明情報
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本・・・市役所等
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票・・・市役所等
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本・・・市役所等
◇不動産を取得する相続人の住民票(住民証明書)・・・市役所等
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人全員の印鑑証明書・・・市役所等
◇固定資産評価額証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース② 遺産分割の審判または調停があった場合
◇登記原因証明情報
・調停調書正本または審判書正本・・・家庭裁判所
◇不動産を取得する相続人の住民票(住所証明書)・・・市役所等
◇固定資産評価証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース③ 特別受益者を除いて遺産分割協議をした場合
◇登記原因証明情報
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本・・・市役所等
・被相続人の住民票除票・・・市役所等
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本・・・市役所等
◇不動産を取得する相続人の住民票(住所証明書)・・・市役所等
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人全員の印鑑証明書・・・市役所等
◇固定資産評価額証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
【概要】
法定相続分(民900)ではなく、遺産を任意に分割して相続登記するには、遺産分割協議(書)が必要です。
遺産分割協議書には相続人全員の署名押印(実印)が必要です。
ケース① 遺産分割協議ある場合
遺産分割虚偽がある場合には、住民票は不動産を相続した相続人だけが必要となります。
ケース② 遺産分割の審判または調停があった場合
遺産分割が家庭裁判所の調停または審判による場合には、いずれも確定証明書付きの調停調書の正本または審判書の正本を添付します。
なお、この場合には、戸籍記載事項証明書または戸籍謄本および印鑑証明書の添付は不要です。
ケース③ 特別受益者を除いて遺産分割協議をした場合
特別協議者を除いて行われた遺産分割協議は有効とされます。
この場合、その特別受益者の印鑑証明書(期限の定めはありません。)と共に実印を押印した特別受益証明書を添付して相続登記を行います。
以上、不動産の遺産分割協議がある場合の所有権移転登記』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
不動産を法定相続分ではなく、任意に分割して相続登記するには、それを証する遺産分割協議書等の添付が必要となります。
【申請書類関係】
申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
申請時期:特になし
申請費用:所有権移転登録免許税 相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4 司法書士報酬
【添付資料一覧】
ケース① 遺産分割協議がある場合
◇登記原因証明情報
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本・・・市役所等
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票・・・市役所等
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本・・・市役所等
◇不動産を取得する相続人の住民票(住民証明書)・・・市役所等
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人全員の印鑑証明書・・・市役所等
◇固定資産評価額証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース② 遺産分割の審判または調停があった場合
◇登記原因証明情報
・調停調書正本または審判書正本・・・家庭裁判所
◇不動産を取得する相続人の住民票(住所証明書)・・・市役所等
◇固定資産評価証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース③ 特別受益者を除いて遺産分割協議をした場合
◇登記原因証明情報
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本・・・市役所等
・被相続人の住民票除票・・・市役所等
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本・・・市役所等
◇不動産を取得する相続人の住民票(住所証明書)・・・市役所等
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人全員の印鑑証明書・・・市役所等
◇固定資産評価額証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
【概要】
法定相続分(民900)ではなく、遺産を任意に分割して相続登記するには、遺産分割協議(書)が必要です。
遺産分割協議書には相続人全員の署名押印(実印)が必要です。
ケース① 遺産分割協議ある場合
遺産分割虚偽がある場合には、住民票は不動産を相続した相続人だけが必要となります。
ケース② 遺産分割の審判または調停があった場合
遺産分割が家庭裁判所の調停または審判による場合には、いずれも確定証明書付きの調停調書の正本または審判書の正本を添付します。
なお、この場合には、戸籍記載事項証明書または戸籍謄本および印鑑証明書の添付は不要です。
ケース③ 特別受益者を除いて遺産分割協議をした場合
特別協議者を除いて行われた遺産分割協議は有効とされます。
この場合、その特別受益者の印鑑証明書(期限の定めはありません。)と共に実印を押印した特別受益証明書を添付して相続登記を行います。
以上、不動産の遺産分割協議がある場合の所有権移転登記』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年11月13日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 187 『不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記』
本日は、不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記について、お話させていただきます。
遺言が有る場合においては、その遺言の文言と内容により、相続を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合と、遺贈を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合等があります。
今回は、相続を登記原因とした場合の所有権移転登記について、お話させていただきます。
【申請書類等】
◇申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
◇申請人 :相続または全相続人が包括遺贈により不動産を取得した場合の(全)相続人、またはその代理人
◇申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
◇申請時期:相続開始後、特になし
◇申請費用:所有権移転登録免許税(不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4)+司法書士報酬
【添付資料一覧】
◇登記事項証明書
・遺言書
・遺言者の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本
・遺言者の住民票除票
・相続人または相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人の住民票(住所証明書)
◇相続人全員の印鑑証明書
◇固定資産評価証明書
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
【概要】
■遺言がある場合において、相続が登記原因となるとき
遺言による所有権移転登記をする場合、遺言の文書と内容によって、登記原因が相続となるか遺贈となるか、さらに、登記申請の形態も相違してきます。
◇文言・・相続させるの場合
・対象者 :相続人のみ
・登記原因:相続
・登記申請形態:相続人単独申請
◇文言・・遺贈するの場合
①対象者 :法定相続人
ⅰ.包括遺贈の場合
〇受遺者が相続人全員の場合
・登記原因:相続
・登記申請事項:相続人の単独申請
〇受遺者が相続人の一部の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
ⅱ.特定遺贈の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
②対象者 :第三者
〇包括遺贈、特定遺贈共に
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
以上、不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記について、お話させていただきました。
次回は、『相続させる遺言のポイント】について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺言が有る場合においては、その遺言の文言と内容により、相続を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合と、遺贈を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合等があります。
今回は、相続を登記原因とした場合の所有権移転登記について、お話させていただきます。
【申請書類等】
◇申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
◇申請人 :相続または全相続人が包括遺贈により不動産を取得した場合の(全)相続人、またはその代理人
◇申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
◇申請時期:相続開始後、特になし
◇申請費用:所有権移転登録免許税(不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4)+司法書士報酬
【添付資料一覧】
◇登記事項証明書
・遺言書
・遺言者の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本
・遺言者の住民票除票
・相続人または相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人の住民票(住所証明書)
◇相続人全員の印鑑証明書
◇固定資産評価証明書
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
【概要】
■遺言がある場合において、相続が登記原因となるとき
遺言による所有権移転登記をする場合、遺言の文書と内容によって、登記原因が相続となるか遺贈となるか、さらに、登記申請の形態も相違してきます。
◇文言・・相続させるの場合
・対象者 :相続人のみ
・登記原因:相続
・登記申請形態:相続人単独申請
◇文言・・遺贈するの場合
①対象者 :法定相続人
ⅰ.包括遺贈の場合
〇受遺者が相続人全員の場合
・登記原因:相続
・登記申請事項:相続人の単独申請
〇受遺者が相続人の一部の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
ⅱ.特定遺贈の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
②対象者 :第三者
〇包括遺贈、特定遺贈共に
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
以上、不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記について、お話させていただきました。
次回は、『相続させる遺言のポイント】について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年11月12日
相続の事が少しずつ分かるいいお話186 『不動産の法定相続による所有権移転登記』
本日は、『不動産の法定相続による所有権移転登記』についてお話させてい
1.不動産を法定相続により所有権移転登記するには次の様な流れの手続きによります。
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。
◇申請書類関係
・申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
・申請時期:特になし
・申請費用:所有権移転登記免許税⇒相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1,000分の4+司法書士報酬
【添付資料一覧】
ケース① 未分割の場合
◇登記原因証明書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
※なお、相続の場合には通常『登記識別情報または登記済証』は不要となりますが、しかし、被相続人が住所変更をしていたが、その変更登記を行っていなかった場合に、住民票の除票等で同一本人であることが追跡確認出来ないときには、必要となる場合があります。・・ケース②~⑧についても同様です。
ケース② 相続人全員による申請の場合
ケース①と同じもの
ケース③ 共同相続人のうち1人の申請の場合
ケース①と同じもの
ケース④ 胎児が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員(胎児を除く。)の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
④-A 相続登記後に胎児が生きて生まれた場合(所有権登記名義人表示変更登記)
◇登記原因証明情報
・出生した新生児の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇出生した新生児の住民票の写し(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇母親の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
④-B 相続登記後に胎児が死産だった場合(所有権更正登記)
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇母親の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
ケース⑤ 未成年者が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相族人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限勝訴
◇相続関係説明図
◇特別代理人選任通知書⇒家庭裁判所で請求
ケース⑥ 代襲相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース⑦ 外国人が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項承継所もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人の記載のある被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書もたは戸籍、除籍謄本
◇相続人の印鑑証明書またはサイン証明書⇒市役所等、領事館で請求
◇相続人の登録原票記載事項証明書(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース⑧ 特別縁故者が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・確定証明書付審判書正本⇒家庭裁判所で請求
◇特別縁故者の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
【概要要点】
◇不動産の相続登記
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。この手続きは、登記所(地方法務局など)で、所有権移転申請をすることになります。
◇相続による所有権移転登記の要否
相続登記しなくても違法ではありませんが、そのまま放置しておくと、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、後日の相続処理などが大変面倒になります。
◇登記申請書と登記済証書
登記申請書は、平成16年11月1日からA4判横書きが標準用紙となりました。
不動産の登記が完了すると、登記識別情報(オンライン未指定庁においては登記済証)が交付されます。再発行ができませんので慎重に保管してください。
以上、不動産の法定相続による所有権移転登記に必要な書類他手続きの概要について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.不動産を法定相続により所有権移転登記するには次の様な流れの手続きによります。
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。
◇申請書類関係
・申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
・申請時期:特になし
・申請費用:所有権移転登記免許税⇒相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1,000分の4+司法書士報酬
【添付資料一覧】
ケース① 未分割の場合
◇登記原因証明書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
※なお、相続の場合には通常『登記識別情報または登記済証』は不要となりますが、しかし、被相続人が住所変更をしていたが、その変更登記を行っていなかった場合に、住民票の除票等で同一本人であることが追跡確認出来ないときには、必要となる場合があります。・・ケース②~⑧についても同様です。
ケース② 相続人全員による申請の場合
ケース①と同じもの
ケース③ 共同相続人のうち1人の申請の場合
ケース①と同じもの
ケース④ 胎児が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員(胎児を除く。)の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
④-A 相続登記後に胎児が生きて生まれた場合(所有権登記名義人表示変更登記)
◇登記原因証明情報
・出生した新生児の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇出生した新生児の住民票の写し(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇母親の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
④-B 相続登記後に胎児が死産だった場合(所有権更正登記)
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇母親の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
ケース⑤ 未成年者が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相族人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限勝訴
◇相続関係説明図
◇特別代理人選任通知書⇒家庭裁判所で請求
ケース⑥ 代襲相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース⑦ 外国人が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項承継所もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人の記載のある被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書もたは戸籍、除籍謄本
◇相続人の印鑑証明書またはサイン証明書⇒市役所等、領事館で請求
◇相続人の登録原票記載事項証明書(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース⑧ 特別縁故者が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・確定証明書付審判書正本⇒家庭裁判所で請求
◇特別縁故者の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
【概要要点】
◇不動産の相続登記
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。この手続きは、登記所(地方法務局など)で、所有権移転申請をすることになります。
◇相続による所有権移転登記の要否
相続登記しなくても違法ではありませんが、そのまま放置しておくと、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、後日の相続処理などが大変面倒になります。
◇登記申請書と登記済証書
登記申請書は、平成16年11月1日からA4判横書きが標準用紙となりました。
不動産の登記が完了すると、登記識別情報(オンライン未指定庁においては登記済証)が交付されます。再発行ができませんので慎重に保管してください。
以上、不動産の法定相続による所有権移転登記に必要な書類他手続きの概要について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年10月29日
相続の事が少しずつわかるいいお話184 『銀行預金名義変更のポイント②』
本日は、『銀行預金の名義変更のポイント②』として、ケース④~⑦までのポイントについて、お話させていただきます。
ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
共同相続人の協議が整わないとき、または行方不明者などがあって遺産分割協議ができないときは、共同相続人は共同してまたは1人で、家庭裁判所に遺産の分割の申し立てることができます。
家庭裁判所は、まず調停委員の立ち会いのもとで『調停』にかけ、相続人全員の合意が成立すれば、合意のとおりの調停調書が作成され確定判決が下されます。
調停が成立しないときは『審判』による分割を行うこととなります。
審判は、裁判所が当事者・利害関係者の言い分や調査により、具体的な分割の決定をします。
家庭裁判所の調停等による遺産分割決定等の後に預金の名義変更をする場合は、調停に関する家庭裁判所の確定判決を証明する書類が必要になります。
調停で確定した場合には家庭裁判所の調停調書謄本、審判で決定された場合は、家庭裁判所の審判書謄本となります。
ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合
裁判上の和解とは、民事裁判の手続きの中で、当事者がお互いにその主張を譲り合って紛争の解決に向けた合意を形成することにより、判決によらず裁判を終わらせることです。
裁判上の和解は、紛争解決に向けた当事者同士の任意の合意ですが、最終的に裁判所書記官がその和解を調書に記載することにより、裁判所の言い渡す判決と同じ効力が与えられます。
この調書を『和解調書』および『確定証明書」といいます。
裁判上の和解による和解調書がある場合に預金の名義変更をするときは、裁判所の確定判決を証明する書類である和解証書謄本および確定証明書が必要になります。
ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合
遺言による特定受遺者が申し出る場合、特定受遺者であることを証明するために遺言書またはその写しが必要となります。
銀行によっては、遺言書の原本を確認することもありますので、預入先の銀行へ事前の確認をお奨めします。
遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認証明書が必要となります。
また銀行では、遺言書の全文があり、日付が記載されていることおよび遺言書の署名押印がしていることを確認します。
ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合
相続財産管理人は、相続人の存在、不存在が明らかでない場合や相続人全員が相続を放棄し相続する者がいない場合に、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所により選任されます。
相続財産管理人は相続財産を清算して国庫に帰属させることになります。
また相続人全員で、相続財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ『限定承認』を選択した場合、相続人のうち1名を相続財産管理人として選任してもらいその者が以後の手続きを行います。
相続財産管理人が申し出る場合において預金の名義変更を行うときは、相続財産管理人を証明するために相続財産管理人選任の審判書謄本や限定承認申述書謄本が必要となります。
次回は、『銀行の貸金庫を開けるとき』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
共同相続人の協議が整わないとき、または行方不明者などがあって遺産分割協議ができないときは、共同相続人は共同してまたは1人で、家庭裁判所に遺産の分割の申し立てることができます。
家庭裁判所は、まず調停委員の立ち会いのもとで『調停』にかけ、相続人全員の合意が成立すれば、合意のとおりの調停調書が作成され確定判決が下されます。
調停が成立しないときは『審判』による分割を行うこととなります。
審判は、裁判所が当事者・利害関係者の言い分や調査により、具体的な分割の決定をします。
家庭裁判所の調停等による遺産分割決定等の後に預金の名義変更をする場合は、調停に関する家庭裁判所の確定判決を証明する書類が必要になります。
調停で確定した場合には家庭裁判所の調停調書謄本、審判で決定された場合は、家庭裁判所の審判書謄本となります。
ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合
裁判上の和解とは、民事裁判の手続きの中で、当事者がお互いにその主張を譲り合って紛争の解決に向けた合意を形成することにより、判決によらず裁判を終わらせることです。
裁判上の和解は、紛争解決に向けた当事者同士の任意の合意ですが、最終的に裁判所書記官がその和解を調書に記載することにより、裁判所の言い渡す判決と同じ効力が与えられます。
この調書を『和解調書』および『確定証明書」といいます。
裁判上の和解による和解調書がある場合に預金の名義変更をするときは、裁判所の確定判決を証明する書類である和解証書謄本および確定証明書が必要になります。
ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合
遺言による特定受遺者が申し出る場合、特定受遺者であることを証明するために遺言書またはその写しが必要となります。
銀行によっては、遺言書の原本を確認することもありますので、預入先の銀行へ事前の確認をお奨めします。
遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認証明書が必要となります。
また銀行では、遺言書の全文があり、日付が記載されていることおよび遺言書の署名押印がしていることを確認します。
ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合
相続財産管理人は、相続人の存在、不存在が明らかでない場合や相続人全員が相続を放棄し相続する者がいない場合に、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所により選任されます。
相続財産管理人は相続財産を清算して国庫に帰属させることになります。
また相続人全員で、相続財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ『限定承認』を選択した場合、相続人のうち1名を相続財産管理人として選任してもらいその者が以後の手続きを行います。
相続財産管理人が申し出る場合において預金の名義変更を行うときは、相続財産管理人を証明するために相続財産管理人選任の審判書謄本や限定承認申述書謄本が必要となります。
次回は、『銀行の貸金庫を開けるとき』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年10月28日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 183 『銀行預金の名義変更のポイント①』
本日は、前回に引き続いて、『銀行預金の名義変更のポイント①』について、お話させていただきます。
◇ケース1 相続人が名義変更する場合
相続預金の解約でなく、名義変更を行う場合には、新しい名義人の印鑑および『新印鑑届』が必要です。
また、非課税貯蓄預金(マル優)の相続がある場合には、『非課税貯蓄者死亡届』の提出が必要となりますので、各銀行にお問い合わせください。
◇ケース2 被相続人が家族名義で行った預金
家族名義である理由や受入れの状況などを聴衆され、銀行が所持している入金票・印鑑届出印の照合がなされた上で、預金者の認定が行われます。
また預金名義人の念書が求められます。
念書は各銀行所定の用紙か、ない場合には作成した上で、預金が預金名義人のものでない旨を記載し、署名押印します。
なお、預金を生前に贈与し、課税当局から家族名義預金と認定されないように次のような『贈与の証拠』を残しておくとよいでしょう。
①贈与者銀行口座から受贈者が開設した銀行口座へ預金を振り込む。
②届出印鑑は贈与者の印鑑とは別にし、本人の印鑑を押印する。また、受贈者またはその親権者が通帳、印鑑。証書などを保管する。
③年額110万円超の贈与をし、贈与税の申告・納付を行い、贈与税の申告書。納付書は、しっかり保存しておく。
④贈与時に贈与契約書を作成し、確実性を高める場合に、公証人役場等で確定日付をとっておく。
◇ケース3 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
遺言執行者は、法律上、相続人の代理人とみなされます。
相続財産の管理その他遺言の執行に関する一切の行為をし、遺言の内容の実現を行います。
遺言執行者は、財産目録などを作成した上で、預金の名義変更など、相続手続きの一切を単独で行うことができます。
遺言執行者には相続人がなっても構いませんが、未成年者と破産者はなることができません。
遺言執行者は、遺言によって指定される場合と、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、受贈者など)の申立により家庭裁判所で選任される場合があります。
遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行者が誰であるかを証明する書類が必要となります。
自筆証書遺言書の場合にはその原本を、遺言書が公正証書遺言の場合は公正証書の謄本が必要書類となります。
家庭裁判所で選任された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行選任に関する家庭裁判所の審判書謄本が必要となります。
ただし、遺言執行者が預金の払戻しを請求した場合において、遺言執行者の本人確認が行われれば、共同相続人全員の印鑑証明書を提出しなくても払戻ができるなど、金融機関によって多少の取扱いの相違がありますので、各取引銀行への確認が必要です。
次回は、ケース④から⑦までのポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
◇ケース1 相続人が名義変更する場合
相続預金の解約でなく、名義変更を行う場合には、新しい名義人の印鑑および『新印鑑届』が必要です。
また、非課税貯蓄預金(マル優)の相続がある場合には、『非課税貯蓄者死亡届』の提出が必要となりますので、各銀行にお問い合わせください。
◇ケース2 被相続人が家族名義で行った預金
家族名義である理由や受入れの状況などを聴衆され、銀行が所持している入金票・印鑑届出印の照合がなされた上で、預金者の認定が行われます。
また預金名義人の念書が求められます。
念書は各銀行所定の用紙か、ない場合には作成した上で、預金が預金名義人のものでない旨を記載し、署名押印します。
なお、預金を生前に贈与し、課税当局から家族名義預金と認定されないように次のような『贈与の証拠』を残しておくとよいでしょう。
①贈与者銀行口座から受贈者が開設した銀行口座へ預金を振り込む。
②届出印鑑は贈与者の印鑑とは別にし、本人の印鑑を押印する。また、受贈者またはその親権者が通帳、印鑑。証書などを保管する。
③年額110万円超の贈与をし、贈与税の申告・納付を行い、贈与税の申告書。納付書は、しっかり保存しておく。
④贈与時に贈与契約書を作成し、確実性を高める場合に、公証人役場等で確定日付をとっておく。
◇ケース3 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
遺言執行者は、法律上、相続人の代理人とみなされます。
相続財産の管理その他遺言の執行に関する一切の行為をし、遺言の内容の実現を行います。
遺言執行者は、財産目録などを作成した上で、預金の名義変更など、相続手続きの一切を単独で行うことができます。
遺言執行者には相続人がなっても構いませんが、未成年者と破産者はなることができません。
遺言執行者は、遺言によって指定される場合と、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、受贈者など)の申立により家庭裁判所で選任される場合があります。
遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行者が誰であるかを証明する書類が必要となります。
自筆証書遺言書の場合にはその原本を、遺言書が公正証書遺言の場合は公正証書の謄本が必要書類となります。
家庭裁判所で選任された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行選任に関する家庭裁判所の審判書謄本が必要となります。
ただし、遺言執行者が預金の払戻しを請求した場合において、遺言執行者の本人確認が行われれば、共同相続人全員の印鑑証明書を提出しなくても払戻ができるなど、金融機関によって多少の取扱いの相違がありますので、各取引銀行への確認が必要です。
次回は、ケース④から⑦までのポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年10月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話し182 『銀行預金の名義変更②』
本日は、前回の続きで、『銀行預金の名義変更』についての添付書類の種類について、お話させていただきます。
ケース① 相続人が名義変更するときの一般的な添付書類
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.預金名義人の預金通帳・届出印・キャッシュカード
ⅲ.被相続人の戸籍・除籍事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅳ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅴ.相続人全員の印鑑証明書
ⅵ.相続人全員の実印
ⅶ.銀行手続きを行うものの実印
ⅷ.遺言書(原本)
ⅸ.各銀行所定の死亡届出書
ⅹ.各銀行所定の念書
ケース② 被相続人が家族名義で行った預金の場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅳ.相続人全員の印鑑証明書
ⅴ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅵ.各銀行所定の死亡届出書
ⅶ.各銀行所定の相続人の念書
ⅷ.各銀行所定の預金名義人の念書
ケース③ 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.遺言書原本(公正証書遺言の場合は公正証書の謄本)及び遺言執行者選任審書謄本
ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.家庭裁判所の調停調書謄本または審判調停謄本
ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合
ⅰ.相続人全員の印鑑証明書
ⅱ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅲ.各銀行所定の死亡届出書
ⅳ.各銀行所定の相続人の念書
ⅴ.家庭裁判所の和解蝶よ謄本および確定証明書
ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.受遺者の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.遺言書
ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.相続人全員の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.相続財産管理人選任審判書謄本
ⅶ.限定承認申述書
以上、各ケースごとの一般的に必要とされる添付書類について記載させていただきました。
上記の添付書類は、個別の事情に応じて異なってくる場合がありますので、最終的には各銀行にお問い合わせください。
次回は、上記の7つのケースごとの注意点ついてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
ケース① 相続人が名義変更するときの一般的な添付書類
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.預金名義人の預金通帳・届出印・キャッシュカード
ⅲ.被相続人の戸籍・除籍事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅳ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅴ.相続人全員の印鑑証明書
ⅵ.相続人全員の実印
ⅶ.銀行手続きを行うものの実印
ⅷ.遺言書(原本)
ⅸ.各銀行所定の死亡届出書
ⅹ.各銀行所定の念書
ケース② 被相続人が家族名義で行った預金の場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅳ.相続人全員の印鑑証明書
ⅴ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅵ.各銀行所定の死亡届出書
ⅶ.各銀行所定の相続人の念書
ⅷ.各銀行所定の預金名義人の念書
ケース③ 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.遺言書原本(公正証書遺言の場合は公正証書の謄本)及び遺言執行者選任審書謄本
ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.家庭裁判所の調停調書謄本または審判調停謄本
ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合
ⅰ.相続人全員の印鑑証明書
ⅱ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅲ.各銀行所定の死亡届出書
ⅳ.各銀行所定の相続人の念書
ⅴ.家庭裁判所の和解蝶よ謄本および確定証明書
ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.受遺者の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.遺言書
ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.相続人全員の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.相続財産管理人選任審判書謄本
ⅶ.限定承認申述書
以上、各ケースごとの一般的に必要とされる添付書類について記載させていただきました。
上記の添付書類は、個別の事情に応じて異なってくる場合がありますので、最終的には各銀行にお問い合わせください。
次回は、上記の7つのケースごとの注意点ついてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年10月14日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 181 『銀行預金の名義変更』
本日は、『銀行預金の名義変更』について、お話させていただきます。
遺産分割後に相続預金の名義変更をする場合、銀行所定の『名義変更依頼書』に必要事項を記載して、添付書類と共に提出します。
なお、銀行預金の名義変更については次の7つのケースが考えられます。
ケース①:相続人が名義変更をする場合
ケース②:被相続人が家族名義で行った預金の場合
ケース③:遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ケース④:家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ケース⑤:裁判上の和解による和解調書がある場合
ケース⑥:遺言による特定受遺者が申し出る場合
ケース⑦:相続財産管理人が申し出る場合
提出書類:各銀行所定の名義書換請求書、相続確認書
提出人 :ケース①②④⑤・・相続人
ケース③・・・・・遺言執行者
ケース⑥・・・・・特定受贈者
ケース⑦・・・・・相続財産管理人
提出先 :預入先の各銀行
提出時期:特になし
提出費用:特になし
【ポイント】
◇前提として遺産分割協議の確定
預金を相続するには、銀行口座の名義変更が必要となります。
銀行口座の名義変更を行うには、まず遺産分割協議が確定していることが前提となります。
これは、被相続人の名義である預貯金を一部の相続人が勝手に名義変更することを防止するために、被相続人の死亡を金融機関が確認すると預金の凍結をするためです。
凍結された預貯金の名義変更を受けるためには、遺産分割が確定した上で所定の手続きをしなければなりません。
◇名義書換手続
預入先である各銀行所定の『名義書換請求書』に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人の署名をしたうえで実印を押印し、添付書類と共にその現行に提出します。
その際、代表相続人は名義を書き換えるか、解約して支払いを受けるかを選択して記入します。
名義書換請求書および相続確認書は各銀行で所定の用紙をもらいます。
◇提出書類等
請求用紙や添付書類は、銀行預金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なる場合がありますので、最終的には各銀行に確認していただく必要があります。
次回は、上記7つのケースごとの一般的な添付書類の種類とポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺産分割後に相続預金の名義変更をする場合、銀行所定の『名義変更依頼書』に必要事項を記載して、添付書類と共に提出します。
なお、銀行預金の名義変更については次の7つのケースが考えられます。
ケース①:相続人が名義変更をする場合
ケース②:被相続人が家族名義で行った預金の場合
ケース③:遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ケース④:家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ケース⑤:裁判上の和解による和解調書がある場合
ケース⑥:遺言による特定受遺者が申し出る場合
ケース⑦:相続財産管理人が申し出る場合
提出書類:各銀行所定の名義書換請求書、相続確認書
提出人 :ケース①②④⑤・・相続人
ケース③・・・・・遺言執行者
ケース⑥・・・・・特定受贈者
ケース⑦・・・・・相続財産管理人
提出先 :預入先の各銀行
提出時期:特になし
提出費用:特になし
【ポイント】
◇前提として遺産分割協議の確定
預金を相続するには、銀行口座の名義変更が必要となります。
銀行口座の名義変更を行うには、まず遺産分割協議が確定していることが前提となります。
これは、被相続人の名義である預貯金を一部の相続人が勝手に名義変更することを防止するために、被相続人の死亡を金融機関が確認すると預金の凍結をするためです。
凍結された預貯金の名義変更を受けるためには、遺産分割が確定した上で所定の手続きをしなければなりません。
◇名義書換手続
預入先である各銀行所定の『名義書換請求書』に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人の署名をしたうえで実印を押印し、添付書類と共にその現行に提出します。
その際、代表相続人は名義を書き換えるか、解約して支払いを受けるかを選択して記入します。
名義書換請求書および相続確認書は各銀行で所定の用紙をもらいます。
◇提出書類等
請求用紙や添付書類は、銀行預金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なる場合がありますので、最終的には各銀行に確認していただく必要があります。
次回は、上記7つのケースごとの一般的な添付書類の種類とポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年10月10日
相続の事が少しずつ分かるいいお話180 『遺産分割前の預貯金等の払戻』
本日は、『遺産名義変更に関する手続き』のうち、預貯金等①について、お話させていただきます。
1.遺産分割前に預金の払戻しをするとき
相続開始後、遺産分割前に葬式費用の支払い等に充てるため等、被相続人名義の預金を引き出す場合は、預金払戻請求を金融機関に依頼します。
①提出書類 : 各銀行所定の預金払戻請求書
②提出人 : 共同相続人全員
③提出先 : 預入先の各銀行
④亭主時期 : 遺産分割協議前に払戻しを受けるとき
⑤提出費用 : 特になし
【一般的な添付書類】
①被相続人の預金通帳(または証書)・届出印・キャッシュカード
②被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本、改製原戸籍謄本
③相続人全員または受遺者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書(3ヵ月以内)
⑤各銀行所定の死亡届出書
⑥各銀行所定の相続人の念書等
◇解説
①相続開始と預金の凍結
金融機関は預貯金者(被相続人)の死亡を確認すると一部の相続人が預金を勝手に引き出せないように、被相続人の名義の預金を凍結します。
②分割確定前一部引き出しの必要な場合
凍結された預金の払い戻しを受けるためには遺産分割が確定したうえで、所定の手続きを踏まなければなりません。
しかし、遺産分割前に葬式費用の支払いに充てるため等、預金の引き出しを請求しなければならない場合は、預け入れしている各銀行所定の『預金払戻請求書』に必要事項を記載し、添付書類と共にその銀行に提出する必要があります。
なお、請求用紙や添付書類等は各銀行によって異なってまいりますので、事前に取引銀行に直接、お問い合わせしてください。
預金払戻請求書に記載されている一般的な内容というのは、遺産分割協議成立前ではありますが、預金の一部を引き落とすことに相続人全員が同意していることと、相続人のうちの代表者一名の者にその払い戻しを行うのを同意しているなどの内容です。
要は、預金名義者の死亡により、その預金は一旦、相続人全員の共有財産となりますので遺産分割前であるときや遺言書がないときなどは、預金の払い戻し一つとっても、相続人全員の合意を証明して手続きを行う必要があります。
相続人全員であることを証するために、被相続人や相続人全員の戸籍謄本等が必要となってきます。
金融機関側も、相続人全員の合意がないにもかかわらず誤って一部の相続人に預金の払い戻しを行ってしまうと誰のものともなるか分からない財産を勝手に払戻したこととなり、責任問題にも発展していくことから、かなり慎重に手続きを行っていくわけです。
金融機関によって、その慎重さには温度差がありますので、手続き手順はしつこいようですが、各金融機関にお問い合わせください。
本日は、『遺産分割前の預貯金の払戻し』について、お話させていただきました。
次回は、『銀行預金の名義変更』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.遺産分割前に預金の払戻しをするとき
相続開始後、遺産分割前に葬式費用の支払い等に充てるため等、被相続人名義の預金を引き出す場合は、預金払戻請求を金融機関に依頼します。
①提出書類 : 各銀行所定の預金払戻請求書
②提出人 : 共同相続人全員
③提出先 : 預入先の各銀行
④亭主時期 : 遺産分割協議前に払戻しを受けるとき
⑤提出費用 : 特になし
【一般的な添付書類】
①被相続人の預金通帳(または証書)・届出印・キャッシュカード
②被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本、改製原戸籍謄本
③相続人全員または受遺者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書(3ヵ月以内)
⑤各銀行所定の死亡届出書
⑥各銀行所定の相続人の念書等
◇解説
①相続開始と預金の凍結
金融機関は預貯金者(被相続人)の死亡を確認すると一部の相続人が預金を勝手に引き出せないように、被相続人の名義の預金を凍結します。
②分割確定前一部引き出しの必要な場合
凍結された預金の払い戻しを受けるためには遺産分割が確定したうえで、所定の手続きを踏まなければなりません。
しかし、遺産分割前に葬式費用の支払いに充てるため等、預金の引き出しを請求しなければならない場合は、預け入れしている各銀行所定の『預金払戻請求書』に必要事項を記載し、添付書類と共にその銀行に提出する必要があります。
なお、請求用紙や添付書類等は各銀行によって異なってまいりますので、事前に取引銀行に直接、お問い合わせしてください。
預金払戻請求書に記載されている一般的な内容というのは、遺産分割協議成立前ではありますが、預金の一部を引き落とすことに相続人全員が同意していることと、相続人のうちの代表者一名の者にその払い戻しを行うのを同意しているなどの内容です。
要は、預金名義者の死亡により、その預金は一旦、相続人全員の共有財産となりますので遺産分割前であるときや遺言書がないときなどは、預金の払い戻し一つとっても、相続人全員の合意を証明して手続きを行う必要があります。
相続人全員であることを証するために、被相続人や相続人全員の戸籍謄本等が必要となってきます。
金融機関側も、相続人全員の合意がないにもかかわらず誤って一部の相続人に預金の払い戻しを行ってしまうと誰のものともなるか分からない財産を勝手に払戻したこととなり、責任問題にも発展していくことから、かなり慎重に手続きを行っていくわけです。
金融機関によって、その慎重さには温度差がありますので、手続き手順はしつこいようですが、各金融機関にお問い合わせください。
本日は、『遺産分割前の預貯金の払戻し』について、お話させていただきました。
次回は、『銀行預金の名義変更』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年10月04日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 179 『不動産の価格評価』
本日は、不動産の価格調査についてお話させていただきます。
Ⅰ.不動産の価格評価
1.不動産の価格の特徴
不動産の価格は、不動産の効用および総体的希少性並びに不動産に対する有効需要に影響を与える次の要因により形成されます。
①需要と供給の原則
②変動の原則
③代替えの原則(代替性を有する材の価格は相互に影響する)
④最有効使用の原則(不動産の価格は最有効使用を前提に形成される)
⑤均衡の原則(構成要素の均衡により最有効となる)
⑥収益逓増及び逓減の原則(追加投資の判断)
⑦収益配分の原則(収益は資本・労働・経営・土地に配分される)
⑧寄与の原則
⑨適合の原則(周囲の環境との適合により最有効となる)
⑩競争の原則・予備の原則があり、相互に関連している
2.公的土地評価
公的な土地の価格の目安となるものとして、それぞれ、次の種類のものがあります。
◇土地価格の種類
①公示価格・・・・・国土交通省土地鑑定委員会が公表
基準値標準価格・・都道府県が公表
②路線価価格・・・・相続税評価に用いられる
③固定資産税評価額・固定資産税の課税標準のもとになる
④実勢価格・・・・・実際の売買実例より推定される
3.不動産鑑定評価
不動産の鑑定評価方法としては、各々、次の方式があります。
◇不動産鑑定の評価方式
①原価方式・・不動産の最調達(建築造成等による新規の調達)に要する減価に着目
②比較方式・・不動産の取引事例または賃貸借等の事例に着目する。
③収益方式・・不動産から生みだされる収益に着目する。
鑑定評価方式の適用にあたっては、鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきです。
この原則として減価方式、比較方式及び収益方式の3方式を併用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により3方式の併用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めなければなりません。
以上、『不動産の価格評価』 について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
Ⅰ.不動産の価格評価
1.不動産の価格の特徴
不動産の価格は、不動産の効用および総体的希少性並びに不動産に対する有効需要に影響を与える次の要因により形成されます。
①需要と供給の原則
②変動の原則
③代替えの原則(代替性を有する材の価格は相互に影響する)
④最有効使用の原則(不動産の価格は最有効使用を前提に形成される)
⑤均衡の原則(構成要素の均衡により最有効となる)
⑥収益逓増及び逓減の原則(追加投資の判断)
⑦収益配分の原則(収益は資本・労働・経営・土地に配分される)
⑧寄与の原則
⑨適合の原則(周囲の環境との適合により最有効となる)
⑩競争の原則・予備の原則があり、相互に関連している
2.公的土地評価
公的な土地の価格の目安となるものとして、それぞれ、次の種類のものがあります。
◇土地価格の種類
①公示価格・・・・・国土交通省土地鑑定委員会が公表
基準値標準価格・・都道府県が公表
②路線価価格・・・・相続税評価に用いられる
③固定資産税評価額・固定資産税の課税標準のもとになる
④実勢価格・・・・・実際の売買実例より推定される
3.不動産鑑定評価
不動産の鑑定評価方法としては、各々、次の方式があります。
◇不動産鑑定の評価方式
①原価方式・・不動産の最調達(建築造成等による新規の調達)に要する減価に着目
②比較方式・・不動産の取引事例または賃貸借等の事例に着目する。
③収益方式・・不動産から生みだされる収益に着目する。
鑑定評価方式の適用にあたっては、鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきです。
この原則として減価方式、比較方式及び収益方式の3方式を併用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により3方式の併用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めなければなりません。
以上、『不動産の価格評価』 について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年10月03日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 178 『役所調査/道路調査』
本日は、『役所調査/道路調査』 についてお話させていただきます。
土地の価値は、接している土地の状況(公道か私道か、道路の幅の広さや、接している長さや、高低差や、などなど)によって、大きく変わってくることがあります。
道路の状況によっては、最悪、建物が建たない場合や、敷地の一部を道路に供する必要(セットバック)が有る場合があります。
土地の評価にあっては、道路の調査はとても重要なものとなってきます。
1.道路の確認
(1)道路と敷地との関係とは
原則として、建築基準法上の道路は4m(6m)以上だが、現に建築物が建ち並んでいる道で、特定行政庁の指定があったものは、幅員が4m(6m)未満であっても道路とみなされます。
(いわゆる42条2項道路、みなし道路ともいいます)
この場合、現況道路の中心線から2m(3m)ずつ両側に後退した線が道路境界線とみなされます。
ただし、中心線から2m未満で一方ががけ地、川、線路敷地等である場合には、川などから4mの線が道路境界線となります。
都市計画区域内及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法上の道路(自動車専用道路は除く)に2m以上接していなければならないとされています。
例外としては、敷地の周囲に広い空き地を有する建築物などで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務は適用されないこととされています。
(2)公道か私道かを市町村役場の管理課等で確認します。
(3)42条2項道路と位置指定道路の確認をします。
市町村役場の道路課等で道路の種別の確認を行い(42条2項道路、位置指定道路)、道路図面を取得します。
■4m以上 建築基準法上の道路には次の種類のものがあります。
1.建築基準法第42条第1項
①1号道路 道路法にいう道路(国道、県道、市町村道)※自動車専用道路は接道不可
②2号道路 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発等の道路
③3号道路 建築基準法施行時に既にあった道。(法以前道路、既存道路)
④4号道路 都市計画道路等で2年以内に事業が施行される予定のあるもの
⑤5号道路 道路の位置の指定をうけたもの ※位置指定道路
2.建築基準法第43条
⑥但し書き道路 幅員4m以上で建築基準法42条に該当しない道路(農道、港湾施設道路、河川管理用道路、学校外周道路など)許可が必要
■4m未満の道路には次の種類のものがあります。
1.建築基準法42条
⑦2項道路 公道または私道
2.建築基準法43条
⑧但し書き道路 42条2項に該当しない道路 許可が必要
※①・④は公道 ②は原則公道 ③は公道および私道 ⑤は私道 ⑥は私道
⑦公道および私道 ⑧は公道および私道
※43条但し書きにて敷地に建築する場合、建築指導課の許可で階数・規模・用途などの建築制限があります。
以上、『役所調査/道路調査』 について、お話させていただきました。
次回からは、『不動産の価格評価』 について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
土地の価値は、接している土地の状況(公道か私道か、道路の幅の広さや、接している長さや、高低差や、などなど)によって、大きく変わってくることがあります。
道路の状況によっては、最悪、建物が建たない場合や、敷地の一部を道路に供する必要(セットバック)が有る場合があります。
土地の評価にあっては、道路の調査はとても重要なものとなってきます。
1.道路の確認
(1)道路と敷地との関係とは
原則として、建築基準法上の道路は4m(6m)以上だが、現に建築物が建ち並んでいる道で、特定行政庁の指定があったものは、幅員が4m(6m)未満であっても道路とみなされます。
(いわゆる42条2項道路、みなし道路ともいいます)
この場合、現況道路の中心線から2m(3m)ずつ両側に後退した線が道路境界線とみなされます。
ただし、中心線から2m未満で一方ががけ地、川、線路敷地等である場合には、川などから4mの線が道路境界線となります。
都市計画区域内及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法上の道路(自動車専用道路は除く)に2m以上接していなければならないとされています。
例外としては、敷地の周囲に広い空き地を有する建築物などで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務は適用されないこととされています。
(2)公道か私道かを市町村役場の管理課等で確認します。
(3)42条2項道路と位置指定道路の確認をします。
市町村役場の道路課等で道路の種別の確認を行い(42条2項道路、位置指定道路)、道路図面を取得します。
■4m以上 建築基準法上の道路には次の種類のものがあります。
1.建築基準法第42条第1項
①1号道路 道路法にいう道路(国道、県道、市町村道)※自動車専用道路は接道不可
②2号道路 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発等の道路
③3号道路 建築基準法施行時に既にあった道。(法以前道路、既存道路)
④4号道路 都市計画道路等で2年以内に事業が施行される予定のあるもの
⑤5号道路 道路の位置の指定をうけたもの ※位置指定道路
2.建築基準法第43条
⑥但し書き道路 幅員4m以上で建築基準法42条に該当しない道路(農道、港湾施設道路、河川管理用道路、学校外周道路など)許可が必要
■4m未満の道路には次の種類のものがあります。
1.建築基準法42条
⑦2項道路 公道または私道
2.建築基準法43条
⑧但し書き道路 42条2項に該当しない道路 許可が必要
※①・④は公道 ②は原則公道 ③は公道および私道 ⑤は私道 ⑥は私道
⑦公道および私道 ⑧は公道および私道
※43条但し書きにて敷地に建築する場合、建築指導課の許可で階数・規模・用途などの建築制限があります。
以上、『役所調査/道路調査』 について、お話させていただきました。
次回からは、『不動産の価格評価』 について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年10月01日
相続の事が少しずつ分かるいいお話177 『役所調査/都市計画・用途地域』
本日は、『役所調査/都市計画・用途地域』 について、お話させていただきます。
1.役所調査
(1)都市計画・用途地域確認
都市計画区域の指定は、次のように指定します。
・1つの都道府県に指定する場合は関係市町村と都市計画地方審議会の意見を聞き国土交通大臣の認可を得て都道府県知事が指定します。
・2つ以上の都府県にわたって指定する場合は関係都府県の意見を聴き国土交通大臣が指定します。
①市街化区域及び市街化調整区域
◇市街化区域とは、既に市街地を形成している区域(規制市街地)+おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(計画開発区域)
◇市街化調整区域は、市街化を抑制する区域
◇未線引き都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域に区分されていない区域(三大都市圏の一定の区域と一定の大都市以外の区域に定ることができます)
②地域地区
地域地区は市街化区域と市街化調整区域の2つに分けられます。
ⅰ.用途地域
住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の合計12種類があります。
【住居系】
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居専用地域
【商業系】
近隣商業地域
商業地域
【工業系】
準工業地域
工業地域
工業専用地域
市街化区域内では少なくとも用途地域を定める。市街化調整区域では原則として用途地域を定めないこととする(同法13条)。非線引き都市計画区域や準都市計画区域内においても、用途地域を定めることができる。
ⅱ.補助的用途地区(主なものを列挙)
特別用途地区・特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区(建築物の高さの最高限度または建築物の高さの最低限度を定める地区)、高度利用地区(容積率の最高・最低限度及び建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区)、特定街区、都市再生特別地区、防火地域または準防火地域(市街地における火災の危険を防除するために定める地域。都市計画で、防火地域及び準防火地域が指定されると建築基準法で具体的な規制が行われる。)、景観地区、風致地区(都市の風致を維持するため定める地区。建築物の建築、宅地の造成、木材の伐採についての規制)
③建築基準法
ⅰ.集団規定
a)用途についての規定・・別添資料6①
特定行政庁の許可があればこの用途制限規定にかかわらず、建築物を建築することができる。また、敷地が2以上の用途地域にまたがるときは、過半の属する地域の用途制限を受ける。
b)建物の建ぺい率の制限・・別添資料6③の一部参照
・建ぺい率とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう(同法53条)
◇建ぺい率=建築物の建築面積÷敷地面積
・敷地が建ぺい率制限の異なる地域にわたる場合の取扱い
建物の敷地が建ぺい率の異なる規制数値である異なる複数の地域にわたる場合は、それぞれの地域の建ぺい率の最高限度の数値に、その地域に係る敷地が敷地全体に占める割合を乗じた数の合計が、その敷地全体の建ぺい率の最高限度となる。(加重平均)
・建物の敷地が防火地域の内外にわたる場合の取扱い
その敷地内の建物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして建ぺい率の緩和に関する規定を適用する。(同法53条)
c)建物の容積率の制限
・建物の敷地が、容積率の規制数値の異なる複数の地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率の最高限度の数値にその地域に係る敷地の敷地全体に占める割合を乗じた数値の合計が、その敷地全体の容積率の最高限度になる(加重平均)
・次の床面積は容積率算定上の延べ床面積に算入しなくてよい。
◇自動車車庫等の床面積で建築物の床面積の合計の5分の1までの面積
◇住宅用地の地階(天井が地盤面から高さ1m以下にあるもの)の床面積で建築物の住宅部分の床面積の合計の3分の1までの面積
◇共同住宅における共用廊下または階段(エレベーターそのものは除く)の床面積
・以下の建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率はその許可の範囲で緩和される。(同法52条)
◇その敷地の周囲に広い公園、広場、道路、その他の空地を有する建築物
◇同一敷地内の建築物の機械室、その他これに類する部分の床面積の合計が、建築物の延べ面積に対して、著しく大きい割合を有する場合。
d)建築物の高さに対する制限
道路斜線、隣地斜線、北側斜線の制限が適用された場合に一定の位置において確保される採光、通風等について一定の基準に適合する建築物については天空率による制限に適合した建物を工夫することにより、斜線制限を超えた高さの建物の建築が可能。
e)防火・準防火地域内の制限
以上、『役所調査/都市計画・用途地域確認』について、お話させていただきました。
次回は、『役所調査/道路の確認』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.役所調査
(1)都市計画・用途地域確認
都市計画区域の指定は、次のように指定します。
・1つの都道府県に指定する場合は関係市町村と都市計画地方審議会の意見を聞き国土交通大臣の認可を得て都道府県知事が指定します。
・2つ以上の都府県にわたって指定する場合は関係都府県の意見を聴き国土交通大臣が指定します。
①市街化区域及び市街化調整区域
◇市街化区域とは、既に市街地を形成している区域(規制市街地)+おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(計画開発区域)
◇市街化調整区域は、市街化を抑制する区域
◇未線引き都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域に区分されていない区域(三大都市圏の一定の区域と一定の大都市以外の区域に定ることができます)
②地域地区
地域地区は市街化区域と市街化調整区域の2つに分けられます。
ⅰ.用途地域
住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の合計12種類があります。
【住居系】
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居専用地域
【商業系】
近隣商業地域
商業地域
【工業系】
準工業地域
工業地域
工業専用地域
市街化区域内では少なくとも用途地域を定める。市街化調整区域では原則として用途地域を定めないこととする(同法13条)。非線引き都市計画区域や準都市計画区域内においても、用途地域を定めることができる。
ⅱ.補助的用途地区(主なものを列挙)
特別用途地区・特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区(建築物の高さの最高限度または建築物の高さの最低限度を定める地区)、高度利用地区(容積率の最高・最低限度及び建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区)、特定街区、都市再生特別地区、防火地域または準防火地域(市街地における火災の危険を防除するために定める地域。都市計画で、防火地域及び準防火地域が指定されると建築基準法で具体的な規制が行われる。)、景観地区、風致地区(都市の風致を維持するため定める地区。建築物の建築、宅地の造成、木材の伐採についての規制)
③建築基準法
ⅰ.集団規定
a)用途についての規定・・別添資料6①
特定行政庁の許可があればこの用途制限規定にかかわらず、建築物を建築することができる。また、敷地が2以上の用途地域にまたがるときは、過半の属する地域の用途制限を受ける。
b)建物の建ぺい率の制限・・別添資料6③の一部参照
・建ぺい率とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう(同法53条)
◇建ぺい率=建築物の建築面積÷敷地面積
・敷地が建ぺい率制限の異なる地域にわたる場合の取扱い
建物の敷地が建ぺい率の異なる規制数値である異なる複数の地域にわたる場合は、それぞれの地域の建ぺい率の最高限度の数値に、その地域に係る敷地が敷地全体に占める割合を乗じた数の合計が、その敷地全体の建ぺい率の最高限度となる。(加重平均)
・建物の敷地が防火地域の内外にわたる場合の取扱い
その敷地内の建物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして建ぺい率の緩和に関する規定を適用する。(同法53条)
c)建物の容積率の制限
・建物の敷地が、容積率の規制数値の異なる複数の地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率の最高限度の数値にその地域に係る敷地の敷地全体に占める割合を乗じた数値の合計が、その敷地全体の容積率の最高限度になる(加重平均)
・次の床面積は容積率算定上の延べ床面積に算入しなくてよい。
◇自動車車庫等の床面積で建築物の床面積の合計の5分の1までの面積
◇住宅用地の地階(天井が地盤面から高さ1m以下にあるもの)の床面積で建築物の住宅部分の床面積の合計の3分の1までの面積
◇共同住宅における共用廊下または階段(エレベーターそのものは除く)の床面積
・以下の建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率はその許可の範囲で緩和される。(同法52条)
◇その敷地の周囲に広い公園、広場、道路、その他の空地を有する建築物
◇同一敷地内の建築物の機械室、その他これに類する部分の床面積の合計が、建築物の延べ面積に対して、著しく大きい割合を有する場合。
d)建築物の高さに対する制限
道路斜線、隣地斜線、北側斜線の制限が適用された場合に一定の位置において確保される採光、通風等について一定の基準に適合する建築物については天空率による制限に適合した建物を工夫することにより、斜線制限を超えた高さの建物の建築が可能。
e)防火・準防火地域内の制限
以上、『役所調査/都市計画・用途地域確認』について、お話させていただきました。
次回は、『役所調査/道路の確認』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年09月26日
相続の事が少しずつ分かるいいお話176『登記記録以外の資料の調査』
本日は登記以外の資料の調査についてお話させていただきます。
1.登記記録以外の資料の調査
①地図・公図・地積測量図・建物図面
ⅰ.地図
不動産登記法14条は土地及び建物の所在、位置、区画を明らかにするため、図面(地図・建物所在図)を登記所に備えることとしており、この図面は測量された現地復元能力を有する図面であることとされ、この地図の整備には時間と費用を要するため、十分に備えつけは完了していません。
ⅱ.公図
公図とは、各筆の土地の区画及び地積を明確にした地図をいいます。
測量精度は高くありません。
登記された土地が現地のどこに位置し、その形状や区画がどのようなものであるか確認できるよう、この公図を不動産登記法では登記所に備えるようにしています。
ⅲ.地積測量図
土地の形状および面積測定の結果を示した図面です。
土地の表示登記、地積の変更の登記、土地の分筆または合筆の登記申請書に添付して提出するもので、すべての土地について存在するものではありません。
ⅳ.建物図面
建物の位置及び形状を明確にするために作成された図面です。
主たる建物または付属建物の別、付属建物の符号、各階の別、及び床面積等を記載しなければなりません。
②供給処理施設(インフラ)
ⅰ.上水道施設図
前面道路内に上水道菅が埋設されているか、敷地内に上水道が引き込まれているか、その上水道管の口径は何ミリのものが入っているか、かつ、その位置(現地で)を確認します。
口径(一般的に13mm)によっては引き込み直しが必要なときがあります。
ⅱ.下水道設備図
前面道路に下水道管が埋設されているか(埋設されていないとき浄化槽の種類)、敷地内の汚水枡の有無、かつ、その位置(現地で)を確認します。
ⅲ。ガス引き込み図
敷地内引き込み有無、かつ、その位置の確認
以上、『登記記録以外の資料の調査』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.登記記録以外の資料の調査
①地図・公図・地積測量図・建物図面
ⅰ.地図
不動産登記法14条は土地及び建物の所在、位置、区画を明らかにするため、図面(地図・建物所在図)を登記所に備えることとしており、この図面は測量された現地復元能力を有する図面であることとされ、この地図の整備には時間と費用を要するため、十分に備えつけは完了していません。
ⅱ.公図
公図とは、各筆の土地の区画及び地積を明確にした地図をいいます。
測量精度は高くありません。
登記された土地が現地のどこに位置し、その形状や区画がどのようなものであるか確認できるよう、この公図を不動産登記法では登記所に備えるようにしています。
ⅲ.地積測量図
土地の形状および面積測定の結果を示した図面です。
土地の表示登記、地積の変更の登記、土地の分筆または合筆の登記申請書に添付して提出するもので、すべての土地について存在するものではありません。
ⅳ.建物図面
建物の位置及び形状を明確にするために作成された図面です。
主たる建物または付属建物の別、付属建物の符号、各階の別、及び床面積等を記載しなければなりません。
②供給処理施設(インフラ)
ⅰ.上水道施設図
前面道路内に上水道菅が埋設されているか、敷地内に上水道が引き込まれているか、その上水道管の口径は何ミリのものが入っているか、かつ、その位置(現地で)を確認します。
口径(一般的に13mm)によっては引き込み直しが必要なときがあります。
ⅱ.下水道設備図
前面道路に下水道管が埋設されているか(埋設されていないとき浄化槽の種類)、敷地内の汚水枡の有無、かつ、その位置(現地で)を確認します。
ⅲ。ガス引き込み図
敷地内引き込み有無、かつ、その位置の確認
以上、『登記記録以外の資料の調査』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年09月24日
相続の事が少しずつ分かるいいお話175 『登記事項証明書等の見方』
本日は、『登記事項証明書等の見方』について、お話させていただきます。
1.登記事項証明書等の見方
登記事項証明書や登記簿謄本は、対象不動産の過去から現在への物理的変動及び権利関係の変動が記載されています。(移記されて閉鎖登記記録等の確認を要する場合もあります。)
また、記載は順位番号に古い順から新しい順に行われます。
したがって、新しい変動内容ほど順位番号が大きくなってきます。
①表題部
土地、建物の表示に関する事項が記載されます。
「地積」「床面積」の項目には過去から現在への地積・床面積の動きが表示されます。
その変動の原因は「原因及びその日付」の項目に、分筆・合筆・錯誤、または新築・増築などと表示されることとなります。(不動産番号とは不動産を識別するために1筆の土地又は1個の建物ごとに標題部に記録される番号、記号その他の符号で登記申請書等に不動産番号を記載すれば不動産の表示の記載を省略することができます。)
②権利部
ⅰ.甲区
所有権に関する事項が記載されます。
登記の目的(所有権の移転・差し押さえなど)、原因(売買、相続、代物弁済など)、共有の場合は、各共有分の各持分などが記載されています。
1つの不動産(1筆の土地・1個の建物)について2つ以上の所有権は存在しないので、最も順位番号の大きい欄に記載されている所有権が、現在の所有権を表示し、その記載より小さい順位番号に記載されている内容は、過去の所有者の変動が表示されることとなります。
ⅱ.乙区
所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
登記の目的(抵当権設定・地役権設定・賃借権設定など)、原因、債権額または極度額、共同担保目録番号、その他の条件や特約などが記載されます。
1つの不動産(1筆の土地・1個の建物)について2つ以上の抵当権が存在する(同順位または順位の異なる抵当権)場合もあります。
本日は、『登記事項証明書等の見方』について、お話させていただきました。
次回は、『登記記録以外の資料の調査』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.登記事項証明書等の見方
登記事項証明書や登記簿謄本は、対象不動産の過去から現在への物理的変動及び権利関係の変動が記載されています。(移記されて閉鎖登記記録等の確認を要する場合もあります。)
また、記載は順位番号に古い順から新しい順に行われます。
したがって、新しい変動内容ほど順位番号が大きくなってきます。
①表題部
土地、建物の表示に関する事項が記載されます。
「地積」「床面積」の項目には過去から現在への地積・床面積の動きが表示されます。
その変動の原因は「原因及びその日付」の項目に、分筆・合筆・錯誤、または新築・増築などと表示されることとなります。(不動産番号とは不動産を識別するために1筆の土地又は1個の建物ごとに標題部に記録される番号、記号その他の符号で登記申請書等に不動産番号を記載すれば不動産の表示の記載を省略することができます。)
②権利部
ⅰ.甲区
所有権に関する事項が記載されます。
登記の目的(所有権の移転・差し押さえなど)、原因(売買、相続、代物弁済など)、共有の場合は、各共有分の各持分などが記載されています。
1つの不動産(1筆の土地・1個の建物)について2つ以上の所有権は存在しないので、最も順位番号の大きい欄に記載されている所有権が、現在の所有権を表示し、その記載より小さい順位番号に記載されている内容は、過去の所有者の変動が表示されることとなります。
ⅱ.乙区
所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
登記の目的(抵当権設定・地役権設定・賃借権設定など)、原因、債権額または極度額、共同担保目録番号、その他の条件や特約などが記載されます。
1つの不動産(1筆の土地・1個の建物)について2つ以上の抵当権が存在する(同順位または順位の異なる抵当権)場合もあります。
本日は、『登記事項証明書等の見方』について、お話させていただきました。
次回は、『登記記録以外の資料の調査』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年09月21日
相続の事が少しずつ分かるいいお話174『宅建業法の無免許営業って・・』
本日は、宅地建物業法の『無免許営業』について、お話させていただきます。
宅建業法の無免許営業とは、宅地建物取引業の免許を持たない人が、広い宅地を所有していたとして、その宅地を区画割りして利益を目的として不特定多数のかたに売却する行為は、『宅地建物取引業』に該当することから、その区画割りして不特定多数の方に分譲した行為は、無免許で『宅地建物取引業』を行ったとして、無免許営業に該当することとなります。
その売買を不動産業者に仲介で依頼したものであっても、無免許営業に該当するというものでした。
ただ、その無免許営業については、何区画分譲したらそれに該当するかなどの明確な基準の定めはなく、各都道府県で、その取り扱いは異なるようです。
一部、厳しい都道府県では、2区画から無免許営業に該当することとしているようですし、反して20区画でも何も言われない都道府県もあるようです。
この無免許営業については、売主の地主さんへの罰則の規定はあるのですが、売主の地主さんへの罰則よりは、その仲介を行った不動産業者に対して『無免許営業幇助』による宅建業法による罰則が適用されることが多いようです。
土地の時価が毎年下落しているなか、広い土地を一括購入して分譲する不動産業者が減っているなか、広い土地を処分しなければならない地主さんにとっては、面倒なことです。
もっとも、自分で『宅地建物取引業』の免許を取得すればいいわけですが、試験をうけて合格後に店舗を準備してそのほか登録費用で約200万円程、かかってきます。
とても、毎年、継続的に売却したい一団の土地があればともかく、数年に一度程度の売却行為であればそこまでの手間と費用の負担は厳しいものでしょう。
土地の地価が右肩上がりから下落基調にかわってきたこの時代において、相続税の納付のために土地を売却しなければならないといったときに、一括で購入してくれる不動産業者が少なくなってきたことから価格を競わせるような有利な価格交渉も出来なくなってきたりとか、なかなか一括では売れなくなってきたりとか、厳しい局面を迎えています。
このように考えてくると、そもそも、自分の土地を細かく区画割りして不動産仲介業者に売却を依頼することに、何の問題が生じてくるのかが、疑問となってきます。
この無免許営業は、宅地建物取引業の免許のない者は土地の分譲を行ってはいけないということですが、その分譲をプロの不動産仲介業者が行えば売買契約の取引上は、何らの問題は生じないと考えます。
昔のように、売り易い時代から、売却困難な時代に変わったなか、宅建業法の見直しも必要ではないでしょうか?
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
宅建業法の無免許営業とは、宅地建物取引業の免許を持たない人が、広い宅地を所有していたとして、その宅地を区画割りして利益を目的として不特定多数のかたに売却する行為は、『宅地建物取引業』に該当することから、その区画割りして不特定多数の方に分譲した行為は、無免許で『宅地建物取引業』を行ったとして、無免許営業に該当することとなります。
その売買を不動産業者に仲介で依頼したものであっても、無免許営業に該当するというものでした。
ただ、その無免許営業については、何区画分譲したらそれに該当するかなどの明確な基準の定めはなく、各都道府県で、その取り扱いは異なるようです。
一部、厳しい都道府県では、2区画から無免許営業に該当することとしているようですし、反して20区画でも何も言われない都道府県もあるようです。
この無免許営業については、売主の地主さんへの罰則の規定はあるのですが、売主の地主さんへの罰則よりは、その仲介を行った不動産業者に対して『無免許営業幇助』による宅建業法による罰則が適用されることが多いようです。
土地の時価が毎年下落しているなか、広い土地を一括購入して分譲する不動産業者が減っているなか、広い土地を処分しなければならない地主さんにとっては、面倒なことです。
もっとも、自分で『宅地建物取引業』の免許を取得すればいいわけですが、試験をうけて合格後に店舗を準備してそのほか登録費用で約200万円程、かかってきます。
とても、毎年、継続的に売却したい一団の土地があればともかく、数年に一度程度の売却行為であればそこまでの手間と費用の負担は厳しいものでしょう。
土地の地価が右肩上がりから下落基調にかわってきたこの時代において、相続税の納付のために土地を売却しなければならないといったときに、一括で購入してくれる不動産業者が少なくなってきたことから価格を競わせるような有利な価格交渉も出来なくなってきたりとか、なかなか一括では売れなくなってきたりとか、厳しい局面を迎えています。
このように考えてくると、そもそも、自分の土地を細かく区画割りして不動産仲介業者に売却を依頼することに、何の問題が生じてくるのかが、疑問となってきます。
この無免許営業は、宅地建物取引業の免許のない者は土地の分譲を行ってはいけないということですが、その分譲をプロの不動産仲介業者が行えば売買契約の取引上は、何らの問題は生じないと考えます。
昔のように、売り易い時代から、売却困難な時代に変わったなか、宅建業法の見直しも必要ではないでしょうか?
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年09月20日
相続の事が少しずつ分かるいいお話173『財産コンサルタントと不動産コンサルタントの違い』
本日は、不動産コンサルタンンと財産コンサルタントとの違いについてお話させていただきます。
『不動産のコンサルタント業務』と『財産のコンサルタント業務』の違いについて、バードレポートというブログに非常に分かり易く掲載されていましたので、その内容をベースとしてご紹介させていただきます。
不動産コンサルタント業務は『客観的な不動産』を扱いますが、財産コンサルタント業務は『主観的な財産』を扱うものです。
例えば、ある土地があるとして、客観的に不動産としてみれば、用途地域や容積率等から3階建ての賃貸マンションの建築が最有効活用となる土地とします。
その土地をAさんが持っていた場合、老後の生活資金のため3階建てのアパートを建てるのがAさんにとっての『財産』としての最有効活用になることでしょう。
ところがもしその土地を大地主のBさんが持っていたとすれば、将来の相続税の納税のための建物を建てずに、駐車場にしておくことがBさんにとっての『財産』としての最有効活用ということもあるでしょう。
土地オーナーの皆様にとっては、賃貸マンション建築を代表とする『土地の有効活用』は『目的』ではないこととなります。
例えば『相続対策』が『目的)なのであって、『土地の有効活用』は『手段』なのです。言い換えれば『財産』としてその土地をどうするのかが『目的』であり、『不動産』としてその土地を活かすのかは『手段』となるのです。
そして、『財産コンサルタント』とは、クライアントの方の『目的』を、不動産調査や現状分析にもとづいて、顕在化させて、その対処の結果生じる不動産ニーズを建築売買等で実行支援させていただくものとなります。
その『財産コンサルタント』の手順としましては、次の通りとなってきます。
まず、クライアントの方から、親族関係・財産・所得ほかについての説明を受けます。次に路線価での相続税評価額と相続税額を算出し、相続税の納税が可能か、兄弟間の分割が可能かを検討します。
あらためて、クライアントの方に、その結果を報告し、建築・購入・売却・保険その他の対策案を提案させていただきます。
そのご提案は理詰めに根拠を示させていただくこととなります。
なぜこの土地にこういう建物を建てなくてはいけないのか、なぜこれを買わなくてはいけないのかと・・『そうしなくては、これこれの理由で相続税が払えなくなるからです。』といったような、『お願いですからこれを買ってください。』等の営業を目的としたものではありません。
そして検討とその説明を繰り返しながらその対策案を実行させていただくこととなります。
このようにして、納税・分割・節税のバランスを取りながら対策実行を行っていきます。
要は、クライアントの方のためになることを、クライアントの方のために提案し、実行させていただくということです。
※最後に、ここでいう『不動産コンサルタント業務』とは、あくまで、『手段』としてのご提案に留まっている業務を指していますので、不動産コンサルタントの名称の全てが、それに該当するものではありません。
不動産コンサルタントの名称のもと、当然『財産コンサルティング業務』を行っているケースも数多くありますのでお断りさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
『不動産のコンサルタント業務』と『財産のコンサルタント業務』の違いについて、バードレポートというブログに非常に分かり易く掲載されていましたので、その内容をベースとしてご紹介させていただきます。
不動産コンサルタント業務は『客観的な不動産』を扱いますが、財産コンサルタント業務は『主観的な財産』を扱うものです。
例えば、ある土地があるとして、客観的に不動産としてみれば、用途地域や容積率等から3階建ての賃貸マンションの建築が最有効活用となる土地とします。
その土地をAさんが持っていた場合、老後の生活資金のため3階建てのアパートを建てるのがAさんにとっての『財産』としての最有効活用になることでしょう。
ところがもしその土地を大地主のBさんが持っていたとすれば、将来の相続税の納税のための建物を建てずに、駐車場にしておくことがBさんにとっての『財産』としての最有効活用ということもあるでしょう。
土地オーナーの皆様にとっては、賃貸マンション建築を代表とする『土地の有効活用』は『目的』ではないこととなります。
例えば『相続対策』が『目的)なのであって、『土地の有効活用』は『手段』なのです。言い換えれば『財産』としてその土地をどうするのかが『目的』であり、『不動産』としてその土地を活かすのかは『手段』となるのです。
そして、『財産コンサルタント』とは、クライアントの方の『目的』を、不動産調査や現状分析にもとづいて、顕在化させて、その対処の結果生じる不動産ニーズを建築売買等で実行支援させていただくものとなります。
その『財産コンサルタント』の手順としましては、次の通りとなってきます。
まず、クライアントの方から、親族関係・財産・所得ほかについての説明を受けます。次に路線価での相続税評価額と相続税額を算出し、相続税の納税が可能か、兄弟間の分割が可能かを検討します。
あらためて、クライアントの方に、その結果を報告し、建築・購入・売却・保険その他の対策案を提案させていただきます。
そのご提案は理詰めに根拠を示させていただくこととなります。
なぜこの土地にこういう建物を建てなくてはいけないのか、なぜこれを買わなくてはいけないのかと・・『そうしなくては、これこれの理由で相続税が払えなくなるからです。』といったような、『お願いですからこれを買ってください。』等の営業を目的としたものではありません。
そして検討とその説明を繰り返しながらその対策案を実行させていただくこととなります。
このようにして、納税・分割・節税のバランスを取りながら対策実行を行っていきます。
要は、クライアントの方のためになることを、クライアントの方のために提案し、実行させていただくということです。
※最後に、ここでいう『不動産コンサルタント業務』とは、あくまで、『手段』としてのご提案に留まっている業務を指していますので、不動産コンサルタントの名称の全てが、それに該当するものではありません。
不動産コンサルタントの名称のもと、当然『財産コンサルティング業務』を行っているケースも数多くありますのでお断りさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年09月18日
相続の事が少しずつ分かるいいお話172『不動産現状分析方法③』
本日は、『不動産現状分析方法③』について、お話させていただきます。
本日は、不動産現状分析における登記記録の調査についてのお話です。
不動産については、所有者がだれであるかを確認することは、すごく、重要なことであり、その確認は登記事項証明書により確認することとなります。
1.登記記録の調査
①所有者
対象となる不動産の所有者について、登記事項が記載された登記事項証明書の交付を受ける等により確認します。
現地に居住していても、相続登記が未了で依頼者等の所有名義となっていない場合もあります。
また。所有者確認のために固定資産税評価証明書を依頼者等に求めることが必要となることもあります。
②所有権以外の権利
借地権の場合は、土地の登記記録には登録されていないことがほとんどです。
借地権の対抗力は建物の登記によって与えられますし、ほとんどの地主さんは借地権の登記には同意しないことが多いからです。
また、通行権は地役権の登記はされていない場合があります。
なお、私道に面している土地は私道について共有持分等を有しているかの調査が必要となります。
2.登記記録の調査方法
①登記事項証明書の交付等
だれでも登記所において手数料を納付して登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面)および登記事項要約書(登記記録に記録されている事項の概要を記した書面)の交付を請求することができます。
登記事項証明書等の交付請求や登記簿謄抄本の交付申請や閲覧申請等は、土地の場合は『地番』、家屋の場合は『家屋番号』を記載することとなります。
『地番』が不明な場合は、公図と住宅地図を照らし併せて把握します。
『家屋番号』が不明な場合は、所有者または地番上の建物で申請する場合もあります。
なお、登記記録の記載内容は、必ずしも真実の物理的状況・真実の権利関係が記載されているとは限りません。
例えば、現況が『宅地』であるのに土地の地目が『畑』として登記されている場合や、現実の所有者名が登記記録における所有者と違っている場合もあります。
以上、『不動産現状分析方法③』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
本日は、不動産現状分析における登記記録の調査についてのお話です。
不動産については、所有者がだれであるかを確認することは、すごく、重要なことであり、その確認は登記事項証明書により確認することとなります。
1.登記記録の調査
①所有者
対象となる不動産の所有者について、登記事項が記載された登記事項証明書の交付を受ける等により確認します。
現地に居住していても、相続登記が未了で依頼者等の所有名義となっていない場合もあります。
また。所有者確認のために固定資産税評価証明書を依頼者等に求めることが必要となることもあります。
②所有権以外の権利
借地権の場合は、土地の登記記録には登録されていないことがほとんどです。
借地権の対抗力は建物の登記によって与えられますし、ほとんどの地主さんは借地権の登記には同意しないことが多いからです。
また、通行権は地役権の登記はされていない場合があります。
なお、私道に面している土地は私道について共有持分等を有しているかの調査が必要となります。
2.登記記録の調査方法
①登記事項証明書の交付等
だれでも登記所において手数料を納付して登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面)および登記事項要約書(登記記録に記録されている事項の概要を記した書面)の交付を請求することができます。
登記事項証明書等の交付請求や登記簿謄抄本の交付申請や閲覧申請等は、土地の場合は『地番』、家屋の場合は『家屋番号』を記載することとなります。
『地番』が不明な場合は、公図と住宅地図を照らし併せて把握します。
『家屋番号』が不明な場合は、所有者または地番上の建物で申請する場合もあります。
なお、登記記録の記載内容は、必ずしも真実の物理的状況・真実の権利関係が記載されているとは限りません。
例えば、現況が『宅地』であるのに土地の地目が『畑』として登記されている場合や、現実の所有者名が登記記録における所有者と違っている場合もあります。
以上、『不動産現状分析方法③』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年09月17日
相続の事が少しずつ分かるいいお話171『不動産現状分析方法②』
本日は、『不動産の現状分析方法②』についてを、お話しさせていただきます。
本日は、不動産現状分析方法のうち、現地調査についてのお話をさせていただきます。
1.現地調査
①交通・接近状況
最寄り駅や、駅からのルートについて調査します。
駅からの距離、バス便であれば最寄駅からの時間、バス停からの距離を調査します。
②市場性等
貸ビル、賃貸マンションまたはアパートの建設の場合など、賃貸需要がどの程度見込めるか、現地や周辺の状況を調査します。
必要な場合は、地元不動産業者に聞き込みを行ったりします。
③現地の状況
現地は更地か、または建物が建っているかを確認します。
新たに建物を建設する場合に解体撤去に要する期間や費用を調査します。
④地形、地勢
土地の形状や傾斜、高低差などを、おおよそ目視で確認します。
⑤境界
現地には境界杭があるのか、塀などに境界らしきペイントがなされているのかを確認します。
土地の売却の場合はもちろん、建物を建築する際も境界を確定する必要が生じます。
また、越境物はないかどうかも確認します。
⑥道路
接道状況はどうなっているか、接道状況によっては共同住宅等の建設ができない場合があるので注意を要します。
また、対象となる土地には、隣地の通行の用に供されている部分はないか、袋地通行権の対象となる無道路地を囲んでいるほうの土地ではないか、等々、権利関係調査のまえに目視で確認します。
⑦生活関連施設
ⅰ.上水道
前面道路の埋設状況の確認(公営か民営か)、水道管の口径の確認(何mmか)、井戸か敷地内に引き込み済みか、かつ、その位置の確認等をします。
ⅱ.下水道
本下水対応か、浄化槽対応か、本下水対応地域の時、前面道路の埋設は、かつ、敷地内に汚水枡の引き込み済みか、かつ、その位置の確認をします。
ⅲ.ガス
都市ガスかプロパンガスかの確認をします。
ⅳ.電気
電柱の位置、敷地内の電柱の有無の確認をします。
以上、『不動産現状分析方法』のうち現地調査について、お話させていただきました。
次回は、引き続き『不動産現状分析方法③』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
本日は、不動産現状分析方法のうち、現地調査についてのお話をさせていただきます。
1.現地調査
①交通・接近状況
最寄り駅や、駅からのルートについて調査します。
駅からの距離、バス便であれば最寄駅からの時間、バス停からの距離を調査します。
②市場性等
貸ビル、賃貸マンションまたはアパートの建設の場合など、賃貸需要がどの程度見込めるか、現地や周辺の状況を調査します。
必要な場合は、地元不動産業者に聞き込みを行ったりします。
③現地の状況
現地は更地か、または建物が建っているかを確認します。
新たに建物を建設する場合に解体撤去に要する期間や費用を調査します。
④地形、地勢
土地の形状や傾斜、高低差などを、おおよそ目視で確認します。
⑤境界
現地には境界杭があるのか、塀などに境界らしきペイントがなされているのかを確認します。
土地の売却の場合はもちろん、建物を建築する際も境界を確定する必要が生じます。
また、越境物はないかどうかも確認します。
⑥道路
接道状況はどうなっているか、接道状況によっては共同住宅等の建設ができない場合があるので注意を要します。
また、対象となる土地には、隣地の通行の用に供されている部分はないか、袋地通行権の対象となる無道路地を囲んでいるほうの土地ではないか、等々、権利関係調査のまえに目視で確認します。
⑦生活関連施設
ⅰ.上水道
前面道路の埋設状況の確認(公営か民営か)、水道管の口径の確認(何mmか)、井戸か敷地内に引き込み済みか、かつ、その位置の確認等をします。
ⅱ.下水道
本下水対応か、浄化槽対応か、本下水対応地域の時、前面道路の埋設は、かつ、敷地内に汚水枡の引き込み済みか、かつ、その位置の確認をします。
ⅲ.ガス
都市ガスかプロパンガスかの確認をします。
ⅳ.電気
電柱の位置、敷地内の電柱の有無の確認をします。
以上、『不動産現状分析方法』のうち現地調査について、お話させていただきました。
次回は、引き続き『不動産現状分析方法③』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)