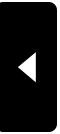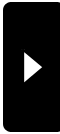PR
2013年04月17日
相続の事が少しずつ分かるいいお話95 『自筆証書遺言②』
本日は、前回に引き続き、『自筆証書遺言』の続きを、お話させていただきます。
1 書式、用紙、筆記用具の注意点
書式については法に定められた特別な書き方というものはありません。
重要なことは、遺言であるということをはっきりさせることにありますので、標題には『遺言書』と書くことが大事です。
用紙は、便箋でも、半紙でも、原稿用紙や罫紙でも、文字は書けるものであれば何でもOKです。極論、ノートや日記などに記載してもOKですが、単なる下書きや覚え書きではないかとの疑問をもたれる恐れがありますので、遺言書としての本質性を疑われる可能性があることから、お奨めはできないと言われています。
また、遺言の内容を記載した用紙が数枚になるときは、ホチキスやのりづけ等でとじたうえで割印を押印しておくとよろしいでしょう。
筆記用具は、筆、ボールペン、万年筆など、特に定められたものはなく、全くの自由となります。
ただし、鉛筆は消えてしまうことがありますので、避けた方がよろしいでしょう。
2 日付の注意点
遺言書には、年、月、日を必ず、自署で記載してください。日付印を打ったものは遺言書全体が無効となります。
日付は、西暦でも元号でもどちらでもかまいません。
日付の記載それ自体から客観的に遺言をした年月日が特定できればよく、遺言者の『喜寿の日』とか『70歳の誕生日』とかの記載のしかたでも有効となります。
しかし『○年○月吉日』のような書き方は、吉日は客観的なものではなく、また同じ日でも複数あることから無効とされます。わざわざ、紛らわしい遺言の記載をすることもないので、喜寿の日と書いた場合でも、さらに年月日をきちんと書いておいた方が、無難でしょう。
本日は、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。
次回も引き続き、『自筆証書遺言』の氏名や印についてのお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 書式、用紙、筆記用具の注意点
書式については法に定められた特別な書き方というものはありません。
重要なことは、遺言であるということをはっきりさせることにありますので、標題には『遺言書』と書くことが大事です。
用紙は、便箋でも、半紙でも、原稿用紙や罫紙でも、文字は書けるものであれば何でもOKです。極論、ノートや日記などに記載してもOKですが、単なる下書きや覚え書きではないかとの疑問をもたれる恐れがありますので、遺言書としての本質性を疑われる可能性があることから、お奨めはできないと言われています。
また、遺言の内容を記載した用紙が数枚になるときは、ホチキスやのりづけ等でとじたうえで割印を押印しておくとよろしいでしょう。
筆記用具は、筆、ボールペン、万年筆など、特に定められたものはなく、全くの自由となります。
ただし、鉛筆は消えてしまうことがありますので、避けた方がよろしいでしょう。
2 日付の注意点
遺言書には、年、月、日を必ず、自署で記載してください。日付印を打ったものは遺言書全体が無効となります。
日付は、西暦でも元号でもどちらでもかまいません。
日付の記載それ自体から客観的に遺言をした年月日が特定できればよく、遺言者の『喜寿の日』とか『70歳の誕生日』とかの記載のしかたでも有効となります。
しかし『○年○月吉日』のような書き方は、吉日は客観的なものではなく、また同じ日でも複数あることから無効とされます。わざわざ、紛らわしい遺言の記載をすることもないので、喜寿の日と書いた場合でも、さらに年月日をきちんと書いておいた方が、無難でしょう。
本日は、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。
次回も引き続き、『自筆証書遺言』の氏名や印についてのお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月14日
相続の事が少しずつ分かるいいお話94 『自筆証書遺言』
本日は、遺言の方式のうち、『自筆証書遺言』について、お話させていただきます。
1 自筆証書遺言の作成について
必ず自分で書くことが必要です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、遺言書の作成日付、氏名等を自分で手書きし、押印して作成します。つまり、全部を自分で書くことが必要となります。
自筆証書遺言では、遺言者の真意を確保するべく、偽造・変造を防ぐため、自書を求めています。
すなわち、パソコン・ワープロで作成した遺言書は、遺言者自身が作ったものであることを証明しても自筆証書遺言とは認められないこととなります。
また、手が震えるなどして思うように書けない人は、手を支えてもらって自書を援助してもらうことはかまいませせん。ただし、手を支えている人が作為的に遺言者の真意とは異なる言葉を記載する危険性もあることから、過去の最高裁の判決では、手を支えていた人の意思が介入した形跡のないことを、筆跡の上で判定できた場合に限って自書といえることとしています。
のちのちのトラブルの危険性を考えると、十分に字を書けない人には公正証書遺言の作成をおすすめします。
以上、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。
次回も、『自筆証書遺言』について(書式、用紙、筆記器具等)お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 自筆証書遺言の作成について
必ず自分で書くことが必要です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、遺言書の作成日付、氏名等を自分で手書きし、押印して作成します。つまり、全部を自分で書くことが必要となります。
自筆証書遺言では、遺言者の真意を確保するべく、偽造・変造を防ぐため、自書を求めています。
すなわち、パソコン・ワープロで作成した遺言書は、遺言者自身が作ったものであることを証明しても自筆証書遺言とは認められないこととなります。
また、手が震えるなどして思うように書けない人は、手を支えてもらって自書を援助してもらうことはかまいませせん。ただし、手を支えている人が作為的に遺言者の真意とは異なる言葉を記載する危険性もあることから、過去の最高裁の判決では、手を支えていた人の意思が介入した形跡のないことを、筆跡の上で判定できた場合に限って自書といえることとしています。
のちのちのトラブルの危険性を考えると、十分に字を書けない人には公正証書遺言の作成をおすすめします。
以上、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。
次回も、『自筆証書遺言』について(書式、用紙、筆記器具等)お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月13日
相続の事が少しずつ分かるいいお話93 『遺言の方式Ⅱ』
本日も遺言の形式についてお話させていただきます。
1 公正証書遺言が安心
通常、遺言をしようとする場合には、自筆証書、公正証書、秘密証書の三つの方式があります。
自筆証書遺言は、証人の必要がなく、1人でいつでも自由に作れ、費用もいらないという利点があります。反面、書き方をよく知らないために形式が不備となり、法律上の効力が生じないことがあります。また、せっかく作った遺言書が紛失したり発見されなかったり隠匿されたり、誰かに変造される危険性もあります。本当に本人が書いたのか(偽造ではないか)というトラブルがおきることもあります。自筆証書遺言はすべて自分で書かねばなりませんので、字の書けない人は公正証書遺言によらざるをえません。
秘密証書遺言は、誰にも内容を知れずに遺言書を作れる点が長所です。しかし、この遺言書は、公証役場に保存されるものではないので、紛失したり、誰かにもちだされたり、破り捨てられる危険があります。
公正証書遺言には、次のような利点があります。
①遺言書の原本は遺言の時から二〇年間(さらに遺言者が一〇〇歳に達するまで)公証役場に保存されますので、遺言書の紛失、盗難、偽造、変造という心配がありません。
②公証人は、この道の専門家ですから、方式が不備な遺言とか趣旨が不明な遺言を作ることは、まず考えられませんので、遺言の方式や内容をめぐって後日トラブルを生じる余地は少ないと考えられます。
③公正証書遺言は、自筆証書遺言などのように、遺言者死亡後に相続人らが家庭裁判所へ行って検認手続をとる必要もありません。
④公正証書遺言は、遺言の内容を遺言者がこ口授(口頭で述べること)し、公証人が筆記して作るものですから、字の書けない人でも遺言することができます。
⑤また口が不自由な人の場合は、通訳人の通訳か自署により、口授に代えることができます。耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えることで、読み聞かせに代えることができます。
反して公正証書遺言には、次のような短所があります。
①遺言の際に証人の立会が必要ですので、遺言の内容を証人には知れてしまいます。
誰にも内容を知れずに遺言をしたいという人は秘密証書遺言によるのが適当です。
②たいした負担ではないものの、若干の手間と費用がかかかります。
③ひんぱんに書き換える人は、自筆証書遺言がむいていると思われます。
以上のことを考えますと、公正証書遺言が、短所はあるものの総合的には安心感の高い遺言と思います。
以上、『遺言の方式』について、お話させていただきました。
次回も引き続き、『遺言の方式』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 公正証書遺言が安心
通常、遺言をしようとする場合には、自筆証書、公正証書、秘密証書の三つの方式があります。
自筆証書遺言は、証人の必要がなく、1人でいつでも自由に作れ、費用もいらないという利点があります。反面、書き方をよく知らないために形式が不備となり、法律上の効力が生じないことがあります。また、せっかく作った遺言書が紛失したり発見されなかったり隠匿されたり、誰かに変造される危険性もあります。本当に本人が書いたのか(偽造ではないか)というトラブルがおきることもあります。自筆証書遺言はすべて自分で書かねばなりませんので、字の書けない人は公正証書遺言によらざるをえません。
秘密証書遺言は、誰にも内容を知れずに遺言書を作れる点が長所です。しかし、この遺言書は、公証役場に保存されるものではないので、紛失したり、誰かにもちだされたり、破り捨てられる危険があります。
公正証書遺言には、次のような利点があります。
①遺言書の原本は遺言の時から二〇年間(さらに遺言者が一〇〇歳に達するまで)公証役場に保存されますので、遺言書の紛失、盗難、偽造、変造という心配がありません。
②公証人は、この道の専門家ですから、方式が不備な遺言とか趣旨が不明な遺言を作ることは、まず考えられませんので、遺言の方式や内容をめぐって後日トラブルを生じる余地は少ないと考えられます。
③公正証書遺言は、自筆証書遺言などのように、遺言者死亡後に相続人らが家庭裁判所へ行って検認手続をとる必要もありません。
④公正証書遺言は、遺言の内容を遺言者がこ口授(口頭で述べること)し、公証人が筆記して作るものですから、字の書けない人でも遺言することができます。
⑤また口が不自由な人の場合は、通訳人の通訳か自署により、口授に代えることができます。耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えることで、読み聞かせに代えることができます。
反して公正証書遺言には、次のような短所があります。
①遺言の際に証人の立会が必要ですので、遺言の内容を証人には知れてしまいます。
誰にも内容を知れずに遺言をしたいという人は秘密証書遺言によるのが適当です。
②たいした負担ではないものの、若干の手間と費用がかかかります。
③ひんぱんに書き換える人は、自筆証書遺言がむいていると思われます。
以上のことを考えますと、公正証書遺言が、短所はあるものの総合的には安心感の高い遺言と思います。
以上、『遺言の方式』について、お話させていただきました。
次回も引き続き、『遺言の方式』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月12日
相続の事が少しずつ分かるいいお話92 『遺言の方式』
本日は、『遺言の方式』について、お話させていただきます。
2.遺言の方式
遺言の方式には大きく分けてⅠ普通方式とⅡ特別方式とに分かれます。
Ⅰ普通方式はさらに、①自筆証書遺言方式、②公正証書遺言方式、③秘密証書遺言に分かれます。
①自筆証書遺言とは、遺言者が遺言全文、日付、氏名を自署し、印を押す方式です。
②公正証書遺言とは、公証人が作成する方式です。遺言者が外国にいる場合は、日本国領事が公証人の職務を行い、作成します。
③秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名し印を押し(遺言者の署名以外の部分は、自書でなくてもよく、他人に書いてもらっても、ワープロで打ってもかまいません)、その遺言書を封入して遺言書に押した印と同じ印で封印したうえ、証人二人の立会いのうえ公証人に提出して、それが自分の遺言書であること、自筆でないときは、遺言の内容を書いた者の氏名と住所を公証人に申述して行う方式です。実際にはほとんど用いられていないのが現状です。
Ⅱ特別方式は遺言者が重病で死亡が迫っているときとか、伝染病などで一般社会と隔絶した場所にいるとかの理由で普通の方式ができない場合に認められる簡便な方式です。
実際に問題となるのは死亡危急時遺言(臨終遺言)ですが、死亡危急死遺言とは、次の様な遺言となります。
①危急時遺言
病気などのため客観的に死亡が危急に迫った場合、口頭で遺言することが認められています。この場合は、①証人3人以上の立会いのもとで、②その1人に遺言の趣旨を口頭で述べ、③その証人がこれを筆記し、④遺言者と他の証人に読み聞かせ、⑤各証人が筆記の正確なことを承認した後署名押印します。遺言者は署名も押印もいりません。
この方式によった場合には、遺言の日から二〇日以内に家庭裁判所の確認をえなければ効力を生じません。
また、証人についても条件があり、一定の人は証人になれません。
緊急事態ですから証人の印は拇印でかまいません。
3.方式を守っていない由比銀の効力
以上の方式に従わない遺言は、法律上の効力が認められません。日付の記載のない自筆証書遺言や、テープによる遺言、臨終の際に相続人だけに口頭で述べたことなどは、いずれも法律上無効です。そのようなものは、偽造・変造のおそれがあったり歪曲して伝えられる危険が有ったりするので、強い効力を持たせることが出来なくなります。
しかし、相続人が死者の意思を尊重することは何ら差し支えありませんから、方式を守っていない遺言であっても、それが遺言者の意思と認められる以上は、それによって遺産分割の協議をすることができます。
以上、本日は『遺言の方式』について、お話させていただきました。
次回も、『遺言の方式Ⅱ』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2.遺言の方式
遺言の方式には大きく分けてⅠ普通方式とⅡ特別方式とに分かれます。
Ⅰ普通方式はさらに、①自筆証書遺言方式、②公正証書遺言方式、③秘密証書遺言に分かれます。
①自筆証書遺言とは、遺言者が遺言全文、日付、氏名を自署し、印を押す方式です。
②公正証書遺言とは、公証人が作成する方式です。遺言者が外国にいる場合は、日本国領事が公証人の職務を行い、作成します。
③秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名し印を押し(遺言者の署名以外の部分は、自書でなくてもよく、他人に書いてもらっても、ワープロで打ってもかまいません)、その遺言書を封入して遺言書に押した印と同じ印で封印したうえ、証人二人の立会いのうえ公証人に提出して、それが自分の遺言書であること、自筆でないときは、遺言の内容を書いた者の氏名と住所を公証人に申述して行う方式です。実際にはほとんど用いられていないのが現状です。
Ⅱ特別方式は遺言者が重病で死亡が迫っているときとか、伝染病などで一般社会と隔絶した場所にいるとかの理由で普通の方式ができない場合に認められる簡便な方式です。
実際に問題となるのは死亡危急時遺言(臨終遺言)ですが、死亡危急死遺言とは、次の様な遺言となります。
①危急時遺言
病気などのため客観的に死亡が危急に迫った場合、口頭で遺言することが認められています。この場合は、①証人3人以上の立会いのもとで、②その1人に遺言の趣旨を口頭で述べ、③その証人がこれを筆記し、④遺言者と他の証人に読み聞かせ、⑤各証人が筆記の正確なことを承認した後署名押印します。遺言者は署名も押印もいりません。
この方式によった場合には、遺言の日から二〇日以内に家庭裁判所の確認をえなければ効力を生じません。
また、証人についても条件があり、一定の人は証人になれません。
緊急事態ですから証人の印は拇印でかまいません。
3.方式を守っていない由比銀の効力
以上の方式に従わない遺言は、法律上の効力が認められません。日付の記載のない自筆証書遺言や、テープによる遺言、臨終の際に相続人だけに口頭で述べたことなどは、いずれも法律上無効です。そのようなものは、偽造・変造のおそれがあったり歪曲して伝えられる危険が有ったりするので、強い効力を持たせることが出来なくなります。
しかし、相続人が死者の意思を尊重することは何ら差し支えありませんから、方式を守っていない遺言であっても、それが遺言者の意思と認められる以上は、それによって遺産分割の協議をすることができます。
以上、本日は『遺言の方式』について、お話させていただきました。
次回も、『遺言の方式Ⅱ』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月08日
相続の事が少しずつ分かるいいお話91 『遺言の内容Ⅳ』
今日は、『遺言の内容』について、引き続き、お話させていただきます。
1 相続人の廃除、認知
【廃除】
相続人の廃除とは、配偶者や子などの推定相続人が、被相続人に対し虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行をしたりする場合に、相続権を剥奪することです。
廃除は遺言しただけで効力が生ずるのではなく、家庭裁判所の審判ではじめて決まります。そこで、廃除の遺言をする場合は、必ず遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は、遺言者死亡後遅滞なく家庭裁判所に廃除の審判の申し立てをしなければなりません。審判時には遺言者はいませんので、廃除の理由についての証拠は生前に保存しておかなければなりません。
【認知】
認知とは、父親が、妻以外の人との間にもうけた子(胎児も含む)を自分の子として認めることで、戸籍上の届出によって行います。
遺言によっては認知する場合は、遺言者の死亡によって効力を生じますが、遺言執行者が戸籍上の届出をしなければなりません。
認知された子は、子として父親の相続人となります。ただし、結婚外で生まれた子であるため「非嫡出子」といって、相続分は妻が産んだ嫡出子の二分の一です。これを変えたいときは、遺言で相続分の指定か遺贈をします。
妻に言えない隠し子を遺言で認知するというのは、被嫡出子の人権からみれば、認知しないよりましともいえますが、妻や嫡出の子たちにとっては、予期しない相続人が突然あらわれることになるのでトラブルになる可能性が大きいことです。
認知の届出を相続人に任せずに、遺言執行者を選任して、その者にさせることにしているのはそのためですから、遺言の際必ず遺言執行者を指定しておきましょう。
本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきました。
次回も、『遺言の内容』の続きについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 相続人の廃除、認知
【廃除】
相続人の廃除とは、配偶者や子などの推定相続人が、被相続人に対し虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行をしたりする場合に、相続権を剥奪することです。
廃除は遺言しただけで効力が生ずるのではなく、家庭裁判所の審判ではじめて決まります。そこで、廃除の遺言をする場合は、必ず遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は、遺言者死亡後遅滞なく家庭裁判所に廃除の審判の申し立てをしなければなりません。審判時には遺言者はいませんので、廃除の理由についての証拠は生前に保存しておかなければなりません。
【認知】
認知とは、父親が、妻以外の人との間にもうけた子(胎児も含む)を自分の子として認めることで、戸籍上の届出によって行います。
遺言によっては認知する場合は、遺言者の死亡によって効力を生じますが、遺言執行者が戸籍上の届出をしなければなりません。
認知された子は、子として父親の相続人となります。ただし、結婚外で生まれた子であるため「非嫡出子」といって、相続分は妻が産んだ嫡出子の二分の一です。これを変えたいときは、遺言で相続分の指定か遺贈をします。
妻に言えない隠し子を遺言で認知するというのは、被嫡出子の人権からみれば、認知しないよりましともいえますが、妻や嫡出の子たちにとっては、予期しない相続人が突然あらわれることになるのでトラブルになる可能性が大きいことです。
認知の届出を相続人に任せずに、遺言執行者を選任して、その者にさせることにしているのはそのためですから、遺言の際必ず遺言執行者を指定しておきましょう。
本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきました。
次回も、『遺言の内容』の続きについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月07日
相続の事が少しずつ分かるいいお話90 『遺言の内容Ⅲ』
本日は、前回に続いて『遺言の内容」の続きについて、お話させていただきます。
1 遺贈について、相続人以外のものに財産を譲ろうとするとき
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲与することをいいます。贈与に似ているようですが、遺贈の場合は、相続税として納税することとなり、贈与税より税金がずっと安くなるなどの違いがあります。このことから、相続人以外に財産を譲る場合には、遺贈によるのが良い選択でしょう。
①遺産の何割をあげるというような遺言を遺すことを包括遺贈といいます。
相続人以外の人に対して、『遺産の3割をあげる」とか、『遺産の4分の1を与える』等のように割合で示したものを包括遺贈といいます。
包括遺贈は、その内容から、遺言によって相続人を作り出すこととなります。すなわち、包括受遺者(遺言より財産をもらう人)は『相続人と同一の権利義務を有する』ので、被相続人の債務も承継し、それがいやなら、限定承認や放棄をすることも自由です。この場合の期間や手続きなどは相続の限定承認や放棄と同様の決まりとなります。
また、具体的に財産を取得するためには、相続人間と遺産分割協議を行う必要が有ります。
法定相続人以外の人(たとえば内縁の妻、長男の妻、子供があるときの親・兄弟など)に財産を取得させたいときはこの方法か特定遺贈によることが宜しいでしょう。
相続人以外のある人に全財産をあげるという包括遺贈も原則として有効です。相続人から遺留分減殺請求がなされることがあるだけですが、不倫な関係を維持するためになされた場合などは、公序良俗違反として無効とされることがあります。
以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。
次回も引き続き、『遺言の内容』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 遺贈について、相続人以外のものに財産を譲ろうとするとき
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲与することをいいます。贈与に似ているようですが、遺贈の場合は、相続税として納税することとなり、贈与税より税金がずっと安くなるなどの違いがあります。このことから、相続人以外に財産を譲る場合には、遺贈によるのが良い選択でしょう。
①遺産の何割をあげるというような遺言を遺すことを包括遺贈といいます。
相続人以外の人に対して、『遺産の3割をあげる」とか、『遺産の4分の1を与える』等のように割合で示したものを包括遺贈といいます。
包括遺贈は、その内容から、遺言によって相続人を作り出すこととなります。すなわち、包括受遺者(遺言より財産をもらう人)は『相続人と同一の権利義務を有する』ので、被相続人の債務も承継し、それがいやなら、限定承認や放棄をすることも自由です。この場合の期間や手続きなどは相続の限定承認や放棄と同様の決まりとなります。
また、具体的に財産を取得するためには、相続人間と遺産分割協議を行う必要が有ります。
法定相続人以外の人(たとえば内縁の妻、長男の妻、子供があるときの親・兄弟など)に財産を取得させたいときはこの方法か特定遺贈によることが宜しいでしょう。
相続人以外のある人に全財産をあげるという包括遺贈も原則として有効です。相続人から遺留分減殺請求がなされることがあるだけですが、不倫な関係を維持するためになされた場合などは、公序良俗違反として無効とされることがあります。
以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。
次回も引き続き、『遺言の内容』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月06日
相続の事が少しずつ分かるいいお話89 『遺言の内容Ⅱ』
本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきます。
1 遺産分割方法の指定⇒分割のトラブル防止策
◇何をあげるかを具体的に指定する。
遺産分割方法の指定とは、土地・建物は妻に、預貯金と株券は長男に、預貯金の一部は長女というように、財産分配の方法を定めるものです。遺産の全部について指定することもできますし、一部だけを指定することもできます。
全部について分割方法を指定しておけば、遺産分割をめぐる相続人のトラブルは未然に防げることになりますので、分割のトラブル防止方法としてお奨めです。
なお、上記の例で、長男の取得する預貯金と株の価額が、長男の法定相続分を上まっている場合には、相続分の指定(法定相続分の変更)の内容を抱合することとなります。
法定相続分は遺言で事由に変えることができますので、このような指定は有効となります。
ただし、他の相続人の遺留分(原則は法定相続分の2分の1、その他例外あり)を侵害してしまう場合は、遺留分減殺請求を受けることがありあます。
遺産分割方法の指定は、遺言により第三者に依頼することもできます。
分割方法の指定だけを依頼すると、その依頼を受けた人は、法定相続分に従って分割方法を定めることとなります。
なお、土地・建物を共有とする遺言も可能です。
一筆の土地を2人以上の相続人に与える場合には、予め分筆をしておき、各人に一筆づつ指定するのが争いを避けるためによい方法です。
建物の敷地に供されていて、分割出来ない土地は、共有にすることもできます。
以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。
次回も、『遺言の内容』の続きについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 遺産分割方法の指定⇒分割のトラブル防止策
◇何をあげるかを具体的に指定する。
遺産分割方法の指定とは、土地・建物は妻に、預貯金と株券は長男に、預貯金の一部は長女というように、財産分配の方法を定めるものです。遺産の全部について指定することもできますし、一部だけを指定することもできます。
全部について分割方法を指定しておけば、遺産分割をめぐる相続人のトラブルは未然に防げることになりますので、分割のトラブル防止方法としてお奨めです。
なお、上記の例で、長男の取得する預貯金と株の価額が、長男の法定相続分を上まっている場合には、相続分の指定(法定相続分の変更)の内容を抱合することとなります。
法定相続分は遺言で事由に変えることができますので、このような指定は有効となります。
ただし、他の相続人の遺留分(原則は法定相続分の2分の1、その他例外あり)を侵害してしまう場合は、遺留分減殺請求を受けることがありあます。
遺産分割方法の指定は、遺言により第三者に依頼することもできます。
分割方法の指定だけを依頼すると、その依頼を受けた人は、法定相続分に従って分割方法を定めることとなります。
なお、土地・建物を共有とする遺言も可能です。
一筆の土地を2人以上の相続人に与える場合には、予め分筆をしておき、各人に一筆づつ指定するのが争いを避けるためによい方法です。
建物の敷地に供されていて、分割出来ない土地は、共有にすることもできます。
以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。
次回も、『遺言の内容』の続きについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月05日
相続の事が少しずつ分かるいいお話88 『遺言の内容』
本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきます。
1 相続分の指定・・・長男や妻に多くを遺す方法
相続分指定とは、遺言で法定相続分を変更することをいいます。
これは遺言でしかすることはできません。
相続人の一人または全員について、割合で指定するのが通常で、妻に全財産を相続させるなどというのも、本来相続分の指定ですが、判例は遺産分割を待たずに権利移転するという強い効果を認めています。
相続人のうちの一部の者の相続分だけを指定したときは、他の相続人の相続分は法定相続分によることになります。たとえば子A、B、Cがあるとき『Cに二分の一を相続させる』という指定をすると、残り二分の一を、子A、Bが均等に分けることになります。この場合妻がいたとすると複雑になります。妻の相続分は子と独立だという考え方があるため、妻が二分の一(残り全部)をとって、子A、Bはゼロだとされる可能性があるのです。このようなことまで考えて遺言しているとも思えず、争いになる可能性があります。このような混乱を避けるためには、全員について指定することが無難な方法といえます。
相続分の指定は第三者に委託することもできます。
なお、相続分の指定が他の相続人の遺留品を侵害するときは、遺留分減殺請求を受けることがあります。
以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言の内容』について、その続きを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 相続分の指定・・・長男や妻に多くを遺す方法
相続分指定とは、遺言で法定相続分を変更することをいいます。
これは遺言でしかすることはできません。
相続人の一人または全員について、割合で指定するのが通常で、妻に全財産を相続させるなどというのも、本来相続分の指定ですが、判例は遺産分割を待たずに権利移転するという強い効果を認めています。
相続人のうちの一部の者の相続分だけを指定したときは、他の相続人の相続分は法定相続分によることになります。たとえば子A、B、Cがあるとき『Cに二分の一を相続させる』という指定をすると、残り二分の一を、子A、Bが均等に分けることになります。この場合妻がいたとすると複雑になります。妻の相続分は子と独立だという考え方があるため、妻が二分の一(残り全部)をとって、子A、Bはゼロだとされる可能性があるのです。このようなことまで考えて遺言しているとも思えず、争いになる可能性があります。このような混乱を避けるためには、全員について指定することが無難な方法といえます。
相続分の指定は第三者に委託することもできます。
なお、相続分の指定が他の相続人の遺留品を侵害するときは、遺留分減殺請求を受けることがあります。
以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言の内容』について、その続きを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月04日
相続の事が少しずつ分かるいいお話87 『遺言できる内容Ⅱ』
今回は前回に引き続き『どのようなことが遺言出来ますか』について、お話させていただきいます。
1 法に定められている遺言等以外の遺言はどうなるのか
法は法的効力を認める遺言事項を前回の十二種類に限定しています。
そこで、『お母さんを大事にして兄弟仲良く暮らせ』とか、『葬儀に際しては花輪、献花は返上し、質素なものに』、とか『勤勉節約に努力し、富める兄弟は貧しき兄弟を援助するように』などの教訓、道徳、家訓的教示には法律的拘束力は認められません。
しかし、右のような遺言を遺言書に書いてはいけないというものではありません。法律上は無視されるというだけで、道義上は尊重されるのが通常です。
2 臓器の提供の遺言、尊厳死の遺言
『臓器の移植に関する法律』六条と『医学及び歯学の教育のための献体に関する法律』四条は、いずれも本人の書面による承諾がある場合は、遺族の反対がない限り、臓器の摘出、政情解剖ができると定めています。遺言でこれらの承諾の意思表示をすることは意味のあることです。
また、延命治療を拒否する『尊厳死の宣言書(リヴィング・ウィル)』がアメリカで普及し、日本でも登録が始まっています。患者の自己決定権と関連し論議の多いところですが、現在までのところわが国では特別な法的効力は認められていません。
以上、『どのようなことを遺言できますか』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 法に定められている遺言等以外の遺言はどうなるのか
法は法的効力を認める遺言事項を前回の十二種類に限定しています。
そこで、『お母さんを大事にして兄弟仲良く暮らせ』とか、『葬儀に際しては花輪、献花は返上し、質素なものに』、とか『勤勉節約に努力し、富める兄弟は貧しき兄弟を援助するように』などの教訓、道徳、家訓的教示には法律的拘束力は認められません。
しかし、右のような遺言を遺言書に書いてはいけないというものではありません。法律上は無視されるというだけで、道義上は尊重されるのが通常です。
2 臓器の提供の遺言、尊厳死の遺言
『臓器の移植に関する法律』六条と『医学及び歯学の教育のための献体に関する法律』四条は、いずれも本人の書面による承諾がある場合は、遺族の反対がない限り、臓器の摘出、政情解剖ができると定めています。遺言でこれらの承諾の意思表示をすることは意味のあることです。
また、延命治療を拒否する『尊厳死の宣言書(リヴィング・ウィル)』がアメリカで普及し、日本でも登録が始まっています。患者の自己決定権と関連し論議の多いところですが、現在までのところわが国では特別な法的効力は認められていません。
以上、『どのようなことを遺言できますか』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月03日
相続の事が少しずつ分かるいいお話86 『遺言できる内容』
本日は、『どうのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきます。
◇法的な効力の生ずる遺言事項は法律で決められている
遺言ですることのできる行為として法が定めているものは次の一二種類です。これ以外のことを遺言しても法律上の効力は認められません。
1 身分に関する事項
①認知
②後見人の指定(民法839条)および後見監督人の指定(民法848条)
自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子が有る場合に、その子の親代わりとなる者、およびその者を監督するものを指定すること。
2 相続に関する事項
③相続人の廃除および廃除の取り消し
④相続分の指定または指定の委託
⑤遺産分割方法の指定または指定の委託
⑥遺産分割の禁止(民法908条)
これによって相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能となります。
⑦相続人間の担保責任の指定(民法914条)
⑧遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
⑨遺言執行者の指定または指定の委託
3 財産処分に関する事項
⑩遺贈
⑪一般財団法人の定款の作成(一般社団・一般財団法152条2項)
⑫遺言信託(信託法3条2号)
以上のうち①、③、⑩、⑪、⑫は生前行為もできますが(遺贈は生前なら贈与となり少し扱いが違います)、それ以外は遺言でしかできません。
以上、『どのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきました。
次回は、『どのようなことを遺言出来ますかⅡ』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
◇法的な効力の生ずる遺言事項は法律で決められている
遺言ですることのできる行為として法が定めているものは次の一二種類です。これ以外のことを遺言しても法律上の効力は認められません。
1 身分に関する事項
①認知
②後見人の指定(民法839条)および後見監督人の指定(民法848条)
自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子が有る場合に、その子の親代わりとなる者、およびその者を監督するものを指定すること。
2 相続に関する事項
③相続人の廃除および廃除の取り消し
④相続分の指定または指定の委託
⑤遺産分割方法の指定または指定の委託
⑥遺産分割の禁止(民法908条)
これによって相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能となります。
⑦相続人間の担保責任の指定(民法914条)
⑧遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
⑨遺言執行者の指定または指定の委託
3 財産処分に関する事項
⑩遺贈
⑪一般財団法人の定款の作成(一般社団・一般財団法152条2項)
⑫遺言信託(信託法3条2号)
以上のうち①、③、⑩、⑪、⑫は生前行為もできますが(遺贈は生前なら贈与となり少し扱いが違います)、それ以外は遺言でしかできません。
以上、『どのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきました。
次回は、『どのようなことを遺言出来ますかⅡ』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月02日
相続の事が少しずつ分かるいいお話85 『遺言の必要な時とは』
本日は、『どういう場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきます、
相続をめぐるお話を受けたとき、『遺言さえあれば争いは生じなかったのに』とか『遺言さえあればこのように不当な結果にならなかったのに』と感じることは、多々、あることです。
遺言は誰もが遺しておくことが望ましいのですが、とりわけ遺言を必要とされる方は次のような方です。
◇法律で定められている相続人に遺産を分けてやりたくない場合
親不幸で浪費癖のある子どもや、離婚訴訟中の配偶者、離縁訴訟中の養子などには財産をやりたくないと思っても、遺言なしに死亡すると、これらの人も当然に相続してしまいます。そこで遺言で他の人に相続させる必要があります。
◇子どものいない夫婦や内縁の夫婦の場合
法定相続では、子供のいない夫婦の場合、どちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。しかし遺言さえしておけば、自分の配偶者にすべて相続させることができます。特に相続人が兄弟姉妹の場合には、遺留分もないので、一切口出しをさせずにすみます。
また実質は夫婦として生活してきながら、婚姻届を出していないいわゆる内縁関係の場合、内縁配偶者に相続させたければ遺言をしておかなければなりません。そうでないと、他に相続人がいる場合、内縁配偶者は何も相続できないことになります。
以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきました。
次回は、また今回の続きとして、遺言の必要なケースについてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
相続をめぐるお話を受けたとき、『遺言さえあれば争いは生じなかったのに』とか『遺言さえあればこのように不当な結果にならなかったのに』と感じることは、多々、あることです。
遺言は誰もが遺しておくことが望ましいのですが、とりわけ遺言を必要とされる方は次のような方です。
◇法律で定められている相続人に遺産を分けてやりたくない場合
親不幸で浪費癖のある子どもや、離婚訴訟中の配偶者、離縁訴訟中の養子などには財産をやりたくないと思っても、遺言なしに死亡すると、これらの人も当然に相続してしまいます。そこで遺言で他の人に相続させる必要があります。
◇子どものいない夫婦や内縁の夫婦の場合
法定相続では、子供のいない夫婦の場合、どちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。しかし遺言さえしておけば、自分の配偶者にすべて相続させることができます。特に相続人が兄弟姉妹の場合には、遺留分もないので、一切口出しをさせずにすみます。
また実質は夫婦として生活してきながら、婚姻届を出していないいわゆる内縁関係の場合、内縁配偶者に相続させたければ遺言をしておかなければなりません。そうでないと、他に相続人がいる場合、内縁配偶者は何も相続できないことになります。
以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきました。
次回は、また今回の続きとして、遺言の必要なケースについてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年04月01日
相続の事が少しずつ分かるいいお話84 『遺言が必要な場合とは』
本日は、『どういう場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきます、
相続をめぐるお話を受けたとき、『遺言さえあれば争いは生じなかったのに』とか『遺言さえあればこのように不当な結果にならなかったのに』と感じることは、多々、あることです。
遺言は誰もが遺しておくことが望ましいのですが、とりわけ遺言を必要とされる方は次のような方です。
◇法律で定められている相続人に遺産を分けてやりたくない場合
親不幸で浪費癖のある子どもや、離婚訴訟中の配偶者、離縁訴訟中の養子などには財産をやりたくないと思っても、遺言なしに死亡すると、これらの人も当然に相続してしまいます。そこで遺言で他の人に相続させる必要があります。
◇子どものいない夫婦や内縁の夫婦の場合
法定相続では、子供のいない夫婦の場合、どちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。
しかし遺言さえしておけば、自分の配偶者にすべて相続させることができます。特に相続人が兄弟姉妹の場合には、遺留分もないので、一切口出しをさせずにすみます。
また実質は夫婦として生活してきながら、婚姻届を出していないいわゆる内縁関係の場合、内縁配偶者に相続させたければ遺言をしておかなければなりません。
そうでないと、他に相続人がいる場合、内縁配偶者は何も相続できないことになります。
以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきました。
次回は、また今回の続きとして、遺言の必要なケースについてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
相続をめぐるお話を受けたとき、『遺言さえあれば争いは生じなかったのに』とか『遺言さえあればこのように不当な結果にならなかったのに』と感じることは、多々、あることです。
遺言は誰もが遺しておくことが望ましいのですが、とりわけ遺言を必要とされる方は次のような方です。
◇法律で定められている相続人に遺産を分けてやりたくない場合
親不幸で浪費癖のある子どもや、離婚訴訟中の配偶者、離縁訴訟中の養子などには財産をやりたくないと思っても、遺言なしに死亡すると、これらの人も当然に相続してしまいます。そこで遺言で他の人に相続させる必要があります。
◇子どものいない夫婦や内縁の夫婦の場合
法定相続では、子供のいない夫婦の場合、どちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。
しかし遺言さえしておけば、自分の配偶者にすべて相続させることができます。特に相続人が兄弟姉妹の場合には、遺留分もないので、一切口出しをさせずにすみます。
また実質は夫婦として生活してきながら、婚姻届を出していないいわゆる内縁関係の場合、内縁配偶者に相続させたければ遺言をしておかなければなりません。
そうでないと、他に相続人がいる場合、内縁配偶者は何も相続できないことになります。
以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきました。
次回は、また今回の続きとして、遺言の必要なケースについてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年03月31日
相続の事が少しずつ分かるいいお話83『遺言のすすめ・・・・』
本日は、『遺言のすすめ・・・』をお話させていただきます。
遺言というと、うちの家族はいさかいをするはずないとか、臨終のことを連想するので気分が悪いという人はかなり多いようです。相続というのは法定相続のことだと思い込んでいる人がほとんどかもしれません。
しかし、日本でも江戸時代までの庶民法(町人百姓に対する法)では、遺言相続が原則で、法定相続は、被相続人が『頓死』したり『不慮の死』にあったりしたときに適用されるままったくの例外だったようです。善良なる家父は生前に遺産の帰属を確定するのが通例で、それが家父の責任だったともいわれてます。
民法の法定相続は、一般的に一応誰にでも合うように作られた、いわばレディメイドの服です。これは遺言がないときに、何の決まりがなくても困るということで決められたもので、体に合わないといって不服をいう方がおかしいのです。本来は、体にぴったり合ったオーダーメイドの服である遺言を作るべきなのです。
すなわち、遺言によってこそ、各人の実情に合った財産の処分ができるのです。そこで、民法は、遺言に法定相続分に優先する効力を与えています。
きちんとした遺言書を作っておきさえすれば、相続紛争は防げたと思われるケースが少なくありません。多くの相続人は、被相続人の遺志を尊重する気持ちをもっていますから、遺言によって紛争を未然に防止することができるのです。この意味で、現代人にとっても、遺言することは、次の世代に財産を残す者の債務といえます。
遺言は死に直面してなすものと思い込んでいる人がおおいようですが、これは正しくありません。死に直面してからでは、適法な遺言をすることがむずかしくなりますし、また、冷静な判断ができなくなる危険もあります。遺言は何回でも変更できるのですから、元気なうちに遺言しておくことをおすすめします。
遺言は満十五歳以上の人であれば、何時でも自由にできます(民法九一六条)。精神障害等によって普段は正常な判断能力がない人であっても、正常な判断能力に戻っているときに遺言をすることができます。遺言の能力は遺言をするときに必要とされているのです(民法九六三条)。成年後見人が遺言をする場合には、正常な状態に戻っていることを証明する医師二人以上の立会いが必要です(民法九七三条)。
以上、『遺言のすすめ・・・』についてお話させていただきました。
次回は、『どういう場合に遺言が必要か・・・』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
遺言というと、うちの家族はいさかいをするはずないとか、臨終のことを連想するので気分が悪いという人はかなり多いようです。相続というのは法定相続のことだと思い込んでいる人がほとんどかもしれません。
しかし、日本でも江戸時代までの庶民法(町人百姓に対する法)では、遺言相続が原則で、法定相続は、被相続人が『頓死』したり『不慮の死』にあったりしたときに適用されるままったくの例外だったようです。善良なる家父は生前に遺産の帰属を確定するのが通例で、それが家父の責任だったともいわれてます。
民法の法定相続は、一般的に一応誰にでも合うように作られた、いわばレディメイドの服です。これは遺言がないときに、何の決まりがなくても困るということで決められたもので、体に合わないといって不服をいう方がおかしいのです。本来は、体にぴったり合ったオーダーメイドの服である遺言を作るべきなのです。
すなわち、遺言によってこそ、各人の実情に合った財産の処分ができるのです。そこで、民法は、遺言に法定相続分に優先する効力を与えています。
きちんとした遺言書を作っておきさえすれば、相続紛争は防げたと思われるケースが少なくありません。多くの相続人は、被相続人の遺志を尊重する気持ちをもっていますから、遺言によって紛争を未然に防止することができるのです。この意味で、現代人にとっても、遺言することは、次の世代に財産を残す者の債務といえます。
遺言は死に直面してなすものと思い込んでいる人がおおいようですが、これは正しくありません。死に直面してからでは、適法な遺言をすることがむずかしくなりますし、また、冷静な判断ができなくなる危険もあります。遺言は何回でも変更できるのですから、元気なうちに遺言しておくことをおすすめします。
遺言は満十五歳以上の人であれば、何時でも自由にできます(民法九一六条)。精神障害等によって普段は正常な判断能力がない人であっても、正常な判断能力に戻っているときに遺言をすることができます。遺言の能力は遺言をするときに必要とされているのです(民法九六三条)。成年後見人が遺言をする場合には、正常な状態に戻っていることを証明する医師二人以上の立会いが必要です(民法九七三条)。
以上、『遺言のすすめ・・・』についてお話させていただきました。
次回は、『どういう場合に遺言が必要か・・・』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
2013年03月30日
相続の事が少しずつ分かるいいお話82 『離婚訴訟中の相続』
本日は、『離婚訴訟中の相続』に関してのお話をさせていただきます。
1.離婚訴訟中の妻でも相続はできるか
①死亡時に婚姻関係があれば相続人
民法は『被相続人の配偶者は常に相続人となる』(八九〇条)としています。
ここにいう配偶者とは、法律上有効な婚姻、すなわち、民法七三九条にいう婚姻届をすませた配偶者をさします。
いったん婚姻届を提出すれば、離婚するまでの間は、夫婦仲が悪くても、別居中でも離婚すべく話合いの最中でも、配偶者であり、相続人です。離婚調停や裁判は、相手方が死亡すると自動的に終了するので、夫死亡後の離婚はありえず、離婚調停中・離婚裁判中の妻も相続人になります。
ですから、配偶者と離婚するつもりで財産を相続させたくない場合、離婚の手続きをはじめると同時に、配偶者以外の者に財産を相続させる旨および配偶者を廃除する旨遺言しておかねばなりません。
また、相続は被相続人の死亡時に開始しますから(民法八八二条)、夫の死亡後に旧性に戻った妻でも、その後再婚した妻でも、夫の相続人です。
②離婚してしまうと相続できない。
逆にいったん離婚届を提出してしまえば、相続人ではありません。したがって、離婚した前妻は相続できません。
また、最近、夫が借りた金について妻に請求されるのを避けるために、形式的に離婚届を提出するケースがままありますが、この場合も相続人ではなくなります。
もちろん、借金だけを相続しても仕方がありませんが、もし財産があった場合には、真実は離婚する意思のなかったことを理由にしても離婚の無効を認めないのが現在の裁判例ですから、やはり相続できません。
何らかの事情により形式的に離婚する場合には、このことを十分考慮し、遺言する配慮も必要です。
③内縁の妻、内縁の夫には相続権はない。
結婚式を挙げ、親族も近所の人も皆夫婦として認めていても、婚姻届を提出していない内縁の配偶者には相続権はありません。
ただし、相続人が誰もいない場合には、特別縁故者として財産の分与を家庭裁判所に申し立てることにより、財産の全部または一部を受ける途があります。
なお、一連の社会立法においては、遺族給付について、内縁の配偶者を法律上の配偶者と区別せずに、受給資格を与えて保護しています(労働基準法七九条・同施行規則四二条、船員法九三条・同施行規則六三条、船員保険法一条、厚生年金保険法三条二項、国家公務員等共済組合法二条一項、国家公務員災害補償法一六条一項、地方公務員等共済組合法二条一項・地方公務員災害補償法三二条等。)
これらの内縁配偶者などに財産を承継させるには、その旨遺言しておかねばなりません。
しかし、内縁配偶者については、結婚の実態があるのですから、婚姻届は形式だけだなどと考えずに、婚姻届を提出しておくことが、万一の場合のトラブルを解消する最後の方法です。
以上、『離婚訴訟中の相続』について、お話させていただきました。
次回以降は、『遺言』についてを、何回かに分けてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援
1.離婚訴訟中の妻でも相続はできるか
①死亡時に婚姻関係があれば相続人
民法は『被相続人の配偶者は常に相続人となる』(八九〇条)としています。
ここにいう配偶者とは、法律上有効な婚姻、すなわち、民法七三九条にいう婚姻届をすませた配偶者をさします。
いったん婚姻届を提出すれば、離婚するまでの間は、夫婦仲が悪くても、別居中でも離婚すべく話合いの最中でも、配偶者であり、相続人です。離婚調停や裁判は、相手方が死亡すると自動的に終了するので、夫死亡後の離婚はありえず、離婚調停中・離婚裁判中の妻も相続人になります。
ですから、配偶者と離婚するつもりで財産を相続させたくない場合、離婚の手続きをはじめると同時に、配偶者以外の者に財産を相続させる旨および配偶者を廃除する旨遺言しておかねばなりません。
また、相続は被相続人の死亡時に開始しますから(民法八八二条)、夫の死亡後に旧性に戻った妻でも、その後再婚した妻でも、夫の相続人です。
②離婚してしまうと相続できない。
逆にいったん離婚届を提出してしまえば、相続人ではありません。したがって、離婚した前妻は相続できません。
また、最近、夫が借りた金について妻に請求されるのを避けるために、形式的に離婚届を提出するケースがままありますが、この場合も相続人ではなくなります。
もちろん、借金だけを相続しても仕方がありませんが、もし財産があった場合には、真実は離婚する意思のなかったことを理由にしても離婚の無効を認めないのが現在の裁判例ですから、やはり相続できません。
何らかの事情により形式的に離婚する場合には、このことを十分考慮し、遺言する配慮も必要です。
③内縁の妻、内縁の夫には相続権はない。
結婚式を挙げ、親族も近所の人も皆夫婦として認めていても、婚姻届を提出していない内縁の配偶者には相続権はありません。
ただし、相続人が誰もいない場合には、特別縁故者として財産の分与を家庭裁判所に申し立てることにより、財産の全部または一部を受ける途があります。
なお、一連の社会立法においては、遺族給付について、内縁の配偶者を法律上の配偶者と区別せずに、受給資格を与えて保護しています(労働基準法七九条・同施行規則四二条、船員法九三条・同施行規則六三条、船員保険法一条、厚生年金保険法三条二項、国家公務員等共済組合法二条一項、国家公務員災害補償法一六条一項、地方公務員等共済組合法二条一項・地方公務員災害補償法三二条等。)
これらの内縁配偶者などに財産を承継させるには、その旨遺言しておかねばなりません。
しかし、内縁配偶者については、結婚の実態があるのですから、婚姻届は形式だけだなどと考えずに、婚姻届を提出しておくことが、万一の場合のトラブルを解消する最後の方法です。
以上、『離婚訴訟中の相続』について、お話させていただきました。
次回以降は、『遺言』についてを、何回かに分けてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援
2013年03月29日
相続の事が少しずつ分かるいいお話81 『相続と信用保証』
本日は、相続が起きたときの信用保証について、お話させていただきます。
信用保証は原則として相続されません。
ただし、企業間の売掛金取引契約などの継続的取引の保証人となった場合には話が異なります。
これらの保証では、責任のおよぶ範囲が極めて広汎になり、相続人としては額が決まらないと、相続を承認するか放棄するかも決められないことになるからです。
そこで、判例では、契約で保証人の責任限度および保証期間が具体的に取り決められていない場合には、相続がはじまったときに発生していた具体的な金額の債務だけが相続され、その後の義務は相続されないとしています。(最高裁昭和37年11月9日判決)
これに対して、契約で保証責任の限度額が定められている場合には、保証人の義務はそのまま相続されるとされています。もっともこの点については反対の考えもあります。
なお、2004年の民法改正によって、2005年4月1日以降に締結された金融機関との融資・手形割引等を主債務とする『貸金等根保証契約』については、極度額の定めがなければ無効となり(民法四六五条の二第二項)、極度額の定めがあっても主債務者が死亡したときには元本が確定するとされ、『貸金等根保証契約』自体は相続されないことが明確になりました。(民法四六五条の四第三号)
本日は、信用保証のお話をさせていただきました。
次回は、離婚訴訟中の相続について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援
信用保証は原則として相続されません。
ただし、企業間の売掛金取引契約などの継続的取引の保証人となった場合には話が異なります。
これらの保証では、責任のおよぶ範囲が極めて広汎になり、相続人としては額が決まらないと、相続を承認するか放棄するかも決められないことになるからです。
そこで、判例では、契約で保証人の責任限度および保証期間が具体的に取り決められていない場合には、相続がはじまったときに発生していた具体的な金額の債務だけが相続され、その後の義務は相続されないとしています。(最高裁昭和37年11月9日判決)
これに対して、契約で保証責任の限度額が定められている場合には、保証人の義務はそのまま相続されるとされています。もっともこの点については反対の考えもあります。
なお、2004年の民法改正によって、2005年4月1日以降に締結された金融機関との融資・手形割引等を主債務とする『貸金等根保証契約』については、極度額の定めがなければ無効となり(民法四六五条の二第二項)、極度額の定めがあっても主債務者が死亡したときには元本が確定するとされ、『貸金等根保証契約』自体は相続されないことが明確になりました。(民法四六五条の四第三号)
本日は、信用保証のお話をさせていただきました。
次回は、離婚訴訟中の相続について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援
2013年03月28日
相続の事が少しずつ分かるいいお話80 『保証債務』
本日は、相続がおきた時の保証債務の扱いについて、お話させていただきます。
1.通常の保証債務は相続されます。
例えば、友人が銀行から金1000万円を借りるに際し保証人になった場合などのような、1回限りで金額の確定している保証債務は相続されることとなります。
この時、相続人は保証債務には気がつかないことが多いので、次のような相続の承認・放棄の熟慮期間がいつから始まるのかが争われた例があります。
すなわち、相続開始後、3カ月以内に、相続放棄をするか限定承認をするかの手続きをしないと、単純承認といって被相続人の全ての財産と債務を継承しますので、保証人となっていた事に気づかずに3カ月を経過してしまった場合のケースで、最高裁は次の判決を出しています。
相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから始まるかが争われた事件で、最高裁は、死んだ親族の財産、借金の有無を調べることが困難な状況にあり、財産、借金がまったくないと信じるに相当な理由があると認められるときには、死亡で法律上の相続人となったときからではなく、財産、借金があることを相続人が知った時から起算すべきだとしています。
本日は、通常の保証債務のお話をさせていただきました。
次回は、信用保証についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
1.通常の保証債務は相続されます。
例えば、友人が銀行から金1000万円を借りるに際し保証人になった場合などのような、1回限りで金額の確定している保証債務は相続されることとなります。
この時、相続人は保証債務には気がつかないことが多いので、次のような相続の承認・放棄の熟慮期間がいつから始まるのかが争われた例があります。
すなわち、相続開始後、3カ月以内に、相続放棄をするか限定承認をするかの手続きをしないと、単純承認といって被相続人の全ての財産と債務を継承しますので、保証人となっていた事に気づかずに3カ月を経過してしまった場合のケースで、最高裁は次の判決を出しています。
相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから始まるかが争われた事件で、最高裁は、死んだ親族の財産、借金の有無を調べることが困難な状況にあり、財産、借金がまったくないと信じるに相当な理由があると認められるときには、死亡で法律上の相続人となったときからではなく、財産、借金があることを相続人が知った時から起算すべきだとしています。
本日は、通常の保証債務のお話をさせていただきました。
次回は、信用保証についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
2013年03月27日
相続の事が少しずつ分かるいいお話79 『相続対策と生命保険②』
今日は、相続対策と生命保険の活用の続きについてお話させていただきます。
そもそも、生命保険とは人の亡くなったときに備えて入るものですから生命保険と相続は関連が深いものとなります。
一家の大黒柱が働き盛りで倒れてしまった、寝たきりになってしまった。高度障害になってしまった。最悪、亡くなってしまった。
この様な時に、生命保険に加入していれば、当面の生活は凌げることとなります。
一般的なライフプラン上での生命保険であれば、子供の独立までの教育費、生活費と奥さんの老後の必要資金をシミュレーションして必要保証額を見直しをしながら継続加入していくこととなります。
ポイントは子どもの小さい内は保証額を厚く大きくなるにつれ保証額を調整していく。
終身部分と定期部分の組み合わせを保険料の兼ね合いで考えていくのが一般的です。
相続税の納税に備えて生命保険の加入を考える場合、一生涯保証が続く終身保険への加入が基本となります。
また、一次相続(一般的にご主人が早く亡くなるのでご主人の相続)と比べて二次相続は配偶者の相続税額の軽減の適用がなく税負担が重くなりますから二次相続まで考えた対策が重要となります。
なお、生命保険のメリットとして被相続人が保険料を支払っていた場合は、死亡保険金に非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり現金を保険料に転嫁することにより、課税後の手取額、すなわち可処分金額が増えることとなります。
また、相続人を契約者(保険料負担者)として(相続人に保険料の負担能力の無い時は、保険料は被相続人から相続人に現金贈与をして相続人から支払う。)死亡保険金を受領した時の課税を相続税ではなく、所得税の一時所得(所得金額=【死亡保険金―正味払込保険料―50万円】×1/2)とする生命保険金の加入も納税資金として有効な対策となります。
この場合、保険料支払者は相続人ですので被相続人の所得税の計算上、その生命保険契約に関わる生命保険料控除は被相続人の適用となりませんので注意が必要です。
また、保険料の現金贈与における贈与税の負担(年110万円までは非課税)を考慮しておく必要があります。
以上、相続対策と生命保険の活用についてお話させて頂きました。
次回は、事業承継と生命保険の活用についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
そもそも、生命保険とは人の亡くなったときに備えて入るものですから生命保険と相続は関連が深いものとなります。
一家の大黒柱が働き盛りで倒れてしまった、寝たきりになってしまった。高度障害になってしまった。最悪、亡くなってしまった。
この様な時に、生命保険に加入していれば、当面の生活は凌げることとなります。
一般的なライフプラン上での生命保険であれば、子供の独立までの教育費、生活費と奥さんの老後の必要資金をシミュレーションして必要保証額を見直しをしながら継続加入していくこととなります。
ポイントは子どもの小さい内は保証額を厚く大きくなるにつれ保証額を調整していく。
終身部分と定期部分の組み合わせを保険料の兼ね合いで考えていくのが一般的です。
相続税の納税に備えて生命保険の加入を考える場合、一生涯保証が続く終身保険への加入が基本となります。
また、一次相続(一般的にご主人が早く亡くなるのでご主人の相続)と比べて二次相続は配偶者の相続税額の軽減の適用がなく税負担が重くなりますから二次相続まで考えた対策が重要となります。
なお、生命保険のメリットとして被相続人が保険料を支払っていた場合は、死亡保険金に非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり現金を保険料に転嫁することにより、課税後の手取額、すなわち可処分金額が増えることとなります。
また、相続人を契約者(保険料負担者)として(相続人に保険料の負担能力の無い時は、保険料は被相続人から相続人に現金贈与をして相続人から支払う。)死亡保険金を受領した時の課税を相続税ではなく、所得税の一時所得(所得金額=【死亡保険金―正味払込保険料―50万円】×1/2)とする生命保険金の加入も納税資金として有効な対策となります。
この場合、保険料支払者は相続人ですので被相続人の所得税の計算上、その生命保険契約に関わる生命保険料控除は被相続人の適用となりませんので注意が必要です。
また、保険料の現金贈与における贈与税の負担(年110万円までは非課税)を考慮しておく必要があります。
以上、相続対策と生命保険の活用についてお話させて頂きました。
次回は、事業承継と生命保険の活用についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
2013年03月26日
相続の事が少しずつ分かるいいお話78 『相続対策と生命保険』
本日は、相続における生命保険の活用についてお話させていただきます。
先ずは、遺産分割においての生命保険の特徴として次の様な特徴があります。
被相続人の死亡によって支払われた生命保険金(保険料は被相続人が支払った分)は、保険金受取人の固有の財産となりますので被相続人の相続人間で分割する相続財産には含まれませんので、特定の人に残してあげたい場合や老後の介護をしてくれた長男の嫁に残してあげたいときに有効に活用できます。
生命保険で保険金受取人を指定しておきますと他の相続人等からその生命保険に権利の主張は出来なこととなります。
但し、余りにも極端に相続財産の大半が生命保険で1人の者に偏った遺産分割となった場合に生命保険を持ち戻しの対象にすべきとの判例がありますので、相続財産の大半を生命保険で継承させ特定の者にその大半を分割するとした場合、状況によっては、相続人間で分割すべき持ち戻しによる特別受益の扱いとなることもあり得ます。
続いては、税務上の面ですが・・・
・相続人の取得した生命保険金については、一定額の非課税の適用があります。
一定額は、500万円×法定相続人の数(相続人のうち、相続放棄をした者がいた場合でも放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算します。
つまり、相続人が4人いたとすると500万円×4人で2000万円を相続人の取得した生命保険金で按分計算して各々の非課税額を計算して控除することが出来ます。(相続人の取得した生命保険金だけが対象となります。)
現金で相続財産を残すよりも、終身保険に加入して生命保険金で遺すほうが相続税を少なくする事ができる事となります。
他、相続税の納入資金等他の活用がありますが、又、次回以降、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
先ずは、遺産分割においての生命保険の特徴として次の様な特徴があります。
被相続人の死亡によって支払われた生命保険金(保険料は被相続人が支払った分)は、保険金受取人の固有の財産となりますので被相続人の相続人間で分割する相続財産には含まれませんので、特定の人に残してあげたい場合や老後の介護をしてくれた長男の嫁に残してあげたいときに有効に活用できます。
生命保険で保険金受取人を指定しておきますと他の相続人等からその生命保険に権利の主張は出来なこととなります。
但し、余りにも極端に相続財産の大半が生命保険で1人の者に偏った遺産分割となった場合に生命保険を持ち戻しの対象にすべきとの判例がありますので、相続財産の大半を生命保険で継承させ特定の者にその大半を分割するとした場合、状況によっては、相続人間で分割すべき持ち戻しによる特別受益の扱いとなることもあり得ます。
続いては、税務上の面ですが・・・
・相続人の取得した生命保険金については、一定額の非課税の適用があります。
一定額は、500万円×法定相続人の数(相続人のうち、相続放棄をした者がいた場合でも放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算します。
つまり、相続人が4人いたとすると500万円×4人で2000万円を相続人の取得した生命保険金で按分計算して各々の非課税額を計算して控除することが出来ます。(相続人の取得した生命保険金だけが対象となります。)
現金で相続財産を残すよりも、終身保険に加入して生命保険金で遺すほうが相続税を少なくする事ができる事となります。
他、相続税の納入資金等他の活用がありますが、又、次回以降、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
2013年03月25日
相続の事が少しずつ分かるいいお話77『相続対策と不動産』
本日は、相続税の節税対策に絡んでくる相続対策と不動産棚卸について、少し、お話させていただきます。
相続が発生した時には、自分の所有していた財産が、誰かしらに継承されるわけですが・・・
その継承について、誰に・・いくら・・どのように・・継承するのか・・・その分け方はきれいに分けられるのか・・どうしようか・・・
又、相続が発生し、自分の所有している財産に対して相続税は発生するのか・・発生するとその税額はいかほどか・・相続税が発生するとなると・・税額を低くできる方法はあるのか・・・
相続に備えて、何を準備しておくべきか・・
何から始めればいいのか・・
等々、色々な考えに及ぶ事と思います。
将来に向けて、どうしようか?との考えにあたり、まず、確認いただきたいのが、自分の相続財産の確認と状況です。
株は・・投資信託は・・国債は・・預金は・・生命保険は・・土地は・・自宅は・・貸家は・・各種会員権は・・貸付金(同族会社や友人)・・未収給与(同族会社)は・・等々の財産が、どの程度、あるのか・・・
逆に、銀行借入金は・・敷金は・・知人からの借入金は・・同族会社からの借入金は・・等々、財産同様に債務はどの程度あるのか・・
特に、債務の承継については、債権者の方と相続発生後の承継人指定等について、お話をされておくことが重要となります。
又、保証人になられている債務も分かるように記録を遺しておくことが大事です。
他に、気を付けるべきは、会社を経営されている場合の、会社間への貸付金(未収給与等も)等の整理も進めておくことも大事です。
そして、相続財産の分割を考えるにも、納税を考えるにも、重要なのが、不動産の棚卸と現状分析となります。
要は、所有している全ての不動産の調査を行っておくことが重要です。
全面の道路に問題は・・4m未満でセットバックが必要か・・私道で権利形態は・・建て替えの出来る道路か・・等々
インフラ設備は・・水道管の太さは・・引き込みは必要か・・下水道はどうなっているか・・等々
相続税評価額はいくら・・評価額を下げられる有効な方法は・・等々
時価はどの程度・・売却したら手元にいくら残る・・等々
収益を産んでいない土地は・・又、有効な活用方法はあるのか・・等々
納税のため売却が必要な時に・・どの不動産から売却するか・・残しておきたい不動産の優先順位は・・等々
子供の誰に何の不動産を分けてあげるか・・その分けるときの不動産価値をどう計算する・・等々
不動産は分ける時も、処分する時も、専門的な知識を基に優先順位や不動産の状況を分析して決断していかなければなりません。
その為には、あらかじめ、不動産全般の状況確認(現状分析)が、必要となります。
その時、現状分析を、誰に依頼されるかが、ポイントとなります。
不動産に詳しい不動産業者さんの場合、調査が仕事では、ありませんので、売りたい、買いたいという話になりがちです。
建築業者さんは、建物を建てたい気持から、有効活用のいい話をされがちです。
金融機関は、担保がしっかりしていれば、お金を借りてくれる方向の話をされがちです。
先ずは、現状分析をクライアントの立場で纏め上げ、その後の提案もクライアントの立場にたち、建てない方がいいと思われる時には、建てないほうがいい。売却のタイミングでないと思われる時には、今は、売却しない方がいいと提案してくれる業者さんに依頼することが大事です。
例えば、不動産のコンサルティングやFPの業務をされている方や財産全般のコンサルティングをされている方、不動産の知識はもとより、建築、経理や税務、できれば保険もからめた総合的な提案をしてくれる方が、望ましいことかと思います。
次回は、相続対策と保険について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
相続が発生した時には、自分の所有していた財産が、誰かしらに継承されるわけですが・・・
その継承について、誰に・・いくら・・どのように・・継承するのか・・・その分け方はきれいに分けられるのか・・どうしようか・・・
又、相続が発生し、自分の所有している財産に対して相続税は発生するのか・・発生するとその税額はいかほどか・・相続税が発生するとなると・・税額を低くできる方法はあるのか・・・
相続に備えて、何を準備しておくべきか・・
何から始めればいいのか・・
等々、色々な考えに及ぶ事と思います。
将来に向けて、どうしようか?との考えにあたり、まず、確認いただきたいのが、自分の相続財産の確認と状況です。
株は・・投資信託は・・国債は・・預金は・・生命保険は・・土地は・・自宅は・・貸家は・・各種会員権は・・貸付金(同族会社や友人)・・未収給与(同族会社)は・・等々の財産が、どの程度、あるのか・・・
逆に、銀行借入金は・・敷金は・・知人からの借入金は・・同族会社からの借入金は・・等々、財産同様に債務はどの程度あるのか・・
特に、債務の承継については、債権者の方と相続発生後の承継人指定等について、お話をされておくことが重要となります。
又、保証人になられている債務も分かるように記録を遺しておくことが大事です。
他に、気を付けるべきは、会社を経営されている場合の、会社間への貸付金(未収給与等も)等の整理も進めておくことも大事です。
そして、相続財産の分割を考えるにも、納税を考えるにも、重要なのが、不動産の棚卸と現状分析となります。
要は、所有している全ての不動産の調査を行っておくことが重要です。
全面の道路に問題は・・4m未満でセットバックが必要か・・私道で権利形態は・・建て替えの出来る道路か・・等々
インフラ設備は・・水道管の太さは・・引き込みは必要か・・下水道はどうなっているか・・等々
相続税評価額はいくら・・評価額を下げられる有効な方法は・・等々
時価はどの程度・・売却したら手元にいくら残る・・等々
収益を産んでいない土地は・・又、有効な活用方法はあるのか・・等々
納税のため売却が必要な時に・・どの不動産から売却するか・・残しておきたい不動産の優先順位は・・等々
子供の誰に何の不動産を分けてあげるか・・その分けるときの不動産価値をどう計算する・・等々
不動産は分ける時も、処分する時も、専門的な知識を基に優先順位や不動産の状況を分析して決断していかなければなりません。
その為には、あらかじめ、不動産全般の状況確認(現状分析)が、必要となります。
その時、現状分析を、誰に依頼されるかが、ポイントとなります。
不動産に詳しい不動産業者さんの場合、調査が仕事では、ありませんので、売りたい、買いたいという話になりがちです。
建築業者さんは、建物を建てたい気持から、有効活用のいい話をされがちです。
金融機関は、担保がしっかりしていれば、お金を借りてくれる方向の話をされがちです。
先ずは、現状分析をクライアントの立場で纏め上げ、その後の提案もクライアントの立場にたち、建てない方がいいと思われる時には、建てないほうがいい。売却のタイミングでないと思われる時には、今は、売却しない方がいいと提案してくれる業者さんに依頼することが大事です。
例えば、不動産のコンサルティングやFPの業務をされている方や財産全般のコンサルティングをされている方、不動産の知識はもとより、建築、経理や税務、できれば保険もからめた総合的な提案をしてくれる方が、望ましいことかと思います。
次回は、相続対策と保険について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
2013年03月24日
相続の事が少しずつ分かるいいお話76『相続税納税対策』
本日は、前回お話させて頂きました『相続対策』の『円満な遺産分割』に続きまして『相続税の納税対策』について、お話させて頂きます。
前回、お話させて頂きました通り、近年の相続対策の順位は、第一に『円満な遺産分割』、第二に『相続税の納税対策』、第三に『相続税の節税対策』と言われています。
被相続人が、生前に自分の相続の対策を考えるにあたっては、先ずご自身の相続財産となるべき財産を性格に把握し、誰に何を遺すかの考えを整理しながら、相続税がいくらかかるかをシミュレーションンしつつ、各相続人への分け方と相続税の払い方を考えていくことが、合理的かと思います。
そして、それに、基づいて、節税の対策を実施していく流れが賢明と考えます。
賃貸マンション建築等の節税対策が、先行しますと、いざ、分けるときに分けられない財産となってしまいます。
また、売却して分割しようにも、かえって、売却しにくくなってしまった。
そんな、ケースが、今までに、多々、見られます。
地価が上昇しつづけている時代でしたら、売却しにくくなるというケースが想像出来ないような時代でしたので、いざというときは売却して解決が図れる。そんな時代でした。
近年は、土地価格の上昇は、期待出来ないようになりました。
土地価格の上昇が見込めない現代においては、将来の相続税のシミュレーションと財産の現状分析に基づいて納税方法を検討しておくことが大事です。
相続財産の60%は不動産であると言われています。
何ら納税対策を考えないまま相続を迎えた場合、金融資産が納税資金に遠く及ばないときは、不動産を一部売却するか、もしくは延納や物納等の方法に拠らなければならなくなります。
事前に、財産の現状分析を行った上で、納税のために売却する不動産を決めておくとか、次の相続までに時間の余裕がある時は土地活用を行い土地活用のキャッシュを留保して納税資金を貯めておくとか、延納を考えるとか、物納の準備を行っておくとか、いろいろな方策を考えておくことが重要となります。
何よりも、将来にむけて、早目、早目に財産の現状分析を行っておくことが重要です。
次回は、『相続対策』のうち『相続税の節税対策』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
前回、お話させて頂きました通り、近年の相続対策の順位は、第一に『円満な遺産分割』、第二に『相続税の納税対策』、第三に『相続税の節税対策』と言われています。
被相続人が、生前に自分の相続の対策を考えるにあたっては、先ずご自身の相続財産となるべき財産を性格に把握し、誰に何を遺すかの考えを整理しながら、相続税がいくらかかるかをシミュレーションンしつつ、各相続人への分け方と相続税の払い方を考えていくことが、合理的かと思います。
そして、それに、基づいて、節税の対策を実施していく流れが賢明と考えます。
賃貸マンション建築等の節税対策が、先行しますと、いざ、分けるときに分けられない財産となってしまいます。
また、売却して分割しようにも、かえって、売却しにくくなってしまった。
そんな、ケースが、今までに、多々、見られます。
地価が上昇しつづけている時代でしたら、売却しにくくなるというケースが想像出来ないような時代でしたので、いざというときは売却して解決が図れる。そんな時代でした。
近年は、土地価格の上昇は、期待出来ないようになりました。
土地価格の上昇が見込めない現代においては、将来の相続税のシミュレーションと財産の現状分析に基づいて納税方法を検討しておくことが大事です。
相続財産の60%は不動産であると言われています。
何ら納税対策を考えないまま相続を迎えた場合、金融資産が納税資金に遠く及ばないときは、不動産を一部売却するか、もしくは延納や物納等の方法に拠らなければならなくなります。
事前に、財産の現状分析を行った上で、納税のために売却する不動産を決めておくとか、次の相続までに時間の余裕がある時は土地活用を行い土地活用のキャッシュを留保して納税資金を貯めておくとか、延納を考えるとか、物納の準備を行っておくとか、いろいろな方策を考えておくことが重要となります。
何よりも、将来にむけて、早目、早目に財産の現状分析を行っておくことが重要です。
次回は、『相続対策』のうち『相続税の節税対策』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)