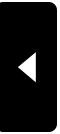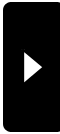PR
2013年05月26日
相続の事が少しずつ分かるいいお話115『遺言執行者④』
本日は、『遺言執行者の解任、辞任等』について、お話させていただきます。
遺執行者がその任務を怠ったとき、その他の正当な事情があるときは、相続人・受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求して遺言執行者を解任してもらうことができます。
反して、遺言執行者は正当な事情があるときに限って、家庭裁判所の許可をもらって、辞任をすることができます。
遺言執行者の報酬は遺言で定められていればそれに従って、遺言で報酬について何もふれていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうこととなります。
遺言執行につき費用がかかれば報酬とともに相続財産の中から支払われることとなります。
ただし、この費用は、被相続人の債務には該当しないので、税務上の控除は出来ないこととなります。
なお、遺言の執行が終わったなら、遺言執行者はすぐにそのことを相続人に通知しなければならないこととなります。
以上、『遺言執行者の辞任・解任等』について、お話させていただきました。
次回は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺執行者がその任務を怠ったとき、その他の正当な事情があるときは、相続人・受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求して遺言執行者を解任してもらうことができます。
反して、遺言執行者は正当な事情があるときに限って、家庭裁判所の許可をもらって、辞任をすることができます。
遺言執行者の報酬は遺言で定められていればそれに従って、遺言で報酬について何もふれていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうこととなります。
遺言執行につき費用がかかれば報酬とともに相続財産の中から支払われることとなります。
ただし、この費用は、被相続人の債務には該当しないので、税務上の控除は出来ないこととなります。
なお、遺言の執行が終わったなら、遺言執行者はすぐにそのことを相続人に通知しなければならないこととなります。
以上、『遺言執行者の辞任・解任等』について、お話させていただきました。
次回は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年05月25日
相続の事が少しずつ分かるいいお話114 『遺言執行者③』
本日は、『遺言執行者の権利と義務』について、お話させていただきます。
1 遺言執行者の権利と義務
遺言執行者が最初に行わなければならないのは、相続財産の財産目録を作って、これを相続人に渡すこととなります。
その次に、遺言執行者は、相続財産の管理をしつつ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。
たとえば、遺贈の実行としては、不動産の登記名義変更の手続きや引き渡し、動産の引き渡しなどのほか、相続財産の管理としては、賃貸不動産等が有ればその賃料の取り立てやその他の債権の回収などがあります。
必要なときには、調停や訴訟を起こしたり、その逆として訴訟の被告となることもあります。
遺言執行者にはこのような権限と義務が与えられている半面、相続人は、相続財産の処分など、この遺言執行者の執行を妨げるような行為はできなくなります。
相続人が、これに反して行った相続財産の処分等の行為は無効となります。
ただし、遺言が特定の相続財産についてだけなされた場合には、前記した遺言執行者の権限・義務および相続人の財産処分についての制限は、その特定の相続財産のみに適用されます。
たとえばある土地の遺贈についてだけ遺言があったときは、遺言執行者はその土地についてだけの財産目録を作り、管理、執行すればよいこととなり、相続人もそれ以外の財産を自由に処分することが出来ることとなります。
遺言執行者はやむを得ない事由があるときは、第三者にその任務を自分に代わって行わせることができます。
以上、『遺言執行者の権利と義務等』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者の解任・辞任等』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言執行者の権利と義務
遺言執行者が最初に行わなければならないのは、相続財産の財産目録を作って、これを相続人に渡すこととなります。
その次に、遺言執行者は、相続財産の管理をしつつ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。
たとえば、遺贈の実行としては、不動産の登記名義変更の手続きや引き渡し、動産の引き渡しなどのほか、相続財産の管理としては、賃貸不動産等が有ればその賃料の取り立てやその他の債権の回収などがあります。
必要なときには、調停や訴訟を起こしたり、その逆として訴訟の被告となることもあります。
遺言執行者にはこのような権限と義務が与えられている半面、相続人は、相続財産の処分など、この遺言執行者の執行を妨げるような行為はできなくなります。
相続人が、これに反して行った相続財産の処分等の行為は無効となります。
ただし、遺言が特定の相続財産についてだけなされた場合には、前記した遺言執行者の権限・義務および相続人の財産処分についての制限は、その特定の相続財産のみに適用されます。
たとえばある土地の遺贈についてだけ遺言があったときは、遺言執行者はその土地についてだけの財産目録を作り、管理、執行すればよいこととなり、相続人もそれ以外の財産を自由に処分することが出来ることとなります。
遺言執行者はやむを得ない事由があるときは、第三者にその任務を自分に代わって行わせることができます。
以上、『遺言執行者の権利と義務等』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者の解任・辞任等』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年05月21日
相続の事が少しずつ分かるいいお話113 『遺言執行者②』
本日は、『遺言執行者の指定他』について、お話させていただきます。
1 遺言執行者は遺言により指定することができます。
指定するのには、予め、その人の同意をえておく必要はないこととなります。
遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
ただし、未成年者および破産者は遺言執行者にはなれません。
相続人を遺言執行者とすることは、遺言執行者をおく趣旨に反する場合(例:相続人を廃除する遺言の執行)は認められないこととなりますが、その他の場合は可能です。
相続人が多勢いる場合、その1人を遺言執行者にすることは迅速な処理から意味のあることです。
遺言執行者に指定された人は、遺言執行者に就職するかどうかは自由です。
辞退してもかまわないこととなります。
辞退しようとする人は、その旨を相続人に意思を伝えれば(口頭でも文書でも)よいこととなります。
2 相続人、受遺者などの利害関係人は遺言執行者の選任を申し立て、遺言の実行をしてもらうこともできます。
遺言執行者がいないとき(指定された人が辞退したときも含む)、または死亡などでいなくなったときは、相続人や受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求をして遺言執行者を選任してもらうことができます。遺贈を受けたが相続人が財産をかかえ込んでしまって、なかなか遺言を実行してくれないといった場合には。直接相続人を相手にして調停や訴訟を起こすこともできますが、場合によっては遺言執行者を選任してもらって、遺言執行者に遺言内容を実現してもらうのも一つの方法となります。
遺言執行者の選任の請求は、相続開始地(被相続人が亡くなるときに住んでいた土地)を管轄する家庭裁判所に審判の申し立てをして行います。
家庭裁判所では、非公開で申立人や相続人などから事情を聴いて、遺言内容やその執行の難易などの事情を勘案して遺言執行者を選任します。
場合によっては、弁護士を執行者に選任することも少なくありません。
以上、『遺言執行者の指定等』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者の権利と義務他』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言執行者は遺言により指定することができます。
指定するのには、予め、その人の同意をえておく必要はないこととなります。
遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
ただし、未成年者および破産者は遺言執行者にはなれません。
相続人を遺言執行者とすることは、遺言執行者をおく趣旨に反する場合(例:相続人を廃除する遺言の執行)は認められないこととなりますが、その他の場合は可能です。
相続人が多勢いる場合、その1人を遺言執行者にすることは迅速な処理から意味のあることです。
遺言執行者に指定された人は、遺言執行者に就職するかどうかは自由です。
辞退してもかまわないこととなります。
辞退しようとする人は、その旨を相続人に意思を伝えれば(口頭でも文書でも)よいこととなります。
2 相続人、受遺者などの利害関係人は遺言執行者の選任を申し立て、遺言の実行をしてもらうこともできます。
遺言執行者がいないとき(指定された人が辞退したときも含む)、または死亡などでいなくなったときは、相続人や受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求をして遺言執行者を選任してもらうことができます。遺贈を受けたが相続人が財産をかかえ込んでしまって、なかなか遺言を実行してくれないといった場合には。直接相続人を相手にして調停や訴訟を起こすこともできますが、場合によっては遺言執行者を選任してもらって、遺言執行者に遺言内容を実現してもらうのも一つの方法となります。
遺言執行者の選任の請求は、相続開始地(被相続人が亡くなるときに住んでいた土地)を管轄する家庭裁判所に審判の申し立てをして行います。
家庭裁判所では、非公開で申立人や相続人などから事情を聴いて、遺言内容やその執行の難易などの事情を勘案して遺言執行者を選任します。
場合によっては、弁護士を執行者に選任することも少なくありません。
以上、『遺言執行者の指定等』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者の権利と義務他』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年05月19日
相続の事が少しずつ分かるいいお話112 『二世帯住宅の憂鬱』
本日は、二世帯住宅の相続対策という相談事例についてのお話をさせていただきます。
内容は、ご長男夫婦が夫の実家である父名義の土地に区分所有(登記は各々、父とご長男名義で登記)している二世帯住宅に同居しているわけですが、ご長男には嫁いでいる妹さんが2名おられ、父の相続時はもとより母の2次相続での遺産分割協議についての相談でした。
2次相続の時(母が父より長生きする前提)に、兄弟3人でどうやってわけるかが悩みの種となり、このような相談は後を絶たないようです。
ここからは仮定の話ですが、父名義の土地と自宅の区分所有分の権利の他に、預貯金、保険と株式の相続財産があったとして、不動産を除く金融資産で妹さん2人分の法定相続分を充足するのでれあれば、二世帯住宅の土地と父名義分の家屋をご長男が取得するにあたり法定相続分の問題はなく、比較的、すっきり話は纏まるでしょう。
問題は、不動産を除く金融資産で、妹さん2人分の法定相続分に足らない時です。
足らない分は、どうするか?
ご長男に、資力の余裕があれば代償分割という方法もとれます。
代償分割は、一時金でも、分割払い(相手のの相続人が了承すれば)でも可能ですので一考の余地はあります。
もっとも、遺言書で自宅の土地と区分所有の建物は、長男に相続、その他の金融資産は妹2人と遺しておけば、遺留分(この場合は法定相続分の2分の1)を犯していなければ、遺贈による分割で事なきを得ます。
最近、よくいわれるのは、この遺言とあわせてエンディングノートに自分の思いを載せて遺しておくことです。
その思いが、相続人に伝わることで円満に相続の手続きがなされるとも言われています。
さて、遺言を遺したものの、妹さんお二人の遺留分を侵害していた場合、妹さんお二人ともその遺言書通りの内容で了承すれば、そのまま、遺贈による分割で終わりますが、遺留分にみたないことに納得がいかなく遺留分の減殺請求をされた時には、ご長男は遺留分の不足分を妹さんお二人に支払わなければなりません。
それは、現金でもOKですし、支払う現金がなければ土地の共有持分の登記をするか土地建物を売却してそのお金で支払うか等になってきます。
このように考えると、相続税の税金計算にも居住用の自宅がふくまれていることは、住む家にまで税金を課税されると最悪、売却しないと払えないこととなることは、いささか、個人の財産への侵害が強すぎるとも思います。(もっとも、居住用の土地の相続税評価は一定の要件を満たせば小規模住宅用地の特例が適用され240㎡までは20%評価となりますが・・・)
また、民法上の相続財産に、親の自宅も含まれる(親の家を継承していない場合は別ですが・・・)のは、家の継承を考えると難しい面もあるように感じます。
その意味では、旧民法の家長制度は家の継承という点では、優れていたのかもしれません。
いずれにしても、財産を遺されるかたは、生前に誰に何を遺されるのか考えておき、円満な遺産相続の方法を考えることが重要であると考えます。
そして、それぞれの財産の評価(遺産分割のベースとなる実勢相場と相続税の計算のベースとなる相続税評価額。※不動産については実勢相場と相続税評価額には乖離が生じることが、多々あります。)を算定して、遺留分に問題が無いか(遺留分を満たしていなくても相続人本人が減殺請求をしなければ遺言通りとなりますので、あくまで遺留分に拘って遺言を遺すことも無いと思いますが、遺留分を充足しているか否かを意識しておくことは重要であると思います。)、相続税は発生するのか、相続税がかかるときはどうやって払うかなどの対策を準備しておくことが重要かと思います。
その他、生前の生活資金や必要資金をシミュレーションした上で、ご自身の生活のキャッシュフローもあわせて考えて、相続で何を遺してあげられるかの把握も重要なこととなってくると考えます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
内容は、ご長男夫婦が夫の実家である父名義の土地に区分所有(登記は各々、父とご長男名義で登記)している二世帯住宅に同居しているわけですが、ご長男には嫁いでいる妹さんが2名おられ、父の相続時はもとより母の2次相続での遺産分割協議についての相談でした。
2次相続の時(母が父より長生きする前提)に、兄弟3人でどうやってわけるかが悩みの種となり、このような相談は後を絶たないようです。
ここからは仮定の話ですが、父名義の土地と自宅の区分所有分の権利の他に、預貯金、保険と株式の相続財産があったとして、不動産を除く金融資産で妹さん2人分の法定相続分を充足するのでれあれば、二世帯住宅の土地と父名義分の家屋をご長男が取得するにあたり法定相続分の問題はなく、比較的、すっきり話は纏まるでしょう。
問題は、不動産を除く金融資産で、妹さん2人分の法定相続分に足らない時です。
足らない分は、どうするか?
ご長男に、資力の余裕があれば代償分割という方法もとれます。
代償分割は、一時金でも、分割払い(相手のの相続人が了承すれば)でも可能ですので一考の余地はあります。
もっとも、遺言書で自宅の土地と区分所有の建物は、長男に相続、その他の金融資産は妹2人と遺しておけば、遺留分(この場合は法定相続分の2分の1)を犯していなければ、遺贈による分割で事なきを得ます。
最近、よくいわれるのは、この遺言とあわせてエンディングノートに自分の思いを載せて遺しておくことです。
その思いが、相続人に伝わることで円満に相続の手続きがなされるとも言われています。
さて、遺言を遺したものの、妹さんお二人の遺留分を侵害していた場合、妹さんお二人ともその遺言書通りの内容で了承すれば、そのまま、遺贈による分割で終わりますが、遺留分にみたないことに納得がいかなく遺留分の減殺請求をされた時には、ご長男は遺留分の不足分を妹さんお二人に支払わなければなりません。
それは、現金でもOKですし、支払う現金がなければ土地の共有持分の登記をするか土地建物を売却してそのお金で支払うか等になってきます。
このように考えると、相続税の税金計算にも居住用の自宅がふくまれていることは、住む家にまで税金を課税されると最悪、売却しないと払えないこととなることは、いささか、個人の財産への侵害が強すぎるとも思います。(もっとも、居住用の土地の相続税評価は一定の要件を満たせば小規模住宅用地の特例が適用され240㎡までは20%評価となりますが・・・)
また、民法上の相続財産に、親の自宅も含まれる(親の家を継承していない場合は別ですが・・・)のは、家の継承を考えると難しい面もあるように感じます。
その意味では、旧民法の家長制度は家の継承という点では、優れていたのかもしれません。
いずれにしても、財産を遺されるかたは、生前に誰に何を遺されるのか考えておき、円満な遺産相続の方法を考えることが重要であると考えます。
そして、それぞれの財産の評価(遺産分割のベースとなる実勢相場と相続税の計算のベースとなる相続税評価額。※不動産については実勢相場と相続税評価額には乖離が生じることが、多々あります。)を算定して、遺留分に問題が無いか(遺留分を満たしていなくても相続人本人が減殺請求をしなければ遺言通りとなりますので、あくまで遺留分に拘って遺言を遺すことも無いと思いますが、遺留分を充足しているか否かを意識しておくことは重要であると思います。)、相続税は発生するのか、相続税がかかるときはどうやって払うかなどの対策を準備しておくことが重要かと思います。
その他、生前の生活資金や必要資金をシミュレーションした上で、ご自身の生活のキャッシュフローもあわせて考えて、相続で何を遺してあげられるかの把握も重要なこととなってくると考えます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年05月17日
相続の事が少しずつ分かるいいお話111 『遺言執行者』
本日は、『遺言執行者』について、お話させていただきます。
1 遺言の執行に遺言執行者が必要となる場合
遺言の執行が必要となる場合、その内容によって、法律により『遺言執行者』が遺言の執行をしなければならないと定められているものと、そのような定めのないものとがあります。
必ず遺言執行者により執行しなければならないのは、認知と推定相続人の廃除および廃除の取消しとなります。
これらの行為は相続人の相続分に大きな影響を与える行為ですから、相続人自身の手で行うことは妥当でないと考えられるからです。
遺贈や財団への財産への拠出は、相続人が行ってもよいのですが、相続人の利益に反することもありますので、その場合は遺言執行者を設けて執行させた方がよろしいでしょう。
遺贈の場合の登記では、遺言執行者がいた方が便利です。
銀行預金の払い戻しも、公正証書遺言で遺言執行者がいる場合はスムーズにいくこともあるようです。
以上、『遺言執行者』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者の指定他』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言の執行に遺言執行者が必要となる場合
遺言の執行が必要となる場合、その内容によって、法律により『遺言執行者』が遺言の執行をしなければならないと定められているものと、そのような定めのないものとがあります。
必ず遺言執行者により執行しなければならないのは、認知と推定相続人の廃除および廃除の取消しとなります。
これらの行為は相続人の相続分に大きな影響を与える行為ですから、相続人自身の手で行うことは妥当でないと考えられるからです。
遺贈や財団への財産への拠出は、相続人が行ってもよいのですが、相続人の利益に反することもありますので、その場合は遺言執行者を設けて執行させた方がよろしいでしょう。
遺贈の場合の登記では、遺言執行者がいた方が便利です。
銀行預金の払い戻しも、公正証書遺言で遺言執行者がいる場合はスムーズにいくこともあるようです。
以上、『遺言執行者』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者の指定他』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年05月16日
相続の事が少しずつ分かるいいお話110『遺言書の検認』
本日は、『遺言書の検認に内容』について、お話させていただきます。
1 検認とは
『検認』とは、遺言書の偽造変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために行う手続きです。
家庭裁判所が遺言書の用紙や枚数、ペン書きか毛筆か鉛筆か、遺言の内容、日付、署名、印などを調べて検認調書といわれる記録を作ります。
ですから、偽造や変造余地のない公正証書による遺言は検認の手続きを必要としないのです。
検認の手続きには、家庭裁判所は、相続人やその他の利害関係人を立ち会わせ、立ち会わなかった相続人・受遺者等には検認したことを通知することとなります。
2 検認と遺言の効力は無関係
開封や検認は、遺言書の偽造変造を防ぐための手続きとなりますので、遺言書が有効か無効かということとは関係はありません。
検認を経たからといって、その遺言が有効なものと決まるわけでなく、別に民事訴訟などで無効とされることもあります。
逆に勝手に開封したり、または検認を受けなかったからといって有効な遺言書が無効になるわけではありません。
3 開封や検認を受けなかった場合
封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認を請求しなければならない者が遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり検認手続を経ないで遺言を執行したときは、一定の過料に処せられることとなります。
さらに、遺言書の提出、検認を怠るばかりでなく、相続人がこれを偽造・変造・破棄あるいは隠匿したりすると、その相続人は相続欠格者として相続人となれなくなりますし、相続人以外の受遺者がそのようなことをすると、受遺資格を失い遺贈を一切受けられないこととなりますので、注意を要します。
以上、『遺言書の検認の内容』についてを、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 検認とは
『検認』とは、遺言書の偽造変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために行う手続きです。
家庭裁判所が遺言書の用紙や枚数、ペン書きか毛筆か鉛筆か、遺言の内容、日付、署名、印などを調べて検認調書といわれる記録を作ります。
ですから、偽造や変造余地のない公正証書による遺言は検認の手続きを必要としないのです。
検認の手続きには、家庭裁判所は、相続人やその他の利害関係人を立ち会わせ、立ち会わなかった相続人・受遺者等には検認したことを通知することとなります。
2 検認と遺言の効力は無関係
開封や検認は、遺言書の偽造変造を防ぐための手続きとなりますので、遺言書が有効か無効かということとは関係はありません。
検認を経たからといって、その遺言が有効なものと決まるわけでなく、別に民事訴訟などで無効とされることもあります。
逆に勝手に開封したり、または検認を受けなかったからといって有効な遺言書が無効になるわけではありません。
3 開封や検認を受けなかった場合
封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認を請求しなければならない者が遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり検認手続を経ないで遺言を執行したときは、一定の過料に処せられることとなります。
さらに、遺言書の提出、検認を怠るばかりでなく、相続人がこれを偽造・変造・破棄あるいは隠匿したりすると、その相続人は相続欠格者として相続人となれなくなりますし、相続人以外の受遺者がそのようなことをすると、受遺資格を失い遺贈を一切受けられないこととなりますので、注意を要します。
以上、『遺言書の検認の内容』についてを、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年05月15日
相続の事が少しずつ分かるいいお話109『遺言書の開封』
本日は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。
遺言書を発見した場合には、封印(遺言書が封筒に封入され封に押印のされたもの)のあるものは、すぐに開封してはいけないこととなります。
遺言は、身分関係や財産関係に大きな影響を与えるものですから、公正証書遺言を除いて、家庭裁判所で開封(封印のある遺言書についてだけ)し、検認という手続きをふまなければなりません。
遺言が二通以上でてきたときは、効力としては新しい日付のものを優先しますが、開封や検認の手続きはすべてについてしなければならないこととなります。
1 開封は家庭裁判所で
封印のある遺言書は、家庭裁判所ですべての相続人またはその代理人が立ち会わなければ開封できないこととなります。
もっとも、ある相続人が家庭裁判所での立ち会いに応じない時は、その相続人の立ち会いなしに開封することはできます。
封印のない遺言書には、このような手続きの必要はありません。
2 家庭裁判所で検認を受ける。
公正証書による遺言書以外はみな、家庭裁判所にその遺言書を提出して『検認』という手続きを受けなければなりません。
『臨終遺言』や『船舶遭難時遺言』で家庭裁判所の『確認』を受けたものでも同様となります。
封印のある遺言書については、開封の手続きと一緒に行うこととなります。
以上、『遺言書の開封』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の検認の内容』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺言書を発見した場合には、封印(遺言書が封筒に封入され封に押印のされたもの)のあるものは、すぐに開封してはいけないこととなります。
遺言は、身分関係や財産関係に大きな影響を与えるものですから、公正証書遺言を除いて、家庭裁判所で開封(封印のある遺言書についてだけ)し、検認という手続きをふまなければなりません。
遺言が二通以上でてきたときは、効力としては新しい日付のものを優先しますが、開封や検認の手続きはすべてについてしなければならないこととなります。
1 開封は家庭裁判所で
封印のある遺言書は、家庭裁判所ですべての相続人またはその代理人が立ち会わなければ開封できないこととなります。
もっとも、ある相続人が家庭裁判所での立ち会いに応じない時は、その相続人の立ち会いなしに開封することはできます。
封印のない遺言書には、このような手続きの必要はありません。
2 家庭裁判所で検認を受ける。
公正証書による遺言書以外はみな、家庭裁判所にその遺言書を提出して『検認』という手続きを受けなければなりません。
『臨終遺言』や『船舶遭難時遺言』で家庭裁判所の『確認』を受けたものでも同様となります。
封印のある遺言書については、開封の手続きと一緒に行うこととなります。
以上、『遺言書の開封』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の検認の内容』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年05月08日
相続の事が少しずつ分かるいいお話108『遺言書の預り』
本日は、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。
1 遺言書を他人に預かってもらう場合には、利害関係の無い公正な第三者に頼みましょう。
遺言書を遺言者自身が保管せずに、配偶者やその他の相続人、友人などに預けておくことも多いようです。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくことが適当なこととなります。
遺贈や相続分の指定により財産をあげることとした者に預けておけば、誠意をもって面倒をみてもらえるという感がえ方もあります。
ただし、自筆証書遺言の場合は、後に隠匿、改ざんといった面倒な問題にならないためには、遺産に何の利害関係をもたない公正な第三者に保管してもらうとよろしいでしょう。
弁護士に頼んでその事務所で預かってもらうのも一案です。
弁護士は書類の保管には気を使っていますし、守秘義務についても厳密ですので安心でしょう。
また、取引銀行で預かってもらのも一案です。
『封緘預かり』と、貸金庫という制度がありますので、どりらでも安心ですので、どちらでもよろしいかと思います。
ただし、これらの制度は銀行と取引先(遺言者)の寄託契約あるいは金庫の賃貸借契約と解されていますので、遺言者の死後遺言書を返してもらうには相続人全員の同意のあることを証明する書面を必要とすることになりますので注意が必要です。
以上、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言書を他人に預かってもらう場合には、利害関係の無い公正な第三者に頼みましょう。
遺言書を遺言者自身が保管せずに、配偶者やその他の相続人、友人などに預けておくことも多いようです。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくことが適当なこととなります。
遺贈や相続分の指定により財産をあげることとした者に預けておけば、誠意をもって面倒をみてもらえるという感がえ方もあります。
ただし、自筆証書遺言の場合は、後に隠匿、改ざんといった面倒な問題にならないためには、遺産に何の利害関係をもたない公正な第三者に保管してもらうとよろしいでしょう。
弁護士に頼んでその事務所で預かってもらうのも一案です。
弁護士は書類の保管には気を使っていますし、守秘義務についても厳密ですので安心でしょう。
また、取引銀行で預かってもらのも一案です。
『封緘預かり』と、貸金庫という制度がありますので、どりらでも安心ですので、どちらでもよろしいかと思います。
ただし、これらの制度は銀行と取引先(遺言者)の寄託契約あるいは金庫の賃貸借契約と解されていますので、遺言者の死後遺言書を返してもらうには相続人全員の同意のあることを証明する書面を必要とすることになりますので注意が必要です。
以上、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年05月04日
相続の事が少しずつ分かるいいお話107 『遺言書の保管』
本日は、『遺言の保管』について、お話させていただきます。
1 遺言の意思表示をしても遺言書が見つからなければ遺言の効力は生じない。
遺言は、遺言者の意思が、しっかりと、かつ、正確に相続人等に伝えられるように、必ず書面で、しかも民法の定める方式に従った書面によってなされることが要求されているわけです。
しかし、遺言者が生前にせっかく方式に従った遺言を遺したとしても、その遺言書が見つからなければ遺言は、当然、何の効果も発揮せず、遺産分割協議によることとなります。
2 遺言書は安全で分かりやすい場所に保管
1のような危険があることから、遺言書は、他の書類と紛れたり紛失したりしない場所で、しかも遺言者が亡くなった後でも相続人達がすぐわかるような、しかし隠匿されたり書き換えられたりする心配のない安全な場所に保管しておくことが大事です。
ただし、あまり難しいところにしまってしまいますと、相続人達が発見できないおそれもありますし、発見されても死後何年もたっていて遺産分割も済んでしまっていては法律関係が複雑になり厄介なこととなります。
この点、公正証書遺言による遺言であれば安心です。
公正証書はその原本が公証役場に保管されて安全ですから、相続人たちにどこの公証役場に遺言書があるということを明らかにしておけばよろしいわけです。
なお、遺言者以外の者が、遺言者の生前に遺言公正証書の閲覧を請求しても、公証人はこの請求には応じませんから、秘密の点からも安心です。
以上、『遺言書の保管』について、お話させていただきました。
次回は、補足として『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言の意思表示をしても遺言書が見つからなければ遺言の効力は生じない。
遺言は、遺言者の意思が、しっかりと、かつ、正確に相続人等に伝えられるように、必ず書面で、しかも民法の定める方式に従った書面によってなされることが要求されているわけです。
しかし、遺言者が生前にせっかく方式に従った遺言を遺したとしても、その遺言書が見つからなければ遺言は、当然、何の効果も発揮せず、遺産分割協議によることとなります。
2 遺言書は安全で分かりやすい場所に保管
1のような危険があることから、遺言書は、他の書類と紛れたり紛失したりしない場所で、しかも遺言者が亡くなった後でも相続人達がすぐわかるような、しかし隠匿されたり書き換えられたりする心配のない安全な場所に保管しておくことが大事です。
ただし、あまり難しいところにしまってしまいますと、相続人達が発見できないおそれもありますし、発見されても死後何年もたっていて遺産分割も済んでしまっていては法律関係が複雑になり厄介なこととなります。
この点、公正証書遺言による遺言であれば安心です。
公正証書はその原本が公証役場に保管されて安全ですから、相続人たちにどこの公証役場に遺言書があるということを明らかにしておけばよろしいわけです。
なお、遺言者以外の者が、遺言者の生前に遺言公正証書の閲覧を請求しても、公証人はこの請求には応じませんから、秘密の点からも安心です。
以上、『遺言書の保管』について、お話させていただきました。
次回は、補足として『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年05月02日
相続の事が少しずつ分かるいいお話106 『偽造等による遺言』
本日は、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきます。
1 偽造の遺言
偽造の遺言書などは、もともとは、本人の遺言ではないわけですから、効力を生ずることはありません。
その遺言により財産の遺贈をうけたと称する人が財産を要求してきたりしたときは、相続人はその遺言の無効を主張して争えばよいわけです。
また、相続人および利害関係人の側から、その遺言を有効だと主張する人を相手に遺言無効確認の訴えを起して裁判所にその無効を確認してもらうこともできます。
2 脅迫・詐欺による遺言
脅迫・詐欺による場合は、遺言者がその後も生存していることも多いこととなります。
遺言者は、この脅迫もしくは騙されてなした遺言をいつでも取り消すことができることとなりますし、また取り消さずに新しく遺言を行うことによってこの遺言を撤回する方法もあります。
要は、取り消しは、その意思表示が一般人に分かるようにしおけばいいわけですから、特別に方式は決まっていません。
遺言者が取消しも撤回もしないで死亡したときは、遺言者の相続人がその取消権を相続しますから、相続人が遺言の取消しをすることができます。取消しをしたうえで遺言無効確認の訴えを起こすことも可能です。なお、遺言の取消しには、共同相続人が何人かいれば、その相続分が過半数以上になるだけの相続人の決議を得ることが必要です。
3 詐欺・脅迫・偽造者の欠格
詐欺または強迫によって遺言させたり、遺言書を偽造・変造したりした者は、欠格者として相続人になることも遺贈を受けることもできないこととなります。
つまりは、遺言の取消しを相談する際にも、こうした人達は相続人として扱う必要はないこととなります。
以上、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の保管』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 偽造の遺言
偽造の遺言書などは、もともとは、本人の遺言ではないわけですから、効力を生ずることはありません。
その遺言により財産の遺贈をうけたと称する人が財産を要求してきたりしたときは、相続人はその遺言の無効を主張して争えばよいわけです。
また、相続人および利害関係人の側から、その遺言を有効だと主張する人を相手に遺言無効確認の訴えを起して裁判所にその無効を確認してもらうこともできます。
2 脅迫・詐欺による遺言
脅迫・詐欺による場合は、遺言者がその後も生存していることも多いこととなります。
遺言者は、この脅迫もしくは騙されてなした遺言をいつでも取り消すことができることとなりますし、また取り消さずに新しく遺言を行うことによってこの遺言を撤回する方法もあります。
要は、取り消しは、その意思表示が一般人に分かるようにしおけばいいわけですから、特別に方式は決まっていません。
遺言者が取消しも撤回もしないで死亡したときは、遺言者の相続人がその取消権を相続しますから、相続人が遺言の取消しをすることができます。取消しをしたうえで遺言無効確認の訴えを起こすことも可能です。なお、遺言の取消しには、共同相続人が何人かいれば、その相続分が過半数以上になるだけの相続人の決議を得ることが必要です。
3 詐欺・脅迫・偽造者の欠格
詐欺または強迫によって遺言させたり、遺言書を偽造・変造したりした者は、欠格者として相続人になることも遺贈を受けることもできないこととなります。
つまりは、遺言の取消しを相談する際にも、こうした人達は相続人として扱う必要はないこととなります。
以上、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の保管』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年05月01日
相続の事が少しずつ分かるいいお話105『遺言書の無効』
本日は、『遺言書の無効』について、お話させて頂きます。
1 遺言の無効
遺言は重大な法律行為となりますから、遺言者が遺言の時に自分の行為の意味を理解できるだけの能力を備えた上で、かつ本人の自由な意思に基づいてなされたものでなければなりません。
したがって、遺言の当時遺言者が錯乱していて遺言をする能力を欠いていたといった場合は、その遺言は無効であって、遺言としての効力をまったくもたないこととなります。
次回は、『偽造の遺言と脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言の無効
遺言は重大な法律行為となりますから、遺言者が遺言の時に自分の行為の意味を理解できるだけの能力を備えた上で、かつ本人の自由な意思に基づいてなされたものでなければなりません。
したがって、遺言の当時遺言者が錯乱していて遺言をする能力を欠いていたといった場合は、その遺言は無効であって、遺言としての効力をまったくもたないこととなります。
次回は、『偽造の遺言と脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年04月29日
相続の事が少しずつ分かるいいお話104 『遺言の撤回』
本日は、『遺言で撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合』について、お話させていただきます。
1 遺言で撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合
遺言の撤回は、遺言の方式(前回のお話の内容)によることとされていますが、民法は次の四つの場合には、撤回の遺言がなくても遺言の撤回があったものとして扱うこととされています。
①後の遺言で前の遺言内容に抵触する遺言をしたとき(民法1023条1項)
②遺言をした後にその遺言内容に抵触する法律行為をしたとき(民法1023条2項)
③遺言者が故意に遺言書を破棄したとき(民法1024条前段)
④遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき(民法1024条後段)
民法がこのような規定を定めたのには、こうした事実があれば遺言者には撤回の意思があると認められることから、このように扱うことこそが遺言者の最終意思にかなうと考えられることによるからです。
次回は、上記①~④の場合のそれぞれの詳細の内容について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言で撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合
遺言の撤回は、遺言の方式(前回のお話の内容)によることとされていますが、民法は次の四つの場合には、撤回の遺言がなくても遺言の撤回があったものとして扱うこととされています。
①後の遺言で前の遺言内容に抵触する遺言をしたとき(民法1023条1項)
②遺言をした後にその遺言内容に抵触する法律行為をしたとき(民法1023条2項)
③遺言者が故意に遺言書を破棄したとき(民法1024条前段)
④遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき(民法1024条後段)
民法がこのような規定を定めたのには、こうした事実があれば遺言者には撤回の意思があると認められることから、このように扱うことこそが遺言者の最終意思にかなうと考えられることによるからです。
次回は、上記①~④の場合のそれぞれの詳細の内容について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年04月28日
相続の事が少しずつ分かるいいお話103 『遺言の撤回と変更』
本日は、『遺言の撤回と変更』について、お話させていただきます。
1 遺言者は以前の遺言を自由に撤回・変更することができます。
民法では、『遺言者は、何時でも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を取り消すことができる。』(民1022上)と規定して、遺言撤回自由の原則を認めています。
遺言はもともと、遺言者の最終の意思を尊重し、それに効力を認めようとする制度ですから、遺言者が一度遺言をしてもその後死亡するまでの間に意思を自由に変えることができ、かつ法律がこれを保障するのは当然のこととなります。
したがって、遺言者は、何の原因がなくても、誰の同意も必要とせずに、全部でも一部でも前の遺言を撤回、変更することができることとなります。また、遺言を撤回する権利を放棄するなどということもできないこととなります(民1026条)。たとえば、『この遺言は今後絶対に変更しない』などと遺言書に書いてあったとしても無意味となります。
遺言の撤回は、有効な方式に従った遺言により行います。『○年○月○日付遺言書による遺言の全部(または××の部分)を撤回する。』と遺言すればよいこととなります。
有効な方式による遺言でさえあれば、その方式の種類は問われないこととなります。
前の公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回することもできます。
なお、混乱を避けるためには、前の遺言書を破り棄てておくのがよろしいでしょう。
本日は、『遺言の撤回と変更』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言の撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言者は以前の遺言を自由に撤回・変更することができます。
民法では、『遺言者は、何時でも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を取り消すことができる。』(民1022上)と規定して、遺言撤回自由の原則を認めています。
遺言はもともと、遺言者の最終の意思を尊重し、それに効力を認めようとする制度ですから、遺言者が一度遺言をしてもその後死亡するまでの間に意思を自由に変えることができ、かつ法律がこれを保障するのは当然のこととなります。
したがって、遺言者は、何の原因がなくても、誰の同意も必要とせずに、全部でも一部でも前の遺言を撤回、変更することができることとなります。また、遺言を撤回する権利を放棄するなどということもできないこととなります(民1026条)。たとえば、『この遺言は今後絶対に変更しない』などと遺言書に書いてあったとしても無意味となります。
遺言の撤回は、有効な方式に従った遺言により行います。『○年○月○日付遺言書による遺言の全部(または××の部分)を撤回する。』と遺言すればよいこととなります。
有効な方式による遺言でさえあれば、その方式の種類は問われないこととなります。
前の公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回することもできます。
なお、混乱を避けるためには、前の遺言書を破り棄てておくのがよろしいでしょう。
本日は、『遺言の撤回と変更』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言の撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年04月27日
相続の事が少しずつ分かるいいお話102『公正証書遺言作成準備』
本日は、公正証書遺言作成において準備するものを、お話させていただきます。
1 実印と印鑑証明書
本人の印鑑証明書と実印が必要となります。
公証人に遺言の内容を口頭で述べる人が遺言者本人であることを証明するために必要となります。
実印の登録をしていなかったとか、または、印鑑証明書等を取り寄せる時間のないときは、運転免許書やパスポート、外国人登録証明書などの官公署発行の写真入り証明書(企業などが発行する身分証明書は本人を証するものとしては不適格となります。)と認印を持参することになります。
2 その他用意しておきたいもの
相続財産に不動産がある場合は、登記簿謄本か登記済証(権利証)を持参します。
相続や遺贈により不動産の所有名義を換える際に、遺言書は所有権移転登記のために必要な書類となるので、土地、建物の表示が正確に記載されている必要があります。
あわせて、作成手数料算出の参考とするため、固定資産税の評価証明書もとっておくとよろしいでしょう。遺言を正確にするために、遺言者および遺言により遺産を取得させる人の戸籍謄本なども用意するとよろしいでしょう。
以上の書類は、できれば、予め公証人に渡しておくとことをおすすめします。
以上、『公正証書遺言作成の準備』についてお話させていただきました。
次回も、遺言に関するお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 実印と印鑑証明書
本人の印鑑証明書と実印が必要となります。
公証人に遺言の内容を口頭で述べる人が遺言者本人であることを証明するために必要となります。
実印の登録をしていなかったとか、または、印鑑証明書等を取り寄せる時間のないときは、運転免許書やパスポート、外国人登録証明書などの官公署発行の写真入り証明書(企業などが発行する身分証明書は本人を証するものとしては不適格となります。)と認印を持参することになります。
2 その他用意しておきたいもの
相続財産に不動産がある場合は、登記簿謄本か登記済証(権利証)を持参します。
相続や遺贈により不動産の所有名義を換える際に、遺言書は所有権移転登記のために必要な書類となるので、土地、建物の表示が正確に記載されている必要があります。
あわせて、作成手数料算出の参考とするため、固定資産税の評価証明書もとっておくとよろしいでしょう。遺言を正確にするために、遺言者および遺言により遺産を取得させる人の戸籍謄本なども用意するとよろしいでしょう。
以上の書類は、できれば、予め公証人に渡しておくとことをおすすめします。
以上、『公正証書遺言作成の準備』についてお話させていただきました。
次回も、遺言に関するお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年04月26日
相続の事が少しずつ分かるいいお話101『公正証書遺言作成準備』
本日は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。
公正証書遺言の作成には、次の様な準備が必要となってきます。
1 証人の用意
最初に、証人二人を用意することが必要となります。
この証人は誰でもいいというわけではありません。
証人は、遺言者が、正常な精神状態で、遺言を公証人に口頭で述べたことを確認し、公証人の事務を監督する役割を負うことから、『未成年者』や遺言者の『推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系尊属』(例、夫、妻、息子、娘、嫁、婿、孫など)、『公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人』は証人にはなれないこととなります。
この証人になれない人を証人として作られた遺言は、無効となります。
証人は、遺言の内容を知ってしまいますので、信用のおける人、秘密を守れる人がよろしいでしょう。
菩提寺の僧侶、友人などの他、弁護士に証人となってもらうこともできます。
弁護士に依頼すればもう一人の証人も用意してもらえます。
証人には認印を準備してもらいます。
次回も、公正証書遺言の準備について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
公正証書遺言の作成には、次の様な準備が必要となってきます。
1 証人の用意
最初に、証人二人を用意することが必要となります。
この証人は誰でもいいというわけではありません。
証人は、遺言者が、正常な精神状態で、遺言を公証人に口頭で述べたことを確認し、公証人の事務を監督する役割を負うことから、『未成年者』や遺言者の『推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系尊属』(例、夫、妻、息子、娘、嫁、婿、孫など)、『公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人』は証人にはなれないこととなります。
この証人になれない人を証人として作られた遺言は、無効となります。
証人は、遺言の内容を知ってしまいますので、信用のおける人、秘密を守れる人がよろしいでしょう。
菩提寺の僧侶、友人などの他、弁護士に証人となってもらうこともできます。
弁護士に依頼すればもう一人の証人も用意してもらえます。
証人には認印を準備してもらいます。
次回も、公正証書遺言の準備について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年04月25日
相続の事が少しずつ分かるいいお話100『公正証書遺言の注意点』
本日は、『公正証書遺言の書き方の注意点』についてお話させていただきます。
1 公正証書遺言の手続きは次の通りとなります。
①証人二人以上で立ち会いをし、遺言者が口頭で遺言の内容を口頭で述べることとなります。(法律上は口授と呼んでいます。)公証人はこれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます。
②遺言者と証人は筆記が正確であることを確認したら、署名と捺印をします。
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名にかえることができます。また、遺言者の印は原則として実印であることが必要ですが、証人は認印でOKです。
③最後に、公証人が署名と押印をします。
なお、口が不自由な場合には、通訳人の通訳か辞書により、口授に代えることができます。
耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により伝えることで、読み聞かせに代えることができます。
以上、公正証書遺言の書き方の注意点についてお話させて頂きました。
次回は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 公正証書遺言の手続きは次の通りとなります。
①証人二人以上で立ち会いをし、遺言者が口頭で遺言の内容を口頭で述べることとなります。(法律上は口授と呼んでいます。)公証人はこれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます。
②遺言者と証人は筆記が正確であることを確認したら、署名と捺印をします。
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名にかえることができます。また、遺言者の印は原則として実印であることが必要ですが、証人は認印でOKです。
③最後に、公証人が署名と押印をします。
なお、口が不自由な場合には、通訳人の通訳か辞書により、口授に代えることができます。
耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により伝えることで、読み聞かせに代えることができます。
以上、公正証書遺言の書き方の注意点についてお話させて頂きました。
次回は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年04月24日
相続の事が少しずつ分かるいいお話99『遺言書の書き方ポイント』
本日は、『遺言の書き方のポイント』について、お話させていただきます。
遺言を遺す際の一番のポイントは、何を、誰に、相続させる(遺贈する)のかを明確にさせることです。
相手が法定相続人なら『相続させる』、法定相続人以外なら『遺贈する』と記載します。
1 相続させる物を明確に特定して記載する
相続させる対象物がどのようなものであるかが、遺言者や相続人の当事者間で十分に分かってもいても、第三者が分からないと、相続による名義変更がスムーズになされないことが起こりえます。
土地、建物などでは、遺言書に地番、家屋番号等が明確に記載されていれば、遺言執行者と当該の相続人・受贈者だけで登記をすることができます。
しかし、たとえば『一、自宅の家屋敷は長男丙に。二、軽井沢の別荘は妻乙に相続させる』という遺言書では、物件の表示が遺言書上、抽象的でありあきらかでないので、これだけでは登記を長男丙、妻乙に移転させることはできません。
せっかく、遺言書を作成するのであれば、多少の手間はかかっても、土地、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せて、登記簿通りに不動産の所在、地番(家屋にあっては家屋番号)、地目(家屋にあっては建物の種類・構造)、地積(家屋にあっては床面積)を記載すべきでしょう。
2 相続人を特定して記載する
たとえば、戸籍上の長男が生後間もなく死亡したような場合は、戸籍上は二男でも世間では長男として認識されている場合があります。
ここで『長男に○○を相続させる』と遺言した場合は問題が起きてしまうこととなります。
相続させる人には、遺言者との続柄の他、氏名や生年月日も記載して特定しておくほうがよろしいでしょう。
本日は、『遺言の書き方のポイント』についてお話させていただきました。
次回は、『公正証書遺言の手続きの注意点』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺言を遺す際の一番のポイントは、何を、誰に、相続させる(遺贈する)のかを明確にさせることです。
相手が法定相続人なら『相続させる』、法定相続人以外なら『遺贈する』と記載します。
1 相続させる物を明確に特定して記載する
相続させる対象物がどのようなものであるかが、遺言者や相続人の当事者間で十分に分かってもいても、第三者が分からないと、相続による名義変更がスムーズになされないことが起こりえます。
土地、建物などでは、遺言書に地番、家屋番号等が明確に記載されていれば、遺言執行者と当該の相続人・受贈者だけで登記をすることができます。
しかし、たとえば『一、自宅の家屋敷は長男丙に。二、軽井沢の別荘は妻乙に相続させる』という遺言書では、物件の表示が遺言書上、抽象的でありあきらかでないので、これだけでは登記を長男丙、妻乙に移転させることはできません。
せっかく、遺言書を作成するのであれば、多少の手間はかかっても、土地、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せて、登記簿通りに不動産の所在、地番(家屋にあっては家屋番号)、地目(家屋にあっては建物の種類・構造)、地積(家屋にあっては床面積)を記載すべきでしょう。
2 相続人を特定して記載する
たとえば、戸籍上の長男が生後間もなく死亡したような場合は、戸籍上は二男でも世間では長男として認識されている場合があります。
ここで『長男に○○を相続させる』と遺言した場合は問題が起きてしまうこととなります。
相続させる人には、遺言者との続柄の他、氏名や生年月日も記載して特定しておくほうがよろしいでしょう。
本日は、『遺言の書き方のポイント』についてお話させていただきました。
次回は、『公正証書遺言の手続きの注意点』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年04月23日
相続の事が少しずつ分かるいいお話98 『自筆証書遺言⑤』
本日も、自筆証書遺言の注意点について、お話させていただきます。
1 自筆証書遺言の訂正方法
自筆証書遺言(秘密証書遺言も同様)の場合、遺言書の字句の加除訂正するにも一定の決まった方法によらねばなりません。
加除訂正するには、必ず、①変更した箇所に印を押したうえ、②その場所を指示して変更したことを付記し、③付記したあとの署名をします。印を押すだけでなく署名が必要とされる点に注意が必要です。
いずれにしても、訂正は面倒であることと汚くなるので、全文を新しく書き直す方がよろしいかと思います。
ただし、判例では、明白な誤記の訂正の場合は、訂正要件に反する部分があったとしても遺言は無効にならないとしたケースがあります。
とはいえ、のちのちに面倒なことが起きないように、まず下書きしてをしてから十分に検討のうえ、清書することをおすすめします。
以上、自筆証書遺言の訂正についての注意点についてお話させていただきました。
次回は、『遺言書の書き方のポイント』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 自筆証書遺言の訂正方法
自筆証書遺言(秘密証書遺言も同様)の場合、遺言書の字句の加除訂正するにも一定の決まった方法によらねばなりません。
加除訂正するには、必ず、①変更した箇所に印を押したうえ、②その場所を指示して変更したことを付記し、③付記したあとの署名をします。印を押すだけでなく署名が必要とされる点に注意が必要です。
いずれにしても、訂正は面倒であることと汚くなるので、全文を新しく書き直す方がよろしいかと思います。
ただし、判例では、明白な誤記の訂正の場合は、訂正要件に反する部分があったとしても遺言は無効にならないとしたケースがあります。
とはいえ、のちのちに面倒なことが起きないように、まず下書きしてをしてから十分に検討のうえ、清書することをおすすめします。
以上、自筆証書遺言の訂正についての注意点についてお話させていただきました。
次回は、『遺言書の書き方のポイント』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年04月20日
相続の事が少しずつ分かるいいお話97 『自筆証書遺言④』
本日は、『自筆証書遺言④』について、お話させていただきます。
1 自筆証書遺言の印について
印鑑登録をした実印に拘りません。
三文判でOKです。さらには拇印(指印)でもかまいません。(最高裁平成元年二月一六日判決)
しかし、三文判は誰でも手に入れてしまえることから、偽造した遺言書と疑われ紛争に発展する危険があること、また拇印は不鮮明であることからホ人の拇印であるのか否かを判断するのが困難であることから、おすすめできません。
そのことから、やはり、実印か銀行取引用の印を押印することがよろしいでしょう。
2 封筒について
遺言書を作成して封筒に封入し封印することは必要要件とはなっておりません。
ただし、簡単に人に見られないように封印される方が大多数です。
また、封印しておけば、遺言者死亡後に遺言書を発見した場合、相続人が家庭裁判所に遺言書を持参し、開封する手続き(検認)をとることとなります。
以上、『自筆証書遺言』の注意点についてお話させて頂きました。
次回は、自筆証書遺言の訂正の注意点についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 自筆証書遺言の印について
印鑑登録をした実印に拘りません。
三文判でOKです。さらには拇印(指印)でもかまいません。(最高裁平成元年二月一六日判決)
しかし、三文判は誰でも手に入れてしまえることから、偽造した遺言書と疑われ紛争に発展する危険があること、また拇印は不鮮明であることからホ人の拇印であるのか否かを判断するのが困難であることから、おすすめできません。
そのことから、やはり、実印か銀行取引用の印を押印することがよろしいでしょう。
2 封筒について
遺言書を作成して封筒に封入し封印することは必要要件とはなっておりません。
ただし、簡単に人に見られないように封印される方が大多数です。
また、封印しておけば、遺言者死亡後に遺言書を発見した場合、相続人が家庭裁判所に遺言書を持参し、開封する手続き(検認)をとることとなります。
以上、『自筆証書遺言』の注意点についてお話させて頂きました。
次回は、自筆証書遺言の訂正の注意点についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年04月18日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 96 『自筆証書遺言③』
本日は、『自筆証書遺言』の続きについてお話させていただきます。
1 氏名についての注意点
自分の氏名も必ず自署する必要があります。自署ではなく記名印を押した場合の遺言は無効となります。
氏名は、戸籍上の氏名を記載することとなります。しかし、全く、一字一句同じでなくても問題ありません。
たとえば、『廣』を『広』と書いても有効となります。
また、同一性が分かれば名前だけでも、例えば、『父達也』でも無効とはなりませんが、きちんと『荒木達也』と性も書いてください。
遺言者本人の同一性が十分わかれば通称・芸名・雅号でもよいのですが、遺言者の効力が生じるのは遺言者の死亡後となりますので、雅号・芸名を書く場合でも、雅号・芸名と併せて遺言者の本名を遺言書の中に記載し明らかにしておいた方がよろしいでしょう。
以上、『自筆証書遺言』の氏名の書き方の注意点をお話させていただきました。
次回も、『自筆証書遺言』の注意点について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 氏名についての注意点
自分の氏名も必ず自署する必要があります。自署ではなく記名印を押した場合の遺言は無効となります。
氏名は、戸籍上の氏名を記載することとなります。しかし、全く、一字一句同じでなくても問題ありません。
たとえば、『廣』を『広』と書いても有効となります。
また、同一性が分かれば名前だけでも、例えば、『父達也』でも無効とはなりませんが、きちんと『荒木達也』と性も書いてください。
遺言者本人の同一性が十分わかれば通称・芸名・雅号でもよいのですが、遺言者の効力が生じるのは遺言者の死亡後となりますので、雅号・芸名を書く場合でも、雅号・芸名と併せて遺言者の本名を遺言書の中に記載し明らかにしておいた方がよろしいでしょう。
以上、『自筆証書遺言』の氏名の書き方の注意点をお話させていただきました。
次回も、『自筆証書遺言』の注意点について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)