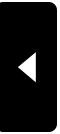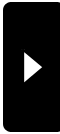PR
2014年01月08日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『生命保険の税務②』について
本日は、『生命保険の税務②』についてを、お話させていただきます。
1・生命保険の税務関係
生命保険に関して保険事故の発生等何らかの動きがあると、その態様に応じて相続税や所得税(一時所得)、贈与税の課税関係が発生します。これらを各税目ごとにみていくこととします。
(1)相続税
税法が注目する保険料負担者(通常は保険契約者、以下保険契約者と表現します)が死亡した場合には、その相続人等に相続税が課されます。
典型的な場合は、保険契約者(すなわち保険料負担者)が被保険者になっている場合において、その人が死亡するケースです。(夫が自分を被保険者、妻や子を受取人として保険を契約した後、夫が死亡した場合)。この場合、その死亡保険金がみなし相続財産として相続税が課されるパターンです(法定相続人1人500万円の非課税枠あり)。
一方、被保険者ではない保険契約者が死亡した(たとえば、孫を被保険者として祖父が保険を契約していたところ、その祖父が死亡した)場合には、死亡保険金は出ません。しかし契約者としての地位(預金にたとえると預金者の立場)は誰かが継承します。すなわち、その承継者が生命保険契約の権利を相続したことになります。これに対して相続税が課されるわけです。
生命保険契約の権利とは、分かりやすく言えば契約を解約した場合の解約返戻金を受け取るこののできる権利です。契約者はいつでも保険を解約することができるのです。相続税の評価額は『解約返戻金』で評価することとなります。
(2)所得税
保険事故が発生した場合において、死亡保険金の受取人が保険契約者(保険料負担者)であった場合には、その受取人には所得税(一時所得)が課されます。父を被保険者として、息子が自らを保険金受取人として保険料を払っていた場合に、父が死亡したというケースです。
この場合の息子は、自らの負担において自らが収入を得たわけですから、当然所得税の対象となるわけです。(実際の所得額は受取保険金から払込み保険料を控除した額をベースに計算する)。なお仮にこのケースで、息子が保険料のうち6割を、被保険者である父が4割を負担していた場合には、その受取保険金のうち6割が所得税、4割が相続税の課税対象となります。要するに保険料の負担割合によって課税されるわけです。
(3)贈与税
先の所得税は、負担者=受取人の場合でしたが、負担者≠受取人であればどうなるでしょうか。この場合は、保険金(満期保険金を含む)を取得した保険金受取人は、保険料負担者から贈与により取得したこととされます。
受取人が何の負担もしないで保険金を取得しているわけですから、当然といえましょう。しかし税率の高い贈与税をかけられたのではたまりません。保険に入る場合には、この辺をよく考えて加入すべきでしょう。
なお、保険契約者を変更すると、従前の契約者から新契約者にこの生命保険契約の権利が贈与されたこととなります。預金の名義をかえたことと同じことですから当然といえましょう。
例をあげますと、Aを被保険者、Bを保険金受取人、Cを保険契約者とした保険契約において、実際の保険料はAが5割、Bが3割、Cが2割を払っていたところ、保険事故が発生し、受取人であるBが1,000万円の死亡保険金を受け取りました。この課税関係はどうなるか、という話です。
答えは、500万円が相続税、300万円が所得税、200万円が贈与税の課税対象となります。
以上、『生命保険の税務②』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
1・生命保険の税務関係
生命保険に関して保険事故の発生等何らかの動きがあると、その態様に応じて相続税や所得税(一時所得)、贈与税の課税関係が発生します。これらを各税目ごとにみていくこととします。
(1)相続税
税法が注目する保険料負担者(通常は保険契約者、以下保険契約者と表現します)が死亡した場合には、その相続人等に相続税が課されます。
典型的な場合は、保険契約者(すなわち保険料負担者)が被保険者になっている場合において、その人が死亡するケースです。(夫が自分を被保険者、妻や子を受取人として保険を契約した後、夫が死亡した場合)。この場合、その死亡保険金がみなし相続財産として相続税が課されるパターンです(法定相続人1人500万円の非課税枠あり)。
一方、被保険者ではない保険契約者が死亡した(たとえば、孫を被保険者として祖父が保険を契約していたところ、その祖父が死亡した)場合には、死亡保険金は出ません。しかし契約者としての地位(預金にたとえると預金者の立場)は誰かが継承します。すなわち、その承継者が生命保険契約の権利を相続したことになります。これに対して相続税が課されるわけです。
生命保険契約の権利とは、分かりやすく言えば契約を解約した場合の解約返戻金を受け取るこののできる権利です。契約者はいつでも保険を解約することができるのです。相続税の評価額は『解約返戻金』で評価することとなります。
(2)所得税
保険事故が発生した場合において、死亡保険金の受取人が保険契約者(保険料負担者)であった場合には、その受取人には所得税(一時所得)が課されます。父を被保険者として、息子が自らを保険金受取人として保険料を払っていた場合に、父が死亡したというケースです。
この場合の息子は、自らの負担において自らが収入を得たわけですから、当然所得税の対象となるわけです。(実際の所得額は受取保険金から払込み保険料を控除した額をベースに計算する)。なお仮にこのケースで、息子が保険料のうち6割を、被保険者である父が4割を負担していた場合には、その受取保険金のうち6割が所得税、4割が相続税の課税対象となります。要するに保険料の負担割合によって課税されるわけです。
(3)贈与税
先の所得税は、負担者=受取人の場合でしたが、負担者≠受取人であればどうなるでしょうか。この場合は、保険金(満期保険金を含む)を取得した保険金受取人は、保険料負担者から贈与により取得したこととされます。
受取人が何の負担もしないで保険金を取得しているわけですから、当然といえましょう。しかし税率の高い贈与税をかけられたのではたまりません。保険に入る場合には、この辺をよく考えて加入すべきでしょう。
なお、保険契約者を変更すると、従前の契約者から新契約者にこの生命保険契約の権利が贈与されたこととなります。預金の名義をかえたことと同じことですから当然といえましょう。
例をあげますと、Aを被保険者、Bを保険金受取人、Cを保険契約者とした保険契約において、実際の保険料はAが5割、Bが3割、Cが2割を払っていたところ、保険事故が発生し、受取人であるBが1,000万円の死亡保険金を受け取りました。この課税関係はどうなるか、という話です。
答えは、500万円が相続税、300万円が所得税、200万円が贈与税の課税対象となります。
以上、『生命保険の税務②』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2014年01月04日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『生命保険の税務①』について
さて、本日は『生命保険の税務①』について、お話させていただきます。
1・生命保険の税務
(1)生命保険の仕組み
生命保険は大きく分けて、定期保険と生存保険、そしてその両者が組み合わされた混合保険の3種類に区分されます。
定期保険とは、一定の期間に保険事故(死亡)が発生した場合に保険金が支払われるだけのものです。貯蓄性がなく掛け捨て保険ともいわれ、その分保険料は低廉です。
生存保険とは、一定期間経過後に生存していた場合に、満期保険金が支払われるものです。一般に養老保険といわれかなり貯蓄性が高く、その分払い込む保険料も高くなっています。
一般に普及されている保険は、定期付養老保険といった両者の混合された保険です。さらにこれに一定の障害の場合に特約を付ける等、これらの組み合わせ方を変えることによって、実にさまざまな保険が販売されているのです。
これらの保険は一定期間に限っての保険ですが、10数年前頃に死亡時点まで保険期間とする終身保険が開発されました。現在は定期付終身保険が主流になっています。
さて、保険に加入した場合に、生命保険会社から受けられるものには、次のようなものがあります。死亡保険金、満期保険金、各種の特約に基づく給付金(入院給付金等)、保険会社を中途解約した場合の解約返戻金です。さらには保険契約者は、保険会社から借り入れることもできます(契約者貸付)。これらに対する税の取り扱いが、ここでの課題となっているわけです。
保険契約に関しての登場人物は次の通りとなります。
・保険契約者・・・保険会社と契約する人です。保険契約者は保険契約に関する全権を握っています。中途解約にて解約返戻金を手にすることや契約者貸付けを受けることもできます。保険金受取人を変えることもできます。
・被保険者・・・保険をかけられる人です。この人の状況によって支払うべき保険料の額が決定されます。むろん高齢者は高く、若い人であれば安くなります。したがって原則として契約の途中で被保険者を変更することはできません。
・保険金受取人・・・保険金を受け取ることのできる人です。受取人は甲60%、乙40%といった決め方もOK。死亡保険金の受取人はAで満期保険金はB、ということも可能です。受取人を途中で変更しても課税関係は発生しません。(課税は、実際に保険金が支給されてからの話なのです。)
・保険会社・・・保険業法に定められた生命保険会社です。
本来、保険契約の当事者間における登場人物はこの4者だけなのですが、税法は独自に隠れた主人公を登場させます。次に掲げるこの人が出てくるために、課税関係が複雑になるのです。
・保険料負担者・・・保険料を実際に支払っている人です。本来これは契約者のはずです。保険会社も契約者が負担しているものとみなしており、保険証券への記載等保険会社には一切保険料負担者は登場しません。
確かに、世の中には妻が契約者である保険料を夫が払っているといった話は少なからずあります。いわば夫のお金を妻名義で預金している、ようなものでしょう。
保険においては、契約者以外の者が保険料を払った場合においても、その時点では課税関係は発生させません。保険金の支払いがある等、実際にお金が動いたときに、初めて実際の負担者に応じた課税が行われていくのです。
以上、『生命保険の税務①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『生命保険の税務②』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
1・生命保険の税務
(1)生命保険の仕組み
生命保険は大きく分けて、定期保険と生存保険、そしてその両者が組み合わされた混合保険の3種類に区分されます。
定期保険とは、一定の期間に保険事故(死亡)が発生した場合に保険金が支払われるだけのものです。貯蓄性がなく掛け捨て保険ともいわれ、その分保険料は低廉です。
生存保険とは、一定期間経過後に生存していた場合に、満期保険金が支払われるものです。一般に養老保険といわれかなり貯蓄性が高く、その分払い込む保険料も高くなっています。
一般に普及されている保険は、定期付養老保険といった両者の混合された保険です。さらにこれに一定の障害の場合に特約を付ける等、これらの組み合わせ方を変えることによって、実にさまざまな保険が販売されているのです。
これらの保険は一定期間に限っての保険ですが、10数年前頃に死亡時点まで保険期間とする終身保険が開発されました。現在は定期付終身保険が主流になっています。
さて、保険に加入した場合に、生命保険会社から受けられるものには、次のようなものがあります。死亡保険金、満期保険金、各種の特約に基づく給付金(入院給付金等)、保険会社を中途解約した場合の解約返戻金です。さらには保険契約者は、保険会社から借り入れることもできます(契約者貸付)。これらに対する税の取り扱いが、ここでの課題となっているわけです。
保険契約に関しての登場人物は次の通りとなります。
・保険契約者・・・保険会社と契約する人です。保険契約者は保険契約に関する全権を握っています。中途解約にて解約返戻金を手にすることや契約者貸付けを受けることもできます。保険金受取人を変えることもできます。
・被保険者・・・保険をかけられる人です。この人の状況によって支払うべき保険料の額が決定されます。むろん高齢者は高く、若い人であれば安くなります。したがって原則として契約の途中で被保険者を変更することはできません。
・保険金受取人・・・保険金を受け取ることのできる人です。受取人は甲60%、乙40%といった決め方もOK。死亡保険金の受取人はAで満期保険金はB、ということも可能です。受取人を途中で変更しても課税関係は発生しません。(課税は、実際に保険金が支給されてからの話なのです。)
・保険会社・・・保険業法に定められた生命保険会社です。
本来、保険契約の当事者間における登場人物はこの4者だけなのですが、税法は独自に隠れた主人公を登場させます。次に掲げるこの人が出てくるために、課税関係が複雑になるのです。
・保険料負担者・・・保険料を実際に支払っている人です。本来これは契約者のはずです。保険会社も契約者が負担しているものとみなしており、保険証券への記載等保険会社には一切保険料負担者は登場しません。
確かに、世の中には妻が契約者である保険料を夫が払っているといった話は少なからずあります。いわば夫のお金を妻名義で預金している、ようなものでしょう。
保険においては、契約者以外の者が保険料を払った場合においても、その時点では課税関係は発生させません。保険金の支払いがある等、実際にお金が動いたときに、初めて実際の負担者に応じた課税が行われていくのです。
以上、『生命保険の税務①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『生命保険の税務②』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月27日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『贈与税③』について
本日は、『贈与税③について』をお話させていただきます。
(1)その他のみなし贈与
以下に、各種のみなし贈与とされるものをいくつか列挙します。ただしこれは常識的に当然と思われるものばかりです。税の根本は『常識』なのです。
①信託
信託とは、委託者(依頼者)の財産を処分すること等により、一定の目的のために、委託者(信託銀行等)に対して受益者(信託により利益を受ける人)のために財産権の管理または処分を行わせることをいうものとされています。
したがって、委託者以外の者が受益者となる信託行為(他益信託)があった場合には、受益者がその信託を受ける権利を、委託者から贈与により取得したものとみなされることになるのです。
なお、受益者が学術研究者や学資を受ける学生である等の、一定の公益を目的とする信託(公益信託)から交付される金品については、非課税とされています。個人が特別障害者を受益者とする信託契約を信託銀行と締結した一定の特別障害者扶養信託に関しても、贈与税は課されません。
②負担付贈与
ローン付きのアパートの贈与といった負担付贈与があった場合には、贈与財産の時価から負担額(ローン残高等)を差し引いた価格に相当する財産の贈与があったものとみなされます。
負担付贈与は、事実上低額譲受けと、その実態は同じです。税務上も同様の取扱いをしているわけです。
③共有持分の放棄
共有財産における共有持分の放棄は、その持分が他の共有者に対してその持分に応じて贈与されたものとみなされます。
⑤財産分与
離婚による財産分与によって取得した財産は、贈与税は課されません。しかし、その分与財産の額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合には、その部分は課税対象となります。
以上、『贈与税③』についてを、お話させていただきました。
次回は、『生命保険の税務』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
(1)その他のみなし贈与
以下に、各種のみなし贈与とされるものをいくつか列挙します。ただしこれは常識的に当然と思われるものばかりです。税の根本は『常識』なのです。
①信託
信託とは、委託者(依頼者)の財産を処分すること等により、一定の目的のために、委託者(信託銀行等)に対して受益者(信託により利益を受ける人)のために財産権の管理または処分を行わせることをいうものとされています。
したがって、委託者以外の者が受益者となる信託行為(他益信託)があった場合には、受益者がその信託を受ける権利を、委託者から贈与により取得したものとみなされることになるのです。
なお、受益者が学術研究者や学資を受ける学生である等の、一定の公益を目的とする信託(公益信託)から交付される金品については、非課税とされています。個人が特別障害者を受益者とする信託契約を信託銀行と締結した一定の特別障害者扶養信託に関しても、贈与税は課されません。
②負担付贈与
ローン付きのアパートの贈与といった負担付贈与があった場合には、贈与財産の時価から負担額(ローン残高等)を差し引いた価格に相当する財産の贈与があったものとみなされます。
負担付贈与は、事実上低額譲受けと、その実態は同じです。税務上も同様の取扱いをしているわけです。
③共有持分の放棄
共有財産における共有持分の放棄は、その持分が他の共有者に対してその持分に応じて贈与されたものとみなされます。
⑤財産分与
離婚による財産分与によって取得した財産は、贈与税は課されません。しかし、その分与財産の額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合には、その部分は課税対象となります。
以上、『贈与税③』についてを、お話させていただきました。
次回は、『生命保険の税務』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『贈与税②』について
本日は『贈与税②』についてお話させていただきます。
1・みなし贈与財産
税法は、贈与税の課税対象を単なる民法の定める贈与に限定していません。相続税の補完税としての任務を果たすには、民法上の贈与という狭い枠に止まっていられなのです。したがって民法上の贈与以外の実質的な贈与を、贈与とみなして課税対象としたわけです。以下の『みなし贈与財産』がそれです。
(1)定額譲受け
著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価との差額が贈与されたものとみなして贈与税が課されます。極めて当然のことといえましょう。なおこの『著しく低い』かどうかは、社会通念に従い判断されますが、やはり親族間ではシビアにみられるものと思われます。
ここで問題となるのは、贈与税計算のベースとなる『時価』とは何かです。税法においては、いろいろなケースで時価(価格も同義語)という用語が出てきますが、その意味するところは微妙に違うのです。
相続・贈与税の場合には、時価は2通りの意味があります。一つは建前としての評価、すなわち相続税評価額。もう一つは、本当の時価(自由な経済取引の下で成立する取引価格)です。相続税評価額は、本当の時価よりやや堅め(低め)に評価されています。
さて、ここは大切かつまぎらわしいところですから、事例で説明させていただきます。父親が時価(公示価格ベース)1,000万円、相続税評価額800万円(公示の8割水準)の更地を、息子に600万円という著しく低い対価で譲渡したというケースの場合です。
この場合に贈与とみなされる金額は、1,000万円との差額の400万円か、800万円との差額の200万円か、という話です。結論は400万円です。要するに低額譲受けの場合の時価は、本当の時価を基準とするのです。
ただし、父親がこの土地を息子に贈与(対価はゼロ)した場合には、原則どおり相続評価額である800万円が課税対象となります。つまり、一部でも対価を払う(すなわち低額譲受け)と、基準が本当の時価になってしまうのです。
ところで、実務上最も問題となるのは、『時価がいくらなのか』という点です。事実不動産の時価は、たとえて言うならストライクゾーンのように一定の幅があるものなのです。公示価格にしても、その幅の中のひとつの数値にすぎません。
まず、言える事は、路線価評価額(諸調整率適用後)を0.8で割り戻した額が一つの基準となることです。『公示価格が時価であることと、路線価は公示価格の8割水準にあること』が一つの基準となっています。
しかし、この『路線価÷0.8』では実勢相場にそぐわないと思われる様な場合には、安易に当事者間で価格を決めずに不動産鑑定士や税理士等の専門の方に相談された方がよろしいかと思います。
(2)債務免除
債務の免除や、第三者のためにする債務の弁済等により利益を受けた場合は、これらの利益に相当する贈与があったものとみなして、贈与税が課されます。これも当然の規定といえましょう。
また、連帯債務者が自己の負担すべき債務の部分を超えて弁済し、かつそれによって得た他の連帯債務者に対する求償権を放棄した場合には、贈与があったものとみなされます。保証人が保証債務を履行したうえで、主たる債務者に対する求償権を放棄した場合も同様です。
ただし、これらの場合においても、その債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときは、その困難とされる部分に対しては贈与税は課されません。また、資力を喪失した債務者の扶養義務者がその債務の引受けや弁済を行った場合にも贈与税は課されない(逆に一般の人が債務引受けを行うと課税対象となる)こととされています。
以上、『贈与税②について』をお話させていただきました。
次回は『贈与税③について』をお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
1・みなし贈与財産
税法は、贈与税の課税対象を単なる民法の定める贈与に限定していません。相続税の補完税としての任務を果たすには、民法上の贈与という狭い枠に止まっていられなのです。したがって民法上の贈与以外の実質的な贈与を、贈与とみなして課税対象としたわけです。以下の『みなし贈与財産』がそれです。
(1)定額譲受け
著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価との差額が贈与されたものとみなして贈与税が課されます。極めて当然のことといえましょう。なおこの『著しく低い』かどうかは、社会通念に従い判断されますが、やはり親族間ではシビアにみられるものと思われます。
ここで問題となるのは、贈与税計算のベースとなる『時価』とは何かです。税法においては、いろいろなケースで時価(価格も同義語)という用語が出てきますが、その意味するところは微妙に違うのです。
相続・贈与税の場合には、時価は2通りの意味があります。一つは建前としての評価、すなわち相続税評価額。もう一つは、本当の時価(自由な経済取引の下で成立する取引価格)です。相続税評価額は、本当の時価よりやや堅め(低め)に評価されています。
さて、ここは大切かつまぎらわしいところですから、事例で説明させていただきます。父親が時価(公示価格ベース)1,000万円、相続税評価額800万円(公示の8割水準)の更地を、息子に600万円という著しく低い対価で譲渡したというケースの場合です。
この場合に贈与とみなされる金額は、1,000万円との差額の400万円か、800万円との差額の200万円か、という話です。結論は400万円です。要するに低額譲受けの場合の時価は、本当の時価を基準とするのです。
ただし、父親がこの土地を息子に贈与(対価はゼロ)した場合には、原則どおり相続評価額である800万円が課税対象となります。つまり、一部でも対価を払う(すなわち低額譲受け)と、基準が本当の時価になってしまうのです。
ところで、実務上最も問題となるのは、『時価がいくらなのか』という点です。事実不動産の時価は、たとえて言うならストライクゾーンのように一定の幅があるものなのです。公示価格にしても、その幅の中のひとつの数値にすぎません。
まず、言える事は、路線価評価額(諸調整率適用後)を0.8で割り戻した額が一つの基準となることです。『公示価格が時価であることと、路線価は公示価格の8割水準にあること』が一つの基準となっています。
しかし、この『路線価÷0.8』では実勢相場にそぐわないと思われる様な場合には、安易に当事者間で価格を決めずに不動産鑑定士や税理士等の専門の方に相談された方がよろしいかと思います。
(2)債務免除
債務の免除や、第三者のためにする債務の弁済等により利益を受けた場合は、これらの利益に相当する贈与があったものとみなして、贈与税が課されます。これも当然の規定といえましょう。
また、連帯債務者が自己の負担すべき債務の部分を超えて弁済し、かつそれによって得た他の連帯債務者に対する求償権を放棄した場合には、贈与があったものとみなされます。保証人が保証債務を履行したうえで、主たる債務者に対する求償権を放棄した場合も同様です。
ただし、これらの場合においても、その債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときは、その困難とされる部分に対しては贈与税は課されません。また、資力を喪失した債務者の扶養義務者がその債務の引受けや弁済を行った場合にも贈与税は課されない(逆に一般の人が債務引受けを行うと課税対象となる)こととされています。
以上、『贈与税②について』をお話させていただきました。
次回は『贈与税③について』をお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月19日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『贈与税①』について
本日は、『贈与税①』についてお話させていただきます。
1・贈与税とは
(1)相続税の補完税
贈与税は、相続税を補完するための税として設けられたものです、すなわち贈与税がなかったならば、あらかじめ生前に子供達に財産を贈与して将来の相続財産を減らすことにより、相続税の負担を軽減することができてしまうからです。要するに、贈与税は相続税を徴収するための手段なのです。
むろんこの点だけではなく、贈与を受けた者(受贈者)の担税力の増加に着目しての課税、という側面もあります。したがって、ともすると『贈与所得』といった所得税の対象にもなりうるわけですが、贈与税の課税対象とされていることから、所得税の課税対象外となっているわけです。(二重課税の排除)。
しかし、基本はあくまで相続税の補完税です。そもそも、贈与税は相続税法の一部として定められています。贈与税法という法律はないのです。(この点を称してよく『1税法2税目』といいます。ひとつの税法に2種類の税が定められている、という意味です)。したがって、税の扇の要である税率をはじめ、多くが相続税との関連で規定されています。贈与財産の評価も相続税評価で行います。
贈与税は、個人が個人から贈与を受けた場合に課される税です。したがって、個人が法人から贈与を受けた場合には、贈与税の対象外です。むろん非課税というわけではなく、所得税(一時所得)が課されます。理由は、贈与する法人は相続税と無縁の存在であり、これを補完する必要がないからです。
一方、法人が贈与を受けた場合には、法人税(受贈益)が課されます。ただし、一般に法人税が課されていない人格のない社団(PTA他)等が個人から贈与を受けた場合には、その社団等は個人とみなされて贈与税が課されます。
(2)贈与とは
贈与税は、贈与によって取得した財産に対して課税されます。この場合贈与とは、民法上の贈与をいいます。すなわち、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいうのです。(民法549条)
しかし、贈与税は単に民法上の贈与のみならず、実質的に贈与と同様の効果を有する行為についても、みなし贈与として課税対象に含めています。(みなし贈与については、次回、お話させていただきます。)
ところで、本来の贈与であっても、その贈与の事実の把握には困難が伴います。そもそも贈与であるのかそうでないのか、その贈与はいつ行われたか、が定かでなかったり、贈与税を免れるために外見上は贈与でない体裁をとっていたり、と課税実務上その判定が難しいのです。しかし、これらに対し手をこまねいてはいられません。まずは外観を重視して課税を行っていくのです。
たとえば、対価の授受がないまま不動産や株式等の名義が変更された場合には、原則として贈与があったものと取扱います。当事者から、『いや単に名義を移しただけであって、真の権利者は元の名義人であり、贈与はしていない』という理屈の下に、贈与税を免れようとする主張がなされる可能性がありましょう。。しかしこのような場合には、課税実務上、名義変更という外観によって贈与を認定するのです。
ただし中には、納税者のこの主張が正しい場合もあるでしょう。その場合には、納税者が税務署に対して贈与ではない』旨の説得や立証を行う必要があります。税務署がこれに納得すれば課税は行われないこととなるわけです。
以上、『贈与税①』についてお話させていただきました。
次回は、『贈与税②』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
1・贈与税とは
(1)相続税の補完税
贈与税は、相続税を補完するための税として設けられたものです、すなわち贈与税がなかったならば、あらかじめ生前に子供達に財産を贈与して将来の相続財産を減らすことにより、相続税の負担を軽減することができてしまうからです。要するに、贈与税は相続税を徴収するための手段なのです。
むろんこの点だけではなく、贈与を受けた者(受贈者)の担税力の増加に着目しての課税、という側面もあります。したがって、ともすると『贈与所得』といった所得税の対象にもなりうるわけですが、贈与税の課税対象とされていることから、所得税の課税対象外となっているわけです。(二重課税の排除)。
しかし、基本はあくまで相続税の補完税です。そもそも、贈与税は相続税法の一部として定められています。贈与税法という法律はないのです。(この点を称してよく『1税法2税目』といいます。ひとつの税法に2種類の税が定められている、という意味です)。したがって、税の扇の要である税率をはじめ、多くが相続税との関連で規定されています。贈与財産の評価も相続税評価で行います。
贈与税は、個人が個人から贈与を受けた場合に課される税です。したがって、個人が法人から贈与を受けた場合には、贈与税の対象外です。むろん非課税というわけではなく、所得税(一時所得)が課されます。理由は、贈与する法人は相続税と無縁の存在であり、これを補完する必要がないからです。
一方、法人が贈与を受けた場合には、法人税(受贈益)が課されます。ただし、一般に法人税が課されていない人格のない社団(PTA他)等が個人から贈与を受けた場合には、その社団等は個人とみなされて贈与税が課されます。
(2)贈与とは
贈与税は、贈与によって取得した財産に対して課税されます。この場合贈与とは、民法上の贈与をいいます。すなわち、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいうのです。(民法549条)
しかし、贈与税は単に民法上の贈与のみならず、実質的に贈与と同様の効果を有する行為についても、みなし贈与として課税対象に含めています。(みなし贈与については、次回、お話させていただきます。)
ところで、本来の贈与であっても、その贈与の事実の把握には困難が伴います。そもそも贈与であるのかそうでないのか、その贈与はいつ行われたか、が定かでなかったり、贈与税を免れるために外見上は贈与でない体裁をとっていたり、と課税実務上その判定が難しいのです。しかし、これらに対し手をこまねいてはいられません。まずは外観を重視して課税を行っていくのです。
たとえば、対価の授受がないまま不動産や株式等の名義が変更された場合には、原則として贈与があったものと取扱います。当事者から、『いや単に名義を移しただけであって、真の権利者は元の名義人であり、贈与はしていない』という理屈の下に、贈与税を免れようとする主張がなされる可能性がありましょう。。しかしこのような場合には、課税実務上、名義変更という外観によって贈与を認定するのです。
ただし中には、納税者のこの主張が正しい場合もあるでしょう。その場合には、納税者が税務署に対して贈与ではない』旨の説得や立証を行う必要があります。税務署がこれに納得すれば課税は行われないこととなるわけです。
以上、『贈与税①』についてお話させていただきました。
次回は、『贈与税②』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月18日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『金融資産の評価②』について
さて、本日は、『金融資産の評価②』についてお話させていただきます。
(1)上場株式
上場株式は、日々その株価が公表されているため、その株価を評価のベースとします。しかし一般に株価はかなり変動するもので、課税時期の株価だけでは、評価額が市場の特殊要因等により左右されかねません。
そこで上場株式は、以下の4種の株価のうち最も低いものにより評価することとし、ある程度の期間を通じた取引価格も考慮することとしています。
・課税時期当日の終わり値(当日が休日の場合には、当日に最も近い日の終わり値)
・課税時期の属する月の終わり値の平均値
・課税時期の 前月 の終わり値の平均値
・課税時期の前々月 の終わり値の平均値
なお、各月の終わり値の平均の株価の資料は、各税務署に備えつけてあり(路線価と同じ場所)、実務的にはこれを見て評価します。
ところで、上場株式を保有している場合には、その多くが配当金を受け取っています。課税時期においてこれらの配当金をすべて受け取っていれば問題ないのですが、そうでない場合には、配当期待権や未収配当としての評価を行うことがあります。
たとえば、3月決算のA社の株式の配当金10万円(手取りは8万円)を受け取る権利があったとしましょう。A社は3月末現在の株主宛の配当交付の決定は6月下旬の株主総会で行います。この3ヶ月弱の期間における株主の権利を配当期待権というわけです。
6月下旬の株主総会により正式に10万円の配当金交付が決定されても、実際に株主に交付されるのは数週間後です。この間の株主は、未収配当金としての評価を受けるわけです。なおこの場合評価額は、配当期待権・未収配当金とも、手取り金額の8万円となります。
ところで、株式には上場株式の他、取引相場のない株式(いわゆる自社株式)があります。この自社株式の評価(事業承継税制)は、かなり複雑ですので、税理士等の専門の方にご相談いただく事をお奨めします。
(2)その他の金融資産
①ゴルフの会員権
ゴルフの会員権の評価についてはいろいろ規定されていますが、要するに、『取引相場×70%』で評価されています。
とはいえ、ゴルフの会員権の取引相場については、今日かなり厳しい状況になっているものも少なくありません。これらに関しては、評価の基本『客観的な価値』に立ち返って、臨機応変に対処することとなりましょう。
②貸付金
貸付債権は、一般にその元本と課税時期までの既経過利子相当額との合計額で評価します。
しかし通常貸付が行われる背景には、いろいろな事情がある場合が少なくありません。そもそも、先方に返す気があるのかどうか、返す気があるとしても本当に返してくれるのかどうか、さらには返す資力があるのかどうか。むろん相手によってはビジネスライクに『返してくれ』と言えない場合もあります。
しかし税法は、その辺のところはおかまいなしに、相続財産に加算してきます。回収不能として評価する必要なしとされるケースも、相手方に破産宣告があった場合や業績不振等により事業廃止や6か月以上休業している場合等、極めて限定的な取り扱いとなっています。
やはり、相続間近となった場合は、これらの貸付金債権は整理(放棄、回収等)しておくべきといえましょう。
③出資
一般の有限会社、合名会社、合資会社等への出資は、取引相場のない株式(自社株式)の評価方法を準用します。
しかし、農業協同組合や漁業協同組合等のように、組合員に対するサービス的業務を行う一般的な産業団体に対する出資は、原則として払込済みの出資額によって評価します。信用金庫や信用組合に対する出資も同様です。
以上、『金融資産の評価②』についてお話させていただきました。
次回は、『贈与税①』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
(1)上場株式
上場株式は、日々その株価が公表されているため、その株価を評価のベースとします。しかし一般に株価はかなり変動するもので、課税時期の株価だけでは、評価額が市場の特殊要因等により左右されかねません。
そこで上場株式は、以下の4種の株価のうち最も低いものにより評価することとし、ある程度の期間を通じた取引価格も考慮することとしています。
・課税時期当日の終わり値(当日が休日の場合には、当日に最も近い日の終わり値)
・課税時期の属する月の終わり値の平均値
・課税時期の 前月 の終わり値の平均値
・課税時期の前々月 の終わり値の平均値
なお、各月の終わり値の平均の株価の資料は、各税務署に備えつけてあり(路線価と同じ場所)、実務的にはこれを見て評価します。
ところで、上場株式を保有している場合には、その多くが配当金を受け取っています。課税時期においてこれらの配当金をすべて受け取っていれば問題ないのですが、そうでない場合には、配当期待権や未収配当としての評価を行うことがあります。
たとえば、3月決算のA社の株式の配当金10万円(手取りは8万円)を受け取る権利があったとしましょう。A社は3月末現在の株主宛の配当交付の決定は6月下旬の株主総会で行います。この3ヶ月弱の期間における株主の権利を配当期待権というわけです。
6月下旬の株主総会により正式に10万円の配当金交付が決定されても、実際に株主に交付されるのは数週間後です。この間の株主は、未収配当金としての評価を受けるわけです。なおこの場合評価額は、配当期待権・未収配当金とも、手取り金額の8万円となります。
ところで、株式には上場株式の他、取引相場のない株式(いわゆる自社株式)があります。この自社株式の評価(事業承継税制)は、かなり複雑ですので、税理士等の専門の方にご相談いただく事をお奨めします。
(2)その他の金融資産
①ゴルフの会員権
ゴルフの会員権の評価についてはいろいろ規定されていますが、要するに、『取引相場×70%』で評価されています。
とはいえ、ゴルフの会員権の取引相場については、今日かなり厳しい状況になっているものも少なくありません。これらに関しては、評価の基本『客観的な価値』に立ち返って、臨機応変に対処することとなりましょう。
②貸付金
貸付債権は、一般にその元本と課税時期までの既経過利子相当額との合計額で評価します。
しかし通常貸付が行われる背景には、いろいろな事情がある場合が少なくありません。そもそも、先方に返す気があるのかどうか、返す気があるとしても本当に返してくれるのかどうか、さらには返す資力があるのかどうか。むろん相手によってはビジネスライクに『返してくれ』と言えない場合もあります。
しかし税法は、その辺のところはおかまいなしに、相続財産に加算してきます。回収不能として評価する必要なしとされるケースも、相手方に破産宣告があった場合や業績不振等により事業廃止や6か月以上休業している場合等、極めて限定的な取り扱いとなっています。
やはり、相続間近となった場合は、これらの貸付金債権は整理(放棄、回収等)しておくべきといえましょう。
③出資
一般の有限会社、合名会社、合資会社等への出資は、取引相場のない株式(自社株式)の評価方法を準用します。
しかし、農業協同組合や漁業協同組合等のように、組合員に対するサービス的業務を行う一般的な産業団体に対する出資は、原則として払込済みの出資額によって評価します。信用金庫や信用組合に対する出資も同様です。
以上、『金融資産の評価②』についてお話させていただきました。
次回は、『贈与税①』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月16日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『金融資産の評価①』について
さて、今回は相続税の財産評価の内、『金融資産の評価①』についてお話させて頂きます。
■金融資産
(1)預貯金
預貯金は、課税時期における預け入れ残高に、税引き後の既経過利子の額を加算した金額により評価します。
既経過利子の額とは、課税時期で解約するとした場合に受け取るべき利息をいい、実際にはこれに20%の源泉所得税が課されるため、これを控除した額を預貯金の元本に加算するのです。
要するに預貯金の評価額は、課税時期にその預貯金を中途解約した場合の元利金の手取り額というわけです。
ただし普通預金や通知預金のように、既経過利子の額が少額なものについては、課税時期の預入れ残高により評価します。以上いずれもリーズナブルなルールといえましょう。
預貯金には、むろん郵便局の定額貯金が含まれます。さらに形の上では有価証券に分類されていますが、事実上の定期預金ともいえる貸付信託も、中途解約手取り額の評価(買取割引額を算入)と考えてもよいものと思われます。
(2)一般の有価証券
①利付公社債
利付公社債の評価は、その発行価格(券面金額ではありません。通常発行価格は、券面金額100円に対して99円と異なった額になっています)に、税引後の既経過利子の額を加算したものとなります。実務上は、券面額100円当たりの金額という単価ベースで算出します。
ただし、利付債は確定利付きの債権であるため、金利の変動により流通価格が日々変動しています。したがって、これらの市場価格が把握できる場合で、その市場価格が発行価格よりも低いときは、市場価格をベースにこれに税引き後既経過利子を加算した額で評価します。
②割引債
割引発行の公社債の評価も、考え方は上記利付債と同様です。ただし既経過利子の計算部分を、券面金額と発行価格の差額である『償還差益』を基に行うだけです。すなわち『発行価格+既経過償還差益の額』で評価するわけです。
ただし、この割引債の市場価格が把握でき、かつそれが上記の評価額を下回っている場合には、その市場価格で評価します(割引債の市場価格は、既経過償還差益を折り込んで形成されています)。
③投資信託
投資信託の受益証券は換金性が高く、また投資している株式等の価額を基として、毎日の時価額が基準価額として日経新聞などに掲載されています。
したがって、投資信託の受益証券は、課税時期におけるこの基準価額により評価します(実務上は、これらの投資信託を取り扱った証券会社等の金融機関から基準価格を教えてもらっているようです)。
以上、今回は『金融資産の評価①』についてお話させていただきました。
次回は、『金融資産の評価②』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
■金融資産
(1)預貯金
預貯金は、課税時期における預け入れ残高に、税引き後の既経過利子の額を加算した金額により評価します。
既経過利子の額とは、課税時期で解約するとした場合に受け取るべき利息をいい、実際にはこれに20%の源泉所得税が課されるため、これを控除した額を預貯金の元本に加算するのです。
要するに預貯金の評価額は、課税時期にその預貯金を中途解約した場合の元利金の手取り額というわけです。
ただし普通預金や通知預金のように、既経過利子の額が少額なものについては、課税時期の預入れ残高により評価します。以上いずれもリーズナブルなルールといえましょう。
預貯金には、むろん郵便局の定額貯金が含まれます。さらに形の上では有価証券に分類されていますが、事実上の定期預金ともいえる貸付信託も、中途解約手取り額の評価(買取割引額を算入)と考えてもよいものと思われます。
(2)一般の有価証券
①利付公社債
利付公社債の評価は、その発行価格(券面金額ではありません。通常発行価格は、券面金額100円に対して99円と異なった額になっています)に、税引後の既経過利子の額を加算したものとなります。実務上は、券面額100円当たりの金額という単価ベースで算出します。
ただし、利付債は確定利付きの債権であるため、金利の変動により流通価格が日々変動しています。したがって、これらの市場価格が把握できる場合で、その市場価格が発行価格よりも低いときは、市場価格をベースにこれに税引き後既経過利子を加算した額で評価します。
②割引債
割引発行の公社債の評価も、考え方は上記利付債と同様です。ただし既経過利子の計算部分を、券面金額と発行価格の差額である『償還差益』を基に行うだけです。すなわち『発行価格+既経過償還差益の額』で評価するわけです。
ただし、この割引債の市場価格が把握でき、かつそれが上記の評価額を下回っている場合には、その市場価格で評価します(割引債の市場価格は、既経過償還差益を折り込んで形成されています)。
③投資信託
投資信託の受益証券は換金性が高く、また投資している株式等の価額を基として、毎日の時価額が基準価額として日経新聞などに掲載されています。
したがって、投資信託の受益証券は、課税時期におけるこの基準価額により評価します(実務上は、これらの投資信託を取り扱った証券会社等の金融機関から基準価格を教えてもらっているようです)。
以上、今回は『金融資産の評価①』についてお話させていただきました。
次回は、『金融資産の評価②』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月13日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『課税価格の計算』について
本日は相続税の『課税価格の計算』についてお話させていただきます。
相続税の課税対象となる遺産の額を課税価格といい、本来の相続財産やみなし相続財産を加算することにより求めます。
さらにこの額に、相続開始前3年以内の贈与財産を加算し、一定の債務や葬式費用を控除します。
(1)3年内贈与財産
相続人等が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けている場合は、その受増財産はその相続人等の相続税の課税価格に加算されます。要するに、その贈与はなかったものとみなされるわけです。なかったものとみなされた贈与に関して、既に支払い済みの贈与税があれば、この額は相続税の前払いと考え、相続税額から控除されます。これが、贈与税額控除の規定です。
この場合、贈与がなかったものとみなされる対象は、相続または遺贈により財産を取得した人に限られます。したがって、相続人ではあるが財産を全く取得していない人や、遺言で財産を取得していない一般の人は、相続開始前に贈与を受けていても何の問題もありません。
なお、『相続開始前3年以内』とは、3年前の応答日以降をいい、相続財産に加算される財産の価額は、贈与時の価額(相続開始時点のものでない)です。ただし、贈与税の配偶者控除の規定(婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与の特例)を受けた贈与は、加算の対象外とされています。
(2)債務控除
相続税の課税価格の計算においては、プラス財産は加算される一方、債務といったマイナス財産は当然減算されなければなりません。これが債務控除の制度です。
ただし相続税法は、債務控除の対象者を相続人と包括受遺者(遺言で包括遺贈を受けた者)に制限しています。つまり遺言によって特定の財産を取得した相続人以外の人には適用がないのです。したがって、遺言で相続人以外の人に借金付きのアパート等を残すことは、お勧めできないわけです。さらに、制限納税義務者(住所が国内にない人)に対する債務控除の範囲にも一定の制限があります。(公租公課や取得財産に関連する債務はOK)
債務控除の対象となる債務は、相続開始の際に現に存するもので確実と認められるものに限られています。したがって保証債務は、既に債務者が弁済不能で保証債務の履行をせざるを得ない状況等でないと、債務控除の対象にならないことになります。(この点は実に厳しい判定をなされてしまいます。)
被相続人の所得に対する所得税(相続開始の年の準確定申告によるものを含む)や、固定資産税等も、当然債務控除の対象となります。なおこの固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者が納税義務を負うこととされているため、仮に2月に相続開始した場合であっても、その年分の金額が(むろん納期限はまだ先であっても)債務控除の対象となります。
(3)葬式費用
葬式費用は、相続に伴い必然的に生じる出費であり、相続財産から負担すべき費用とも考えられることから、債務と同様に、これを負担した者の課税価格から控除することとされています。
葬式費用の控除は、債務控除の一種として定められています。したがって、相続人以外の特定受贈者は控除の対象となりません。また制限納税義務者も同様です。
控除の対象となる葬式費用は、葬式およびこれに関連した費用(お布施、戒名、各種飲食代等)の他、死体の捜索や死体、遺骨の運搬に要した費用も含みます。
ただし、初七日等の後日の法会に要する費用や、墓碑や墓地の購入日、医学上等の特例の処遇に要した費用は控除の対象外です。さらに香典返戻費用も対象外となります。そもそも香典収入(遺族への贈与)が贈与税の上で非課税とされており、その裏返しとしての香典返礼費用は、控除の対象からはずしたわけです。
なお相続税の申告に関しては、証拠書類として葬式費用の領収書(コピー)を添付するケースが多いのですが、領収書がないから控除できない、ということはありません。事実お布施や運転手さんへの心付け、近所の人達へのお礼等の領収書は、事実上もらえないものです。
しかし、これらの支出も当然控除対象となります。したがって、これらの支出額はしっかりメモしておきたいものです。
(4)未分割の場合
相続税の課税価格は、税額または遺贈により財産を取得した者ごとに、取得財産の価額を計算し、その合計額に基づき相続税額の総額を計算する手順となっています。
しかし相続人が複数いる場合において、遺産の配分で争いが起きること等により、相続税の申告期限(相続開始後10ヵ月)までに、遺産の分割の合意が得られないケースもないわけではありません。このように、遺産が未分割(一部の未分割を含む)の場合には、その未分割財産は、法定相続分で分割されたものと仮定して課税価格を計算し、税額を算出することとされています。
さてその後において、遺産分割が成立した場合においては当然各相続人が負担すべき相続税額と、未分割の段階における当初申告による税額は異なってきます。そこで税法は、このズレを修正させるべき申告書(修正申告書等)を提出することができるものと定めています。
ここで留意すべきは、税法の条文の末尾である『提出することができる』という規定です。つまり修正申告してもいいし、しなくてもいいのです。相続税の総額は遺産の分割状況によって全く変わりませんので、『相続人間で税負担の不公平があると思えば申告してもいいですよ』と言っているにすぎないということになります。
以上『課税価格の計算』についてお話させていただきました。
次回は、『金融資産の評価』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
相続税の課税対象となる遺産の額を課税価格といい、本来の相続財産やみなし相続財産を加算することにより求めます。
さらにこの額に、相続開始前3年以内の贈与財産を加算し、一定の債務や葬式費用を控除します。
(1)3年内贈与財産
相続人等が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けている場合は、その受増財産はその相続人等の相続税の課税価格に加算されます。要するに、その贈与はなかったものとみなされるわけです。なかったものとみなされた贈与に関して、既に支払い済みの贈与税があれば、この額は相続税の前払いと考え、相続税額から控除されます。これが、贈与税額控除の規定です。
この場合、贈与がなかったものとみなされる対象は、相続または遺贈により財産を取得した人に限られます。したがって、相続人ではあるが財産を全く取得していない人や、遺言で財産を取得していない一般の人は、相続開始前に贈与を受けていても何の問題もありません。
なお、『相続開始前3年以内』とは、3年前の応答日以降をいい、相続財産に加算される財産の価額は、贈与時の価額(相続開始時点のものでない)です。ただし、贈与税の配偶者控除の規定(婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与の特例)を受けた贈与は、加算の対象外とされています。
(2)債務控除
相続税の課税価格の計算においては、プラス財産は加算される一方、債務といったマイナス財産は当然減算されなければなりません。これが債務控除の制度です。
ただし相続税法は、債務控除の対象者を相続人と包括受遺者(遺言で包括遺贈を受けた者)に制限しています。つまり遺言によって特定の財産を取得した相続人以外の人には適用がないのです。したがって、遺言で相続人以外の人に借金付きのアパート等を残すことは、お勧めできないわけです。さらに、制限納税義務者(住所が国内にない人)に対する債務控除の範囲にも一定の制限があります。(公租公課や取得財産に関連する債務はOK)
債務控除の対象となる債務は、相続開始の際に現に存するもので確実と認められるものに限られています。したがって保証債務は、既に債務者が弁済不能で保証債務の履行をせざるを得ない状況等でないと、債務控除の対象にならないことになります。(この点は実に厳しい判定をなされてしまいます。)
被相続人の所得に対する所得税(相続開始の年の準確定申告によるものを含む)や、固定資産税等も、当然債務控除の対象となります。なおこの固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者が納税義務を負うこととされているため、仮に2月に相続開始した場合であっても、その年分の金額が(むろん納期限はまだ先であっても)債務控除の対象となります。
(3)葬式費用
葬式費用は、相続に伴い必然的に生じる出費であり、相続財産から負担すべき費用とも考えられることから、債務と同様に、これを負担した者の課税価格から控除することとされています。
葬式費用の控除は、債務控除の一種として定められています。したがって、相続人以外の特定受贈者は控除の対象となりません。また制限納税義務者も同様です。
控除の対象となる葬式費用は、葬式およびこれに関連した費用(お布施、戒名、各種飲食代等)の他、死体の捜索や死体、遺骨の運搬に要した費用も含みます。
ただし、初七日等の後日の法会に要する費用や、墓碑や墓地の購入日、医学上等の特例の処遇に要した費用は控除の対象外です。さらに香典返戻費用も対象外となります。そもそも香典収入(遺族への贈与)が贈与税の上で非課税とされており、その裏返しとしての香典返礼費用は、控除の対象からはずしたわけです。
なお相続税の申告に関しては、証拠書類として葬式費用の領収書(コピー)を添付するケースが多いのですが、領収書がないから控除できない、ということはありません。事実お布施や運転手さんへの心付け、近所の人達へのお礼等の領収書は、事実上もらえないものです。
しかし、これらの支出も当然控除対象となります。したがって、これらの支出額はしっかりメモしておきたいものです。
(4)未分割の場合
相続税の課税価格は、税額または遺贈により財産を取得した者ごとに、取得財産の価額を計算し、その合計額に基づき相続税額の総額を計算する手順となっています。
しかし相続人が複数いる場合において、遺産の配分で争いが起きること等により、相続税の申告期限(相続開始後10ヵ月)までに、遺産の分割の合意が得られないケースもないわけではありません。このように、遺産が未分割(一部の未分割を含む)の場合には、その未分割財産は、法定相続分で分割されたものと仮定して課税価格を計算し、税額を算出することとされています。
さてその後において、遺産分割が成立した場合においては当然各相続人が負担すべき相続税額と、未分割の段階における当初申告による税額は異なってきます。そこで税法は、このズレを修正させるべき申告書(修正申告書等)を提出することができるものと定めています。
ここで留意すべきは、税法の条文の末尾である『提出することができる』という規定です。つまり修正申告してもいいし、しなくてもいいのです。相続税の総額は遺産の分割状況によって全く変わりませんので、『相続人間で税負担の不公平があると思えば申告してもいいですよ』と言っているにすぎないということになります。
以上『課税価格の計算』についてお話させていただきました。
次回は、『金融資産の評価』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月12日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『非課税財産』について
本日は、相続税の『非課税財産』について、お話させていただきます。
1・非課税財産
以下の財産は、社会政策的見地や国民感情等を配慮して非課税とされています。
(1)墓所、霊びょう、祭具等
要するにお墓の類です。墓地、墓石をはじめ神棚、神体、神具、仏壇、仏具、位牌等です。ただし、これらのものであっても、商品や投資対象として所有されているものは含まれません(以前相続税対策として、純金で仏壇を作って非課税を主張した人がいたため、国税庁がこのような通達を作ったそうです)。
(2)一定の生命保険金、退職金
相続人の生活安定の見地から、相続人が(相続でない者は不可)取得した生命保険金や退職金のうち、それぞれ一定の非課税限度額までの金額は非課税です。非課税限度額は、
『500万円×法定相続人の数』
です。この場合の法定相続人の数は、基礎控除を計算する場合と同じ(相続放棄者も含む、養子の数は制限)です。一方『相続人が取得した』という場合の相続人は、純粋に民法の定める相続人をいいます(特にことわりがない場合は、『相続人』の用語はこのように理解して下さい。)すなわち正式に相続を放棄した者(相続人ではない)が受け取った保険金等には、非課税規定は適用されないのです。
なお、複数の者が保険金等を受け取った場合において、その合計額が非課税限度額を超える場合には、各人が適用を受けるべき非課税金額は、受け取った保険金等の額で按分することになっています。
(3)国等への贈与財産
相続財産を相続税の申告期限まで(相続発生後10ヶ月)に、国や地方公共団体、さらには公益を目的とする事業を営む法人のうち一定のものに贈与した場合には、その贈与財産は相続税の計算上非課税とされます。この公益を目的とする法人はかなり多岐にわたっています。
(4)特定公益信託
相続財産である金銭を、相続税の申告期限までに特定公益信託の信託財産として支出した場合には非課税となります。
(5)その他
その他以下のうち、一定のものが非課税とされています。
・公益事業を行う者が取得した公益事業用財産
・個人立幼稚園の教育用財産
・心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利
以上『非課税財産』についてお話させていただきました。
次回は『課税価格の計算』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
1・非課税財産
以下の財産は、社会政策的見地や国民感情等を配慮して非課税とされています。
(1)墓所、霊びょう、祭具等
要するにお墓の類です。墓地、墓石をはじめ神棚、神体、神具、仏壇、仏具、位牌等です。ただし、これらのものであっても、商品や投資対象として所有されているものは含まれません(以前相続税対策として、純金で仏壇を作って非課税を主張した人がいたため、国税庁がこのような通達を作ったそうです)。
(2)一定の生命保険金、退職金
相続人の生活安定の見地から、相続人が(相続でない者は不可)取得した生命保険金や退職金のうち、それぞれ一定の非課税限度額までの金額は非課税です。非課税限度額は、
『500万円×法定相続人の数』
です。この場合の法定相続人の数は、基礎控除を計算する場合と同じ(相続放棄者も含む、養子の数は制限)です。一方『相続人が取得した』という場合の相続人は、純粋に民法の定める相続人をいいます(特にことわりがない場合は、『相続人』の用語はこのように理解して下さい。)すなわち正式に相続を放棄した者(相続人ではない)が受け取った保険金等には、非課税規定は適用されないのです。
なお、複数の者が保険金等を受け取った場合において、その合計額が非課税限度額を超える場合には、各人が適用を受けるべき非課税金額は、受け取った保険金等の額で按分することになっています。
(3)国等への贈与財産
相続財産を相続税の申告期限まで(相続発生後10ヶ月)に、国や地方公共団体、さらには公益を目的とする事業を営む法人のうち一定のものに贈与した場合には、その贈与財産は相続税の計算上非課税とされます。この公益を目的とする法人はかなり多岐にわたっています。
(4)特定公益信託
相続財産である金銭を、相続税の申告期限までに特定公益信託の信託財産として支出した場合には非課税となります。
(5)その他
その他以下のうち、一定のものが非課税とされています。
・公益事業を行う者が取得した公益事業用財産
・個人立幼稚園の教育用財産
・心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利
以上『非課税財産』についてお話させていただきました。
次回は『課税価格の計算』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月09日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『みなし相続財産の種別』について
本日は『みなし相続財産の種別』について、お話させていただきます。
1・みなし相続財産には、具体的には次のようなものがあります。
①生命保険金等
被相続人が保険料を負担していた生命保険金を、被相続人の死亡により相続人またはそれ以外の者が取得した場合には、前者の場合は相続により、後者(相続人以外の者が取得)の場合は遺贈により取得したものとみなされます。偶然な事故に基因する死亡に伴い受け取る損害保険契約に基づく保険金も同様です。
この場合、相続とみなされる(受取人が相続人)か、遺贈とみなされる(それ以外)かは大きな差が生じます。後者では、『法定相続人1人当たり500万円』の非課税規定が受けられないからです。
なお保険金の受け取りの際には、通常割戻し金または前納保険料等を受け取りますが、これらもみなし相続財産としての受取保険金に含むものして取り扱います。逆に契約者貸付金や未払保険料として保険金から控除されたものがある場合にも、原則として控除後の金額を受取保険金として取り扱います。
②死亡退職金
被相続人の死亡に基因して、相続人等が被相続人に支給されるべきであった退職金を受け取った場合(死亡後3以内に支給が確定したものに限る)、この退職金も相続財産であるとみなされます。
なお、相続人が支給を受けた場合に限って相続とみなされ、『法定相続人1人当たり500万円』の非課税規定を受けられる点は、死亡保険金の場合と全く同じです。この場合、退職金の支給を受けるべき者とは、
・まず退職給与規定等に定めのある場合は、その規定のとおりとする(通常、大企業や役所では配偶者と定められているようです。)
・規定がない場合には、実際に取得した者(相続人全員で取得者を決めた場合はその者)とする。
とされています。要するに、規定がある場合にはそれに従い、ない場合は基本的には相続人等の任意ということになりましょう。
③生命保険契約に関する権利
被相続人が子供や孫を被保険者とする生命保険契約(掛捨保険を除く)に関する保険料を支払っていた場合に相続が発生した場合には、生命保険契約の権利が相続財産として次のとおりカウントされます。
まず子や孫という若い人を被保険者とした場合に支払った保険料は、(被保険者は滅多に死亡しないため)いわば預金のようなものです。この場合、保険契約者が預金者の地位にあります。つまり、契約者がこの預金(保険)を解約すれば払い込んだ保険料全額程度を手にすることができるのです。
このように被相続人が保険料を支払っていた場合には、保険契約者には『生命保険契約の権利』として相続財産に計上される事となります。
さて、被相続人が保険料を払っているということは、通常はその被相続人が保険契約者であろうと思われます。その場合には、この生命保険契約の権利は本来の(うまり民法上も)相続財産となります。但し、稀に被相続人と別の人が、保険契約者である場合があります。この場合には(民法上は、この権利は保険契約者に帰属することになりますが)これを相続財産とみなすわけです。
④定期金に関する権利等
郵便年金契約等の定期金給付契約で被相続人がその掛金(保険料)を負担し、かつ被相続人以外の者が契約者あるもの、についても上記③と同様の理由からみなし相続財産となります。
以上、『みなし相続財産の種別』につきましてお話させていただきました。
次回は『非課税財産』に関してのお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
1・みなし相続財産には、具体的には次のようなものがあります。
①生命保険金等
被相続人が保険料を負担していた生命保険金を、被相続人の死亡により相続人またはそれ以外の者が取得した場合には、前者の場合は相続により、後者(相続人以外の者が取得)の場合は遺贈により取得したものとみなされます。偶然な事故に基因する死亡に伴い受け取る損害保険契約に基づく保険金も同様です。
この場合、相続とみなされる(受取人が相続人)か、遺贈とみなされる(それ以外)かは大きな差が生じます。後者では、『法定相続人1人当たり500万円』の非課税規定が受けられないからです。
なお保険金の受け取りの際には、通常割戻し金または前納保険料等を受け取りますが、これらもみなし相続財産としての受取保険金に含むものして取り扱います。逆に契約者貸付金や未払保険料として保険金から控除されたものがある場合にも、原則として控除後の金額を受取保険金として取り扱います。
②死亡退職金
被相続人の死亡に基因して、相続人等が被相続人に支給されるべきであった退職金を受け取った場合(死亡後3以内に支給が確定したものに限る)、この退職金も相続財産であるとみなされます。
なお、相続人が支給を受けた場合に限って相続とみなされ、『法定相続人1人当たり500万円』の非課税規定を受けられる点は、死亡保険金の場合と全く同じです。この場合、退職金の支給を受けるべき者とは、
・まず退職給与規定等に定めのある場合は、その規定のとおりとする(通常、大企業や役所では配偶者と定められているようです。)
・規定がない場合には、実際に取得した者(相続人全員で取得者を決めた場合はその者)とする。
とされています。要するに、規定がある場合にはそれに従い、ない場合は基本的には相続人等の任意ということになりましょう。
③生命保険契約に関する権利
被相続人が子供や孫を被保険者とする生命保険契約(掛捨保険を除く)に関する保険料を支払っていた場合に相続が発生した場合には、生命保険契約の権利が相続財産として次のとおりカウントされます。
まず子や孫という若い人を被保険者とした場合に支払った保険料は、(被保険者は滅多に死亡しないため)いわば預金のようなものです。この場合、保険契約者が預金者の地位にあります。つまり、契約者がこの預金(保険)を解約すれば払い込んだ保険料全額程度を手にすることができるのです。
このように被相続人が保険料を支払っていた場合には、保険契約者には『生命保険契約の権利』として相続財産に計上される事となります。
さて、被相続人が保険料を払っているということは、通常はその被相続人が保険契約者であろうと思われます。その場合には、この生命保険契約の権利は本来の(うまり民法上も)相続財産となります。但し、稀に被相続人と別の人が、保険契約者である場合があります。この場合には(民法上は、この権利は保険契約者に帰属することになりますが)これを相続財産とみなすわけです。
④定期金に関する権利等
郵便年金契約等の定期金給付契約で被相続人がその掛金(保険料)を負担し、かつ被相続人以外の者が契約者あるもの、についても上記③と同様の理由からみなし相続財産となります。
以上、『みなし相続財産の種別』につきましてお話させていただきました。
次回は『非課税財産』に関してのお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月08日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『相続財産』について
『相続財産』
(1)納税義務者
相続税の納税義務者は、相続または遺贈(死因贈与を含む、以下同じ)により財産を取得した個人です。
納税義務者は、無制限納税義務者と制限納税義務者に区分されます。前者は、相続等により財産を取得した時の住所地が日本国内にある者であり、後者は日本国内にない者(期間が1年以上と見込まれる海外勤務者等)をいいます(この場合被相続人の住所地は無関係です)。
制限納税義務者は、相続財産のうち日本国内にある財産についてのみ相続税が課されます。一方、無制限納税義務者に対してはそのような制限はなく、全世界にある遺産が課税対象となります。
(2)本来の相続財産
相続開始に際しては、被相続人に属していた一切の権利義務(一身専属権を除く)が、相続人に相続されます。この相続財産が課税対象とされるわけですが、これは具体的には、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいうものと解されています。すなわち不動産や金融資産に限らず、理屈の上では庭木庭石の一本一個に至るまで課税対象となるのです。
具体的には、物件、質権、無体財産権から電話加入権や営業権等、経済価値が認められるものすべて(あくまで経済的価値のあるものに限られます)となります。ただし質権、抵当権等は独立した財産ではないため課税の対象外です。
(3)みなし相続財産
生命保険契約においては、被相続人を被保険者とし、保険金受取人を配偶者や子とする契約を、被相続人自身が契約(当然保険料も被相続人が負担)する場合が多いものと思われます。この場合で被相続人が死去すれば、当然保険金受取人(たとえば配偶者とする)に保険金(1,000万円とする)が支払われます。
この死亡保険金1,000万円は、民法上は相続財産ではなく、配偶者固有の財産と考えられます。つまり1,000万円は、配偶者が保険金受取人という立場でしたものであって、遺産として相続したものではない、というわけなのです。(ただしこの場合にも民法上は、特別受益として遺産に払戻すべき、と考えられているようです)。
しかし相続税法は、このような死亡保険金は事実上相続財産と同様の効果があるとして、相続財産とみなして相続税の課税対象としています。(契約形態によって相続税が課されない場合には、死亡保険金の受取人には所得税等が課されるものと思われます)。
したがって、このようなみなし相続財産は民法上は遺産でないため、原則として遺産分割の対象とすべきではありません。さらに、不用意に遺産分割協議書に本来の保険金受取人以外の者を取得者として記載すると、贈与の問題が生じかねませんので注意が必要です。
以上、『相続財産』についての簡単なお話をさせていただきました。
次回は、『みなし相続財産の種別』と『非課税財産』についてのお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
(1)納税義務者
相続税の納税義務者は、相続または遺贈(死因贈与を含む、以下同じ)により財産を取得した個人です。
納税義務者は、無制限納税義務者と制限納税義務者に区分されます。前者は、相続等により財産を取得した時の住所地が日本国内にある者であり、後者は日本国内にない者(期間が1年以上と見込まれる海外勤務者等)をいいます(この場合被相続人の住所地は無関係です)。
制限納税義務者は、相続財産のうち日本国内にある財産についてのみ相続税が課されます。一方、無制限納税義務者に対してはそのような制限はなく、全世界にある遺産が課税対象となります。
(2)本来の相続財産
相続開始に際しては、被相続人に属していた一切の権利義務(一身専属権を除く)が、相続人に相続されます。この相続財産が課税対象とされるわけですが、これは具体的には、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいうものと解されています。すなわち不動産や金融資産に限らず、理屈の上では庭木庭石の一本一個に至るまで課税対象となるのです。
具体的には、物件、質権、無体財産権から電話加入権や営業権等、経済価値が認められるものすべて(あくまで経済的価値のあるものに限られます)となります。ただし質権、抵当権等は独立した財産ではないため課税の対象外です。
(3)みなし相続財産
生命保険契約においては、被相続人を被保険者とし、保険金受取人を配偶者や子とする契約を、被相続人自身が契約(当然保険料も被相続人が負担)する場合が多いものと思われます。この場合で被相続人が死去すれば、当然保険金受取人(たとえば配偶者とする)に保険金(1,000万円とする)が支払われます。
この死亡保険金1,000万円は、民法上は相続財産ではなく、配偶者固有の財産と考えられます。つまり1,000万円は、配偶者が保険金受取人という立場でしたものであって、遺産として相続したものではない、というわけなのです。(ただしこの場合にも民法上は、特別受益として遺産に払戻すべき、と考えられているようです)。
しかし相続税法は、このような死亡保険金は事実上相続財産と同様の効果があるとして、相続財産とみなして相続税の課税対象としています。(契約形態によって相続税が課されない場合には、死亡保険金の受取人には所得税等が課されるものと思われます)。
したがって、このようなみなし相続財産は民法上は遺産でないため、原則として遺産分割の対象とすべきではありません。さらに、不用意に遺産分割協議書に本来の保険金受取人以外の者を取得者として記載すると、贈与の問題が生じかねませんので注意が必要です。
以上、『相続財産』についての簡単なお話をさせていただきました。
次回は、『みなし相続財産の種別』と『非課税財産』についてのお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月07日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『遺言』について
1・遺言の要式性
遺言は死後に効力が生じるため、その真実生や内容が問題になっても遺言者に確認することができません。したがって遺言者の真意を確保するために、遺言には一定の方式が要求されています。
その意味から遺言の形式は、次の3種類に限定されています。(これ以外にも死亡応急者の遺言等の特別の方式が4種類定められています。)
①自筆証書遺言
これは遺言者が、その全文、日付および氏名を自書したうえで、これに印を押さなければなりません。さらに遺言者の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示しこれを変更した旨を付記したうえで、これに署名押印しなければその効力が生じないこととされています。
留意点は、全文を自書することです(ワープロなどは不可)。日付は、複数の遺言が存在した場合の優先を判定する意味にも重要です。押印は実印である必要はありません。
自筆証書遺言は、3種の方式のうち最も簡単な方法です。とにかく上記の指示のとおりに書くだけでできてしまします(書き誤りの訂正方法は多少やっかいです。謝ったら書き直せばいいのです。なお、遺言書は特に密封する必要もありません)。他の方法が面倒であれば、この方法で十分であろうと思われます。ただし紛失や変造等のおそれがないわけではないことや、保管方法にも工夫を要することにもなりましょう。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、交渉役場の公証人に遺言書を作成してもらう方法です。
多少手間がかかることと費用(相続財産に応じて10~30万円位?)を要することが欠点といえましょう。さらに2人の証人も必要となります。
しかし紛失や隠匿のおそれが全くなく、秘密の確保は十分。相続発生時においても家庭裁判所の検認を受ける必要はなく、遺言内容の効力についても全く心配ありません。要するに百パーセント確実な遺言を残そうとするのであれば、公正証書遺言に限るのです。
③秘密証書遺言
この方式は、とにかく内容を一切誰にも知らせない状況で作成するためのものです(欠点が多く、実際にはほとんど利用されていないようです)。
したがって書面自体には方式はなく(ワープロも可)、ただこの遺言書に署名と押印したうえで、公証人と証人の立会いの下でこれを封入するのです。但し公証人等は遺言内容をチェックしているわけでなく、不明確な内容である場合等後日の紛争が気がかりとなります。また遺言書の保管も公証人が行うわけではありません。
2・遺言の効力
遺言は遺言者の意思表示のみで成立する単独行動です。一般の契約のように相手側の承諾は一切不要なのです。さらに遺言の効力は、遺言作成(意思表示)の時ではなく、遺言者の死亡の時に初めて生じます。この点も一般の契約と異なる点といえましょう。
遺言により財産を贈与することを遺贈といいます。遺贈によく似たものとして死因贈与があります。死因贈与とは『死んだら贈与する』という約束です。贈与者の死亡により効力を生じる点は遺贈と同じですが、死因贈与はあくまで契約(双方の意思の合致)であり、受贈者側の承諾を必要とするのです。
ただし、相続税法では死因贈与を遺贈とみなす、と定めています。要するに両者を同一視して取り扱うのです。
さてご承知のように遺言者は、いつでもその遺言を取り消すことができます。実際に遺言書を破棄してもいいし、新たに遺言書を作成してもかまいません。日付の古い遺言書で新しいものと抵触する部分は取り消されたものとみなされるからです。
遺言書の保管については、民法には何の規定もありません。遺言者が自らの責任で保管するわけです。保管者としては遺言によって守られているであろう配偶者等が多いようですが、友人や弁護士である場合、さらには貸金庫に置いておく等、多岐にわたるようです。いずれにしても内容が漏れたり、破棄や隠匿されないような工夫が必要となります。
3・遺言の執行
一般に遺言の内容を実現することを、遺言の執行といいます。
まず、その準備行為として、遺言書を家庭裁判所へ提出して、その検認を受けなければなりません。検認は、遺言者が真に遺言者の作成したものであるかどうかを確かめ、その保存を確実にするために行われる一種の証拠保全手続きとされています。したがって、これらを要しない公正証書遺言には、検認手続は不要です。
ただし、検認は遺言者の正当を立証するわけではありません。検認を経ていないからといって、遺言が無効になるわけでもありません。しかしその一方で、検認を受けていない遺言書では、登記所が受け付けてくれないのも事実です。なお封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人(代理人)の立会いのもとで開封すべき旨定めらています。
遺言は一般に相続人間の利益が相反する場合が少なくありません。相続人に遺言の執行をさせることは適当でない場合が少なからずあるのです。さらに遺産の内容によっては、その執行や処理に専門的な知識を必要とする場合もありましょう。
したがって、このようなケースでは、遺言で適任者を遺言執行人に指定しておくことが適当かと思われます。遺言執行人とは、いわば遺言者の代理人の立場で遺言の内容を実現していくべき人です。
実際にも少なからぬ遺言で、これが指定されているようです。
なお、遺言による受贈者が法定相続人ではない場合には、不動産の相続登記に際して法定相続人(登記義務者)の実印が必要となります。しかし遺言執行人が指定されていれば、この印は不要です(公正証書遺言も同様)。このような場合には、必ず遺言執行人を指定しておくべきといえましょう。
以上、民本の規定による『遺言』について、お話させていただきました。
次回は、『相続財産』の事についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
遺言は死後に効力が生じるため、その真実生や内容が問題になっても遺言者に確認することができません。したがって遺言者の真意を確保するために、遺言には一定の方式が要求されています。
その意味から遺言の形式は、次の3種類に限定されています。(これ以外にも死亡応急者の遺言等の特別の方式が4種類定められています。)
①自筆証書遺言
これは遺言者が、その全文、日付および氏名を自書したうえで、これに印を押さなければなりません。さらに遺言者の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示しこれを変更した旨を付記したうえで、これに署名押印しなければその効力が生じないこととされています。
留意点は、全文を自書することです(ワープロなどは不可)。日付は、複数の遺言が存在した場合の優先を判定する意味にも重要です。押印は実印である必要はありません。
自筆証書遺言は、3種の方式のうち最も簡単な方法です。とにかく上記の指示のとおりに書くだけでできてしまします(書き誤りの訂正方法は多少やっかいです。謝ったら書き直せばいいのです。なお、遺言書は特に密封する必要もありません)。他の方法が面倒であれば、この方法で十分であろうと思われます。ただし紛失や変造等のおそれがないわけではないことや、保管方法にも工夫を要することにもなりましょう。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、交渉役場の公証人に遺言書を作成してもらう方法です。
多少手間がかかることと費用(相続財産に応じて10~30万円位?)を要することが欠点といえましょう。さらに2人の証人も必要となります。
しかし紛失や隠匿のおそれが全くなく、秘密の確保は十分。相続発生時においても家庭裁判所の検認を受ける必要はなく、遺言内容の効力についても全く心配ありません。要するに百パーセント確実な遺言を残そうとするのであれば、公正証書遺言に限るのです。
③秘密証書遺言
この方式は、とにかく内容を一切誰にも知らせない状況で作成するためのものです(欠点が多く、実際にはほとんど利用されていないようです)。
したがって書面自体には方式はなく(ワープロも可)、ただこの遺言書に署名と押印したうえで、公証人と証人の立会いの下でこれを封入するのです。但し公証人等は遺言内容をチェックしているわけでなく、不明確な内容である場合等後日の紛争が気がかりとなります。また遺言書の保管も公証人が行うわけではありません。
2・遺言の効力
遺言は遺言者の意思表示のみで成立する単独行動です。一般の契約のように相手側の承諾は一切不要なのです。さらに遺言の効力は、遺言作成(意思表示)の時ではなく、遺言者の死亡の時に初めて生じます。この点も一般の契約と異なる点といえましょう。
遺言により財産を贈与することを遺贈といいます。遺贈によく似たものとして死因贈与があります。死因贈与とは『死んだら贈与する』という約束です。贈与者の死亡により効力を生じる点は遺贈と同じですが、死因贈与はあくまで契約(双方の意思の合致)であり、受贈者側の承諾を必要とするのです。
ただし、相続税法では死因贈与を遺贈とみなす、と定めています。要するに両者を同一視して取り扱うのです。
さてご承知のように遺言者は、いつでもその遺言を取り消すことができます。実際に遺言書を破棄してもいいし、新たに遺言書を作成してもかまいません。日付の古い遺言書で新しいものと抵触する部分は取り消されたものとみなされるからです。
遺言書の保管については、民法には何の規定もありません。遺言者が自らの責任で保管するわけです。保管者としては遺言によって守られているであろう配偶者等が多いようですが、友人や弁護士である場合、さらには貸金庫に置いておく等、多岐にわたるようです。いずれにしても内容が漏れたり、破棄や隠匿されないような工夫が必要となります。
3・遺言の執行
一般に遺言の内容を実現することを、遺言の執行といいます。
まず、その準備行為として、遺言書を家庭裁判所へ提出して、その検認を受けなければなりません。検認は、遺言者が真に遺言者の作成したものであるかどうかを確かめ、その保存を確実にするために行われる一種の証拠保全手続きとされています。したがって、これらを要しない公正証書遺言には、検認手続は不要です。
ただし、検認は遺言者の正当を立証するわけではありません。検認を経ていないからといって、遺言が無効になるわけでもありません。しかしその一方で、検認を受けていない遺言書では、登記所が受け付けてくれないのも事実です。なお封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人(代理人)の立会いのもとで開封すべき旨定めらています。
遺言は一般に相続人間の利益が相反する場合が少なくありません。相続人に遺言の執行をさせることは適当でない場合が少なからずあるのです。さらに遺産の内容によっては、その執行や処理に専門的な知識を必要とする場合もありましょう。
したがって、このようなケースでは、遺言で適任者を遺言執行人に指定しておくことが適当かと思われます。遺言執行人とは、いわば遺言者の代理人の立場で遺言の内容を実現していくべき人です。
実際にも少なからぬ遺言で、これが指定されているようです。
なお、遺言による受贈者が法定相続人ではない場合には、不動産の相続登記に際して法定相続人(登記義務者)の実印が必要となります。しかし遺言執行人が指定されていれば、この印は不要です(公正証書遺言も同様)。このような場合には、必ず遺言執行人を指定しておくべきといえましょう。
以上、民本の規定による『遺言』について、お話させていただきました。
次回は、『相続財産』の事についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月06日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『遺産分割方法』について
(1)遺産分割方法
分割協議の成立後に勘違い等で、分割協議書を作り直すこともあると思われます(中には協議書の書き間違いもあるでしょう)。むろん皆の合意の下で作り直せばいいのですが、大きな問題が一つあります。事実上税務署がこれを認めようとしないのです。つまり「それは分割のやり直しではなく贈与だ」というのです。税務署側にしてみれば、これを認めたら一般の贈与すら皆「遺産分割の修正」と逃げられてしまうのではないか、と考えるのです。ですから、一度税務署に提出したもの等は、訂正が効かない(民法に「錯誤は無効」の規定があるとしても、国税側にこれを立証することは困難でしょう)と思っていただきたいのです。
民法は、遺産分割の方法として、現物分割、代償分割、換価分割、共有とする分割の4種類を定めています。内容は読んで字のごとしで、現物分割とは、遺産を現物のまま分割する方法で、換価分割とは、共同相続人が遺産の全部又は一部を金銭に換価し、その代金を分割する方法ですが、このうち代償分割が実務上極めて大切です。
代償分割とは、ある相続人が特定の遺産を相続する代償にその相続人がその固有資産(通常金銭)を他の相続人に支払う、というものです。たとえば、遺産は長男が同居している自宅のみで他に何もない場合に、長男がこの自宅を単独で相続する代わりに、他の相続人に対して長男がたとえば1,000万円を支払う、といったケースです。
これは一見遺産の売買のように思えますが、民法が遺産分割として定めている以上、売買ではないのです。使い方次第では、代償分割は相続対策や節税対策にかなり有効となります。
相続人の中には、諸般の事情からあえて遺産の取得を希望しない人もいます。その意思を表すために先の家庭裁判所に相続放棄の手続きをするケースもあるそうです。
しかし何もそんな面倒なことをする必要はないように思います。要するに、当人に遺産の配分がないと記載されている遺産分割協議書に押印すればよいのです。実務上大半はこれにより事実上の相続放棄を行っています。(わずかではありますが、相続放棄を行うと相続税の取り扱い上で不利になることもあります。)
(2)特別受益と寄与分
相続人の中には、被相続人から婚姻や生計の資本等のために多額の生前贈与や遺贈(遺言による贈与)を受けていることもあります。これらの生前贈与や遺言を受けた相続人を特別受益者、受けた利益を特別受益といいます。
民法は相続の公平の見地から、具体的な相続を査定する(事実上の遺産分割)に当たっては、特別受益分を遺産に持戻した(加算した)ものを相続財産とみなしたうえで、決定すべきことを定めています。
なお、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金は、遺産ではなく保険金受取人の固有資産と考えられています。したがって、死亡保険金は遺産分割の対象とはなりませんが、特別受益と同様の考え方から、分割に当たっては相続財産に持戻しすべきであるとされています。この点は死亡退職金も同様とされています。
一方相続人の中には、被相続人の事業に関する労務の提供や被相続人の療養看護等により、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいる場合もあります。この場合には、その者の寄与分を加算した額を寄与者の相続分とする旨定められています。なお、長男の嫁等は相続人ではありませんから、寄与分の規定は適用できません。規定の対象者は相続人に限定されている点に留意して下さい。
以上の特別受益や寄与分についての規定は、実際の円満な遺産分割においては『私は親の面倒をみたのだから・・・』とか『私は既にこれだけもらっているのだから・・・』といった形で常識的な考え方として生かされています。具体的にこの規定がモノをいって来るのは、家庭裁判所における調停・審判の場であろうと思われます。
今回は『遺産分割方法』と『特別受益と寄与分』につきまして、お話させていただきました。
次回は、『遺言』に関する内容を、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
分割協議の成立後に勘違い等で、分割協議書を作り直すこともあると思われます(中には協議書の書き間違いもあるでしょう)。むろん皆の合意の下で作り直せばいいのですが、大きな問題が一つあります。事実上税務署がこれを認めようとしないのです。つまり「それは分割のやり直しではなく贈与だ」というのです。税務署側にしてみれば、これを認めたら一般の贈与すら皆「遺産分割の修正」と逃げられてしまうのではないか、と考えるのです。ですから、一度税務署に提出したもの等は、訂正が効かない(民法に「錯誤は無効」の規定があるとしても、国税側にこれを立証することは困難でしょう)と思っていただきたいのです。
民法は、遺産分割の方法として、現物分割、代償分割、換価分割、共有とする分割の4種類を定めています。内容は読んで字のごとしで、現物分割とは、遺産を現物のまま分割する方法で、換価分割とは、共同相続人が遺産の全部又は一部を金銭に換価し、その代金を分割する方法ですが、このうち代償分割が実務上極めて大切です。
代償分割とは、ある相続人が特定の遺産を相続する代償にその相続人がその固有資産(通常金銭)を他の相続人に支払う、というものです。たとえば、遺産は長男が同居している自宅のみで他に何もない場合に、長男がこの自宅を単独で相続する代わりに、他の相続人に対して長男がたとえば1,000万円を支払う、といったケースです。
これは一見遺産の売買のように思えますが、民法が遺産分割として定めている以上、売買ではないのです。使い方次第では、代償分割は相続対策や節税対策にかなり有効となります。
相続人の中には、諸般の事情からあえて遺産の取得を希望しない人もいます。その意思を表すために先の家庭裁判所に相続放棄の手続きをするケースもあるそうです。
しかし何もそんな面倒なことをする必要はないように思います。要するに、当人に遺産の配分がないと記載されている遺産分割協議書に押印すればよいのです。実務上大半はこれにより事実上の相続放棄を行っています。(わずかではありますが、相続放棄を行うと相続税の取り扱い上で不利になることもあります。)
(2)特別受益と寄与分
相続人の中には、被相続人から婚姻や生計の資本等のために多額の生前贈与や遺贈(遺言による贈与)を受けていることもあります。これらの生前贈与や遺言を受けた相続人を特別受益者、受けた利益を特別受益といいます。
民法は相続の公平の見地から、具体的な相続を査定する(事実上の遺産分割)に当たっては、特別受益分を遺産に持戻した(加算した)ものを相続財産とみなしたうえで、決定すべきことを定めています。
なお、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金は、遺産ではなく保険金受取人の固有資産と考えられています。したがって、死亡保険金は遺産分割の対象とはなりませんが、特別受益と同様の考え方から、分割に当たっては相続財産に持戻しすべきであるとされています。この点は死亡退職金も同様とされています。
一方相続人の中には、被相続人の事業に関する労務の提供や被相続人の療養看護等により、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいる場合もあります。この場合には、その者の寄与分を加算した額を寄与者の相続分とする旨定められています。なお、長男の嫁等は相続人ではありませんから、寄与分の規定は適用できません。規定の対象者は相続人に限定されている点に留意して下さい。
以上の特別受益や寄与分についての規定は、実際の円満な遺産分割においては『私は親の面倒をみたのだから・・・』とか『私は既にこれだけもらっているのだから・・・』といった形で常識的な考え方として生かされています。具体的にこの規定がモノをいって来るのは、家庭裁判所における調停・審判の場であろうと思われます。
今回は『遺産分割方法』と『特別受益と寄与分』につきまして、お話させていただきました。
次回は、『遺言』に関する内容を、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月05日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『遺産分割』について
【遺産分割】
(1)相続放棄等・・相続は自動承認の形をとっています。すなわち相続人は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続の放棄または限定承認をしない限り、相続を単純承認したことになります。単純承認(限定承認でないという意味)をした場合には、被相続人の権利義務を承認したことになります。
したがって、相続財産よりも相続債務の方が多い場合等には、上記の期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行うことができるわけです。
放棄した者は、初めから相続人でないものとされます。すると、次順位の者が相続人に浮上します。その結果、相続人が大借金を残したことことが明らかな場合には、第3順位までを含めた相続人が全員放棄の手続きをしないと、誰かがとんでもない貧乏くじを引くことになりますから、注意が必要です。
(2)遺産分割・・遺産を配分する方法には優先順位があります。まず遺言があればこれに従います。
2番目、遺言がなければ相続人全員で協議して決めます。(法定相続分は参考程度)。この協議が整わなければ家庭裁判所に持ち込んで調停や審判に委ねます。この場合の判断の基準は法定相続分となります。
上記の2番目が遺産分割です。一般の相続の7~8割以上がこれによっているものと思われます。(遺言はまだ少数派です。)なお遺言があっても、法定相続人や受遺者の全員が、これ以外の配分の方法による遺産分割に合意した場合には、実務上それが認められています。民法等のどこにもそのような規定はないのですが、「無理に遺言を強制してもしかたない」ということのようです。(税法もOK)。
分割協議が成立すれば、通常は遺産分割協議書にその内容を記載して相続人全員が署(記)名捺印します。逆に1人でも反対者がいれば、協議分割は不成立となります。この場合は家庭裁判所での調停、審判となります。こうなると家族の絆にひびが入ってしまいます。このようなことが予想される場合には、あらかじめ遺言を書いておくべきでしょう。なお相続税の申告の際には必ず税務署に提出します。また不動産を相続登記する場合には、遺産分割協議書が登記原因証書になるため、実印の押印が必要となります。
以上、今回は民法の『遺産分割』についてお話させていただきました。
相続が発生した時に、相続税が生じる、生じないに関わらず、相続人の円満な遺産分割が最重要と考えます。
したがいまして、円満な遺産分割のための対策が相続発生前の相続対策の最優先事項と考えます。
それには、先ず、ご所有財産、特に不動産の棚卸調査(財産診断)を基にした財産の現状分析を行う事が大切です。ご所有の不動産の内には、駅前の事業に適した土地もあれば、優良な住宅団地の中で住宅には申し分ないですが事業(アパート他)には適さない土地や調整区域で売却や活用に制限がかかる土地など、多種多彩な特徴があります。納税が発生する時には、納税用の資金の準備をどうするのか?納税資金の方法の見通しがたったら、各相続人への分割をどの様に配分するのかの検討が必要となります。相続が発生してから、ご所有財産を見直すのではなく、あらかじめ、現状分析を行った上で、納税方法、分割方法、、節税方法、や保険の活用等を検討しておく事が重要となります。
次回は、民法の規定の『遺産分割方法』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
(1)相続放棄等・・相続は自動承認の形をとっています。すなわち相続人は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続の放棄または限定承認をしない限り、相続を単純承認したことになります。単純承認(限定承認でないという意味)をした場合には、被相続人の権利義務を承認したことになります。
したがって、相続財産よりも相続債務の方が多い場合等には、上記の期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行うことができるわけです。
放棄した者は、初めから相続人でないものとされます。すると、次順位の者が相続人に浮上します。その結果、相続人が大借金を残したことことが明らかな場合には、第3順位までを含めた相続人が全員放棄の手続きをしないと、誰かがとんでもない貧乏くじを引くことになりますから、注意が必要です。
(2)遺産分割・・遺産を配分する方法には優先順位があります。まず遺言があればこれに従います。
2番目、遺言がなければ相続人全員で協議して決めます。(法定相続分は参考程度)。この協議が整わなければ家庭裁判所に持ち込んで調停や審判に委ねます。この場合の判断の基準は法定相続分となります。
上記の2番目が遺産分割です。一般の相続の7~8割以上がこれによっているものと思われます。(遺言はまだ少数派です。)なお遺言があっても、法定相続人や受遺者の全員が、これ以外の配分の方法による遺産分割に合意した場合には、実務上それが認められています。民法等のどこにもそのような規定はないのですが、「無理に遺言を強制してもしかたない」ということのようです。(税法もOK)。
分割協議が成立すれば、通常は遺産分割協議書にその内容を記載して相続人全員が署(記)名捺印します。逆に1人でも反対者がいれば、協議分割は不成立となります。この場合は家庭裁判所での調停、審判となります。こうなると家族の絆にひびが入ってしまいます。このようなことが予想される場合には、あらかじめ遺言を書いておくべきでしょう。なお相続税の申告の際には必ず税務署に提出します。また不動産を相続登記する場合には、遺産分割協議書が登記原因証書になるため、実印の押印が必要となります。
以上、今回は民法の『遺産分割』についてお話させていただきました。
相続が発生した時に、相続税が生じる、生じないに関わらず、相続人の円満な遺産分割が最重要と考えます。
したがいまして、円満な遺産分割のための対策が相続発生前の相続対策の最優先事項と考えます。
それには、先ず、ご所有財産、特に不動産の棚卸調査(財産診断)を基にした財産の現状分析を行う事が大切です。ご所有の不動産の内には、駅前の事業に適した土地もあれば、優良な住宅団地の中で住宅には申し分ないですが事業(アパート他)には適さない土地や調整区域で売却や活用に制限がかかる土地など、多種多彩な特徴があります。納税が発生する時には、納税用の資金の準備をどうするのか?納税資金の方法の見通しがたったら、各相続人への分割をどの様に配分するのかの検討が必要となります。相続が発生してから、ご所有財産を見直すのではなく、あらかじめ、現状分析を行った上で、納税方法、分割方法、、節税方法、や保険の活用等を検討しておく事が重要となります。
次回は、民法の規定の『遺産分割方法』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月03日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『相続人と相続分②』について
今回は、前回の続きとしまして相続人としての養子の要件と相続分についてお話させて頂きます。
①養子について
養子は人為的につくられた親子関係です。養子関係は、婚姻と同様に役所への所定の届出により行う縁組によりその効力が発生します。
養子縁組の効果は、縁組の日から養子が養親嫡出子たる身分を取得することとなることです。したがって養親子は、相互に相続権および親族的扶養義務を負います。同時に、養子と養親の血族との間にも親族関係が発生します。さらに養子は養親の氏を称しなければなりません(しかし多くの既婚者である女性のように、結婚により氏が改まった者はその必要はありません。)
但し、次のような要件を満たしていないと、縁組は不成立(無効)になります。
・縁組の意思が合致していること(単なる方便のみでは不可)。
・養親となる者は成年に達しており、かつ養子より年長であること。
・直系卑属でない未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を得ること。
・配偶者のある者が未成年者を養子にする場合は、原則として夫婦が共同して縁組すること。
・配偶者のある者が養子になる場合には、他の配偶者の同意を得ること。
養子縁組の当事者は、協議離婚と同じように、話し合いで離縁することができます。離縁がなされれば、ほぼ従前の関係に戻ります。
なお上記で説明しました『普通養子』の他に、総和62年の民法の改正により『特別養子』制度が創設されています。一言でいえば、実親が育てることのできない赤ん坊を、全くの実子同様に育てようとする人が養子にするためのものです。
したがって、養子は6歳未満の幼児であること、縁組により実親等との法律上の関係は消滅すること、離縁は許さないこと等が原則規定とされています。さらに、戸籍上も一見しただけでは養子であることが分からない措置がとられています。
②相続分
相続分とは、相続財産に対する配分の割合をいいます。
民法は以下のとおり相続分を定めています。これを『法定相続分』といいます。(なお遺言で相続分が指定されているものを『指定相続分』といいます。)ただし、相続人の意見の一致により遺産分割協議が整うのであれば、法定相続分に拘束される必要は全くありません。現実にはほとんどの場合、遺産分割協議書の作成等により、自由な割合で遺産を分割しています。
①配偶者と子(第1順位)が相続人である場合は、相続分は各2分の1
②配偶者と直系尊属(第2順位)が相続人である場合は、配偶者の相続分が3分の2、直系尊属が3分の1。
③配偶者および兄弟姉妹(第3順位)が相続人である場合には、配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹は4分の1
④子、直系尊属または兄弟姉妹が複数いる場合には、各自の相続分は(年齢、性別にかかわらず)等しいものとする。
⑤ただし、非嫡出子は嫡出子(婚姻関係にある男女間にに出生した子)の法定相続分の2分の1とし、父母の一方のみの兄弟姉妹(半血兄弟)は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
⑥代襲相続人の相続分の合計は、非代襲者(死亡していた相続人等)の受けるべきであった相続分と同じ割合とする。
以上、『養子』と『相続分』についてお話させていただきました。
なお、相続が発生した場合には、先ず、相続人の確定が必要となります。
相続人の確定には被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの全戸籍を集める必要があります。
全戸籍には、除籍(戸籍記載の全員が結婚・死亡・転籍などでいなくなった戸籍)や改製原戸籍(法改正で様式が改められる前の古い戸籍)も含まれます。これは法定相続人の中でも第1順位となる子を確定するためです。離婚した前妻との間に子がいたり、隠し子を認知していたりすれば、現戸籍には記載がなくても、必ず過去の戸籍をさかのぼれば確認が出来るからです。
他にも、預貯金や株式、不動産などの名義書き換えのたびに、金融機関などの手続き先への提出が求められます。
複雑なケースでは、必要なすべての戸籍を取得するのに1カ月以上かかることもありますので、早め早めの対応をお奨めいたします。
次回は『遺産分割』についてのお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
①養子について
養子は人為的につくられた親子関係です。養子関係は、婚姻と同様に役所への所定の届出により行う縁組によりその効力が発生します。
養子縁組の効果は、縁組の日から養子が養親嫡出子たる身分を取得することとなることです。したがって養親子は、相互に相続権および親族的扶養義務を負います。同時に、養子と養親の血族との間にも親族関係が発生します。さらに養子は養親の氏を称しなければなりません(しかし多くの既婚者である女性のように、結婚により氏が改まった者はその必要はありません。)
但し、次のような要件を満たしていないと、縁組は不成立(無効)になります。
・縁組の意思が合致していること(単なる方便のみでは不可)。
・養親となる者は成年に達しており、かつ養子より年長であること。
・直系卑属でない未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を得ること。
・配偶者のある者が未成年者を養子にする場合は、原則として夫婦が共同して縁組すること。
・配偶者のある者が養子になる場合には、他の配偶者の同意を得ること。
養子縁組の当事者は、協議離婚と同じように、話し合いで離縁することができます。離縁がなされれば、ほぼ従前の関係に戻ります。
なお上記で説明しました『普通養子』の他に、総和62年の民法の改正により『特別養子』制度が創設されています。一言でいえば、実親が育てることのできない赤ん坊を、全くの実子同様に育てようとする人が養子にするためのものです。
したがって、養子は6歳未満の幼児であること、縁組により実親等との法律上の関係は消滅すること、離縁は許さないこと等が原則規定とされています。さらに、戸籍上も一見しただけでは養子であることが分からない措置がとられています。
②相続分
相続分とは、相続財産に対する配分の割合をいいます。
民法は以下のとおり相続分を定めています。これを『法定相続分』といいます。(なお遺言で相続分が指定されているものを『指定相続分』といいます。)ただし、相続人の意見の一致により遺産分割協議が整うのであれば、法定相続分に拘束される必要は全くありません。現実にはほとんどの場合、遺産分割協議書の作成等により、自由な割合で遺産を分割しています。
①配偶者と子(第1順位)が相続人である場合は、相続分は各2分の1
②配偶者と直系尊属(第2順位)が相続人である場合は、配偶者の相続分が3分の2、直系尊属が3分の1。
③配偶者および兄弟姉妹(第3順位)が相続人である場合には、配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹は4分の1
④子、直系尊属または兄弟姉妹が複数いる場合には、各自の相続分は(年齢、性別にかかわらず)等しいものとする。
⑤ただし、非嫡出子は嫡出子(婚姻関係にある男女間にに出生した子)の法定相続分の2分の1とし、父母の一方のみの兄弟姉妹(半血兄弟)は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
⑥代襲相続人の相続分の合計は、非代襲者(死亡していた相続人等)の受けるべきであった相続分と同じ割合とする。
以上、『養子』と『相続分』についてお話させていただきました。
なお、相続が発生した場合には、先ず、相続人の確定が必要となります。
相続人の確定には被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの全戸籍を集める必要があります。
全戸籍には、除籍(戸籍記載の全員が結婚・死亡・転籍などでいなくなった戸籍)や改製原戸籍(法改正で様式が改められる前の古い戸籍)も含まれます。これは法定相続人の中でも第1順位となる子を確定するためです。離婚した前妻との間に子がいたり、隠し子を認知していたりすれば、現戸籍には記載がなくても、必ず過去の戸籍をさかのぼれば確認が出来るからです。
他にも、預貯金や株式、不動産などの名義書き換えのたびに、金融機関などの手続き先への提出が求められます。
複雑なケースでは、必要なすべての戸籍を取得するのに1カ月以上かかることもありますので、早め早めの対応をお奨めいたします。
次回は『遺産分割』についてのお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月02日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『相続人と相続分』について
今回は、相続に関する民法の規定の内、相続人についてお話させていただきます。
①相続とは、被相続人(死者)が生前に持っていた財産上の権利義務を、他の者が包括的に承継することとされています。相続が発生すると、相続人は被相続人の財産に属していた一切の権利義務(一身に専属していたものを除く。)を、包括的に承継します。その期間、遺産は、法定相続分の割合で共同相続人間で共有します。その後、通常は遺産分割によりこれを各相続人に具体的に分割することになります。遺産分割を行うと、分割した遺産は相続開始の時にさかのぼって、各相続人の単独所有に移ります。
②相続人:民法は、相続人を配偶者と血族相続人と定めています。血族とは、血の続いた親族をいいますが、養子は血族としての地位を保ち、実子と同様に取り扱われます。相続人となる血族は、直系卑属(子、孫、ひ孫等)、直系尊属(親、祖父母、曽曽父母等)、並びに兄弟姉妹の3種類からなり、この血族相続人には次の相続順位があります。
まず第1順位が子(代襲者を含みます。)です。第1順位が全くいない場合に第2順位の直系尊属(まず親、親がいないときは祖父母というように親等の近い順)が相続人となります。第1順位、第2順位とも誰もいないときに、第3順位の兄弟姉妹(代襲者を含みます。)が相続人となります。
被相続人の配偶者(婚姻届の出されている法律上の夫、または妻を言う。)は、各血族相続人と並んで、常に相続人となります。
但し、以上の法定相続人であっても、次の場合は相続人となることは、出来なくなります。
『相続欠格』・・故意に被相続人や先・同順位の相続人を殺害する等により処刑された者、詐欺・脅迫により遺言の偽造や隠匿をした者、これらの者は法律上当然に相続人の資格を失います。
『排除』・・推定相続人(被相続人が死亡した場合に相続人となりうる者)が、被相続人を虐待する等の著しい非行があった場合には、被相続人が推定相続人の排除を家庭裁判所に請求し、裁判所が排除を審判により決定すれば、その推定相続人は相続権を失います。
ところで、本来法定相続人であった子や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡していた場合には、これらの子が相続人となります。これを代襲相続人といいます(但し兄弟姉妹の代襲相続は子の一代限りとなります)。代襲相続は本来の相続人が亡くなっていた場合の他、上記の相続欠格や排除により相続権を失った場合にも成立しますが、相続放棄をした場合には該当しません。
なお、先の法定相続人が誰もいないときは、最終的には国庫に帰属することとなります。具体的には、まず相続財産を法人としたうえで相続財産管理人にその管理・精算を委ねます。その後相続人捜索人の広告をしたうえで相続人の不存在を確定します。その上で、被相続人の特別縁故者(内縁の妻など被相続人と生計を一にしていた者や療養看護に努めた者等)の請求があった場合に、裁判所がこれらの者に一部又は全部を分与し、残ったものが国のものになります。
今回は以上、民法の相続人についてお話させていただきました。
次回は、今回の続きで『養子』と『相続分』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
①相続とは、被相続人(死者)が生前に持っていた財産上の権利義務を、他の者が包括的に承継することとされています。相続が発生すると、相続人は被相続人の財産に属していた一切の権利義務(一身に専属していたものを除く。)を、包括的に承継します。その期間、遺産は、法定相続分の割合で共同相続人間で共有します。その後、通常は遺産分割によりこれを各相続人に具体的に分割することになります。遺産分割を行うと、分割した遺産は相続開始の時にさかのぼって、各相続人の単独所有に移ります。
②相続人:民法は、相続人を配偶者と血族相続人と定めています。血族とは、血の続いた親族をいいますが、養子は血族としての地位を保ち、実子と同様に取り扱われます。相続人となる血族は、直系卑属(子、孫、ひ孫等)、直系尊属(親、祖父母、曽曽父母等)、並びに兄弟姉妹の3種類からなり、この血族相続人には次の相続順位があります。
まず第1順位が子(代襲者を含みます。)です。第1順位が全くいない場合に第2順位の直系尊属(まず親、親がいないときは祖父母というように親等の近い順)が相続人となります。第1順位、第2順位とも誰もいないときに、第3順位の兄弟姉妹(代襲者を含みます。)が相続人となります。
被相続人の配偶者(婚姻届の出されている法律上の夫、または妻を言う。)は、各血族相続人と並んで、常に相続人となります。
但し、以上の法定相続人であっても、次の場合は相続人となることは、出来なくなります。
『相続欠格』・・故意に被相続人や先・同順位の相続人を殺害する等により処刑された者、詐欺・脅迫により遺言の偽造や隠匿をした者、これらの者は法律上当然に相続人の資格を失います。
『排除』・・推定相続人(被相続人が死亡した場合に相続人となりうる者)が、被相続人を虐待する等の著しい非行があった場合には、被相続人が推定相続人の排除を家庭裁判所に請求し、裁判所が排除を審判により決定すれば、その推定相続人は相続権を失います。
ところで、本来法定相続人であった子や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡していた場合には、これらの子が相続人となります。これを代襲相続人といいます(但し兄弟姉妹の代襲相続は子の一代限りとなります)。代襲相続は本来の相続人が亡くなっていた場合の他、上記の相続欠格や排除により相続権を失った場合にも成立しますが、相続放棄をした場合には該当しません。
なお、先の法定相続人が誰もいないときは、最終的には国庫に帰属することとなります。具体的には、まず相続財産を法人としたうえで相続財産管理人にその管理・精算を委ねます。その後相続人捜索人の広告をしたうえで相続人の不存在を確定します。その上で、被相続人の特別縁故者(内縁の妻など被相続人と生計を一にしていた者や療養看護に努めた者等)の請求があった場合に、裁判所がこれらの者に一部又は全部を分与し、残ったものが国のものになります。
今回は以上、民法の相続人についてお話させていただきました。
次回は、今回の続きで『養子』と『相続分』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月01日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『相続税』について
本日は、相続財産がいくらあると相続税がかかってきそうなのか、おおよそのお話をしたいと思います。
2000年から2007年の8年間で、毎年、お亡くなりになられた方の中で、相続税が発生しているケースは約4~5%程度です。
相続税には基礎控除がありまして5,000万円+1,000万円×法定相続人の数までは、非課税となります。
仮にお父様がなくなり、法定相続人がお母様と2人の子供の場合は、8,000万円までは相続税がかからないという事になります。
相続財産の中で不動産の評価は、土地に関しましては路線価の付されている地域の土地に関しましては路線価価格に土地の形状その他の要因による増減率(角地・不整形地・奥行長大地など)を乗じたうえで土地の面積を乗じて算出します。
又、路線価の付されていない地域は固定資産税の評価額に地域ごとに定めらています倍率を乗じて算出します。(路線価と倍率表は国税庁ホームページでご欄いただけます。)
一般的に、路線価は実勢相場より多少、低い価格となっておりますので不動産の相続税評価は売買金額のおおよそ7~8割程度(地域と時勢によってかなり異なりますが・・)となることも多いです。
つまり、法定相続人が2~4人程度の場合、全相続財産が1億円を超えるか否かが相続税がかかってくるかどうかのおおよその目安となります。
ただし、法定相続人の数にもよりますし、財産の種類によって評価方法が異なってまいりますので注意をする必要があります。
他、借入金等の債務があれば債務控除として差し引きますし、基礎控除以外にも土地に関しましては小規模宅地の特例(事業の用に供している土地で400㎡まで80%減、住居に供している土地で240㎡まで80%減、アパート等の用に供している土地で200㎡まで50%減、尚、小規模宅地等の特例の適用可否は詳細の要件の確認が必要となります。)がありますし、他にも配偶者税額軽減の特例などさまざまな特例がありますので、1億円を超えても相続税がかからない可能性もあります。
また、ご存知のように、相続税の基礎控除額が現状の60%、つまり、3000万円+600万円×法定相続人の数に減額する税制改正が話題になっています。
それにあわせて、死亡保険金の非課税枠の対象者が、単に相続人であれば適用された者が同居親族であるとか障害者や未成年者に限定されるという改正案も出ています。
このような相続増税時代にむけて、将来の相続税のご負担については、かなり、気になられる事と思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2000年から2007年の8年間で、毎年、お亡くなりになられた方の中で、相続税が発生しているケースは約4~5%程度です。
相続税には基礎控除がありまして5,000万円+1,000万円×法定相続人の数までは、非課税となります。
仮にお父様がなくなり、法定相続人がお母様と2人の子供の場合は、8,000万円までは相続税がかからないという事になります。
相続財産の中で不動産の評価は、土地に関しましては路線価の付されている地域の土地に関しましては路線価価格に土地の形状その他の要因による増減率(角地・不整形地・奥行長大地など)を乗じたうえで土地の面積を乗じて算出します。
又、路線価の付されていない地域は固定資産税の評価額に地域ごとに定めらています倍率を乗じて算出します。(路線価と倍率表は国税庁ホームページでご欄いただけます。)
一般的に、路線価は実勢相場より多少、低い価格となっておりますので不動産の相続税評価は売買金額のおおよそ7~8割程度(地域と時勢によってかなり異なりますが・・)となることも多いです。
つまり、法定相続人が2~4人程度の場合、全相続財産が1億円を超えるか否かが相続税がかかってくるかどうかのおおよその目安となります。
ただし、法定相続人の数にもよりますし、財産の種類によって評価方法が異なってまいりますので注意をする必要があります。
他、借入金等の債務があれば債務控除として差し引きますし、基礎控除以外にも土地に関しましては小規模宅地の特例(事業の用に供している土地で400㎡まで80%減、住居に供している土地で240㎡まで80%減、アパート等の用に供している土地で200㎡まで50%減、尚、小規模宅地等の特例の適用可否は詳細の要件の確認が必要となります。)がありますし、他にも配偶者税額軽減の特例などさまざまな特例がありますので、1億円を超えても相続税がかからない可能性もあります。
また、ご存知のように、相続税の基礎控除額が現状の60%、つまり、3000万円+600万円×法定相続人の数に減額する税制改正が話題になっています。
それにあわせて、死亡保険金の非課税枠の対象者が、単に相続人であれば適用された者が同居親族であるとか障害者や未成年者に限定されるという改正案も出ています。
このような相続増税時代にむけて、将来の相続税のご負担については、かなり、気になられる事と思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年11月30日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『預貯金の相続手続き』について
相続が発生しますと各種手続きが必要となります。
死亡届の提出、電気、ガス、水道の名義変更、準確定申告の手続き等その他もろもろです。
今回は相続が発生した時の預貯金の手続きにつきまして概略のお話をさせていただきます。
預貯金の相続手続きにつきましては、金融機関により多少、異なりますが必要な書類としましては、預金通帳、依頼書(金融機関指定の書式があります)、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本等(被相続人)、印鑑証明書(相続人)等の書類の他に、遺言書があれば遺言書若しくは遺言書が無ければ遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書などとなります。
依頼書は相続人全員の意思を示すものとなり依頼書に相続人全員の実印を押印し相続人全員の戸籍謄本(現戸籍のみで構いません)と遺産分割協議書をそろえてその証明となります。ただし、遺言書がある場合は相続人全員の実印などは不要となります。
書類の中で注意が必要なのが被相続人の除籍謄本等の取り寄せが大変な場合がある事です。
【除籍とは戸籍に記載された人が婚姻や死亡で全員、いなくなったり、他の市町村に転籍した場合の戸籍をいいます。相続手続き上は、被相続人の死亡直後の戸籍だけではなく、出生から死亡までの全戸籍が必要となります(結婚や離婚を繰り返している場合などは、過去の全戸籍がないと、法定相続人の子供全員の確認が出来ないからです)ので全戸籍の取得にかなり手間がかかる場合があります。】
被相続人の取引されていた金融機関ごとに必要な書類が微妙に異なったり、提出した書類を返却してくれる金融期間、返却してくれない金融機関とか、対応はまちまちとなりますので書類取り寄せの前に各金融機関に事前に電話などで、必要な書類や手続きの流れを確認される事をお奨めいたします。
相続手続きは、本当に手間がかかり相続人の方の負担が多いものと思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
死亡届の提出、電気、ガス、水道の名義変更、準確定申告の手続き等その他もろもろです。
今回は相続が発生した時の預貯金の手続きにつきまして概略のお話をさせていただきます。
預貯金の相続手続きにつきましては、金融機関により多少、異なりますが必要な書類としましては、預金通帳、依頼書(金融機関指定の書式があります)、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本等(被相続人)、印鑑証明書(相続人)等の書類の他に、遺言書があれば遺言書若しくは遺言書が無ければ遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書などとなります。
依頼書は相続人全員の意思を示すものとなり依頼書に相続人全員の実印を押印し相続人全員の戸籍謄本(現戸籍のみで構いません)と遺産分割協議書をそろえてその証明となります。ただし、遺言書がある場合は相続人全員の実印などは不要となります。
書類の中で注意が必要なのが被相続人の除籍謄本等の取り寄せが大変な場合がある事です。
【除籍とは戸籍に記載された人が婚姻や死亡で全員、いなくなったり、他の市町村に転籍した場合の戸籍をいいます。相続手続き上は、被相続人の死亡直後の戸籍だけではなく、出生から死亡までの全戸籍が必要となります(結婚や離婚を繰り返している場合などは、過去の全戸籍がないと、法定相続人の子供全員の確認が出来ないからです)ので全戸籍の取得にかなり手間がかかる場合があります。】
被相続人の取引されていた金融機関ごとに必要な書類が微妙に異なったり、提出した書類を返却してくれる金融期間、返却してくれない金融機関とか、対応はまちまちとなりますので書類取り寄せの前に各金融機関に事前に電話などで、必要な書類や手続きの流れを確認される事をお奨めいたします。
相続手続きは、本当に手間がかかり相続人の方の負担が多いものと思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年11月22日
明日、国際会議場で住宅取得に役立つライフプランセミナーを行います・・是非、ご参加ください。
明日23日(土)につくば国際会議場で午後2時50分から住宅取得のためのライフプランのセミナーを行います。
内容は、概ね、次の通りです。
是非、ご来場ください・・・
1.住宅取得のためのライフプランと消費増税のお話
ダイヤモンド社に掲載されていた記事に消費税があがってもマンションは絶対値上がりしません。そのわけは・・・というくだりの記事がありました。
某大手デベロッパーの社員の方が書かれた記事です。
内容は、まず一点目として『分譲マンションはあらかじめ消費税を決めるのが難しい商品』とあります。
この理由は、マンションの価格とは税込に価格を決めてから、消費税を算出するからだそうです。
マンションの価格は土地価格+建物価格+建物にかかる消費税の3つで構成されています。
土地の価格には消費税がかかりません。
消費税のかかる商品でその一部には消費税がかかって、その他の部分には消費税がかからない、このような商品は分譲マンションか分譲戸建住宅ぐらいのものではないでしょうか・・・
このように分譲マンションや分譲戸建住宅は価格の内訳が面倒であり、1戸1戸価格も違うのであらかじめ土地と建物と諸費税を分けることが難しいこととなります。
そしてケースによってはモデルルームのオープンの時点ではあくまで予定価格としておき、決定した価格は後日発表するという場合があります。
これは、モデルルームオープン時はあくまでも、税込の総額でいくらまでついてこれるかを見極めるためで、予定価格を提示する理由は少しでも高く売りたいからです。
そしてこの予定価格を参考にして売れる価格をきめて税込み価格を決定します。
この税込み価格が決定したら、土地と建物の価格に分けるのですがデベッロパーは、国に納付する消費税を抑えるためになるべく高く土地の価格を設定します。
そして残ったのが税込みの建物価格です。
その建物価格を消費税率で割戻す(現状であれば÷1.05)と建物本体価格となります。その残りが消費税額となるわけです。
このように、消費税が何%であろうと税込の総額は変わらないケースが多いようです。
要は、消費税が上がった分はデベロッパーが負担することとなります。
消費税の駆け込み需要は、分譲マンションの土地+建物の価格が決定した後に消費税がかかるので、消費税増額分が高くなりますよとのデベロッパーの営業マンやマスコミの煽りにもよるものでしょう。
そして、消費増税後の駆け込み需要の後には、消費増税前と比べ買いたい人が減ってくるでしょう。
マンションの価格を決めるのは受給バランスとなりますので、買いたい人が減れば価格は下がることとなります。
巷で言われる消費増税後の景気の落ち込みとつながってきます。
政府は、この反動を恐れて、消費増税後は住宅ローン減額の拡充やすまい給付金などの策を講じて消費増税後の反動の影響を、抑えようとしています。
このように考えますと、消費増税前に自分の希望を完全に満たしていない物件は、無理して購入することはなさそうです。
消費増税に振り回されずに、じっくり、選んで物件購入を決めた方が得策のようです。
気にすべきは、住宅ローンの金利の上昇でしょう。
低金利のうちに購入できるか否かによって大きく住宅ローンの返済額は変わってきます。
住宅ローンの金利情勢は、要チエックです。
消費増税に話を戻しますと、住宅購入にとって大事なのは、物件購入時に払う消費税の増額云々よりも、むしろ、消費増税後の消費増税が与える家計への影響でしょう。
大手の経済研究所の試算では、消費税が5%から10%になった時に与える家計の影響度として、年収500万円、家族4人、専業主婦家庭で、年間おおよそ17万円が家計に影響を与えそうとしています。
つまり、現状と同じ生活を維持するためには、年間17万円のコストが余計にかかることとなります。
これが、住宅ローンの返済期間を30年とすると、その30年間で実に、おおよそ510万円もの負担増となってきます。
土地の値上がりも期待できない、消費税の負担も増えていく、・・・このような現状を考えると、これから、住宅の購入を考えている人は、一度、ライフプランのキャッシュフロー表を作成して、老後の生活の準備資金や子どもにかけられる教育資金、さらには必要な生活資金とじっくり向き合ったうえで、住宅にかけられる資金を考えてほしいなと思います。
住宅を購入したものの、老後の生活に窮するようでは本末転倒です。
一般の給与所得者で老後のために準備しておきたい金額は、おおよそ2000万円から3000万円といわれています。
老後に使う生活費やレジャー費等の合計額から老後にもらえる公的年金を差し引いた分がその準備資金となってきます。
老後の準備資金、子どもの教育費、日々の生活費、を計算して、その残りを住宅購入可能金額と考えることが無難でしょう。
そして、最も大事なのは、健康です・・・
体を壊してしまっては元も子もありません・・・
保険金もでない・・・だけど、就業不能・・・そうなってくると医療保険の給付金等ではお話にはなりません・・・
生命保険金には給付される条件があります、死亡や高度障害等々・・・
給付される条件に適合しない・・・だけど就業不能状態になってしまった・・・
住宅ローンの団信の生命保険も同様で、給付されない・・・
健康リスクは、確率は非常に低いでしょうが、一番大きなリスクかもしれません・・・
煙草は止める・・・塩分は控える・・・熱いものは取り過ぎない・・・等々、先ずは生活習慣病を回避するための生活改善が重要かも知れません。
ライフプランを考える・・・健康に気をつける・・・これが、住宅取得に備えて欲しいことと思います。
この内容のセミナーを11月23日(土)につくば国際会議場で開催される『FPの日フォーラム』のミニセミナーでお話させていただきます。
これから、住宅の購入を考えている人は、是非、ご来場ください。
他にメインセミナーとして、伊藤元重東京大学教授のセミナーもあります。
詳しくは、日本FP協会茨城支部のHP(http://www.jafp.or.jp/shibu/ibaraki/) をご覧ください。
2.住宅取得のためのライフプランと相続税改正のお話
今年の税制改正で相続税の基礎控除額が現状の60%に減額されることとなりました・・
実施されるのは再来年の平成27年からです・・・
再来年といっても今年も残りわずか・・・実質、あと一年と迫ってきました・・・
基礎控除額が60%になるというのは・・・どういうことか・・・と申しますと・・・
一次相続で相続人が母と子ども2人の合計3人の場合、現状の相続税法の基礎控除額は、5000万円+1000万円×3人=8000万円となりますが、改正後の基礎控除額は、3000万円+600万円×3人=4800万円となり、実に、その差額は3200万円となります。
つまり、再来年からは、相続人が3人の場合、相続財産の課税価格が4800万円を超えてくると、相続税がかかってくることになってきます。
相続税の課税価額とは、被相続人が相続開始の時に所有していた財産を、相続税法の財産評価基本通達に基づく計算方法で評価した金額の合計額から、債務(住宅ローンや事業用のローン、敷金や預り金の将来返済義務のあるもの等)や葬式費用を控除した残額となります。
相続税がかかってきそうな場合は、相続税対策として相続税の課税価格を下げていく手段を講じていくわけです・・・
が・・・大事なことは相続人間の遺産分割と納税対策となってきますので、相続税の課税価格を下げることばかりに気を取られ相続財産のほとんどを、相続税の課税価格を下げやすい不動産に集中させてしまうと本末転倒の結果となりかねません。
遺産分割で思うように分けられない・・・いざ、納税という時に、結果、不動産を売却しなければならなったが思うように売れない・・・等々・・・
特に、平生18年から物納要件が厳しくなったことにより、延納によっても金銭で納付することが困難でなければ物納は認められなくなりましたし、他には隣地や道路との境界が確定していること、土壌汚染がされていないことなどの条件も厳格に求められています。
これは、平成18年にファンドに対する不動産融資が厳格に規制(信託受益権化する不動産の融資については法令順守や土壌汚染リスクの対策などをきちんと抑えておくことが義務付けられた)されてきたときと同時に決めらたものです。
高額な不動産の取引が厳格化されたことに伴っての処置であったようです。
このように、相続対策は相続人での分割方法を考えて、納税の方法を考えて、そして節税できる方法を考えていくこととなります。
優先順位が相続税の節税でも構わないとは思いますが、あくまでも分割のしやすさと意識して納税のしやすさを考えていきながら進めていくべきでしょう。
現預金や多くの金融資産は相続開始時の額面が相続税評価額となりますが、土地の場合は路線価という国が算定した相続税の財産評価の基準となる数値をつかって求めます。(市街化調整区域内の多くは路線価が付されていませんので固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します)
この路線価は、公示価格か基準地価格(いわゆる時価・・に近い金額)の8割程度で設定されますので、例えば現金5000万円で土地を購入すれば相続税評価額は何をせずとも4000万円近い評価額となってきます。
さらに、この土地に現金で5000万円のアパートを建てた場合(この土地の借地権が60%、借家権が30%として)4000万円×(1-借地権70%×借家権30%)=3160万円の評価額となります。
さらに、さらに、建物の相続税の評価額については固定資産税評価額となりますので時価のおおよそ60%程度が目安となってきます。
つまり、何をしなくても5000万円×60%=3000万円となり、アパートのような貸家の場合は借家権相当分が控除されますので、3000万円×(1-30%)=2100万円となってきます。
これを土地と建物で考えた場合、5000万円+5000万円=10000万円が3160万円+2100万円=5260万円となりその差額4740万円相当の相続税評価額の減額効果が得られることとなります。
この場合に、現金が準備できなければ銀行から借り入れしてその対価にあてることとなります。
その借入金が債務として相続税の評価額を下げる役割を担うこととなります。
この対策から得た相続税の評価額の減額分4740万円は相続人が3人の場合の基礎控除額の減額分3200万円を上回ってきます。
一見、よさげに見えますが、注意をしなければいけないのは、そのアパートの計画がシビアな事業計画書によって検討されたものかでしょう。
アパート等の建築業者は、まず、契約ありきとなりますので事業リスクにはあまり触れない事業計画書を提出してくる場合があります・・・
金利の変動を何も考えていない計画、あろうことかそれを指摘すれば銀行がお金を貸してくれるということは金利上昇によるリスクはない・・・だって、銀行が貸すのだからと言い切ったアパート建築の営業のかたもいたくらいです。
また銀行も、アパートの事業収支も・・もちろん重要な判断基準となりますが、担保がしっかりしている場合や、その他の不動産に根抵当権がつけられるなど、いざというときの回収に不備を残さないような案件であればその融資は通るでしょう。
要は、銀行の判断そのもは、100%の信頼は置かない方がよろしいでしょう・・・最後に何かしらの方法で回収出来ればよいわけです。
相続税の減額を狙っての土地活用であっても、事業としてきちんと成り立つものを行うべきでしょう・・・
そして、その事業収入のストックで納税資金を貯めていく方法もあります。
もっとも、多くの不動産を所有しているかたの場合は、単独の土地活用の検討よりも優先して大事なことは不動産の現状分析を行って、残すものと、活用するものと、納税用にするものと、処分する土地、等に分類することでしょう。その分類をしてからでないと、遺産分割や納税対策、さらには節税対策の検討には着手できませんので、まずは・・・相続に詳しい不動産コンサルタント等に相談してみるべきでしょう。
そして、自分の希望通りの分割を考えてみる、希望通りの土地活用を考えてみる、納税の方法を考えてみる・・・そして出来得る限りの節税を考えていく・・・生前贈与なども効果的です・・・
また、不動産は自宅しかないというかたも安心ではありません・・・
再来年の相続税の基礎控除額の減額により都市部や都市近郊の路線価の高い地域に住宅を所有しているかたは相続税の納税の対象となる可能性が高まってきます・・・
一次相続は配偶者の優遇措置(配偶者の税額軽減)がありますので相続税のかかるケースは少なくなりますが、問題は2次相続でしょう・・・
2次相続でのポイントは『小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の適用の適用』が受けられるか否かとなるでしょう。
基本的には親との同居が前提です・・若しくは相続開始前3年以内は持ち家を持たなくするとか・・・
この要件をきちんと確認して、今後のライフイベントを考えていくという方法もあります。
将来、実家に住むのであれば、今の住居は賃貸でいいのか・・・賃料を払い続けて大家さんだけが儲かるのに抵抗があれば持ち家とするか・・・どっちの選択がいいのかということになってきます。
このような後半部分の・・・不動産は自宅しかないような場合の住宅取得をどう考えるのか・・・
この内容のセミナーを11月23日(土)につくば国際会議場で開催される『FPの日フォーラム』のミニセミナーでお話させていただきます。
これから、住宅の購入を考えている人は、是非、ご来場ください。
他にメインセミナーとして、伊藤元重東京大学教授のセミナーもあります。
詳しくは、日本FP協会茨城支部のHP(http://www.jafp.or.jp/shibu/ibaraki/) をご覧ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
内容は、概ね、次の通りです。
是非、ご来場ください・・・
1.住宅取得のためのライフプランと消費増税のお話
ダイヤモンド社に掲載されていた記事に消費税があがってもマンションは絶対値上がりしません。そのわけは・・・というくだりの記事がありました。
某大手デベロッパーの社員の方が書かれた記事です。
内容は、まず一点目として『分譲マンションはあらかじめ消費税を決めるのが難しい商品』とあります。
この理由は、マンションの価格とは税込に価格を決めてから、消費税を算出するからだそうです。
マンションの価格は土地価格+建物価格+建物にかかる消費税の3つで構成されています。
土地の価格には消費税がかかりません。
消費税のかかる商品でその一部には消費税がかかって、その他の部分には消費税がかからない、このような商品は分譲マンションか分譲戸建住宅ぐらいのものではないでしょうか・・・
このように分譲マンションや分譲戸建住宅は価格の内訳が面倒であり、1戸1戸価格も違うのであらかじめ土地と建物と諸費税を分けることが難しいこととなります。
そしてケースによってはモデルルームのオープンの時点ではあくまで予定価格としておき、決定した価格は後日発表するという場合があります。
これは、モデルルームオープン時はあくまでも、税込の総額でいくらまでついてこれるかを見極めるためで、予定価格を提示する理由は少しでも高く売りたいからです。
そしてこの予定価格を参考にして売れる価格をきめて税込み価格を決定します。
この税込み価格が決定したら、土地と建物の価格に分けるのですがデベッロパーは、国に納付する消費税を抑えるためになるべく高く土地の価格を設定します。
そして残ったのが税込みの建物価格です。
その建物価格を消費税率で割戻す(現状であれば÷1.05)と建物本体価格となります。その残りが消費税額となるわけです。
このように、消費税が何%であろうと税込の総額は変わらないケースが多いようです。
要は、消費税が上がった分はデベロッパーが負担することとなります。
消費税の駆け込み需要は、分譲マンションの土地+建物の価格が決定した後に消費税がかかるので、消費税増額分が高くなりますよとのデベロッパーの営業マンやマスコミの煽りにもよるものでしょう。
そして、消費増税後の駆け込み需要の後には、消費増税前と比べ買いたい人が減ってくるでしょう。
マンションの価格を決めるのは受給バランスとなりますので、買いたい人が減れば価格は下がることとなります。
巷で言われる消費増税後の景気の落ち込みとつながってきます。
政府は、この反動を恐れて、消費増税後は住宅ローン減額の拡充やすまい給付金などの策を講じて消費増税後の反動の影響を、抑えようとしています。
このように考えますと、消費増税前に自分の希望を完全に満たしていない物件は、無理して購入することはなさそうです。
消費増税に振り回されずに、じっくり、選んで物件購入を決めた方が得策のようです。
気にすべきは、住宅ローンの金利の上昇でしょう。
低金利のうちに購入できるか否かによって大きく住宅ローンの返済額は変わってきます。
住宅ローンの金利情勢は、要チエックです。
消費増税に話を戻しますと、住宅購入にとって大事なのは、物件購入時に払う消費税の増額云々よりも、むしろ、消費増税後の消費増税が与える家計への影響でしょう。
大手の経済研究所の試算では、消費税が5%から10%になった時に与える家計の影響度として、年収500万円、家族4人、専業主婦家庭で、年間おおよそ17万円が家計に影響を与えそうとしています。
つまり、現状と同じ生活を維持するためには、年間17万円のコストが余計にかかることとなります。
これが、住宅ローンの返済期間を30年とすると、その30年間で実に、おおよそ510万円もの負担増となってきます。
土地の値上がりも期待できない、消費税の負担も増えていく、・・・このような現状を考えると、これから、住宅の購入を考えている人は、一度、ライフプランのキャッシュフロー表を作成して、老後の生活の準備資金や子どもにかけられる教育資金、さらには必要な生活資金とじっくり向き合ったうえで、住宅にかけられる資金を考えてほしいなと思います。
住宅を購入したものの、老後の生活に窮するようでは本末転倒です。
一般の給与所得者で老後のために準備しておきたい金額は、おおよそ2000万円から3000万円といわれています。
老後に使う生活費やレジャー費等の合計額から老後にもらえる公的年金を差し引いた分がその準備資金となってきます。
老後の準備資金、子どもの教育費、日々の生活費、を計算して、その残りを住宅購入可能金額と考えることが無難でしょう。
そして、最も大事なのは、健康です・・・
体を壊してしまっては元も子もありません・・・
保険金もでない・・・だけど、就業不能・・・そうなってくると医療保険の給付金等ではお話にはなりません・・・
生命保険金には給付される条件があります、死亡や高度障害等々・・・
給付される条件に適合しない・・・だけど就業不能状態になってしまった・・・
住宅ローンの団信の生命保険も同様で、給付されない・・・
健康リスクは、確率は非常に低いでしょうが、一番大きなリスクかもしれません・・・
煙草は止める・・・塩分は控える・・・熱いものは取り過ぎない・・・等々、先ずは生活習慣病を回避するための生活改善が重要かも知れません。
ライフプランを考える・・・健康に気をつける・・・これが、住宅取得に備えて欲しいことと思います。
この内容のセミナーを11月23日(土)につくば国際会議場で開催される『FPの日フォーラム』のミニセミナーでお話させていただきます。
これから、住宅の購入を考えている人は、是非、ご来場ください。
他にメインセミナーとして、伊藤元重東京大学教授のセミナーもあります。
詳しくは、日本FP協会茨城支部のHP(http://www.jafp.or.jp/shibu/ibaraki/) をご覧ください。
2.住宅取得のためのライフプランと相続税改正のお話
今年の税制改正で相続税の基礎控除額が現状の60%に減額されることとなりました・・
実施されるのは再来年の平成27年からです・・・
再来年といっても今年も残りわずか・・・実質、あと一年と迫ってきました・・・
基礎控除額が60%になるというのは・・・どういうことか・・・と申しますと・・・
一次相続で相続人が母と子ども2人の合計3人の場合、現状の相続税法の基礎控除額は、5000万円+1000万円×3人=8000万円となりますが、改正後の基礎控除額は、3000万円+600万円×3人=4800万円となり、実に、その差額は3200万円となります。
つまり、再来年からは、相続人が3人の場合、相続財産の課税価格が4800万円を超えてくると、相続税がかかってくることになってきます。
相続税の課税価額とは、被相続人が相続開始の時に所有していた財産を、相続税法の財産評価基本通達に基づく計算方法で評価した金額の合計額から、債務(住宅ローンや事業用のローン、敷金や預り金の将来返済義務のあるもの等)や葬式費用を控除した残額となります。
相続税がかかってきそうな場合は、相続税対策として相続税の課税価格を下げていく手段を講じていくわけです・・・
が・・・大事なことは相続人間の遺産分割と納税対策となってきますので、相続税の課税価格を下げることばかりに気を取られ相続財産のほとんどを、相続税の課税価格を下げやすい不動産に集中させてしまうと本末転倒の結果となりかねません。
遺産分割で思うように分けられない・・・いざ、納税という時に、結果、不動産を売却しなければならなったが思うように売れない・・・等々・・・
特に、平生18年から物納要件が厳しくなったことにより、延納によっても金銭で納付することが困難でなければ物納は認められなくなりましたし、他には隣地や道路との境界が確定していること、土壌汚染がされていないことなどの条件も厳格に求められています。
これは、平成18年にファンドに対する不動産融資が厳格に規制(信託受益権化する不動産の融資については法令順守や土壌汚染リスクの対策などをきちんと抑えておくことが義務付けられた)されてきたときと同時に決めらたものです。
高額な不動産の取引が厳格化されたことに伴っての処置であったようです。
このように、相続対策は相続人での分割方法を考えて、納税の方法を考えて、そして節税できる方法を考えていくこととなります。
優先順位が相続税の節税でも構わないとは思いますが、あくまでも分割のしやすさと意識して納税のしやすさを考えていきながら進めていくべきでしょう。
現預金や多くの金融資産は相続開始時の額面が相続税評価額となりますが、土地の場合は路線価という国が算定した相続税の財産評価の基準となる数値をつかって求めます。(市街化調整区域内の多くは路線価が付されていませんので固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します)
この路線価は、公示価格か基準地価格(いわゆる時価・・に近い金額)の8割程度で設定されますので、例えば現金5000万円で土地を購入すれば相続税評価額は何をせずとも4000万円近い評価額となってきます。
さらに、この土地に現金で5000万円のアパートを建てた場合(この土地の借地権が60%、借家権が30%として)4000万円×(1-借地権70%×借家権30%)=3160万円の評価額となります。
さらに、さらに、建物の相続税の評価額については固定資産税評価額となりますので時価のおおよそ60%程度が目安となってきます。
つまり、何をしなくても5000万円×60%=3000万円となり、アパートのような貸家の場合は借家権相当分が控除されますので、3000万円×(1-30%)=2100万円となってきます。
これを土地と建物で考えた場合、5000万円+5000万円=10000万円が3160万円+2100万円=5260万円となりその差額4740万円相当の相続税評価額の減額効果が得られることとなります。
この場合に、現金が準備できなければ銀行から借り入れしてその対価にあてることとなります。
その借入金が債務として相続税の評価額を下げる役割を担うこととなります。
この対策から得た相続税の評価額の減額分4740万円は相続人が3人の場合の基礎控除額の減額分3200万円を上回ってきます。
一見、よさげに見えますが、注意をしなければいけないのは、そのアパートの計画がシビアな事業計画書によって検討されたものかでしょう。
アパート等の建築業者は、まず、契約ありきとなりますので事業リスクにはあまり触れない事業計画書を提出してくる場合があります・・・
金利の変動を何も考えていない計画、あろうことかそれを指摘すれば銀行がお金を貸してくれるということは金利上昇によるリスクはない・・・だって、銀行が貸すのだからと言い切ったアパート建築の営業のかたもいたくらいです。
また銀行も、アパートの事業収支も・・もちろん重要な判断基準となりますが、担保がしっかりしている場合や、その他の不動産に根抵当権がつけられるなど、いざというときの回収に不備を残さないような案件であればその融資は通るでしょう。
要は、銀行の判断そのもは、100%の信頼は置かない方がよろしいでしょう・・・最後に何かしらの方法で回収出来ればよいわけです。
相続税の減額を狙っての土地活用であっても、事業としてきちんと成り立つものを行うべきでしょう・・・
そして、その事業収入のストックで納税資金を貯めていく方法もあります。
もっとも、多くの不動産を所有しているかたの場合は、単独の土地活用の検討よりも優先して大事なことは不動産の現状分析を行って、残すものと、活用するものと、納税用にするものと、処分する土地、等に分類することでしょう。その分類をしてからでないと、遺産分割や納税対策、さらには節税対策の検討には着手できませんので、まずは・・・相続に詳しい不動産コンサルタント等に相談してみるべきでしょう。
そして、自分の希望通りの分割を考えてみる、希望通りの土地活用を考えてみる、納税の方法を考えてみる・・・そして出来得る限りの節税を考えていく・・・生前贈与なども効果的です・・・
また、不動産は自宅しかないというかたも安心ではありません・・・
再来年の相続税の基礎控除額の減額により都市部や都市近郊の路線価の高い地域に住宅を所有しているかたは相続税の納税の対象となる可能性が高まってきます・・・
一次相続は配偶者の優遇措置(配偶者の税額軽減)がありますので相続税のかかるケースは少なくなりますが、問題は2次相続でしょう・・・
2次相続でのポイントは『小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の適用の適用』が受けられるか否かとなるでしょう。
基本的には親との同居が前提です・・若しくは相続開始前3年以内は持ち家を持たなくするとか・・・
この要件をきちんと確認して、今後のライフイベントを考えていくという方法もあります。
将来、実家に住むのであれば、今の住居は賃貸でいいのか・・・賃料を払い続けて大家さんだけが儲かるのに抵抗があれば持ち家とするか・・・どっちの選択がいいのかということになってきます。
このような後半部分の・・・不動産は自宅しかないような場合の住宅取得をどう考えるのか・・・
この内容のセミナーを11月23日(土)につくば国際会議場で開催される『FPの日フォーラム』のミニセミナーでお話させていただきます。
これから、住宅の購入を考えている人は、是非、ご来場ください。
他にメインセミナーとして、伊藤元重東京大学教授のセミナーもあります。
詳しくは、日本FP協会茨城支部のHP(http://www.jafp.or.jp/shibu/ibaraki/) をご覧ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年11月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話203 『(根)抵当権の承継の概要』
本日は、(根)抵当権の継承の概要について、ご紹介させていただきます。
【概要】
◇抵当権付不動産の相続登記
不動産の所有者が死亡した場合に、その不動産に債務の担保としての抵当権が担保されているときは、相続人はその抵当権が設定されている状態で相続による不動産の所有権を承継することになります。
このため、抵当権が設定されている場合には、相続人は、まず、抵当権の目的不動産について相続を原因とする所有権移転登記を行い、次に相続を原因とする抵当権債務者の変更登記を行わなければなりません。
◇根抵当権付不動産の相続登記
根抵当権付不動産を相続した場合には、抵当権付不動産の場合と同様に、まず、その不動産について相続を原因とする所有権移転登記を行い、次に相続を原因とする根抵当権債務者の変更登記を行います。
さらに、相続開始時点で根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当権を存続させる場合には、根抵当権者と根抵当権設定者(担保責任者)との間で相続人の内から指定債務者の合意をして、その合意を原因とする根抵当権変更登記を行う必要があります。
こうすることによって、被担保債権は相続後も確定せず、指定債務者が負担する債務も被担保債権に含まれることになります。
以上の登記は、(根)抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者として申請を行います。相続債務の承継・分割は、法律上当然に発生するものであり、債権者と債務者との間の契約などによるものではありません。
よってこの登記申請では、登記原因を承継する添付書面はありません。相続を証明する書類も不要です。
◇指定根抵当権の合意による変更登記をする場合の注意点
この指定根抵当権の合意による変更登記は相続開始後6ヵ月以内に、かつ、債務者の相続による変更登記をした後に登記をすることが必要です。この期間内に合意の登記がされると相続開始後の債務も担保されることになります。
この登記申請は根抵当権者を登記権利者、設定者を登記義務者として行います。登記上の利害関係人の同意は不要です。
しかし、合意の登記がされなかった場合、または、その合意はしたが相続開始後6ヵ月以内にその合意の登記をしなかった場合には、根抵当権の担保すべき元本は相続開始時に現存した債務で確定したものとみなされます。その結果、相続開始後に現に存する債務は引き続きその根抵当権者によって担保されますが、相続開始後に新たに債務者の相続人が負担する債務は担保されないこととなってしまいます。
このため、新たに資金が必要な場合は改めて根抵当権を設定しなければならないこととなりますので注意が必要となるでしょう。
以上、(根)抵当権の承継の概要について、ご紹介させていただきました。
次回は、電話加入権の名義変更について、ご紹介させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
【概要】
◇抵当権付不動産の相続登記
不動産の所有者が死亡した場合に、その不動産に債務の担保としての抵当権が担保されているときは、相続人はその抵当権が設定されている状態で相続による不動産の所有権を承継することになります。
このため、抵当権が設定されている場合には、相続人は、まず、抵当権の目的不動産について相続を原因とする所有権移転登記を行い、次に相続を原因とする抵当権債務者の変更登記を行わなければなりません。
◇根抵当権付不動産の相続登記
根抵当権付不動産を相続した場合には、抵当権付不動産の場合と同様に、まず、その不動産について相続を原因とする所有権移転登記を行い、次に相続を原因とする根抵当権債務者の変更登記を行います。
さらに、相続開始時点で根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当権を存続させる場合には、根抵当権者と根抵当権設定者(担保責任者)との間で相続人の内から指定債務者の合意をして、その合意を原因とする根抵当権変更登記を行う必要があります。
こうすることによって、被担保債権は相続後も確定せず、指定債務者が負担する債務も被担保債権に含まれることになります。
以上の登記は、(根)抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者として申請を行います。相続債務の承継・分割は、法律上当然に発生するものであり、債権者と債務者との間の契約などによるものではありません。
よってこの登記申請では、登記原因を承継する添付書面はありません。相続を証明する書類も不要です。
◇指定根抵当権の合意による変更登記をする場合の注意点
この指定根抵当権の合意による変更登記は相続開始後6ヵ月以内に、かつ、債務者の相続による変更登記をした後に登記をすることが必要です。この期間内に合意の登記がされると相続開始後の債務も担保されることになります。
この登記申請は根抵当権者を登記権利者、設定者を登記義務者として行います。登記上の利害関係人の同意は不要です。
しかし、合意の登記がされなかった場合、または、その合意はしたが相続開始後6ヵ月以内にその合意の登記をしなかった場合には、根抵当権の担保すべき元本は相続開始時に現存した債務で確定したものとみなされます。その結果、相続開始後に現に存する債務は引き続きその根抵当権者によって担保されますが、相続開始後に新たに債務者の相続人が負担する債務は担保されないこととなってしまいます。
このため、新たに資金が必要な場合は改めて根抵当権を設定しなければならないこととなりますので注意が必要となるでしょう。
以上、(根)抵当権の承継の概要について、ご紹介させていただきました。
次回は、電話加入権の名義変更について、ご紹介させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)