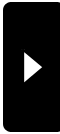PR
2014年10月03日
遺産分割と相続税の土地評価の違いに注意・・・
先月21日(日)に相続士のスキルアップ講座の講師をさせていただきました。
講座の内容は不動産の調査と評価についてでした。
来るべき相続に備えての不動産の調査のポイントや評価の方法や考え方についてお話させていただきました。
不動産の調査は現地や役所や法務局で行うべき調査の内容と方法をお話させていただいておりますが、単にテキストで説明しても実感が湧きにくいと思い某競売物件の鑑定評価書のコピーで物件概要の記載内容を説明しながらこんなレポートを書くための調査が必要ですとお話しました。
この方法は実感が湧きやすくイメージが捉えかったようです。
土地の評価も同様で、一物四課等の基本的なことをテキストで説明してから鑑定評価書で実際の評価の手順を説明することによって、よりよく評価の方法のイメージを捉えられて戴いたようでした。
そんななか、ある聴講生の方からの質問で、相続税対策で一生懸命、相続税の土地の財産評価を下げられる打ち合わせをしているのに、遺産分割の金額がこれと異なることがあるのは理解しにくいというお話がありました。
要は、広い土地を利用区分を分けることによって不整形地をいくつか作...り上げて評価を下げる場合や小規模宅地等の相続税の課税各計算の特例を使って評価を下げる場合など、一生懸命、評価をさげる打ち合わせをしているのに、それが遺産分割の金額と異なるというのは、クライアントとうまく話ができそうにないといったようなご指摘でした、
この質問に対しては、相続税の評価額は、あくまで税金を計算するためのものなので遺産分割とは別なものとして考えたほうがいいでしょうとお答えしました。
例えば、小規模宅地等の特例などは、税金を軽減してくれる特例ですから、これを遺産分割の評価とすると他の相続人はOKと言わないでしょうと一つの例で説明しました。
ただ、実際に他の相続人が何も知らないことをいいことに小規模宅地等の特例後の評価額を前提として法定相続分で遺産分割協議をまとめてしまった例もあります。
遺産分割の全ての手続きが終えたのちにそれにきづいた他の相続人が異議を唱えても後の祭りとなってしまった例です。
逆にいうとこんな事がないように、相続に関する土地評価を勉強しておくことは意義があることと思います。
相続増税を控えているいま、是非、留意してみてください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
講座の内容は不動産の調査と評価についてでした。
来るべき相続に備えての不動産の調査のポイントや評価の方法や考え方についてお話させていただきました。
不動産の調査は現地や役所や法務局で行うべき調査の内容と方法をお話させていただいておりますが、単にテキストで説明しても実感が湧きにくいと思い某競売物件の鑑定評価書のコピーで物件概要の記載内容を説明しながらこんなレポートを書くための調査が必要ですとお話しました。
この方法は実感が湧きやすくイメージが捉えかったようです。
土地の評価も同様で、一物四課等の基本的なことをテキストで説明してから鑑定評価書で実際の評価の手順を説明することによって、よりよく評価の方法のイメージを捉えられて戴いたようでした。
そんななか、ある聴講生の方からの質問で、相続税対策で一生懸命、相続税の土地の財産評価を下げられる打ち合わせをしているのに、遺産分割の金額がこれと異なることがあるのは理解しにくいというお話がありました。
要は、広い土地を利用区分を分けることによって不整形地をいくつか作...り上げて評価を下げる場合や小規模宅地等の相続税の課税各計算の特例を使って評価を下げる場合など、一生懸命、評価をさげる打ち合わせをしているのに、それが遺産分割の金額と異なるというのは、クライアントとうまく話ができそうにないといったようなご指摘でした、
この質問に対しては、相続税の評価額は、あくまで税金を計算するためのものなので遺産分割とは別なものとして考えたほうがいいでしょうとお答えしました。
例えば、小規模宅地等の特例などは、税金を軽減してくれる特例ですから、これを遺産分割の評価とすると他の相続人はOKと言わないでしょうと一つの例で説明しました。
ただ、実際に他の相続人が何も知らないことをいいことに小規模宅地等の特例後の評価額を前提として法定相続分で遺産分割協議をまとめてしまった例もあります。
遺産分割の全ての手続きが終えたのちにそれにきづいた他の相続人が異議を唱えても後の祭りとなってしまった例です。
逆にいうとこんな事がないように、相続に関する土地評価を勉強しておくことは意義があることと思います。
相続増税を控えているいま、是非、留意してみてください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年08月25日
相続対策…備えあれば憂いなし・・・当たり前のことを当たり前にしておきましょう・・・
相続対策・・・相続対策・・・と、世間ではまことしやかに騒がれています・・・
相続対策って・・・何でしょうか・・・
とても、とても、一言ではいい現れそうにありません・・・
相続といえば、まず、相続税という税金が思いつきます。
国が課税する一定の額を超える資産を所有している方がなくなると課税される税金です。
この税金が課される方は、非常に少なく、年間の相続件数のうち、おおよそ4~5%の方が対象となっています。
そして、来年1月1日から、相続税のかかってくる一定の額を超える額が改正されます。
その一定の額とは、相続税法上、基礎控除額と呼ばれているものです。
その基礎控除額は、今年までは、5000万円+1000万円☓法定相続人の数(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算され、例えば、配偶者である相続人が奥様と子供2人で合計3人の場合は8000万円が基礎子控除額となります。
その基礎控除額が、来年1月1日から、3000万円+600万円☓法定相続人の数に改正となります。すなわち、今までの60%までが控除されることとなるわけです・・・
この改正で従来の4~5%の課税対象者が、倍近くになるのではとも、予想されています。
これで、相続対策として相続税という税金を意識せざるを得ない対象者のかたは、相当数、増えてくるでしょう・・・
相続対策として、相続税を意識せざるを得ない対象となる方は、その対策はその人によって千差万別、この対策といった決まり切った対策はありません・・・
相続税の基礎控除額をどの程度、超えてくるのか・・・
先祖伝来、都市部やその都市近郊で、多くの土地を所有し、多くの土地活用をしている方の相続税の対策・・・
会社経営者のオーナーの方の相続税並びに事業承継の対策・・・
不動産は都心部に広めの戸建住宅のみ所有しているものの基礎控除額の減額により相続税が気になりだした方・・・
等々・・・
その資産の規模や内容によって、その対策は大きく方向性や具体的方策は異なってくることとなってきます・・・
この税金対策の前提ともなる共通する大事な相続対策はというと・・・
それは、やはり、遺産分割の準備です・・・
円満とは行かずとも、円滑な手続きが行えるような準備はしておきたいところです・・・
この相続税という税金対策の前提として、なぜ、遺産分割が重要かというと・・・
相続税額の計算上、相続税を減額できるいろいろな特例があります。
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例、配偶者の相続税額の軽減、農地や非上場株式の納税猶予、等々・・・
このような特例は申告期限までに相続人間で相続財産の分割手続きが完了している場合にその適用が受けられることとなります。
申告期限までに、遺産分割が完了していない場合は、分割の完了していない財産は、各共同相続人及び包括受遺者が民法(寄与分を除く)の規定による相続分または包括遺贈の割合に従って所得したものとして相続税の課税価格を計算するものとしています。
そして、相続税の特例の規定の適用は受けられないということになるわけです・・・
ただし、申告期限から3年以内に分割されれば、後追いで適用が受けられる特例のあります。
代表的なものは、配偶者の相続税額の軽減や小規模宅地等の相続税の課税価格計算に特例などです。
ちなみに、農地や非上場株式等の納税猶予は、申告期限までに分割が完了していなければ、その適用は受けることはできないこととなります。
このように、とにもかくにも、相続が発生したら・・・
円滑に遺産分割が行えるような準備を生前にしておきたいところです・・・
その準備に、効果的なものは・・・
やはり、遺言書を遺しておくことでしょう・・・
それも、安全を考えれば、公正証書遺言がいいかもしれません・・・
そして遺産分割を考える時には、相続税の納付の方法まで考えておきたいところです・・・
いくら、かかりそうなのか・・・
かかってきそうな相続税を金融資産で賄えるのか・・・
金融資産で足りない分は、どのようにして工面しようか・・・
土地の一部を売却するか・・・
どの土地を納税用の売却対象の土地としようか・・・
等々の大まかな算段は付けておいたほうがよろしいでしょう・・・
そして、税金の下げられる方法や少しでもお金の残せる土地活用や、遺産分割や納税、節税に使えそうな生命保険の活用等を考えていくこととなってきます・・・
このような相続対策は、まずは、何をしていくべきか・・・
当たり前のことを当たり前にしておくことだと思います。
まずは、自分の財産を改めて見直してみる・・・
何が、どの程度、あるのか・・・
全ての不動産を見てくる・・・
時価相場でいくらくらいになるのか・・・
相続税の評価額がいくらくらいになるのか・・・
そして、子供たちへの思いを整理してみる・・・
例えばエンディングノート等を作りながら、気持ちを整理してみる・・・
そして、誰に何を遺してあげるかを考えてみる・・・
事業をしている方は、その事業をどのように継承していくかも考えなければなりません・・・
自分自身のことを改めて見直してみる・・・
例えば、財産であれば、紙に書き出してみる・・・
等々、本来、当たり前のことを当たり前にしておくことが一番に重要なことかもしれません・・・
ただ、相続対策の場合は、民法や税法及び不動産の知識をフルに活用しますので、その当たり前のことを知ることは、以外に難しく、当たり前のことを当たり前におこなっておくことは、非常に大変です・・・
将来の相続に不安のある方は、早めに専門の方に相談することが賢明な相続対策となるでしょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
相続対策って・・・何でしょうか・・・
とても、とても、一言ではいい現れそうにありません・・・
相続といえば、まず、相続税という税金が思いつきます。
国が課税する一定の額を超える資産を所有している方がなくなると課税される税金です。
この税金が課される方は、非常に少なく、年間の相続件数のうち、おおよそ4~5%の方が対象となっています。
そして、来年1月1日から、相続税のかかってくる一定の額を超える額が改正されます。
その一定の額とは、相続税法上、基礎控除額と呼ばれているものです。
その基礎控除額は、今年までは、5000万円+1000万円☓法定相続人の数(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算され、例えば、配偶者である相続人が奥様と子供2人で合計3人の場合は8000万円が基礎子控除額となります。
その基礎控除額が、来年1月1日から、3000万円+600万円☓法定相続人の数に改正となります。すなわち、今までの60%までが控除されることとなるわけです・・・
この改正で従来の4~5%の課税対象者が、倍近くになるのではとも、予想されています。
これで、相続対策として相続税という税金を意識せざるを得ない対象者のかたは、相当数、増えてくるでしょう・・・
相続対策として、相続税を意識せざるを得ない対象となる方は、その対策はその人によって千差万別、この対策といった決まり切った対策はありません・・・
相続税の基礎控除額をどの程度、超えてくるのか・・・
先祖伝来、都市部やその都市近郊で、多くの土地を所有し、多くの土地活用をしている方の相続税の対策・・・
会社経営者のオーナーの方の相続税並びに事業承継の対策・・・
不動産は都心部に広めの戸建住宅のみ所有しているものの基礎控除額の減額により相続税が気になりだした方・・・
等々・・・
その資産の規模や内容によって、その対策は大きく方向性や具体的方策は異なってくることとなってきます・・・
この税金対策の前提ともなる共通する大事な相続対策はというと・・・
それは、やはり、遺産分割の準備です・・・
円満とは行かずとも、円滑な手続きが行えるような準備はしておきたいところです・・・
この相続税という税金対策の前提として、なぜ、遺産分割が重要かというと・・・
相続税額の計算上、相続税を減額できるいろいろな特例があります。
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例、配偶者の相続税額の軽減、農地や非上場株式の納税猶予、等々・・・
このような特例は申告期限までに相続人間で相続財産の分割手続きが完了している場合にその適用が受けられることとなります。
申告期限までに、遺産分割が完了していない場合は、分割の完了していない財産は、各共同相続人及び包括受遺者が民法(寄与分を除く)の規定による相続分または包括遺贈の割合に従って所得したものとして相続税の課税価格を計算するものとしています。
そして、相続税の特例の規定の適用は受けられないということになるわけです・・・
ただし、申告期限から3年以内に分割されれば、後追いで適用が受けられる特例のあります。
代表的なものは、配偶者の相続税額の軽減や小規模宅地等の相続税の課税価格計算に特例などです。
ちなみに、農地や非上場株式等の納税猶予は、申告期限までに分割が完了していなければ、その適用は受けることはできないこととなります。
このように、とにもかくにも、相続が発生したら・・・
円滑に遺産分割が行えるような準備を生前にしておきたいところです・・・
その準備に、効果的なものは・・・
やはり、遺言書を遺しておくことでしょう・・・
それも、安全を考えれば、公正証書遺言がいいかもしれません・・・
そして遺産分割を考える時には、相続税の納付の方法まで考えておきたいところです・・・
いくら、かかりそうなのか・・・
かかってきそうな相続税を金融資産で賄えるのか・・・
金融資産で足りない分は、どのようにして工面しようか・・・
土地の一部を売却するか・・・
どの土地を納税用の売却対象の土地としようか・・・
等々の大まかな算段は付けておいたほうがよろしいでしょう・・・
そして、税金の下げられる方法や少しでもお金の残せる土地活用や、遺産分割や納税、節税に使えそうな生命保険の活用等を考えていくこととなってきます・・・
このような相続対策は、まずは、何をしていくべきか・・・
当たり前のことを当たり前にしておくことだと思います。
まずは、自分の財産を改めて見直してみる・・・
何が、どの程度、あるのか・・・
全ての不動産を見てくる・・・
時価相場でいくらくらいになるのか・・・
相続税の評価額がいくらくらいになるのか・・・
そして、子供たちへの思いを整理してみる・・・
例えばエンディングノート等を作りながら、気持ちを整理してみる・・・
そして、誰に何を遺してあげるかを考えてみる・・・
事業をしている方は、その事業をどのように継承していくかも考えなければなりません・・・
自分自身のことを改めて見直してみる・・・
例えば、財産であれば、紙に書き出してみる・・・
等々、本来、当たり前のことを当たり前にしておくことが一番に重要なことかもしれません・・・
ただ、相続対策の場合は、民法や税法及び不動産の知識をフルに活用しますので、その当たり前のことを知ることは、以外に難しく、当たり前のことを当たり前におこなっておくことは、非常に大変です・・・
将来の相続に不安のある方は、早めに専門の方に相談することが賢明な相続対策となるでしょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年08月13日
相続増税まであと5カ月お盆で見直す相続対策
ここ数年、猛暑の夏が続いています。
気温35度超が当たり前という感覚になってきました。
今日からお盆です。
お盆といえば里帰り
昨日あたりから帰省ラッシュが始まった模様です・・・
里帰りといえば、都心方面から地方へというイメージが強いですが、地方から都心への里帰りも当然にあるわけです。
東京在住で東京の大学をでて東京の会社に入社して転勤で地方に在住等々・・・
いずれ、定年を迎える頃には東京に定住するといったパターンは多く見受けられます。
大手の会社に勤められると、まさにジプシーのごとく日本国中から世界を駆け巡っての生活を送ることとなってきます。
そのような方達で東京をはじめとした大都市圏に実家がある方は、来年からの相続増税には要注意です。
例えば何代も前から東京23区内に住み続けている一族のかたで、昭和の始めに分家に出たときに100坪の土地を分けてもらった。
バブルのかなり前に先代の相続を迎えたが、ほんの少しの相続税で免れてきた・・・
そして、いままさに80歳後半を過ぎた親の相続を意識するようになってきた・・・
などの条件に合致するような方は、大勢いらっしゃるかもしれません。
そのケースの場合、来年からの相続税改正による基礎控除額の減額にかなりの注意を要することとなってきます。
今年一杯の相続税の基礎控除額は、5000万円+1000万円☓法定相続人の数が基礎控除額となります。
例えば、相続人が奥様と子供2人の合計で3名の場合は、8000万円が基礎控除額となります。
この基礎控除額が来年からは、その60%である4800万円までに減額となります。
実に、40%の3200万円もの基礎控除額が減額することとなってきます。
たとえば、この基礎控除額の減額により相続税の超過累進税率が20%に該当することとなった場合、実に640万円の増税ということになってきます。
この増税に対する対策としては、第一には小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の適用が受けられるか否かです。
小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定は、相続の開始の直前において、被相続人または被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業(不動産貸し付けなどの準事業も含みます)の用または居住の用の供されてる一定の敷地で一定の建物または構築物の敷地の用に供されているもので一定のものに適用される特例です。
こまかい要件はおいといて、例えば親の居住の用に供していた居住用不動産を相続または遺贈で取得した子供は、その土地の相続税の課税価格の評価額のうち、実に80%が軽減されるというものです。
ただし、無尽蔵に軽減されるわけではなく、居住用であれば今年一杯は240㎡、来年以降は330㎡を限度にその軽減の適用が受けられることとなってきます。
ちなみに、事業用(不動産貸付業は除く)は、400㎡までは80%が減額されるkととなります。
アパートなどの不動産貸付業は、200㎡まで50%が減額されることととなってきます。
そして、居住用、事業用、貸付事業用、それぞれを目いっぱいその適用を受けることはできません。
基本的には、一番有利なもののうちから、合計400㎡(事業はその面積、居住用はその面積に5/3を乗じた面積、貸付事業用はその面積に2を乗じた面積お合計した面積)までが限度となります。
そして、来年からはこの面積要件が緩和されて事業用と居住用はそれぞれ目一杯その適用が受けられることとなってきます。
要は事業用の敷地400㎡と居住用330㎡の合計730㎡までが、その適用の対象となることができます。
仮に来年以降、東京23区内の時価相場坪250万円(相続税評価額坪200万円)の330㎡(約100坪)の居住用の敷地を相続で取得した場合、相続税評価額2億円に対し、この規定の特例の適用をうけると実に4千万円までその評価額は圧縮されることとなってきます。
実にその差額は1億6千万円です。
仮に、評価額2億円のままであると超過累進税率15%であったとすると、2400万円の相続税が軽減されることとなってきます。
そして、この小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用については、その対象となる土地を所得した人に対しての要件もあります。
居住用のものに限って言えば、配偶者が取得した場合は無条件でその適用は受けられることとなります。
配偶者以外の子供が取得した場合は、いろいろな適用要件が存在します。
その一つは同居親族であること・・・要は被相続人である親と同居していた場合に受けられる要件です。
そして、非同居であっても、この適用が受けられることもあります。その要件は、自分以外の相続人である親族が同居していなかったこと、と。その土地を取得した子供が、相続開始前3年以内にその子供の所有する家(その子供の配偶者の家を含みます)に居住していなかったことです。
税法の規定ですので、このような文章では誤解を生じることがありますので、税務署とうでご確認いただくか、詳細をお知りになりたい方は、ご遠慮なくご連絡をいただきたいと思います。
このように、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるか否かが相続対策では、とても大きなポイントを占めることとなってきます。
いま、会社の転勤等で親御さんと別居住のかたで、その実家が東京都内であるとか県庁所在地の市街地内とかいった場合は、とりあえずは、相続税の負担を確認されてみたらいかがと思います。
そのうえで、何もしないでいると多額の相続税がかかりそうといった場合は、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を検討してみてください。
とはいえ、この規定の適用を考える上では、その実家を誰に遺してあげたいかといった遺産分割を第一に考えなければなりません。
このお盆で、機会があれば、皆さんで相続税の負担があるのや否や確認していただき、小規模の特例等についても話し合えるのであれば話し合っておきたいところかと思います。
また、90歳まで無告知で加入できる生命保険の商品もありますので、生命保険金の非課税枠に余裕のある方は、非課税枠狙いで、そんな生命保険に加入しておくこともいろいろな面でメリットが生じるときもあります。
まずは、このお盆で、具体的な内容は別として、これからの方向性だけでも話し合えるとよろしいのかなと感じています。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
気温35度超が当たり前という感覚になってきました。
今日からお盆です。
お盆といえば里帰り
昨日あたりから帰省ラッシュが始まった模様です・・・
里帰りといえば、都心方面から地方へというイメージが強いですが、地方から都心への里帰りも当然にあるわけです。
東京在住で東京の大学をでて東京の会社に入社して転勤で地方に在住等々・・・
いずれ、定年を迎える頃には東京に定住するといったパターンは多く見受けられます。
大手の会社に勤められると、まさにジプシーのごとく日本国中から世界を駆け巡っての生活を送ることとなってきます。
そのような方達で東京をはじめとした大都市圏に実家がある方は、来年からの相続増税には要注意です。
例えば何代も前から東京23区内に住み続けている一族のかたで、昭和の始めに分家に出たときに100坪の土地を分けてもらった。
バブルのかなり前に先代の相続を迎えたが、ほんの少しの相続税で免れてきた・・・
そして、いままさに80歳後半を過ぎた親の相続を意識するようになってきた・・・
などの条件に合致するような方は、大勢いらっしゃるかもしれません。
そのケースの場合、来年からの相続税改正による基礎控除額の減額にかなりの注意を要することとなってきます。
今年一杯の相続税の基礎控除額は、5000万円+1000万円☓法定相続人の数が基礎控除額となります。
例えば、相続人が奥様と子供2人の合計で3名の場合は、8000万円が基礎控除額となります。
この基礎控除額が来年からは、その60%である4800万円までに減額となります。
実に、40%の3200万円もの基礎控除額が減額することとなってきます。
たとえば、この基礎控除額の減額により相続税の超過累進税率が20%に該当することとなった場合、実に640万円の増税ということになってきます。
この増税に対する対策としては、第一には小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の適用が受けられるか否かです。
小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定は、相続の開始の直前において、被相続人または被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業(不動産貸し付けなどの準事業も含みます)の用または居住の用の供されてる一定の敷地で一定の建物または構築物の敷地の用に供されているもので一定のものに適用される特例です。
こまかい要件はおいといて、例えば親の居住の用に供していた居住用不動産を相続または遺贈で取得した子供は、その土地の相続税の課税価格の評価額のうち、実に80%が軽減されるというものです。
ただし、無尽蔵に軽減されるわけではなく、居住用であれば今年一杯は240㎡、来年以降は330㎡を限度にその軽減の適用が受けられることとなってきます。
ちなみに、事業用(不動産貸付業は除く)は、400㎡までは80%が減額されるkととなります。
アパートなどの不動産貸付業は、200㎡まで50%が減額されることととなってきます。
そして、居住用、事業用、貸付事業用、それぞれを目いっぱいその適用を受けることはできません。
基本的には、一番有利なもののうちから、合計400㎡(事業はその面積、居住用はその面積に5/3を乗じた面積、貸付事業用はその面積に2を乗じた面積お合計した面積)までが限度となります。
そして、来年からはこの面積要件が緩和されて事業用と居住用はそれぞれ目一杯その適用が受けられることとなってきます。
要は事業用の敷地400㎡と居住用330㎡の合計730㎡までが、その適用の対象となることができます。
仮に来年以降、東京23区内の時価相場坪250万円(相続税評価額坪200万円)の330㎡(約100坪)の居住用の敷地を相続で取得した場合、相続税評価額2億円に対し、この規定の特例の適用をうけると実に4千万円までその評価額は圧縮されることとなってきます。
実にその差額は1億6千万円です。
仮に、評価額2億円のままであると超過累進税率15%であったとすると、2400万円の相続税が軽減されることとなってきます。
そして、この小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用については、その対象となる土地を所得した人に対しての要件もあります。
居住用のものに限って言えば、配偶者が取得した場合は無条件でその適用は受けられることとなります。
配偶者以外の子供が取得した場合は、いろいろな適用要件が存在します。
その一つは同居親族であること・・・要は被相続人である親と同居していた場合に受けられる要件です。
そして、非同居であっても、この適用が受けられることもあります。その要件は、自分以外の相続人である親族が同居していなかったこと、と。その土地を取得した子供が、相続開始前3年以内にその子供の所有する家(その子供の配偶者の家を含みます)に居住していなかったことです。
税法の規定ですので、このような文章では誤解を生じることがありますので、税務署とうでご確認いただくか、詳細をお知りになりたい方は、ご遠慮なくご連絡をいただきたいと思います。
このように、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるか否かが相続対策では、とても大きなポイントを占めることとなってきます。
いま、会社の転勤等で親御さんと別居住のかたで、その実家が東京都内であるとか県庁所在地の市街地内とかいった場合は、とりあえずは、相続税の負担を確認されてみたらいかがと思います。
そのうえで、何もしないでいると多額の相続税がかかりそうといった場合は、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を検討してみてください。
とはいえ、この規定の適用を考える上では、その実家を誰に遺してあげたいかといった遺産分割を第一に考えなければなりません。
このお盆で、機会があれば、皆さんで相続税の負担があるのや否や確認していただき、小規模の特例等についても話し合えるのであれば話し合っておきたいところかと思います。
また、90歳まで無告知で加入できる生命保険の商品もありますので、生命保険金の非課税枠に余裕のある方は、非課税枠狙いで、そんな生命保険に加入しておくこともいろいろな面でメリットが生じるときもあります。
まずは、このお盆で、具体的な内容は別として、これからの方向性だけでも話し合えるとよろしいのかなと感じています。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年07月01日
H26年路線価発表、来年からはいよいよ相続増税時代に・・・
平成26年路線価が発表されました・・・
全国平均は6年連続の下落となりましたが、三大都市圏では上昇に転じてきています。
2極化の傾向は、まだまだ、続きそうです。
東京は、東京五輪のインフラ整備の期待感から投資目的の不動産購入の人気が高まっているようです・・・
この大都市圏を中心とした不動産市況の回復がどの程度まで地方に広がりを見せていくのか・・・興味の湧くところではあります。
アベノミクスによる円安・株高効果と東京五輪の期待感も相まって・・・
この機会とばかりに不動産への投資熱が高まってきたようです。
この不動産市況を始めとした景気の盛り上がりは東京五輪の直前に一つのヤマを迎えるといった意見も耳にしますので、今後の動向は気になるところです・・・
さて、来年からは、相続税の基礎控除額の減額などの増税路線がスタートします。
個人的には、相続税という税金は、他の所得税や法人税などのように一定期間の営業活動のなかから得られた財産の増加(利益)に対して超過累進税率を乗じて課税されるものとは違って、相続がおきて親等の親族から無償で財産が承継され、財産が増加したことに対して税金が課されますので、その納税には多いに苦慮される場合があります。
その財産のなかには、換金できないもの・・・例えば住宅・・・住むために必要不可欠なものです。
この住宅も相続税の課税対象となることが納税資金の工面に苦慮する一つの要因となってきます。
財産は引き継いだものの、それは、単に住むためのもの・・・
昔から、代々、その家で住むための不動産であった・・・
この財産に税金が課されるとすると・・・
最悪、売却して換金するしか納税できる方法が見当たらないといった事態に陥りかねません・・・
税務当局は、こうした住宅については、さすがに相続税の対象からは外していこうといった特例を設けています。
さすがに、住んでいる家まで税金で没収するようなことまでは、考えていないようです。
それが、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特定の規定です。
被相続人や被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供していた住宅を、被相続人の配偶者や被相続人の親族(一定の要件を満たしていることが必要です)が、相続または遺贈で取得した場合に適用が受けられる規定です。
ちなみに、この特例の規定の適用がを受けられると・・・
来年からは住宅敷地の評価額のうち、330㎡(今年は240㎡)までの面積の部分は80%まで減額されることとなります。
都心部では、この特例の規定が使えるのか否かで、大きく、相続税額は変わってくることになります。
この適用は、配偶者が取得すれば細かい適用要件に関係なく適用が受けられます。
これは、配偶者としての税法上の特典でもあるわけです。
問題は、配偶者以外の親族が取得する場合です。
基本的には、相続開始の直前にその住宅に居住していること、かつ、相続開始の時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に住んでいること等他の一定の要件が必要です。
同居していない場合の要件としては、その親族が相続開始前3年以内に自分の持ち家もしくは自分の配偶者の持ち家に住んでいないこと、かつ、相続開始の時から申告期限まで引き続き所有していること等他の要件が必要です。(ちなみに、相続の開始の直前において、この住宅に被相続人の法定相続人に該当する他の親族が住んでいる場合は除かれます)
この小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるか否かが、来年からの相続増税時代に向けての大きなポイントなるべき項目です。
また、住むための住宅のほかにも相続人にとって必要不可欠な財産があります。
それは、被相続人の事業の用に供していた財産です。
被相続人の事業を親族が引き継ぐといった場合に、事業用の財産に相続税が課せられてしまっては、その事業承継にとって大きな障害となってきます。
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定には、事業用の宅地、アパート等の貸付用の宅地、同族会社の事業用の宅地等も対象となっています。
そのほかにも、農地や非上場株式、山林、医業経営者などの納税猶予の規定もあります。
このように、生活に必要なもの(事業承継も含めて)については、それなりに税法の特典ともいえる特例措置が設けられていますので、このような特例措置は、見落としがないように生前のうちに整理して確認しておくべきでしょう。
また、生活していくうえで、必要不可欠なもの・・・
生命保険金もその一つでしょう・・・
働き盛りでなくなてしまったご主人が遺してくれた生命保険金、これからの暮らしを考えていくと、この生命保険金から税金を徴収するのは過酷でしょう・・・
そこで、生命保険金等の非課税の規定の適用があります。
500万円×法定相続人の数が非課税限度額です。
この非課税限度額までの死亡保険金には、相続税は課されないこととなってきます。
ただし、その死亡保険金の保険料を被相続人以外のものが負担していると、根本的に相続税の対象ではなく、贈与税や所得税とばってしまう恐れがありますので注意が必要です。
相続対策として、3社くらいの生命保険会社が、高齢(85歳~90歳までOK)で、かつ、無告知に近い形で加入できる生命保険も販売されています。
ほとんど、投資効果は期待できませんが、生命保険金の非課税の枠に余裕のある方にとっては、現預金等の金融資産を非課税にすることができるメリットが生じてきます。
都心部やその近郊では路線価も上がり調子です・・・
来年からの相続増税時代に向けて、まずは、自宅の相続税評価額、小規模の特例がが受けられるのか否か、受けた場合と受けなかった場合とで、相続税にどの程度の影響が出てくるのか・・・
または、相続開始の時点で金融資産がどの程度、残りそうなのか・・・
納税資金は大丈夫なのか・・・
とりあえず、生命保険に加入して非課税枠を確保しておくべきなのか・・・
このような、判断は、全ての財産の目録と評価額を作成して、各税法の特例や不動産の特性などを考えながら判断するほかありません・・・
路線価も上がり調子となってきました・・・
まずは、財産棚卸と調査から始めてみましょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
全国平均は6年連続の下落となりましたが、三大都市圏では上昇に転じてきています。
2極化の傾向は、まだまだ、続きそうです。
東京は、東京五輪のインフラ整備の期待感から投資目的の不動産購入の人気が高まっているようです・・・
この大都市圏を中心とした不動産市況の回復がどの程度まで地方に広がりを見せていくのか・・・興味の湧くところではあります。
アベノミクスによる円安・株高効果と東京五輪の期待感も相まって・・・
この機会とばかりに不動産への投資熱が高まってきたようです。
この不動産市況を始めとした景気の盛り上がりは東京五輪の直前に一つのヤマを迎えるといった意見も耳にしますので、今後の動向は気になるところです・・・
さて、来年からは、相続税の基礎控除額の減額などの増税路線がスタートします。
個人的には、相続税という税金は、他の所得税や法人税などのように一定期間の営業活動のなかから得られた財産の増加(利益)に対して超過累進税率を乗じて課税されるものとは違って、相続がおきて親等の親族から無償で財産が承継され、財産が増加したことに対して税金が課されますので、その納税には多いに苦慮される場合があります。
その財産のなかには、換金できないもの・・・例えば住宅・・・住むために必要不可欠なものです。
この住宅も相続税の課税対象となることが納税資金の工面に苦慮する一つの要因となってきます。
財産は引き継いだものの、それは、単に住むためのもの・・・
昔から、代々、その家で住むための不動産であった・・・
この財産に税金が課されるとすると・・・
最悪、売却して換金するしか納税できる方法が見当たらないといった事態に陥りかねません・・・
税務当局は、こうした住宅については、さすがに相続税の対象からは外していこうといった特例を設けています。
さすがに、住んでいる家まで税金で没収するようなことまでは、考えていないようです。
それが、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特定の規定です。
被相続人や被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供していた住宅を、被相続人の配偶者や被相続人の親族(一定の要件を満たしていることが必要です)が、相続または遺贈で取得した場合に適用が受けられる規定です。
ちなみに、この特例の規定の適用がを受けられると・・・
来年からは住宅敷地の評価額のうち、330㎡(今年は240㎡)までの面積の部分は80%まで減額されることとなります。
都心部では、この特例の規定が使えるのか否かで、大きく、相続税額は変わってくることになります。
この適用は、配偶者が取得すれば細かい適用要件に関係なく適用が受けられます。
これは、配偶者としての税法上の特典でもあるわけです。
問題は、配偶者以外の親族が取得する場合です。
基本的には、相続開始の直前にその住宅に居住していること、かつ、相続開始の時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に住んでいること等他の一定の要件が必要です。
同居していない場合の要件としては、その親族が相続開始前3年以内に自分の持ち家もしくは自分の配偶者の持ち家に住んでいないこと、かつ、相続開始の時から申告期限まで引き続き所有していること等他の要件が必要です。(ちなみに、相続の開始の直前において、この住宅に被相続人の法定相続人に該当する他の親族が住んでいる場合は除かれます)
この小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるか否かが、来年からの相続増税時代に向けての大きなポイントなるべき項目です。
また、住むための住宅のほかにも相続人にとって必要不可欠な財産があります。
それは、被相続人の事業の用に供していた財産です。
被相続人の事業を親族が引き継ぐといった場合に、事業用の財産に相続税が課せられてしまっては、その事業承継にとって大きな障害となってきます。
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定には、事業用の宅地、アパート等の貸付用の宅地、同族会社の事業用の宅地等も対象となっています。
そのほかにも、農地や非上場株式、山林、医業経営者などの納税猶予の規定もあります。
このように、生活に必要なもの(事業承継も含めて)については、それなりに税法の特典ともいえる特例措置が設けられていますので、このような特例措置は、見落としがないように生前のうちに整理して確認しておくべきでしょう。
また、生活していくうえで、必要不可欠なもの・・・
生命保険金もその一つでしょう・・・
働き盛りでなくなてしまったご主人が遺してくれた生命保険金、これからの暮らしを考えていくと、この生命保険金から税金を徴収するのは過酷でしょう・・・
そこで、生命保険金等の非課税の規定の適用があります。
500万円×法定相続人の数が非課税限度額です。
この非課税限度額までの死亡保険金には、相続税は課されないこととなってきます。
ただし、その死亡保険金の保険料を被相続人以外のものが負担していると、根本的に相続税の対象ではなく、贈与税や所得税とばってしまう恐れがありますので注意が必要です。
相続対策として、3社くらいの生命保険会社が、高齢(85歳~90歳までOK)で、かつ、無告知に近い形で加入できる生命保険も販売されています。
ほとんど、投資効果は期待できませんが、生命保険金の非課税の枠に余裕のある方にとっては、現預金等の金融資産を非課税にすることができるメリットが生じてきます。
都心部やその近郊では路線価も上がり調子です・・・
来年からの相続増税時代に向けて、まずは、自宅の相続税評価額、小規模の特例がが受けられるのか否か、受けた場合と受けなかった場合とで、相続税にどの程度の影響が出てくるのか・・・
または、相続開始の時点で金融資産がどの程度、残りそうなのか・・・
納税資金は大丈夫なのか・・・
とりあえず、生命保険に加入して非課税枠を確保しておくべきなのか・・・
このような、判断は、全ての財産の目録と評価額を作成して、各税法の特例や不動産の特性などを考えながら判断するほかありません・・・
路線価も上がり調子となってきました・・・
まずは、財産棚卸と調査から始めてみましょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年06月28日
争族(遺産分割、遺留分減殺請求)は不動産の価値の認識の相違から始まる・・・
相続の話に欠かせない争族対策・・・
遺産分割のときに相続人間で財産の分割の話し合いがまとまらない・・・
遺言書が遺されていたものの遺留分に満たない相続人が減殺請求をしてその代償金をめぐって話し合いがまとまらない・・・
等々・・・
相続財産の分割をめぐって、相続人間で話がまとまらないと・・・
いわゆる、相続財産の分割をめぐっての争い・・・争族となってきます・・・
争わないためには・・・
遺言書やエンディングノートを遺しておきましょうと・・・
まことしやかにあちこちで耳にし目にします。
この争族となってしまう理由は一言ではいえないでしょう・・・
小さいころからの想いとか、親の愛情とか・・・いろいろなことが絡んでいる場合もあるでしょう・・・
その争族の一つの要因として不動産の価値の相続人間での認識の相違があるでしょう・・・
遺産分割や遺留分の減殺請求の場合、不動産はいくらで評価するのか・・・
相続人間の話し合いで決めていくものですから・・・
当然、法律で定められたものはありません・・・
法律では、いわゆる相続人の相続分が民法で定められているくらいです。
そうなってくると、どうするか・・・
基本的には被相続人が亡くなった時に、市場で売却できる金額となります。
この売却できる金額は、どうやって算出するのか・・・
不動産は、大体いくらくらいで売れるといった売却予想額は査定金額として算出できますが、実際に売りに出してみないといくらで売れるかはわかったものではありません。
不動産には4つの価格の目安が存在しています。
いわゆる一物四価といわれる所以です・・・
固定資産税評価額、路線価、公示価格・基準地価格、そして実際相場価格・・・
固定資産税評価額、路線価、公示価格・基準地価格は、国や地方の行政が毎年(固定資産税評価額は3年に一度)評価額を算出しています。
固定資産税表額は固定資産税を課税するため各市町村が、路線価は相続税や贈与税を課税するため国税庁が、公示価格は売買の価格の目安として国土交通省が、基準地価格は売買の目安として各都道府県が・・・算出し公表しています。
公示価格・基準地価格が時価(売却できそうな金額)水準で算出され、路線価はその8割、固定資産税評価額はその7割水準で算出されています。
さらに、実際の該当する不動産の近くで販売された事例をもとに算出する取引事例価格や収益還元法などを用いて、個々の不動産の価値を算出することができます。
ここで、話を戻しますと・・・
遺産分割や遺留分の減殺請求の場合、相続人間でこの不動産の価格をめぐっての争いがよく生じるわけです・・・
不動産をもらう相続人は不動産はなるべく安く・・・できれば、固定資産税評価額で・・・
不動産以外の財産を貰う人は、不動産はなるべく高く評価することを望んでくるわけです・・・
この不動産の価格というか評価をめぐって、裁判所の調停や審判にいたるときもあります・・・
裁判所までいって、話しがまとまらなければ、裁判官は不動産鑑定士の鑑定評価書をもとに遺産分割の内容を決めていくようです。
このように、分けにくい、換金しにくい、価格がわかりにくい・・・不動産は相続のときには本当に厄介な存在となってきます。
生前の相続対策を考えましょうと奨められて争族対策として固有の財産である生命保険金を利用しましょうと提案されることが、非常に多いかと思いますが・・・
円満、円滑な遺産分割や納税のための相続対策には、いきなり生命保険や土地活用を奨めるのではなくて、全ての不動産の価値(売ったらいくら、貸したらいくら・・・等)を推し量ったうえで検討してみてください。
思い描いていた遺産分割の内容を変更する考えも湧くかもしれません・・・
その遺産分割の内容を替えてくると、当然に納税のプランも変わってくるかもしれません・・・
不動産の価値・・・まずは、ご確認してみてください・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺産分割のときに相続人間で財産の分割の話し合いがまとまらない・・・
遺言書が遺されていたものの遺留分に満たない相続人が減殺請求をしてその代償金をめぐって話し合いがまとまらない・・・
等々・・・
相続財産の分割をめぐって、相続人間で話がまとまらないと・・・
いわゆる、相続財産の分割をめぐっての争い・・・争族となってきます・・・
争わないためには・・・
遺言書やエンディングノートを遺しておきましょうと・・・
まことしやかにあちこちで耳にし目にします。
この争族となってしまう理由は一言ではいえないでしょう・・・
小さいころからの想いとか、親の愛情とか・・・いろいろなことが絡んでいる場合もあるでしょう・・・
その争族の一つの要因として不動産の価値の相続人間での認識の相違があるでしょう・・・
遺産分割や遺留分の減殺請求の場合、不動産はいくらで評価するのか・・・
相続人間の話し合いで決めていくものですから・・・
当然、法律で定められたものはありません・・・
法律では、いわゆる相続人の相続分が民法で定められているくらいです。
そうなってくると、どうするか・・・
基本的には被相続人が亡くなった時に、市場で売却できる金額となります。
この売却できる金額は、どうやって算出するのか・・・
不動産は、大体いくらくらいで売れるといった売却予想額は査定金額として算出できますが、実際に売りに出してみないといくらで売れるかはわかったものではありません。
不動産には4つの価格の目安が存在しています。
いわゆる一物四価といわれる所以です・・・
固定資産税評価額、路線価、公示価格・基準地価格、そして実際相場価格・・・
固定資産税評価額、路線価、公示価格・基準地価格は、国や地方の行政が毎年(固定資産税評価額は3年に一度)評価額を算出しています。
固定資産税表額は固定資産税を課税するため各市町村が、路線価は相続税や贈与税を課税するため国税庁が、公示価格は売買の価格の目安として国土交通省が、基準地価格は売買の目安として各都道府県が・・・算出し公表しています。
公示価格・基準地価格が時価(売却できそうな金額)水準で算出され、路線価はその8割、固定資産税評価額はその7割水準で算出されています。
さらに、実際の該当する不動産の近くで販売された事例をもとに算出する取引事例価格や収益還元法などを用いて、個々の不動産の価値を算出することができます。
ここで、話を戻しますと・・・
遺産分割や遺留分の減殺請求の場合、相続人間でこの不動産の価格をめぐっての争いがよく生じるわけです・・・
不動産をもらう相続人は不動産はなるべく安く・・・できれば、固定資産税評価額で・・・
不動産以外の財産を貰う人は、不動産はなるべく高く評価することを望んでくるわけです・・・
この不動産の価格というか評価をめぐって、裁判所の調停や審判にいたるときもあります・・・
裁判所までいって、話しがまとまらなければ、裁判官は不動産鑑定士の鑑定評価書をもとに遺産分割の内容を決めていくようです。
このように、分けにくい、換金しにくい、価格がわかりにくい・・・不動産は相続のときには本当に厄介な存在となってきます。
生前の相続対策を考えましょうと奨められて争族対策として固有の財産である生命保険金を利用しましょうと提案されることが、非常に多いかと思いますが・・・
円満、円滑な遺産分割や納税のための相続対策には、いきなり生命保険や土地活用を奨めるのではなくて、全ての不動産の価値(売ったらいくら、貸したらいくら・・・等)を推し量ったうえで検討してみてください。
思い描いていた遺産分割の内容を変更する考えも湧くかもしれません・・・
その遺産分割の内容を替えてくると、当然に納税のプランも変わってくるかもしれません・・・
不動産の価値・・・まずは、ご確認してみてください・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年06月14日
相続増税と担税力について・・・
来年1月から相続税の改正が施行されます・・・
超過累進税率の改正もさることながら、何といっても、基礎控除額の減額が今回の増税の大きな要因となってきます。
現状の6000万円と1000万円×法定相続人の数の控除額は、3000万円と600万円×法定相続人の数の控除額へと減額されることとなります。
この影響を大きく受けるのは、いわゆる2次相続と呼ばれるお母さんの相続のときです・・・
一次相続と呼ばれるお父さんの相続の時は配偶者のお母さんが健在であるときが多く、この場合の相続では、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例はその宅地等を配偶者が取得すれば必ず適用を受けられることと、さらに、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用が受けられることにより、相続税がかかってくるハードルはかなり高いこととなってきます。
小規模宅地等の課税価格計算の特例は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の配偶者が取得したときには240㎡まではその宅地等の課税価格のうち実に80%もの価額が減額されるものです。
来年からの相続税の改正で240㎡が330㎡まで面積の要件は緩和されることとなります。
そして、配偶者に対する相続税額の軽減は、最低1億6千万円まで、または全体の課税価格のうち配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続分、子供がいる場合は1/2)までは、相続税がかからないようになっている規定です。
話がそれてしまいましたが、配偶者の優遇規定が受けられる妻か(通常は夫が財産のほとんどを所有しているため妻)か夫が相続人にいる場合は、一般のお勤めの方では、今回の相続増税の影響を受ける人は少ないものと思われます。
問題は、2次相続の時・・・
配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用は当然にないことと、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を受けるためのいくつかの要件が必要となってきます。
その住宅に住んでいた被相続人と同居していたこと、もしくは同居していなかった場合は自分もしくは自分の配偶者の持ち家に相続開始前3年以内にすんでいなかったこと等その他一定の要件を満たしている必要がありあます。
このように考えると、2次相続が発生する前の相続対策の重要性がわかってきます。
ここで、本題の担税力のお話ですが・・・
相続税もしくは消費税または固定資産税や自動車税等以外の税金は、基本的には儲けに対していくらという計算によって税金を課しています。
これに対して、資産を持っているだけで税金を課すのが固定資産税や自動車税・・・
これは、ある程度の資産を所有している人は担税力があるといった判断が課税根拠となっているものでしょうか・・・
自動車は自分で購入して所有しているものですから・・・いざ知らず
固定資産税は、代々、家のものを引き継いだものに対して課税されます。
お金を稼げる不動産に課税されるのならまだ理解できますが・・・
何ら、お金を稼げていない不動産にも課税されてきます。
それも場合によっては、何もしていない土地が、お金を稼げている土地よりも高い固定資産税となるときも多いにあり得ます。
そして、相続税・・・
相続がおきて先代から財産を無償で引き継いだ・・・
これは、無償で財産が増えたことを意味し、財産が増えるということはこれは利益である・・・そして税金は利益にたいして課税する。
いいかえれば、財産が増えることに対して税金は課されるわけです。
相続税は、その財産が無償で増えることとなるわけですから、課税価格そのものに課税されることとなるわけです・・・
ただ、その相続で増えた財産のなかで、担税力のないもの・・・
例えば、稼げていない不動産・・・これは、担税力はないか・・・
稼げていなくても、売れば納税できる・・・物納すれば納税できる・・・
これは、株や投信などの金融商品も同様です・・・売れば納税できる・・・
担税力がないといえるかというと・・・担税力はありそうです。
そうなると、担税力のない財産はというと・・・
売るに売れない財産、物納に出せない・・・相続人に最低限生きていく上で必要な財産・・・
それは、居住用や事業用の財産です・・・
被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用または事業のように供されている不動産や自分の会社の株式です・・・
このように、必要不可欠な財産には、小規模宅地等の特例や農地の農事猶予、非上場株式の納税猶予、山林の納税猶予等の特例規定があります。
最低限、必要な財産・・・生活するための財産、事業承継の財産・・・といったところです・・・
こういったものや、または、生前の贈与で次世代に財産を早めに継承していくための住宅取得資金や教育資金等の贈与税の非課税の特例の規定などがあります。
ここで、来年からの相続税の基礎控除額の減額と小規模宅地等の居住用の特例の緩和の規定を考えてみると・・・
基礎控除額の減額・・・法定相続人を子供三人で考えた場合・・・
現状の8000万円が4800万円の減額となります・・・その差3200万円・・・
この基礎控除額の減額で一番影響を受けやすい都心部の戸建て住宅に住んでいる人を想定で、この3200万円を考えてみると・・・
小規模宅地等の居住用の面積要件が240㎡から330㎡に緩和された・・・その差90㎡(約27坪)
そして基礎控除額の差3200万円をこの27坪で割ってみると・・・@約120万円弱となります・・・
路線価で120万円・・・公示価格ベースで坪約150万円・・・
この坪150万円前後の土地相場の地域が税務当局の特例の設定の目安としたものかもしれません。
相続増税にあたっては・・・
一応は、生活に必要な居住用の財産についての担税力には気を遣ったたのかとは個人的には感じています・・・
いずれにしても、相続増税には、小規模宅地等の特例と生命保険による金融資産の課税価格圧縮で対応したいところです。
まずは、相続税の概算シミュレーションを計算してみたらいかがでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
超過累進税率の改正もさることながら、何といっても、基礎控除額の減額が今回の増税の大きな要因となってきます。
現状の6000万円と1000万円×法定相続人の数の控除額は、3000万円と600万円×法定相続人の数の控除額へと減額されることとなります。
この影響を大きく受けるのは、いわゆる2次相続と呼ばれるお母さんの相続のときです・・・
一次相続と呼ばれるお父さんの相続の時は配偶者のお母さんが健在であるときが多く、この場合の相続では、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例はその宅地等を配偶者が取得すれば必ず適用を受けられることと、さらに、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用が受けられることにより、相続税がかかってくるハードルはかなり高いこととなってきます。
小規模宅地等の課税価格計算の特例は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の配偶者が取得したときには240㎡まではその宅地等の課税価格のうち実に80%もの価額が減額されるものです。
来年からの相続税の改正で240㎡が330㎡まで面積の要件は緩和されることとなります。
そして、配偶者に対する相続税額の軽減は、最低1億6千万円まで、または全体の課税価格のうち配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続分、子供がいる場合は1/2)までは、相続税がかからないようになっている規定です。
話がそれてしまいましたが、配偶者の優遇規定が受けられる妻か(通常は夫が財産のほとんどを所有しているため妻)か夫が相続人にいる場合は、一般のお勤めの方では、今回の相続増税の影響を受ける人は少ないものと思われます。
問題は、2次相続の時・・・
配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用は当然にないことと、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を受けるためのいくつかの要件が必要となってきます。
その住宅に住んでいた被相続人と同居していたこと、もしくは同居していなかった場合は自分もしくは自分の配偶者の持ち家に相続開始前3年以内にすんでいなかったこと等その他一定の要件を満たしている必要がありあます。
このように考えると、2次相続が発生する前の相続対策の重要性がわかってきます。
ここで、本題の担税力のお話ですが・・・
相続税もしくは消費税または固定資産税や自動車税等以外の税金は、基本的には儲けに対していくらという計算によって税金を課しています。
これに対して、資産を持っているだけで税金を課すのが固定資産税や自動車税・・・
これは、ある程度の資産を所有している人は担税力があるといった判断が課税根拠となっているものでしょうか・・・
自動車は自分で購入して所有しているものですから・・・いざ知らず
固定資産税は、代々、家のものを引き継いだものに対して課税されます。
お金を稼げる不動産に課税されるのならまだ理解できますが・・・
何ら、お金を稼げていない不動産にも課税されてきます。
それも場合によっては、何もしていない土地が、お金を稼げている土地よりも高い固定資産税となるときも多いにあり得ます。
そして、相続税・・・
相続がおきて先代から財産を無償で引き継いだ・・・
これは、無償で財産が増えたことを意味し、財産が増えるということはこれは利益である・・・そして税金は利益にたいして課税する。
いいかえれば、財産が増えることに対して税金は課されるわけです。
相続税は、その財産が無償で増えることとなるわけですから、課税価格そのものに課税されることとなるわけです・・・
ただ、その相続で増えた財産のなかで、担税力のないもの・・・
例えば、稼げていない不動産・・・これは、担税力はないか・・・
稼げていなくても、売れば納税できる・・・物納すれば納税できる・・・
これは、株や投信などの金融商品も同様です・・・売れば納税できる・・・
担税力がないといえるかというと・・・担税力はありそうです。
そうなると、担税力のない財産はというと・・・
売るに売れない財産、物納に出せない・・・相続人に最低限生きていく上で必要な財産・・・
それは、居住用や事業用の財産です・・・
被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用または事業のように供されている不動産や自分の会社の株式です・・・
このように、必要不可欠な財産には、小規模宅地等の特例や農地の農事猶予、非上場株式の納税猶予、山林の納税猶予等の特例規定があります。
最低限、必要な財産・・・生活するための財産、事業承継の財産・・・といったところです・・・
こういったものや、または、生前の贈与で次世代に財産を早めに継承していくための住宅取得資金や教育資金等の贈与税の非課税の特例の規定などがあります。
ここで、来年からの相続税の基礎控除額の減額と小規模宅地等の居住用の特例の緩和の規定を考えてみると・・・
基礎控除額の減額・・・法定相続人を子供三人で考えた場合・・・
現状の8000万円が4800万円の減額となります・・・その差3200万円・・・
この基礎控除額の減額で一番影響を受けやすい都心部の戸建て住宅に住んでいる人を想定で、この3200万円を考えてみると・・・
小規模宅地等の居住用の面積要件が240㎡から330㎡に緩和された・・・その差90㎡(約27坪)
そして基礎控除額の差3200万円をこの27坪で割ってみると・・・@約120万円弱となります・・・
路線価で120万円・・・公示価格ベースで坪約150万円・・・
この坪150万円前後の土地相場の地域が税務当局の特例の設定の目安としたものかもしれません。
相続増税にあたっては・・・
一応は、生活に必要な居住用の財産についての担税力には気を遣ったたのかとは個人的には感じています・・・
いずれにしても、相続増税には、小規模宅地等の特例と生命保険による金融資産の課税価格圧縮で対応したいところです。
まずは、相続税の概算シミュレーションを計算してみたらいかがでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年06月11日
相続対策での生命保険の活用で留意したいこと・・・(税金他編)
前回の相続対策と生命保険のお話の続きとして税金等に関するお話等をさせていただきます・・・
相続対策に生命保険を活用する上での税金上の特徴は何か・・・
第一に、被相続人を被保険者とした保険料を被相続人が負担した保険金を相続人が取得した場合は、生命保険金の非課税の適用があります。
生命保険金の非課税は、皆さん、ご承知の通りの、500万円×法定相続人の数(相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとした場合における相続人の数)を限度(非課税限度額)として、相続税の課税価格に算入しなくてよしとされる規定です。
例えば、相続人が妻と子供3人の時は、500万円×4=2000万円が非課税限度額となります。
相続人の取得した生命保険金の合計額が、2000万円以下であれば、それぞれの相続人の取得した生命保険金等の全てが、当然に非課税となります。
相続人の取得した生命保険等の合計額が、2000万円を超える場合には、2000万円をそれぞれの相続人の取得した生命保険金の金額で按分計算して、それぞれの相続人ごとの非課税金額を計算することとなります。
この非課税の規定は、金融商品のなかでは、唯一、生命保険のみに適用されるものです。(他には退職手当金がありますが・・・)
現金預金のまま、相続を迎えるよりは、生命保険金として遺してあげたほうが、相続税がかかってくる人にとっては節税効果は高いものとなってきます。
例えば、相続税率20%の方であれば、上記の2000万円の非課税があるのとないのとでは、2000万円×20%=400万円の差となって現れてきます。
これが、相続税率30%の方であれば、2000万円×30%=600万円の差となって表れてきます。
相続税率20%とは課税価格が3000万円超~5000万円以下、相続税率30%とは課税価格が5000万円超1億円以下となります。
来年から、相続税の基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数に改正されますので、上記の家族構成の場合は3000万円+600万円×4人=5400万円が、相続税の基礎控除額となってきます。
そうなってくると、相続税率20%の対象は基礎控除額減額前で8400万円超~1億400万円以下、相続税率30%の対象は基礎控除額減額前で1億400万円超~1億5400万円以下の財産を所有している方となってきます。
この金額には被相続人が被保険者の被相続人が保険料を支払った生命保険金も含まれることとなってきます。
民法上の相続財産ではないのですが、税法上は税金の取り逃しがないように、みなし相続財産として課税されます。
ただし、生命保険という遺された家族の方にとっては、大事な大事な生活資金となっていくものですから、上記のような非課税規定が設けられているわけです。
ここで、大事なのは、自分の相続税の課税価格が幾らくらいになりそうかの検討をつけることでしょう・・・
上記に記したように、5400万円を超えると課税、8400万円と1億400万円を超えると税率UPとなるわけです・・・
自分が、いま、どのポジションにいるのかの見当をつけてから、相続対策の生命保険の加入を考えるようにしてください。
入りすぎても、少なくても、問題があるかといえば、全てのケースで問題とはいえませんが、もっと考えてから保険に入っておけば良かったと思うことになりかねません・・・
そして、生命保険金の非課税が有効であるということになれば、生命保険の加入をお勧めします・・・
高齢(例えば80歳以上)かつ糖尿病で入れる保険がないと思っていた方も、90歳まで無告知(入院していなければOK)で入れる終身保険も販売されています。
来年からの相続税の基礎控除額減額にあわせて検討されてみたらいかがでしょうか・・・(高齢で加入されますと投資効果はほとんど期待できませんので、生命保険の非課税を活用することにメリットのある方にお勧めな商品です)
ここで、一つ、上記の課税価格の検証ですが、重要な検証ポイントは土地の評価です・・・特に小規模宅地等の課税価格計算の特例の特定居住用宅地等の適用の可否の判定です。
特定居住用宅地等としての小規模宅地等の特例が、今の状態で、問題なく使えるのか否か、今の状態で適合しないのであれば、どのようにすれば適用となるのか・・・を確認してください・・・
ポイントはその住宅を引き継ぐ子供の同居、非同居をめぐっての要件がポイントとなってきます。
また、生命保険の非課税限度額を超える生命保険に加入済みのかたの相続対策として、たとえば納税資金を準備したい・・・といったような場合・・・
もちろん、非課税の範囲内で納税資金の準備が賄えるのであればそれでいいのですが、さらに上乗せして、納税資金や分割対策として生命保険に加入したいといった場合は、生命保険以外の方法との比較検討はしたほうがいいかもしれません。
生命保険の非課税のメリットを享受できないのであれば、例えば、生前贈与で生命保険に加入していく方法にも替えて、NISAを利用して投信等で生命保険を上回る投資効果を狙っていく方法もあるでしょう・・・
生命保険のメリットは、早いうちになくなると、支払保険料を大きく上回る保険金が手に入ることにあります。
逆にいうと、長生きすると投資効果は、さほど、望めないことになってきます。
それであれば、まずは生命保険の非課税限度額まで生命保険に加入してから、それからの上積み分は、生命保険と投信等を織り交ぜての双方の強み、弱みを活かした相続対策お準備もありだと思います・・・・
また、生命保険の特徴である固有の財産としてのメリットは、家族信託等でも同様の効果を得られることは考えられます。
そして、生命保険そのもので、相続税の財産評価額を下げられる方法・・・つまり、低解約返戻金の商品を利用していく方法も考えられますが、評価額の低減ばかりに気を取られてその保険商品そのものが必要のないものであったら本末転倒となりかねませんし、やはり、怖いのは税制改正・・・
オーソドックスに生前贈与等の方法で、相続税の財産評価を下げていく方法がベターかと思われます。
いずれにしても、非課税や固有の財産ですよといった生命保険のいいところばかりで、生命保険の加入を判断せずに、自分の財産の全体を客観的に冷静に分析して、何がいくら必要かを検証して考えてから、その加入を判断してください。
自分で、冷静に客観的に判断できなそうなときは、専門家に相談してみましょう・・・
相続対策は、全ての財産を把握して相続税のシミュレーションや活用の状況等の現状分析を行って、初めて、何の対策が必要かが見えてきます。
美味しそうな話にいきなり飛びつかずに、まずは、自分の財産を振り返って見直してみましょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
相続対策に生命保険を活用する上での税金上の特徴は何か・・・
第一に、被相続人を被保険者とした保険料を被相続人が負担した保険金を相続人が取得した場合は、生命保険金の非課税の適用があります。
生命保険金の非課税は、皆さん、ご承知の通りの、500万円×法定相続人の数(相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとした場合における相続人の数)を限度(非課税限度額)として、相続税の課税価格に算入しなくてよしとされる規定です。
例えば、相続人が妻と子供3人の時は、500万円×4=2000万円が非課税限度額となります。
相続人の取得した生命保険金の合計額が、2000万円以下であれば、それぞれの相続人の取得した生命保険金等の全てが、当然に非課税となります。
相続人の取得した生命保険等の合計額が、2000万円を超える場合には、2000万円をそれぞれの相続人の取得した生命保険金の金額で按分計算して、それぞれの相続人ごとの非課税金額を計算することとなります。
この非課税の規定は、金融商品のなかでは、唯一、生命保険のみに適用されるものです。(他には退職手当金がありますが・・・)
現金預金のまま、相続を迎えるよりは、生命保険金として遺してあげたほうが、相続税がかかってくる人にとっては節税効果は高いものとなってきます。
例えば、相続税率20%の方であれば、上記の2000万円の非課税があるのとないのとでは、2000万円×20%=400万円の差となって現れてきます。
これが、相続税率30%の方であれば、2000万円×30%=600万円の差となって表れてきます。
相続税率20%とは課税価格が3000万円超~5000万円以下、相続税率30%とは課税価格が5000万円超1億円以下となります。
来年から、相続税の基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数に改正されますので、上記の家族構成の場合は3000万円+600万円×4人=5400万円が、相続税の基礎控除額となってきます。
そうなってくると、相続税率20%の対象は基礎控除額減額前で8400万円超~1億400万円以下、相続税率30%の対象は基礎控除額減額前で1億400万円超~1億5400万円以下の財産を所有している方となってきます。
この金額には被相続人が被保険者の被相続人が保険料を支払った生命保険金も含まれることとなってきます。
民法上の相続財産ではないのですが、税法上は税金の取り逃しがないように、みなし相続財産として課税されます。
ただし、生命保険という遺された家族の方にとっては、大事な大事な生活資金となっていくものですから、上記のような非課税規定が設けられているわけです。
ここで、大事なのは、自分の相続税の課税価格が幾らくらいになりそうかの検討をつけることでしょう・・・
上記に記したように、5400万円を超えると課税、8400万円と1億400万円を超えると税率UPとなるわけです・・・
自分が、いま、どのポジションにいるのかの見当をつけてから、相続対策の生命保険の加入を考えるようにしてください。
入りすぎても、少なくても、問題があるかといえば、全てのケースで問題とはいえませんが、もっと考えてから保険に入っておけば良かったと思うことになりかねません・・・
そして、生命保険金の非課税が有効であるということになれば、生命保険の加入をお勧めします・・・
高齢(例えば80歳以上)かつ糖尿病で入れる保険がないと思っていた方も、90歳まで無告知(入院していなければOK)で入れる終身保険も販売されています。
来年からの相続税の基礎控除額減額にあわせて検討されてみたらいかがでしょうか・・・(高齢で加入されますと投資効果はほとんど期待できませんので、生命保険の非課税を活用することにメリットのある方にお勧めな商品です)
ここで、一つ、上記の課税価格の検証ですが、重要な検証ポイントは土地の評価です・・・特に小規模宅地等の課税価格計算の特例の特定居住用宅地等の適用の可否の判定です。
特定居住用宅地等としての小規模宅地等の特例が、今の状態で、問題なく使えるのか否か、今の状態で適合しないのであれば、どのようにすれば適用となるのか・・・を確認してください・・・
ポイントはその住宅を引き継ぐ子供の同居、非同居をめぐっての要件がポイントとなってきます。
また、生命保険の非課税限度額を超える生命保険に加入済みのかたの相続対策として、たとえば納税資金を準備したい・・・といったような場合・・・
もちろん、非課税の範囲内で納税資金の準備が賄えるのであればそれでいいのですが、さらに上乗せして、納税資金や分割対策として生命保険に加入したいといった場合は、生命保険以外の方法との比較検討はしたほうがいいかもしれません。
生命保険の非課税のメリットを享受できないのであれば、例えば、生前贈与で生命保険に加入していく方法にも替えて、NISAを利用して投信等で生命保険を上回る投資効果を狙っていく方法もあるでしょう・・・
生命保険のメリットは、早いうちになくなると、支払保険料を大きく上回る保険金が手に入ることにあります。
逆にいうと、長生きすると投資効果は、さほど、望めないことになってきます。
それであれば、まずは生命保険の非課税限度額まで生命保険に加入してから、それからの上積み分は、生命保険と投信等を織り交ぜての双方の強み、弱みを活かした相続対策お準備もありだと思います・・・・
また、生命保険の特徴である固有の財産としてのメリットは、家族信託等でも同様の効果を得られることは考えられます。
そして、生命保険そのもので、相続税の財産評価額を下げられる方法・・・つまり、低解約返戻金の商品を利用していく方法も考えられますが、評価額の低減ばかりに気を取られてその保険商品そのものが必要のないものであったら本末転倒となりかねませんし、やはり、怖いのは税制改正・・・
オーソドックスに生前贈与等の方法で、相続税の財産評価を下げていく方法がベターかと思われます。
いずれにしても、非課税や固有の財産ですよといった生命保険のいいところばかりで、生命保険の加入を判断せずに、自分の財産の全体を客観的に冷静に分析して、何がいくら必要かを検証して考えてから、その加入を判断してください。
自分で、冷静に客観的に判断できなそうなときは、専門家に相談してみましょう・・・
相続対策は、全ての財産を把握して相続税のシミュレーションや活用の状況等の現状分析を行って、初めて、何の対策が必要かが見えてきます。
美味しそうな話にいきなり飛びつかずに、まずは、自分の財産を振り返って見直してみましょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年06月10日
相続対策での生命保険の活用で留意したいこと(遺産分割編)・・・
先週末に、某生命保険会社の代理店向けのセミナーに参加してきました・・・
冒頭は、医療保険不要論と先進医療特約のメリットのお話でした。
医療保険は不要・・・必要なのは先進医療特約・・・それも交通費用までカバーできる商品にすべきとのこと・・・
それはそうです・・・先進医療が受けられる医療機関は遠方にあることも珍しくなく、交通費が出るのは本当にありがたいものでしょう・・・
そして、後半は、相続対策と生命保険についてのお話でした・・・
金融商品のなかで相続の対策に、一番向いている、適しているのは・・・生命保険です・・・が、話の始まりでした・・・
それは・・・なぜか・・・
もはや、聞きなれた感のあるお話を事例をもとにされました・・・
第一に、何といっても、生命保険は、民法上、受取人の固有の財産であること・・・
すなわち、遺産分割対象の相続財産に加えなくていいこととなるわけです・・・
つまり・・・遺産分割対象外・・・ということは民法上の相続財産を共有する関係にある相続人との話し合いは不要ということになります。
これは、遺言書で財産の取得者を指定しなくても、現金を生命保険にしてあげたい人を保険金受取人に指定しておけば、その目的は達成されることとなります。
シンプルに、2000万円を長男に全額遺してあげたいといったような時は、生命保険に加入しておけば、遺言書を書かなくても事は足りてしまうこととなってきます。
もっとも、そのほかの財産の分割をどうするかという問題もあり、生命保険だけで相続の遺産全体の分割をカバーするのは無理ですので、円滑、円環な遺産分割には遺言書は用意したほうがよろしいでしょう。
また、固有の財産であることから、他の預貯金は遺産分割書や遺言書または相続人全員の合意書(実印と印鑑証明書が通常は必要)がなければ、勝手におろすこともつかうこともできないのに対し、生命保険は何らの他の相続人の書類等の必要もなく保険金受取の手続きが出来ますので、面倒なく現金を受け取ることができます。
介護の面倒を見てくれた特別な人に特別に遺してあげたい・・・といったような時にも有効でしょう・・・
この、固有の財産としての特性を活かした相続対策は、家族信託を利用しても可能となってきます・・・
生命保険がいいか、家族信託がいいかは・・・ケースバイケース・・・
その人その人の状況や事情や財産構成や相続人の数や関係、さらには、財産を残したい人の気持ち・・・どうしたいのか・・・によって、一番、理想に近い形での方策をいくつもの対策のパターンから選択していくほか方法はないでしょう・・・
大体において、あちらを立てればこちらがたたず・・・が、世の常・・・どこに妥協点を見出していくか・・・
できることなら、そのいくつもの対策のパターンと妥協点の見出しに真剣に向き合ってくれる人に、相続対策の生命保険の提案は頼むべきかもしれません・・・
生命保険を利用したパターンや家族信託を利用したパターンなど・・・比較検討したほうがいい場合も当然に出てくるでしょう・・・
結果は同じでも・・・検証に検証を重ねておけば・・・いざ、相続といったときに・・・あのとき、こうしておけばといったようなことは起こりにくいでしょう。
何事も、いろいろなパターンをシミュレーションして、自分の希望にあった方策を探し出してみましょう。
今回は、遺産分割のお話が長くなってしまいましたので、次回に、(税金編)について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
冒頭は、医療保険不要論と先進医療特約のメリットのお話でした。
医療保険は不要・・・必要なのは先進医療特約・・・それも交通費用までカバーできる商品にすべきとのこと・・・
それはそうです・・・先進医療が受けられる医療機関は遠方にあることも珍しくなく、交通費が出るのは本当にありがたいものでしょう・・・
そして、後半は、相続対策と生命保険についてのお話でした・・・
金融商品のなかで相続の対策に、一番向いている、適しているのは・・・生命保険です・・・が、話の始まりでした・・・
それは・・・なぜか・・・
もはや、聞きなれた感のあるお話を事例をもとにされました・・・
第一に、何といっても、生命保険は、民法上、受取人の固有の財産であること・・・
すなわち、遺産分割対象の相続財産に加えなくていいこととなるわけです・・・
つまり・・・遺産分割対象外・・・ということは民法上の相続財産を共有する関係にある相続人との話し合いは不要ということになります。
これは、遺言書で財産の取得者を指定しなくても、現金を生命保険にしてあげたい人を保険金受取人に指定しておけば、その目的は達成されることとなります。
シンプルに、2000万円を長男に全額遺してあげたいといったような時は、生命保険に加入しておけば、遺言書を書かなくても事は足りてしまうこととなってきます。
もっとも、そのほかの財産の分割をどうするかという問題もあり、生命保険だけで相続の遺産全体の分割をカバーするのは無理ですので、円滑、円環な遺産分割には遺言書は用意したほうがよろしいでしょう。
また、固有の財産であることから、他の預貯金は遺産分割書や遺言書または相続人全員の合意書(実印と印鑑証明書が通常は必要)がなければ、勝手におろすこともつかうこともできないのに対し、生命保険は何らの他の相続人の書類等の必要もなく保険金受取の手続きが出来ますので、面倒なく現金を受け取ることができます。
介護の面倒を見てくれた特別な人に特別に遺してあげたい・・・といったような時にも有効でしょう・・・
この、固有の財産としての特性を活かした相続対策は、家族信託を利用しても可能となってきます・・・
生命保険がいいか、家族信託がいいかは・・・ケースバイケース・・・
その人その人の状況や事情や財産構成や相続人の数や関係、さらには、財産を残したい人の気持ち・・・どうしたいのか・・・によって、一番、理想に近い形での方策をいくつもの対策のパターンから選択していくほか方法はないでしょう・・・
大体において、あちらを立てればこちらがたたず・・・が、世の常・・・どこに妥協点を見出していくか・・・
できることなら、そのいくつもの対策のパターンと妥協点の見出しに真剣に向き合ってくれる人に、相続対策の生命保険の提案は頼むべきかもしれません・・・
生命保険を利用したパターンや家族信託を利用したパターンなど・・・比較検討したほうがいい場合も当然に出てくるでしょう・・・
結果は同じでも・・・検証に検証を重ねておけば・・・いざ、相続といったときに・・・あのとき、こうしておけばといったようなことは起こりにくいでしょう。
何事も、いろいろなパターンをシミュレーションして、自分の希望にあった方策を探し出してみましょう。
今回は、遺産分割のお話が長くなってしまいましたので、次回に、(税金編)について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年05月25日
海外移住による節税か租税回避行為かの違いは・・・?
昨日の読売新聞に『香港移住で税回避』というタイトルの記事が掲載されていました。
この記事の内容の概要は次の通りです。
某一部上場企業の会長が、2008年に、代表取締役会長から名誉会長に退いたのちに、東京から香港に転居し、住所を移しました。
その後は、退任した会社から受け取る報酬や株の配当については日本で源泉所得税を納めていたそうです。
ただし、香港や韓国などの海外子会社から受け取る報酬や海外に持つ個人資産の運用益などは、日本での申告をしていなかたそうです。
そして、転居して2年後(2010年6月)には、再度、退任した会社の経営のかじ取りを行うために代表取締役会長に復帰したそうです。
住所は香港のままとし、海外所得の日本での納税は行っていなかったといいます。
ここでポイントとなるのは、同会長は香港移住後も頻繁に来日しては東京の旧自宅を使用し、その日本の滞在日数は香港を大きく上回っていたこと、さらには名誉会長だった時期も役員会で経営方針を示すなどの実質の経営権を握っていたことがあります。
以上のような状況から、東京国税局は生活の本拠は日本の国内にあるとし、海外所得の分も日本で納付すべきであると認定しました。
また、東京国税局は香港では海外で得た所得や株の配当などは非課税で、所得税率も約15%と、最高40%の日本の半分以下になることから、同会長は日本での申告を避けることで、所得税額を減らししたと判断したようです。
同会長の税理士は、香港への移住は会社のグローバル展開などを考えたビジネス上の理由で、税金を逃れるためのものではなかったしていますが、現実的に香港の滞在日数が短かったことは事実なので、国税局の指摘を受け入れたそうです。
この、事実認定による申告漏れの金額は、2011年までの3年間で計約10億円になったようです。
そして、海外での納税額を差し引いた所得税の追徴税額は、無申告加算税を含めて1億数千万円にのぼり、すでに納付されたようです。
今回のケースは、海外に住居を移し、日本の所得税の軽減を図ったものと認定され課税されたケースです。
この東京国税局の事実認定に対して、顧問税理士は、日本の滞在日収が年間の過半を超えていることから、この事実認定を受け入れ税務訴訟等には至らなかったようです。
今回に似たケースである住所は国内にあるとして申告漏れを指摘した『武富士事件』では、最高裁まで争った結果、居住地は『目的)という主観的要素で判断するものではなく、滞在人数など客観的な事実で判断すべきであるとして、国税局の敗訴となり、巨額の課税取り消しで、国は利子分も含めて約2000億円を返還することとなりました。
この武富士事件は、贈与税が対象でしたが、その海外への住所移転は贈与税を免れるためのものとして海外への滞在日数が年間の過半を超えているのにも関わらずに課税したものです。
もっとも、その海外への滞在日数は、顧問の公認会計士等が指導していた事実もあり、その事実も課税の根拠として争いました。
また、その海外の住まいがホテルのような住まいであったということも課税根拠となっていました。
『武富士事件』では、海外滞在が年間の過半を超えていたとしても、その住まいが仮住まい的な寓居であること、海外の滞在日数は、税務の専門家が指導していた事実、等々を課税根拠として争ったわけです。
結果は、冒頭の通り・・国の敗訴でした・・・
租税法律主義は守られなければならないといった趣旨もあったようです。
租税法律主義は、税金は法律で定めた範疇のなかでしか課税できないといったような内容です。
つまり、課税をするののには、常に法理の根拠が必要となるということです。
この租税法律種主義は憲法に規定されていますので、非常に重要な課税根拠となってきます。
ここで、問題なのは、海外の居住者に対する日本の課税の立法でしょう・・・
正直いって、きりがありません・・・
それでも、相続税法では、納税義務者の条文改正を都度、行っては税の取りこぼし防止を図っています・・・
法律で、定めきてていないグレーな事象はどう、対応するか・・・
これは、課税公平の主義に基づいて、その事実を認めると課税上、著しい不公平が生じるときには、その事実認定で課税することとなってくるわけです。
いわゆる、正直者が損をするといったことを防止していくわけです。
今回の、会長への課税に対して国税側は、入念な調査を行っての結果だったようです。
この会長は、日本と香港以外にも、米国、韓国、豪州など多くの国に滞在していたようです。
国税局は各国の滞在機関を綿密に調査して、日本の滞在期間が香港を大きく上回っていたことを突き止めたうえでの課税だったようです。
いかに、立証するかが、国税局側のポイントとなってきます。
いかに、立証されないようにするかが納税者側のポイントとなってきます。
まさに、いたちごっこ・・・
巧妙な税軽減のスキームや商品が表れてくれば、それを防止する『個別的否認規定』が立法される・・・
そして、それを上回るスキームや商品が表れてくる・・・
海外を利用した税の軽減スキームや商品の今後の展開は、どうなっていくことでしょうか・・・?
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
この記事の内容の概要は次の通りです。
某一部上場企業の会長が、2008年に、代表取締役会長から名誉会長に退いたのちに、東京から香港に転居し、住所を移しました。
その後は、退任した会社から受け取る報酬や株の配当については日本で源泉所得税を納めていたそうです。
ただし、香港や韓国などの海外子会社から受け取る報酬や海外に持つ個人資産の運用益などは、日本での申告をしていなかたそうです。
そして、転居して2年後(2010年6月)には、再度、退任した会社の経営のかじ取りを行うために代表取締役会長に復帰したそうです。
住所は香港のままとし、海外所得の日本での納税は行っていなかったといいます。
ここでポイントとなるのは、同会長は香港移住後も頻繁に来日しては東京の旧自宅を使用し、その日本の滞在日数は香港を大きく上回っていたこと、さらには名誉会長だった時期も役員会で経営方針を示すなどの実質の経営権を握っていたことがあります。
以上のような状況から、東京国税局は生活の本拠は日本の国内にあるとし、海外所得の分も日本で納付すべきであると認定しました。
また、東京国税局は香港では海外で得た所得や株の配当などは非課税で、所得税率も約15%と、最高40%の日本の半分以下になることから、同会長は日本での申告を避けることで、所得税額を減らししたと判断したようです。
同会長の税理士は、香港への移住は会社のグローバル展開などを考えたビジネス上の理由で、税金を逃れるためのものではなかったしていますが、現実的に香港の滞在日数が短かったことは事実なので、国税局の指摘を受け入れたそうです。
この、事実認定による申告漏れの金額は、2011年までの3年間で計約10億円になったようです。
そして、海外での納税額を差し引いた所得税の追徴税額は、無申告加算税を含めて1億数千万円にのぼり、すでに納付されたようです。
今回のケースは、海外に住居を移し、日本の所得税の軽減を図ったものと認定され課税されたケースです。
この東京国税局の事実認定に対して、顧問税理士は、日本の滞在日収が年間の過半を超えていることから、この事実認定を受け入れ税務訴訟等には至らなかったようです。
今回に似たケースである住所は国内にあるとして申告漏れを指摘した『武富士事件』では、最高裁まで争った結果、居住地は『目的)という主観的要素で判断するものではなく、滞在人数など客観的な事実で判断すべきであるとして、国税局の敗訴となり、巨額の課税取り消しで、国は利子分も含めて約2000億円を返還することとなりました。
この武富士事件は、贈与税が対象でしたが、その海外への住所移転は贈与税を免れるためのものとして海外への滞在日数が年間の過半を超えているのにも関わらずに課税したものです。
もっとも、その海外への滞在日数は、顧問の公認会計士等が指導していた事実もあり、その事実も課税の根拠として争いました。
また、その海外の住まいがホテルのような住まいであったということも課税根拠となっていました。
『武富士事件』では、海外滞在が年間の過半を超えていたとしても、その住まいが仮住まい的な寓居であること、海外の滞在日数は、税務の専門家が指導していた事実、等々を課税根拠として争ったわけです。
結果は、冒頭の通り・・国の敗訴でした・・・
租税法律主義は守られなければならないといった趣旨もあったようです。
租税法律主義は、税金は法律で定めた範疇のなかでしか課税できないといったような内容です。
つまり、課税をするののには、常に法理の根拠が必要となるということです。
この租税法律種主義は憲法に規定されていますので、非常に重要な課税根拠となってきます。
ここで、問題なのは、海外の居住者に対する日本の課税の立法でしょう・・・
正直いって、きりがありません・・・
それでも、相続税法では、納税義務者の条文改正を都度、行っては税の取りこぼし防止を図っています・・・
法律で、定めきてていないグレーな事象はどう、対応するか・・・
これは、課税公平の主義に基づいて、その事実を認めると課税上、著しい不公平が生じるときには、その事実認定で課税することとなってくるわけです。
いわゆる、正直者が損をするといったことを防止していくわけです。
今回の、会長への課税に対して国税側は、入念な調査を行っての結果だったようです。
この会長は、日本と香港以外にも、米国、韓国、豪州など多くの国に滞在していたようです。
国税局は各国の滞在機関を綿密に調査して、日本の滞在期間が香港を大きく上回っていたことを突き止めたうえでの課税だったようです。
いかに、立証するかが、国税局側のポイントとなってきます。
いかに、立証されないようにするかが納税者側のポイントとなってきます。
まさに、いたちごっこ・・・
巧妙な税軽減のスキームや商品が表れてくれば、それを防止する『個別的否認規定』が立法される・・・
そして、それを上回るスキームや商品が表れてくる・・・
海外を利用した税の軽減スキームや商品の今後の展開は、どうなっていくことでしょうか・・・?
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年05月18日
備えあれば憂いなし・・・将来の相続にむけて準備しておきたいこと
来年からの相続増税時代に向けて、あらゆるところで相続対策、争続対策、相続税対策といった言葉を見かけるようになる機会がふえてきました。
新聞では、相続増税時代に向けての土地活用のセミナーの広告もまことしやかに目立ってきています・・・
TVでは、相続増税時代に向けた特集番組が組まれています・・・
相続問題は昔から大きなテーマとして存在していわけですが、今までは相続税という税金に関しては毎年の亡くなる方のうち約4%の方が対象となるということもあって、相続税の心配をされる方はごく一部の限られる方であったものが、来年からの基礎控除額の減額によって、都市部の土地の路線価の高い地域では、戸建ての持ち家に住んでいるだけで、その心配が出てくることとなってきました。
今までは、相続税なんて気にしなかったかたでも、都心部の持ち家のかたにとっては、今回の基礎控除額減額は・・・それはそれは・・・気になってくるものでしょう・・・
厄介なのは、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例や、配偶者の相続税額の軽減といった特例規定を適用して相続税額が0円となった場合でも、相続税の期限内申告書の提出が必要となってくることです・・・
小規模宅地等の課税価格計算の特例は、来年の改正以降は、330㎡までは評価額の実に80%もの金額が軽減されることとなります。
例えば、被相続人の居住の用に供していた土地が330㎡で路線価が50万円/㎡の場合だと、敷地形状等の要素を考えないで、そのまま乗じて計算すると1億6千5百万円の評価額となります。
その土地を相続や遺贈で取得した者が、被相続人の配偶者であれば、細かな要件を気にすることなく小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を受けることができます。
また、その土地を相続または遺贈により取得した者が、その被相続人の子供であれば、一定の要件(同居しているか非同居の場合はその子供およびその子供の配偶者の所有している家に相続開始前3年を超えて居住していないこと等の要件が必要。この要件は細かい規定ですので必ずご自身で再度、確認してください)を満たしていることと相続開始から申告期限まで引き続きその住居を取得した者がその住宅に居住していることがその必要な要件となってきます。
とにもかくにも、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用を受けることが、できれば、上記1億6千5百万円の評価額は、その20%の3千3百万円に軽減されます。
これは、例えば、相続税の超過累進税率が20%の場合であったとすると、165,000,000円×80%(軽減分)×20%(超過累進税率)≒16,500,000万円の相続税額が軽減されます。
もしくは、この特例の規定を受けることにより相続税の課税価格が、相続税の基礎控除額以下となれば、相続税の納付額は0円となってきます。
この場合のように、税法の特例規定の適用を受けて、相続税額が0円となる場合には、相続税の期限内申告書の提出が必要となってくるわけです。
これからの相続増税にむけて、まず、確認しておきたいこと・・・
それは、現状で相続税はかかってくるのか、かかるとしたいくらなのか・・・を、概算でいいから、掴んでおきたいところです。
概算とはいえ、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定等の税法の特例規定の適用可否の要件については、きちんとその要件を確認しておきましょう・・・
いざ、相続が発生・・・期限内申告書を提出したら、税法の特例規定の適用が否認されたといったものでは、元も子もありません。
特に、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用については、子供が同居するか否かで、その適用がうけられるか否か、が大きく左右されることとなります。
もちろん、同居していなくても、受けられる要件もありますが、上記でお話した自分や配偶者の持家の居住要件のほかにも、被相続人と同居していた別の親族がいなかったことなども必要要件となりますので、細心の注意が必要です。
こう考えてくると、相続増税に向けて、税額のシミュレーションをして、相続税の状況について確認しておく・・・
そして、その次の段階でその税金対策を考える上では、遺産分割を考えなければならないでしょう・・・
今回の税制改正では、都心部に住宅を所有しているだけでも相続税がかかってきそうな増税となっていますので、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるのか、否か、受けようとした場合のその住宅を引き継ぐ子供を誰にするのか、そしてその住宅を引き継がない子供への遺産分割をどう考えるのか・・・等の心の整理をまずはしてみるべきでしょう。
その考えに沿って、円滑な遺産分割のための遺言書を残しておくとか、代償分割用の資金を生命保険で準備しておくとか・・・等の具体的な対策が考えられるようになってきます。
くれぐれも、この逆の流れはお奨めできません・・・
もっとも、まずいのは、いきなりの節税対策です。
たとえば、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)に余裕があるといって、90歳まで無告知(入院していると不可)で入れる生命保険に加入してしまうといったことは、避けるべきでしょう。
こういった保険を活用することはいいのですが、誰に何を引き継いでいくかによって、保険金の受取人や契約者を考えていく必要があります。
遺産分割の青写真が出来上がる前に、相続対策を目的とした相続対策は、土地活用も含めて控えておいたほうがよろしいでしょう・・・
まずは、相続税はどうなるのを確認してみる・・・当然、その確認には財産の棚卸が必要です・・・
財産の棚卸で自分の財産を、再度、確認してみる・・・
そして、今後の老後の生活に必要な資金ややっておきたいことを書き出してみる・・・
幾らくらいは、自分の手許にのこしておいて、あとは、相続の対策で生前贈与をしてしまうとか、その財産ごとの利用区分もしておくべきでしょう・・・
そうなってくると、ファイナンシャルプランナーにライフプウランの相談をしてみるのもいいかもしれません・・・
以上のような相続の準備や老後の生活のファイナンシャルプランニングをきちんとしておくことで、将来の相続についての心配をすることもなく、充実した老後の生活が送れるのではないでしょうか・・・
何といっても・・・備えあれば憂いなし・・・でしょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
新聞では、相続増税時代に向けての土地活用のセミナーの広告もまことしやかに目立ってきています・・・
TVでは、相続増税時代に向けた特集番組が組まれています・・・
相続問題は昔から大きなテーマとして存在していわけですが、今までは相続税という税金に関しては毎年の亡くなる方のうち約4%の方が対象となるということもあって、相続税の心配をされる方はごく一部の限られる方であったものが、来年からの基礎控除額の減額によって、都市部の土地の路線価の高い地域では、戸建ての持ち家に住んでいるだけで、その心配が出てくることとなってきました。
今までは、相続税なんて気にしなかったかたでも、都心部の持ち家のかたにとっては、今回の基礎控除額減額は・・・それはそれは・・・気になってくるものでしょう・・・
厄介なのは、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例や、配偶者の相続税額の軽減といった特例規定を適用して相続税額が0円となった場合でも、相続税の期限内申告書の提出が必要となってくることです・・・
小規模宅地等の課税価格計算の特例は、来年の改正以降は、330㎡までは評価額の実に80%もの金額が軽減されることとなります。
例えば、被相続人の居住の用に供していた土地が330㎡で路線価が50万円/㎡の場合だと、敷地形状等の要素を考えないで、そのまま乗じて計算すると1億6千5百万円の評価額となります。
その土地を相続や遺贈で取得した者が、被相続人の配偶者であれば、細かな要件を気にすることなく小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を受けることができます。
また、その土地を相続または遺贈により取得した者が、その被相続人の子供であれば、一定の要件(同居しているか非同居の場合はその子供およびその子供の配偶者の所有している家に相続開始前3年を超えて居住していないこと等の要件が必要。この要件は細かい規定ですので必ずご自身で再度、確認してください)を満たしていることと相続開始から申告期限まで引き続きその住居を取得した者がその住宅に居住していることがその必要な要件となってきます。
とにもかくにも、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用を受けることが、できれば、上記1億6千5百万円の評価額は、その20%の3千3百万円に軽減されます。
これは、例えば、相続税の超過累進税率が20%の場合であったとすると、165,000,000円×80%(軽減分)×20%(超過累進税率)≒16,500,000万円の相続税額が軽減されます。
もしくは、この特例の規定を受けることにより相続税の課税価格が、相続税の基礎控除額以下となれば、相続税の納付額は0円となってきます。
この場合のように、税法の特例規定の適用を受けて、相続税額が0円となる場合には、相続税の期限内申告書の提出が必要となってくるわけです。
これからの相続増税にむけて、まず、確認しておきたいこと・・・
それは、現状で相続税はかかってくるのか、かかるとしたいくらなのか・・・を、概算でいいから、掴んでおきたいところです。
概算とはいえ、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定等の税法の特例規定の適用可否の要件については、きちんとその要件を確認しておきましょう・・・
いざ、相続が発生・・・期限内申告書を提出したら、税法の特例規定の適用が否認されたといったものでは、元も子もありません。
特に、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用については、子供が同居するか否かで、その適用がうけられるか否か、が大きく左右されることとなります。
もちろん、同居していなくても、受けられる要件もありますが、上記でお話した自分や配偶者の持家の居住要件のほかにも、被相続人と同居していた別の親族がいなかったことなども必要要件となりますので、細心の注意が必要です。
こう考えてくると、相続増税に向けて、税額のシミュレーションをして、相続税の状況について確認しておく・・・
そして、その次の段階でその税金対策を考える上では、遺産分割を考えなければならないでしょう・・・
今回の税制改正では、都心部に住宅を所有しているだけでも相続税がかかってきそうな増税となっていますので、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるのか、否か、受けようとした場合のその住宅を引き継ぐ子供を誰にするのか、そしてその住宅を引き継がない子供への遺産分割をどう考えるのか・・・等の心の整理をまずはしてみるべきでしょう。
その考えに沿って、円滑な遺産分割のための遺言書を残しておくとか、代償分割用の資金を生命保険で準備しておくとか・・・等の具体的な対策が考えられるようになってきます。
くれぐれも、この逆の流れはお奨めできません・・・
もっとも、まずいのは、いきなりの節税対策です。
たとえば、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)に余裕があるといって、90歳まで無告知(入院していると不可)で入れる生命保険に加入してしまうといったことは、避けるべきでしょう。
こういった保険を活用することはいいのですが、誰に何を引き継いでいくかによって、保険金の受取人や契約者を考えていく必要があります。
遺産分割の青写真が出来上がる前に、相続対策を目的とした相続対策は、土地活用も含めて控えておいたほうがよろしいでしょう・・・
まずは、相続税はどうなるのを確認してみる・・・当然、その確認には財産の棚卸が必要です・・・
財産の棚卸で自分の財産を、再度、確認してみる・・・
そして、今後の老後の生活に必要な資金ややっておきたいことを書き出してみる・・・
幾らくらいは、自分の手許にのこしておいて、あとは、相続の対策で生前贈与をしてしまうとか、その財産ごとの利用区分もしておくべきでしょう・・・
そうなってくると、ファイナンシャルプランナーにライフプウランの相談をしてみるのもいいかもしれません・・・
以上のような相続の準備や老後の生活のファイナンシャルプランニングをきちんとしておくことで、将来の相続についての心配をすることもなく、充実した老後の生活が送れるのではないでしょうか・・・
何といっても・・・備えあれば憂いなし・・・でしょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年05月15日
悩ましい相続増税・・・その対策どうしようか・・・
いま、TV東京のニュースを観ていました。
そのニュースでは、相続増税の特集が組まれていました。
都内在住の戸建て住宅に住んでいるごくごく普通の方が出演されいました。
都内の戸建て住宅に住んでいるだけで、今年中は相続税がかからないものの改正後には相続税がかかってくる可能性は高いでしょう。
そんな方たちが信託銀行や生命保険会社のセミナーに参加しては、何とか納税を0にするか0とまではいかないまでも、少しでも少なくしたいと真剣に話を聞いている姿が印象的でした。
そんな出演者の方のお一人の体験のお話がありました。
親御さんの相続の遺産分割で苦労された話から、今度は自分の相続の心配の話をされていました。
何とか、相続税0円で引き継がせたいね、これから、いろいろ勉強して研究しなければというコメントが印象的でした。
そうです・・・
やはり、税金の負担はかけたくないのだなと感じました・・・
きれいごとでいえば、国民としての納税の義務を免れたいのか・・・という見方もあるかもしれませんが・・・
税法の特例等を上手につかって税法の規定に基づいて納税額をなくすのは、節税という国で認められたものですので、できうる限りの節税の方法を知恵を絞って考えに考え抜いて、納税の負担を少なくするのは当然の権利であると考えます。
ここで、大事なのは、再三申し上げてることですが、財産のきちんとした現状分析を行ったうえで、推定相続人への遺産分割や納税がある場合の納税方法も考えながら節税を考えていくことと・・・
まずは、税金を下げられる税法の特例等の規定の適用を考えてみることでしょう。
生前贈与を上手に活用する・・・
教育資金や住宅取得資金の贈与を上手に活用する・・・
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用要件を確認しておく・・・
その他、土地や建物の財産評価の工夫で下げる余地がないか検討してみる・・・
等々の基本的なことを抑えてみましょう・・・
上記の中でも、小規模宅地等の課税価格計算の特例は、住宅用敷地330㎡までは、実に80%もの評価額の軽減ができることとなります。
ただし、同居している場合、していない場合等の細かい適用要件がありますので、きちんと専門家等に確認しておいたほうが無難です。
また、生命保険を使った節税では、生命保険金の非課税枠として500万円×法定相続人の数があります。
つまり、相続人が奥さん、子供2人の3人の場合は1500万円までの死亡保険金は非課税となります。
体調が思わしくない方でも90歳まで無告知(入院していると不可の場合があります)で入れる生命保険金も出てきましたので、生命保険金の非課税枠に余裕のある方は、考えてみてもいいかもしれません・・・
生前贈与や小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定、生命保険の活用・・・等々、将来の相続対策として気になるかたは、下記連絡先(電話、FAX、メール)にご連絡ください。
まずは、電話やメール等で、疑問点等にお答えさせていただきます。
また、財産の現状分析(有料ですが)も承っておりますので、どんなことをされるのか気になる方も、ご遠慮なくご連絡ください。
まずは、その目的とその内容や費用等のご説明をさせていただきます。
相続増税まで、残すところ、あと7カ月強・・・
備えあれば憂いなしです・・・
早めの対応をお奨めします・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
そのニュースでは、相続増税の特集が組まれていました。
都内在住の戸建て住宅に住んでいるごくごく普通の方が出演されいました。
都内の戸建て住宅に住んでいるだけで、今年中は相続税がかからないものの改正後には相続税がかかってくる可能性は高いでしょう。
そんな方たちが信託銀行や生命保険会社のセミナーに参加しては、何とか納税を0にするか0とまではいかないまでも、少しでも少なくしたいと真剣に話を聞いている姿が印象的でした。
そんな出演者の方のお一人の体験のお話がありました。
親御さんの相続の遺産分割で苦労された話から、今度は自分の相続の心配の話をされていました。
何とか、相続税0円で引き継がせたいね、これから、いろいろ勉強して研究しなければというコメントが印象的でした。
そうです・・・
やはり、税金の負担はかけたくないのだなと感じました・・・
きれいごとでいえば、国民としての納税の義務を免れたいのか・・・という見方もあるかもしれませんが・・・
税法の特例等を上手につかって税法の規定に基づいて納税額をなくすのは、節税という国で認められたものですので、できうる限りの節税の方法を知恵を絞って考えに考え抜いて、納税の負担を少なくするのは当然の権利であると考えます。
ここで、大事なのは、再三申し上げてることですが、財産のきちんとした現状分析を行ったうえで、推定相続人への遺産分割や納税がある場合の納税方法も考えながら節税を考えていくことと・・・
まずは、税金を下げられる税法の特例等の規定の適用を考えてみることでしょう。
生前贈与を上手に活用する・・・
教育資金や住宅取得資金の贈与を上手に活用する・・・
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用要件を確認しておく・・・
その他、土地や建物の財産評価の工夫で下げる余地がないか検討してみる・・・
等々の基本的なことを抑えてみましょう・・・
上記の中でも、小規模宅地等の課税価格計算の特例は、住宅用敷地330㎡までは、実に80%もの評価額の軽減ができることとなります。
ただし、同居している場合、していない場合等の細かい適用要件がありますので、きちんと専門家等に確認しておいたほうが無難です。
また、生命保険を使った節税では、生命保険金の非課税枠として500万円×法定相続人の数があります。
つまり、相続人が奥さん、子供2人の3人の場合は1500万円までの死亡保険金は非課税となります。
体調が思わしくない方でも90歳まで無告知(入院していると不可の場合があります)で入れる生命保険金も出てきましたので、生命保険金の非課税枠に余裕のある方は、考えてみてもいいかもしれません・・・
生前贈与や小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定、生命保険の活用・・・等々、将来の相続対策として気になるかたは、下記連絡先(電話、FAX、メール)にご連絡ください。
まずは、電話やメール等で、疑問点等にお答えさせていただきます。
また、財産の現状分析(有料ですが)も承っておりますので、どんなことをされるのか気になる方も、ご遠慮なくご連絡ください。
まずは、その目的とその内容や費用等のご説明をさせていただきます。
相続増税まで、残すところ、あと7カ月強・・・
備えあれば憂いなしです・・・
早めの対応をお奨めします・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年04月27日
資産防衛のための対策につながる不動産調査のあれこれ②・・・
資産防衛のためには、財産の大半を占める不動産の調査や分析は不可欠です・・・
不動産を数多く所有する地主さんも不動産は自宅のみといったかたにも、その調査や分析は重要なこととなります・・・
その調査や分析は、何を知り得るために行いたいのか・・・何を目的とするのか・・・
その第一は、その不動産の現状の価値を知る・・・極論、いくらで売れるものであるのか、換価するとキャッシュは手許にいくら入ってくるのか・・・または、土地活用した場合に毎年毎年いくらの収入が見込めるのか、その収入は売却できる金額に対してどの程度の利回りとなってくるのか等の投資効率を、改めて認識してみることでしょう。
その価値を知ることは、何のために必要となってくるのか・・・
遺産分割で考えた場合、国債等の債権や上場株のように相場が決まっていない不動産は、相続人間でその価値を話あってその価値を協議していきます。
法定相続分での分割を前提としている場合、その不動産の価値の金額如何で、遺産分割で取得できる相続財産が変わってきます。
不動産を取得する相続人は、不動産の価値は低い方を望むでしょうし、それ以外の相続人は不動産の価値は高いことを望むでしょう。
このようなことが、遺産分割が纏まりにくい一つの要因ともなっているようです・・・
不動産は自宅のみといった場合等で、相続財産のうちに占めるその自宅の価値の割合が実に7割や8割を占めるといったようなとき、その自宅は長男に引き継がせる場合、その自宅の価値を算出してその他の相続財産の価値との合計額を見据えて、それぞれの子供への分割を、生前に考えておくべきでしょう・・・
長男には自宅、その自宅は相続財産の実に8割を占めている、子供は他に二男と三男・・・二人合わせた遺留分は1/3・・・
遺言書を遺したとしても遺留分の不足分は、代償分割等で手当てしなければなりません・・・
ここで、その自宅という不動産の価値をいくらで設定して遺留分を考えておくべきか・・・
このようなためにも、不動産の価値を知ってておくことが必要となってきます。
不動産を数多く所有している方の場合は、将来の資産防衛のために、やはり①遺産分割対策、②納税資金対策、③節税対策、等々、優先順位は①から③の順と言われていますが、同時並行的に進めていく必要があります・・・
不動産が数多くあれば、各相続人にそれなりに財産分与は出来ることとなりますので、どのように分けていくかを考えて遺留分を考慮した遺言書を遺して、時には代償分割等の手当てを考えておけば、円満とならずとも円滑な遺産分割で終えることはできるでしょう・・・
その遺産分割対策(争族対策)を考えるには、やはりきちんとした調査に基づく不動産の価値が分かっていたいところです・・・
駅近とロードサイドの商業用施設2つを子供2人にそれぞれ分けるといった場合、一つの商業施設は駅に近く土地の価格が高いことからその他の金融資産等の相続財産は少なめとして一人の子供が貰うこととし、もう1人の子供は駅から離れた土地の価格の低い商業施設であることからその他の金融資産等の相続財産を多く貰うこととした遺言書が遺されていたとします。
実は、その2つの商業施設は、駅に近いものは老朽化していることと駅前シャッター通りの影響も受けて賃料は大幅に下落している、反対に駅から離れたロードサイドの商業施設は車の往来が激しく大いに流行っており賃料は安定している、といった場合、公示価格等の土地の価額だけではその土地の価値を適正にあらわせるものではないでしょう。
商業施設を止めた時点での、キャピタルゲインは駅に近い土地の方が高いかもしれませんが、商業施設として利用している期間のインカムゲインの累計額でそのキャピタルゲインの差額が大きく逆転することも考えられます。
このように、土地の価値は、キャピタルゲインとインカムゲインの両面で将来性をも考慮したうえで算定していくべきでしょう。
その点を怠ると、一見すると平等に考えたはずの遺産分割が、実は、大いに不公平なものとなってしまうかもしれません。
円滑な遺産分割はできるでしょうが、円満にはなりえないかもしれません・・・
また、資産防衛の観点から考えると、土地の価値を公示価格等の値段というもののみで捉えるのではなくて、上段と同様にその活用の状況に拠っての優劣やその将来性を考慮して捉えるべきでしょう・・・
数多くの土地を所有していると当然に、相続税の納税を憂慮しなければなりません。
また、ただの更地で稼げない土地であっても固定資産税等の経費は、毎年かかってくるものですから、土地のリストラ計画も必要となるでしょう・・・稼げない土地は売れるときに売ってその他の稼げる資産に移転していく等・・・以外に・・・本人にとって稼げない土地もその土地の近隣の方にとっては価値のある土地であったりもします。
それで、土地の価値を知るための調査は何・・・といった場合、それは当たり前の調査をするしかないでしょう・・・
都市計画や建築基準法等の法令上の制限を確認する・・・
市街化区域、調整区域、非線引き区域等・・・用途地域、高度地区、特定街区、風致地区等・・・道路制限など・・・
それぞれの土地ごとのかかっている制限の確認が必要です。
道路のセットバックの有無、建てられるもの、建てられないもの、建てられる階数や面積、隣家の火事に備える防火基準、斜線制限による高さの制限等々・・・数え上げたら書ききれなくなってきます。
そして、立地や環境、駅から何分、小学校や中学校まで何分、学区の小中学校の人気(県内一の進学校への進学率の高い公立中学校等)によって価格が変わる場合もあります、そしてスーパーやコンビニ等の商業施設や病院までの距離等々、がその価格に跳ね返ってきます・・・
そして、その土地ごとのその家族にとっての価値も計るべきでしょう・・・
優良な住宅地にある土地、売りに出せば住宅用地としてすぐ売れてしまうほどの人気がある・・・
だけど、住宅は既に所有しているので住宅は必要ない・・・ではその土地に有効活用といった場合、駅から15分も離れた静かな住宅地のため、余り有効活用に適しないといったケースもあるでしょう・・・
他の人にとっては、とても貴重な土地でも本人にとっては売りやすい土地というだけで・・・稼げないといったことがあるわけです。
このような土地は、すぐ売却できるわけですから、子供の住宅用地に充てたいとかいった目的が無い場合は、相続税の納税資金用として青空駐車場としておくのも良いかもしれません・・・
このようにして調査や分析を重ねて、残していきたい土地(自宅や活用)、相続税の納税用とする土地、売れるものならすぐ売却して組み替えたい土地、等に整理して来るべき相続に備えておくべきでしょう。
もちろん、遺産分割のことも考えながらです・・・
そして土地の価値の他の不動産調査の目的は不動産に関連する税金を押さえておくということでしょう・・・
不動産に関連する税金・・・売却すれば個人であれば譲渡所得として所得税、法人であれば法人税が課税されることとなります。
これは、基本的には売買という経済行為がともなって発生するものですから、不動産の代わりに現金が手許に入ってきますので原則、納税の資金には困りません・・・いわゆる担税力があるということです。
それに反して、不動産を所有しているだけでかかってくる税金の代表は固定資産税、そして相続税・・・相続税は家単位でいえば所有しているだけという概念となるのですが個人単位で考えることから親から子に財産が無償で移転したという事実に基づいて・・・子供の財産が無償で増えたという事実に課税するもののようです。
この固定資産税や相続税での悩みや問題は税金を納める原資がないといった場合が大いにありえることです・・・
稼げない土地にも、固定資産税や相続税は課税されてきます。
それも、稼げない更地であればあるほど、税金は高く算出されます。
この事実に便乗じてのアパートやマンション建築の営業が盛んにおこなわれています。
アパートやマンションを建てると税金が安くなりますとの営業トークで、新駅の周辺は新築アパートやマンションが目白押しです。
駅から歩10分以内の立地であれば将来の空室リスクは少ないでしょうが、歩10分を超えてくると築10年も超えてくると競争力の低下から空室リスクは高いものとなってくるでしょう・・・
ここで、注意したいのは駅から10分も超える立地のアパート等の建築は、相続税は実際いくらかかってくるのかを確認し、その納税資金ははいかに手当できるかを検証しながら考えるべきでしょう・・・
空室リスクを負ってまでも、アパート建築による相続税の軽減を図るべきであるのか・・・否か・・・を判断すべきでしょう。
もしかしたら、その他の土地の利用区分を工夫した不整形地等の評価で何とか満足いく節税が可能となるということもありえます。
このように、全体的な調査と分析をきちんとおこなったうえで、全体的なバランスを観ながら・・・リスクを伴った事業計画は練っていくべきでしょう・・・
資産防衛のための対策を練っていくうえでは、不動産の調査と分析はやってもやり過ぎるということは無いのではないでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
不動産を数多く所有する地主さんも不動産は自宅のみといったかたにも、その調査や分析は重要なこととなります・・・
その調査や分析は、何を知り得るために行いたいのか・・・何を目的とするのか・・・
その第一は、その不動産の現状の価値を知る・・・極論、いくらで売れるものであるのか、換価するとキャッシュは手許にいくら入ってくるのか・・・または、土地活用した場合に毎年毎年いくらの収入が見込めるのか、その収入は売却できる金額に対してどの程度の利回りとなってくるのか等の投資効率を、改めて認識してみることでしょう。
その価値を知ることは、何のために必要となってくるのか・・・
遺産分割で考えた場合、国債等の債権や上場株のように相場が決まっていない不動産は、相続人間でその価値を話あってその価値を協議していきます。
法定相続分での分割を前提としている場合、その不動産の価値の金額如何で、遺産分割で取得できる相続財産が変わってきます。
不動産を取得する相続人は、不動産の価値は低い方を望むでしょうし、それ以外の相続人は不動産の価値は高いことを望むでしょう。
このようなことが、遺産分割が纏まりにくい一つの要因ともなっているようです・・・
不動産は自宅のみといった場合等で、相続財産のうちに占めるその自宅の価値の割合が実に7割や8割を占めるといったようなとき、その自宅は長男に引き継がせる場合、その自宅の価値を算出してその他の相続財産の価値との合計額を見据えて、それぞれの子供への分割を、生前に考えておくべきでしょう・・・
長男には自宅、その自宅は相続財産の実に8割を占めている、子供は他に二男と三男・・・二人合わせた遺留分は1/3・・・
遺言書を遺したとしても遺留分の不足分は、代償分割等で手当てしなければなりません・・・
ここで、その自宅という不動産の価値をいくらで設定して遺留分を考えておくべきか・・・
このようなためにも、不動産の価値を知ってておくことが必要となってきます。
不動産を数多く所有している方の場合は、将来の資産防衛のために、やはり①遺産分割対策、②納税資金対策、③節税対策、等々、優先順位は①から③の順と言われていますが、同時並行的に進めていく必要があります・・・
不動産が数多くあれば、各相続人にそれなりに財産分与は出来ることとなりますので、どのように分けていくかを考えて遺留分を考慮した遺言書を遺して、時には代償分割等の手当てを考えておけば、円満とならずとも円滑な遺産分割で終えることはできるでしょう・・・
その遺産分割対策(争族対策)を考えるには、やはりきちんとした調査に基づく不動産の価値が分かっていたいところです・・・
駅近とロードサイドの商業用施設2つを子供2人にそれぞれ分けるといった場合、一つの商業施設は駅に近く土地の価格が高いことからその他の金融資産等の相続財産は少なめとして一人の子供が貰うこととし、もう1人の子供は駅から離れた土地の価格の低い商業施設であることからその他の金融資産等の相続財産を多く貰うこととした遺言書が遺されていたとします。
実は、その2つの商業施設は、駅に近いものは老朽化していることと駅前シャッター通りの影響も受けて賃料は大幅に下落している、反対に駅から離れたロードサイドの商業施設は車の往来が激しく大いに流行っており賃料は安定している、といった場合、公示価格等の土地の価額だけではその土地の価値を適正にあらわせるものではないでしょう。
商業施設を止めた時点での、キャピタルゲインは駅に近い土地の方が高いかもしれませんが、商業施設として利用している期間のインカムゲインの累計額でそのキャピタルゲインの差額が大きく逆転することも考えられます。
このように、土地の価値は、キャピタルゲインとインカムゲインの両面で将来性をも考慮したうえで算定していくべきでしょう。
その点を怠ると、一見すると平等に考えたはずの遺産分割が、実は、大いに不公平なものとなってしまうかもしれません。
円滑な遺産分割はできるでしょうが、円満にはなりえないかもしれません・・・
また、資産防衛の観点から考えると、土地の価値を公示価格等の値段というもののみで捉えるのではなくて、上段と同様にその活用の状況に拠っての優劣やその将来性を考慮して捉えるべきでしょう・・・
数多くの土地を所有していると当然に、相続税の納税を憂慮しなければなりません。
また、ただの更地で稼げない土地であっても固定資産税等の経費は、毎年かかってくるものですから、土地のリストラ計画も必要となるでしょう・・・稼げない土地は売れるときに売ってその他の稼げる資産に移転していく等・・・以外に・・・本人にとって稼げない土地もその土地の近隣の方にとっては価値のある土地であったりもします。
それで、土地の価値を知るための調査は何・・・といった場合、それは当たり前の調査をするしかないでしょう・・・
都市計画や建築基準法等の法令上の制限を確認する・・・
市街化区域、調整区域、非線引き区域等・・・用途地域、高度地区、特定街区、風致地区等・・・道路制限など・・・
それぞれの土地ごとのかかっている制限の確認が必要です。
道路のセットバックの有無、建てられるもの、建てられないもの、建てられる階数や面積、隣家の火事に備える防火基準、斜線制限による高さの制限等々・・・数え上げたら書ききれなくなってきます。
そして、立地や環境、駅から何分、小学校や中学校まで何分、学区の小中学校の人気(県内一の進学校への進学率の高い公立中学校等)によって価格が変わる場合もあります、そしてスーパーやコンビニ等の商業施設や病院までの距離等々、がその価格に跳ね返ってきます・・・
そして、その土地ごとのその家族にとっての価値も計るべきでしょう・・・
優良な住宅地にある土地、売りに出せば住宅用地としてすぐ売れてしまうほどの人気がある・・・
だけど、住宅は既に所有しているので住宅は必要ない・・・ではその土地に有効活用といった場合、駅から15分も離れた静かな住宅地のため、余り有効活用に適しないといったケースもあるでしょう・・・
他の人にとっては、とても貴重な土地でも本人にとっては売りやすい土地というだけで・・・稼げないといったことがあるわけです。
このような土地は、すぐ売却できるわけですから、子供の住宅用地に充てたいとかいった目的が無い場合は、相続税の納税資金用として青空駐車場としておくのも良いかもしれません・・・
このようにして調査や分析を重ねて、残していきたい土地(自宅や活用)、相続税の納税用とする土地、売れるものならすぐ売却して組み替えたい土地、等に整理して来るべき相続に備えておくべきでしょう。
もちろん、遺産分割のことも考えながらです・・・
そして土地の価値の他の不動産調査の目的は不動産に関連する税金を押さえておくということでしょう・・・
不動産に関連する税金・・・売却すれば個人であれば譲渡所得として所得税、法人であれば法人税が課税されることとなります。
これは、基本的には売買という経済行為がともなって発生するものですから、不動産の代わりに現金が手許に入ってきますので原則、納税の資金には困りません・・・いわゆる担税力があるということです。
それに反して、不動産を所有しているだけでかかってくる税金の代表は固定資産税、そして相続税・・・相続税は家単位でいえば所有しているだけという概念となるのですが個人単位で考えることから親から子に財産が無償で移転したという事実に基づいて・・・子供の財産が無償で増えたという事実に課税するもののようです。
この固定資産税や相続税での悩みや問題は税金を納める原資がないといった場合が大いにありえることです・・・
稼げない土地にも、固定資産税や相続税は課税されてきます。
それも、稼げない更地であればあるほど、税金は高く算出されます。
この事実に便乗じてのアパートやマンション建築の営業が盛んにおこなわれています。
アパートやマンションを建てると税金が安くなりますとの営業トークで、新駅の周辺は新築アパートやマンションが目白押しです。
駅から歩10分以内の立地であれば将来の空室リスクは少ないでしょうが、歩10分を超えてくると築10年も超えてくると競争力の低下から空室リスクは高いものとなってくるでしょう・・・
ここで、注意したいのは駅から10分も超える立地のアパート等の建築は、相続税は実際いくらかかってくるのかを確認し、その納税資金ははいかに手当できるかを検証しながら考えるべきでしょう・・・
空室リスクを負ってまでも、アパート建築による相続税の軽減を図るべきであるのか・・・否か・・・を判断すべきでしょう。
もしかしたら、その他の土地の利用区分を工夫した不整形地等の評価で何とか満足いく節税が可能となるということもありえます。
このように、全体的な調査と分析をきちんとおこなったうえで、全体的なバランスを観ながら・・・リスクを伴った事業計画は練っていくべきでしょう・・・
資産防衛のための対策を練っていくうえでは、不動産の調査と分析はやってもやり過ぎるということは無いのではないでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年04月23日
資産防衛のための対策につながる不動産調査のあれこれ・・・
将来の相続に備えて、少しでも資産の防衛が出来るように、遺産分割や納税、節税等の方策を考える必要があります。
資産防衛で、まず、やるべきこと・・・
まずは相続税を始めとした納税によるキャッシュアウトを防衛したい・・・
一番には、税法の特例規定を、使い切ることが重要です。
広大地の特例、相続税の小規模宅地等の課税価格の計算の特例、農地や非上場株式の納税猶予、相続税の配偶者の軽減、住宅取得資金の贈与の非課税、教育資金の贈与の非課税、暦年贈与の非課税、生命保険金等の非課税、退職手当金等の非課税、等々・・・要件を満たせば課税の対象外となります。
例えば、貸家オーナーのお祖父ちゃんの場合、小規模企業共済に加入して、毎年の家賃収入を現預金で残すものから死亡退職金として残すものに切り替えることにより、500万円×法定相続人の数で計算された金額相当分が相続税の計算上は非課税の扱いとなって課税価格に算入しなくて済みます。
また、90歳まで無告知で加入できる一時金で加入できる生命保険の商品もありますので、生命保険金等の非課税(500万円×法定相続人の数)の枠に余裕がある方は、80歳を過ぎても病歴に関係なく(原則、入院していなければOK)加入できますので、このような金融商品で相続税の非課税の規定を上手に利用するのも効果的です。
生前の暦年贈与の非課税も効率的に利用すべきでしょう・・・
毎年、110万円までの贈与は非課税となりますので、子供、孫を含めて例えば6人の直系卑属がいる場合、毎年660万円までの贈与が非課税となりますので、計画的に贈与の非課税は利用するのも効果的な対策です。
もっとも、生前に贈与で現預金等を渡してしまうと、安心して使われてしまうこともありますので、生命保険等に加入させてほうがいいかも知れません、また、生前贈与の加算にも注意が必要です。
まずは、税法の特例に何があるかを知って、使える特例は使っていく、使えるようにしておく、ということがリスクのない節税対策となりますので、先ずは検討しておくことが重要です。
そして、遺産分割を考えて、できれば遺言書(無難的には公正証書遺言)を遺しておくことも考えるべきでしょう。
上段でお話しました税法の特例のなかには、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10月以内)までの遺産分割が纏まってうないと使えないもの(小規模宅地等や配偶者の税額軽減等)もあります。
農地等の納税猶予を除いては、申告期限から3年以内に遺産分割がまとまれば、遡ってその特例が適用でき更正の請求が提出できるものもありますが、一度は納税しなければなりません。
このように、そもそも論として遺産分割で躓いてしまうと、せっかくの税法の特例の適用が受けられなくなってしまうものがありますので、円滑な遺産分割のための手立てはしておいてあげるべきでしょう。
円滑な遺産分割が、資産防衛のためにも大事なキーポイントとなってきます。
そして、相続税の納税に充てられる金融資産が無いときには、納税に備えた資金計画をたてておくべきです。
相続財産のうちに占める財産の多数が不動産である場合は、特にその納税計画を考えておくことは重要です。
自宅や子供や孫の住宅用の土地もしくは活用して稼いでもらう土地等の残しておきたい土地、将来の納税用にいつでも売却できるようにしておく土地、固定資産税ばかりかかって稼げない売却できるならすぐ売却したい土地、等々の仕分けを行って、売却や土地活用から上がってくる収入での納税計画を立てていくことが重要です。
ここで、土地活用を考えていくうえでは、節税にもつながりますし、土地活用のためにした借入金の返済リスクを負うことにもなりますので、慎重な計画が重要なこととなります。
アパートをたてれば、土地や建物の相続税の財産評価額の計算上、節税効果が期待できることとなります。
相続税は下げられるものの、肝心のアパートの経営が行き詰るとアパートの建築資金の返済に詰まってしまい、借入金返済のためにアパートやその他の不動産まで売却しかねないといったことも起こりえます。
そのような事態に陥らないためには、遺産分割や納税計画、土地活用や保険の活用等の相続対策を考えるうえで、全ての不動産の調査・分析がとても重要です。
その不動産調査とは、どのようなことを行っているのか・・・
①不動産の価値をしること(いくらで売れるものなのか・・・いくら稼げるものなのか・・・)
②不動産を所有していることによる将来を含めた税金の負担(不動産を所有することでいくら負担が生じるのか・・・)
大きくは・・・この2点を調べていくだけのことでしょう・・・
具体的な不動産調査のお話は、次回にお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
資産防衛で、まず、やるべきこと・・・
まずは相続税を始めとした納税によるキャッシュアウトを防衛したい・・・
一番には、税法の特例規定を、使い切ることが重要です。
広大地の特例、相続税の小規模宅地等の課税価格の計算の特例、農地や非上場株式の納税猶予、相続税の配偶者の軽減、住宅取得資金の贈与の非課税、教育資金の贈与の非課税、暦年贈与の非課税、生命保険金等の非課税、退職手当金等の非課税、等々・・・要件を満たせば課税の対象外となります。
例えば、貸家オーナーのお祖父ちゃんの場合、小規模企業共済に加入して、毎年の家賃収入を現預金で残すものから死亡退職金として残すものに切り替えることにより、500万円×法定相続人の数で計算された金額相当分が相続税の計算上は非課税の扱いとなって課税価格に算入しなくて済みます。
また、90歳まで無告知で加入できる一時金で加入できる生命保険の商品もありますので、生命保険金等の非課税(500万円×法定相続人の数)の枠に余裕がある方は、80歳を過ぎても病歴に関係なく(原則、入院していなければOK)加入できますので、このような金融商品で相続税の非課税の規定を上手に利用するのも効果的です。
生前の暦年贈与の非課税も効率的に利用すべきでしょう・・・
毎年、110万円までの贈与は非課税となりますので、子供、孫を含めて例えば6人の直系卑属がいる場合、毎年660万円までの贈与が非課税となりますので、計画的に贈与の非課税は利用するのも効果的な対策です。
もっとも、生前に贈与で現預金等を渡してしまうと、安心して使われてしまうこともありますので、生命保険等に加入させてほうがいいかも知れません、また、生前贈与の加算にも注意が必要です。
まずは、税法の特例に何があるかを知って、使える特例は使っていく、使えるようにしておく、ということがリスクのない節税対策となりますので、先ずは検討しておくことが重要です。
そして、遺産分割を考えて、できれば遺言書(無難的には公正証書遺言)を遺しておくことも考えるべきでしょう。
上段でお話しました税法の特例のなかには、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10月以内)までの遺産分割が纏まってうないと使えないもの(小規模宅地等や配偶者の税額軽減等)もあります。
農地等の納税猶予を除いては、申告期限から3年以内に遺産分割がまとまれば、遡ってその特例が適用でき更正の請求が提出できるものもありますが、一度は納税しなければなりません。
このように、そもそも論として遺産分割で躓いてしまうと、せっかくの税法の特例の適用が受けられなくなってしまうものがありますので、円滑な遺産分割のための手立てはしておいてあげるべきでしょう。
円滑な遺産分割が、資産防衛のためにも大事なキーポイントとなってきます。
そして、相続税の納税に充てられる金融資産が無いときには、納税に備えた資金計画をたてておくべきです。
相続財産のうちに占める財産の多数が不動産である場合は、特にその納税計画を考えておくことは重要です。
自宅や子供や孫の住宅用の土地もしくは活用して稼いでもらう土地等の残しておきたい土地、将来の納税用にいつでも売却できるようにしておく土地、固定資産税ばかりかかって稼げない売却できるならすぐ売却したい土地、等々の仕分けを行って、売却や土地活用から上がってくる収入での納税計画を立てていくことが重要です。
ここで、土地活用を考えていくうえでは、節税にもつながりますし、土地活用のためにした借入金の返済リスクを負うことにもなりますので、慎重な計画が重要なこととなります。
アパートをたてれば、土地や建物の相続税の財産評価額の計算上、節税効果が期待できることとなります。
相続税は下げられるものの、肝心のアパートの経営が行き詰るとアパートの建築資金の返済に詰まってしまい、借入金返済のためにアパートやその他の不動産まで売却しかねないといったことも起こりえます。
そのような事態に陥らないためには、遺産分割や納税計画、土地活用や保険の活用等の相続対策を考えるうえで、全ての不動産の調査・分析がとても重要です。
その不動産調査とは、どのようなことを行っているのか・・・
①不動産の価値をしること(いくらで売れるものなのか・・・いくら稼げるものなのか・・・)
②不動産を所有していることによる将来を含めた税金の負担(不動産を所有することでいくら負担が生じるのか・・・)
大きくは・・・この2点を調べていくだけのことでしょう・・・
具体的な不動産調査のお話は、次回にお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年04月18日
遺産分割と納税に備えた不動産調査について・・・
来年からの相続税法改正(基礎控除額が現行の60%に改正他)にむけて、銀行、信託銀行、生保会社、建築会社、デベロッパー等々・・・個人の財産に絡んでくるあらゆる業種や業態の会社が、こぞって相続対策を売り文句とした営業戦略をたてているような感じがします。
相続対策・・・相続と言えば・・・税金・・・相続税といえば一部の資産家の悩むものと思われがちですが、実際は税金に関係ない遺産分割での悩みが深刻なものとなってきます。
兄弟間で親の遺した財産をめぐっての争いがおきた場合、その話し合いの収拾は困難を極めることとなってきます。
多くの財産があるからもめるのか・・・
実は、家庭裁判所への相続の調停申し込みは、相続財産5000万円以下の人の割合が70%を超えるといったデーターもあるように、相続税がかかってくる人のみが心配なのではなく、むしろ、相続税がかかってこない人のほうが遺産分割が纏まらないといった結果となっています。
この要因としては、相続財産の内訳に占める割合として金融資産に比べて不動産の比率が高いことがあるかもしれません。
国税庁の資料では、相続財産のうち不動産(土地+家屋)の占める割合は、約57%(平成21年)となっています。
あくまで、これは、全国平均値さらには路線価ベースでの対比です。
これが、公示価格や実勢相場(路線価は公示価格の約80%で評価)で対比した場合、さらに東京や大阪といった都心部である場合は、その対比は70%をゆうに超えてくるものかもしれません・・・
相続財産のうちに不動産の割合が多いということは、兄弟間で均等に分けるのが難しいからです。
昔は、均等に分筆して分けるのが困難な場合は、均等に共有持分で分割しているケースは多く見受けられました。
そして、50年後には、その共有者は、30人をこえ会ったことも見たことも無い遠い親族と共有している事となってしまいます。
現に、2世帯住居(建物は親との共有持分)を親の土地に建てて住んでいた長男が、母の2次相続で2世帯住宅の土地の分を含めた相続財産の均等分割を要求され、どうにもならずに2世帯住宅を売却して換価分割した例もあります。
また、相続税がかかってくるといった場合、その相続財産の殆どが不動産、相続税を支払える金融資産が無いといった場合、手持ちの不動産を売却して相続税を納める必要がでてきます。
相続の開始後(被相続人の死亡を知った日の翌日)10カ月以内に相続税を計算して国に納付しなければなりません・・・
その時に、すぐ、売却できる土地はなにかです・・・
貸家や賃貸マンションが建っている場合、新しければまだしも、老朽化していた場合は買手は更地での売買を希望するでしょう。
賃借人がいると立退きの交渉が必要となってきます。
そのまま、賃借人つき、オーナチェンジで購入してくれればいいですが、買手が新築前提で考えている場合、ありえない話でしょう。
急な相続でそんな局面に立たされた場合、売却できる土地はどれか・・・たまたま、一番条件のいい虎の子とも言うべき土地の賃貸借契約が完了し、すぐ売却できる状況であったため、その虎の子の土地を売却して相続税を支払ったというケースもあります。
上記のようにならないためには、あらかじめ、長男との2世帯住居を建てるときに遺言書を遺しておくこと、さらには、遺言書があっても遺留分の権利はありますので、不動産の実勢相場をきちんと把握して、遺留分相当額を長男が代償して支払える準備はしておくべきでしょう・・・
ここで、必要なのは、遺産分割での不動産の価格を、どう想定しておくかでしょう・・・
実際の遺産分割では、相続人間でその価格を話会いで決めていきます。
いま、売ったらいくらで売れる・・・といった実勢相場から路線価や固定資産税評価額まで様々な価格があります。
いわゆる一物四価と呼ばれるもので、①固定資産税評価額、②路線価、③公示価格・基準地価格、④実勢相場の4つです。
①から④に行くに従って、高い水準の価格となってきます・・・
それぞれの価格を算出して、他の財産の価格も考慮しながら遺される方が自分で判断していくほかないでしょう・・・
また、納税にあたっては、いつ、相続が発生しても慌てずに納税できる準備はしておくべきでしょう・・・
そのためには、相続税のシミュレーションをして、いくら支払う予定なのかを把握して、手持ちの不動産のうち納税用に売却しても惜しくない不動産を選定しておくべきでしょう。
そして、すぐ、売れるように駐車場等にしておく等の対策が必要です。
この場合は、手持ちの不動産の全てを改めて見直して、残すもの、売却してもいいもの、等に振り分けておくべきでしょう。
相続に備えるために、とにもかくにも、まずは・・・不動産を改めて見直してみてください。
何か、思わぬ気付きやアイデアが思いつくかもしれません・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
相続対策・・・相続と言えば・・・税金・・・相続税といえば一部の資産家の悩むものと思われがちですが、実際は税金に関係ない遺産分割での悩みが深刻なものとなってきます。
兄弟間で親の遺した財産をめぐっての争いがおきた場合、その話し合いの収拾は困難を極めることとなってきます。
多くの財産があるからもめるのか・・・
実は、家庭裁判所への相続の調停申し込みは、相続財産5000万円以下の人の割合が70%を超えるといったデーターもあるように、相続税がかかってくる人のみが心配なのではなく、むしろ、相続税がかかってこない人のほうが遺産分割が纏まらないといった結果となっています。
この要因としては、相続財産の内訳に占める割合として金融資産に比べて不動産の比率が高いことがあるかもしれません。
国税庁の資料では、相続財産のうち不動産(土地+家屋)の占める割合は、約57%(平成21年)となっています。
あくまで、これは、全国平均値さらには路線価ベースでの対比です。
これが、公示価格や実勢相場(路線価は公示価格の約80%で評価)で対比した場合、さらに東京や大阪といった都心部である場合は、その対比は70%をゆうに超えてくるものかもしれません・・・
相続財産のうちに不動産の割合が多いということは、兄弟間で均等に分けるのが難しいからです。
昔は、均等に分筆して分けるのが困難な場合は、均等に共有持分で分割しているケースは多く見受けられました。
そして、50年後には、その共有者は、30人をこえ会ったことも見たことも無い遠い親族と共有している事となってしまいます。
現に、2世帯住居(建物は親との共有持分)を親の土地に建てて住んでいた長男が、母の2次相続で2世帯住宅の土地の分を含めた相続財産の均等分割を要求され、どうにもならずに2世帯住宅を売却して換価分割した例もあります。
また、相続税がかかってくるといった場合、その相続財産の殆どが不動産、相続税を支払える金融資産が無いといった場合、手持ちの不動産を売却して相続税を納める必要がでてきます。
相続の開始後(被相続人の死亡を知った日の翌日)10カ月以内に相続税を計算して国に納付しなければなりません・・・
その時に、すぐ、売却できる土地はなにかです・・・
貸家や賃貸マンションが建っている場合、新しければまだしも、老朽化していた場合は買手は更地での売買を希望するでしょう。
賃借人がいると立退きの交渉が必要となってきます。
そのまま、賃借人つき、オーナチェンジで購入してくれればいいですが、買手が新築前提で考えている場合、ありえない話でしょう。
急な相続でそんな局面に立たされた場合、売却できる土地はどれか・・・たまたま、一番条件のいい虎の子とも言うべき土地の賃貸借契約が完了し、すぐ売却できる状況であったため、その虎の子の土地を売却して相続税を支払ったというケースもあります。
上記のようにならないためには、あらかじめ、長男との2世帯住居を建てるときに遺言書を遺しておくこと、さらには、遺言書があっても遺留分の権利はありますので、不動産の実勢相場をきちんと把握して、遺留分相当額を長男が代償して支払える準備はしておくべきでしょう・・・
ここで、必要なのは、遺産分割での不動産の価格を、どう想定しておくかでしょう・・・
実際の遺産分割では、相続人間でその価格を話会いで決めていきます。
いま、売ったらいくらで売れる・・・といった実勢相場から路線価や固定資産税評価額まで様々な価格があります。
いわゆる一物四価と呼ばれるもので、①固定資産税評価額、②路線価、③公示価格・基準地価格、④実勢相場の4つです。
①から④に行くに従って、高い水準の価格となってきます・・・
それぞれの価格を算出して、他の財産の価格も考慮しながら遺される方が自分で判断していくほかないでしょう・・・
また、納税にあたっては、いつ、相続が発生しても慌てずに納税できる準備はしておくべきでしょう・・・
そのためには、相続税のシミュレーションをして、いくら支払う予定なのかを把握して、手持ちの不動産のうち納税用に売却しても惜しくない不動産を選定しておくべきでしょう。
そして、すぐ、売れるように駐車場等にしておく等の対策が必要です。
この場合は、手持ちの不動産の全てを改めて見直して、残すもの、売却してもいいもの、等に振り分けておくべきでしょう。
相続に備えるために、とにもかくにも、まずは・・・不動産を改めて見直してみてください。
何か、思わぬ気付きやアイデアが思いつくかもしれません・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年04月14日
財産そのものに課税する相続税の創設された経緯は・・・
相続税は、他の国税と何が違うでしょうか・・・
所得税は、一年間のうちに個人が取得した収入から経費を差し引いた所得金額に対して課税されるものです。
法人税は、法人という会社が、一事業年度ごとにあげた益金(収入)から損金(費用)を差し引いた所得に対して課税されるものです。
所得税も法人税も、一年間の労働の対価としての所得に対して課税されますので、その担税能力には問題はなさそうです。
所得がなければ課税されないこととなるからです。
消費税は、課税の対象となる商品を購入するたびに課税されるものです。
低所得者も高所得者も一律の税率で課税されます。
これは、個人で考えた場合、所得税や相続税が超過累進税率で課税されることを考えると、これが真の公平であるのか、でないのか・・・これは、公平でないとする考えが軽減税率導入の根本的な考え方なのかもしれません。
相続税は、ある人が亡くなった時の財産を承継した人に課税されるもの・・・
この場合、その課税がされるか否かは、ある一定の金額以上の財産を遺した場合となります。
そのある一定の金額のハードルが、低められようとしています。
これは、財産に対して直接課税される税金ですから、このハードルが低くなれば低くなるほど、個人の所有している財産の承継できる金額は、減ってくることとなってきます。
何か、日本は社会主義国家と思えてくるような税金のシステムです。
一生懸命、寝ずに働いて一杯儲けて国に多額の所得税を払い、最後に相続税を支払う・・・
もっとも、一生懸命働いてという側面からみると・・・
農地の納税猶予、非上場株式等の納税猶予、山林の納税猶予、等々、事業承継のための税金を回避できる規定は用意されています。
ただ、貸家オーナー等の準事業と呼ばれる収益構造に対しては、そのような制度は存在しません。
つまりは、自分で汗をかかないで残した財産を、同じく汗をかかないで取得した・・・場合、
その財産が増えたという事実に課税することとなるわけです。
この考えは、所得税でも同様です。
一生懸命働いて財産(資本)が増えた・・その増えた財産(当期の利益)に対して課税するわけです・・・
このように、相続という財産の承継によって・・・財産が増えたことに課税するというわけです。
相続税は、いつ、創設されたか・・・
相続税は、日露戦争の戦費を用意立てるために施行されたといいます。
社会主義的発想というよりも、富国強兵の一環だったのでしょう・・・
太平洋戦争後は、何か社会主義的な税金・・・富裕層の財産に課税して、世の中に分配する・・・となったような気がします。
時には、担税力に苦心し、相続税を支払うために、昔からの旧家を売却するといったような話も耳にするところです。
これでは、昔ながらの風景にも影響を及ぼしそうです・・・
相続税のかかってくる方達にとっては、一番、悩ましい税金かもしれません・・・
良きアドバイザーとして、少しでも、お役にたてれば、幸いです・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
所得税は、一年間のうちに個人が取得した収入から経費を差し引いた所得金額に対して課税されるものです。
法人税は、法人という会社が、一事業年度ごとにあげた益金(収入)から損金(費用)を差し引いた所得に対して課税されるものです。
所得税も法人税も、一年間の労働の対価としての所得に対して課税されますので、その担税能力には問題はなさそうです。
所得がなければ課税されないこととなるからです。
消費税は、課税の対象となる商品を購入するたびに課税されるものです。
低所得者も高所得者も一律の税率で課税されます。
これは、個人で考えた場合、所得税や相続税が超過累進税率で課税されることを考えると、これが真の公平であるのか、でないのか・・・これは、公平でないとする考えが軽減税率導入の根本的な考え方なのかもしれません。
相続税は、ある人が亡くなった時の財産を承継した人に課税されるもの・・・
この場合、その課税がされるか否かは、ある一定の金額以上の財産を遺した場合となります。
そのある一定の金額のハードルが、低められようとしています。
これは、財産に対して直接課税される税金ですから、このハードルが低くなれば低くなるほど、個人の所有している財産の承継できる金額は、減ってくることとなってきます。
何か、日本は社会主義国家と思えてくるような税金のシステムです。
一生懸命、寝ずに働いて一杯儲けて国に多額の所得税を払い、最後に相続税を支払う・・・
もっとも、一生懸命働いてという側面からみると・・・
農地の納税猶予、非上場株式等の納税猶予、山林の納税猶予、等々、事業承継のための税金を回避できる規定は用意されています。
ただ、貸家オーナー等の準事業と呼ばれる収益構造に対しては、そのような制度は存在しません。
つまりは、自分で汗をかかないで残した財産を、同じく汗をかかないで取得した・・・場合、
その財産が増えたという事実に課税することとなるわけです。
この考えは、所得税でも同様です。
一生懸命働いて財産(資本)が増えた・・その増えた財産(当期の利益)に対して課税するわけです・・・
このように、相続という財産の承継によって・・・財産が増えたことに課税するというわけです。
相続税は、いつ、創設されたか・・・
相続税は、日露戦争の戦費を用意立てるために施行されたといいます。
社会主義的発想というよりも、富国強兵の一環だったのでしょう・・・
太平洋戦争後は、何か社会主義的な税金・・・富裕層の財産に課税して、世の中に分配する・・・となったような気がします。
時には、担税力に苦心し、相続税を支払うために、昔からの旧家を売却するといったような話も耳にするところです。
これでは、昔ながらの風景にも影響を及ぼしそうです・・・
相続税のかかってくる方達にとっては、一番、悩ましい税金かもしれません・・・
良きアドバイザーとして、少しでも、お役にたてれば、幸いです・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年04月11日
相続を始めとした不動産対策とは・・・
昨日の日本MDRT(生命保険である一定の成績を納めた成績優秀者の称号)東京大会で相続士協会としてブースを設置し相続士試験をPRしてきました。
皆さん、相続に対しては非常に興味を示されておりました。
来年からの相続増税に向けて、お客様に有効なアドバイスができるようにならなければと、ひしひしと感じているのが窺えます。
ある相続のセミナーで講師の先生がおしゃっていました。
相続の対策というのは、究極、不動産に関わる税金を知ること、不動産がいくらで売れるかをおさえること、とおしゃっていました。
もと、都市銀行の行員のかたで、相続対策に使える節税商品なども開発してこらえたそうです。
相続対策と言えば、①遺産分割、②納税の準備、③節税対策、といわれています。
遺産分割や納税のことを考えないで、節税対策として土地活用等を進めていくと、結果、円滑な分割が出来ない、納税ができる金融資産がない・・・結果、虎の子の不動産を売却するといったことが起こらないともいえません・・・
本当は、虎の子の不動産を売却しなくても、そのほかの不動産を売却すれば、とりあえず、凌げたのにといった場合でも・・・
不動産業者さんが、とりあえず、こっちの条件のおちる不動産を売却すれば何とか凌げそうですねといってくれればいいですが・・・当然に、条件のいい土地の売却を押しすすめたいというのが、本音でしょう・・・
もっとも、その判断が出来るほどの情報をお客様からいただけないというのが、現実のところとなってきますが・・・
不動産に関わる税金とは・・・何か・・・
まずは、所得税関係・・・
代表的なものは、不動産を売却した時の譲渡所得、土地や建物であれば、分離課税となります。
相続に絡む場合は、ほとんどが長期になるでしょうから、取得費や必要経費控除後に、住民税等を含めて約20%の税金が貸されます。
相続税を払うために相続財産である不動産を売却した場合には、相続税のうち一定額を譲渡所得の取得費に加算されることとなりますので、相続後に売却した方が納税資金の準備としては効率のよいものとなりますが、問題は不動産の売却はいつ売れるか、いくらで売れるかの具体的な予想が困難なことでしょう・・・
相続後の売却で、申告期限10カ月に決済が間に合わないといった時に、税務署に事情を説明して、とりあえず延納の申請をして切り抜けたことがあります。
最終的に、土地の決済が終了した段階で延納分の相続税を利子と一緒に納めて完了しました。
他には、不動産を賃貸に供してれば、不動産所得が生じてきます・・・
不動産所得や将来の相続の対策のために、不動産管理法人をつくって、家族を社員として所得分散をして、給与所得控除の恩恵をうけながら、超過累進税率の税率も下げていくという節税方法もよく取られています。
不動産管理法人を設立するほどでなければ、賃貸物件の建物のみを子どもに売却か贈与をして、所得分散をするといった方法も取られています。
テーマは所得分散と、法人をつくる場合は、給与所得控除の活用というところでしょう・・・
また、不動産所得にからむ消費税の対策も考えられるでしょう・・・
消費税のかかる駐車場や事業貸家の売り上げを家族の中で分散化させることで、1000万円を下回させれば、消費税の納税は回避できることとなります。
もっとも、駐車場の所得分散は土地の譲渡や贈与が前提となってきますので、事業用の倉庫や事務所といった貸家の譲渡や贈与となるでしょう・・・
他には、固定資産税等々・・・ただの更地で稼がない遊休土地をどうするか・・・
土地の活用が難しい立地、周辺に住宅もお店もなく、とにかく、寂しいといった場合、太陽光発電の可能性があるかもしれません・・・
そういった可能性がなければ、納税用に売れるときに売ってしまった方がいいかもしれません。
固定資産税を、ただ払い続けるだけならば・・・その選択はありえるでしょう・・・
そして、相続税、土地の多くも所有していれば、路線価という評価額(若しくは固定資産税評価額の一定の倍率)を、もとに課税されることとなります。
相続税での不動産の注意点は、何といっても、税法上の特例の規定を意識することでしょう・・・
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例
広大地の評価
農地の納税猶予
さらに会社経営をされている場合、非上場株式等の納税猶予
不整形地評価と利用区分
貸家建築による評価減
等々・・・相続税法には、適正に評価を下げられる計算方法が定められています。
まずは、こういった特例を余すことなく利用することが重要です・・・
以上が、大まかな不動産に関連する税金といったところでしょうか・・・
そして、不動産の価値を知ること・・・
それぞれの不動産が、いま、いくらで売れるかを知っておく・・・
これが、分からないと、そもそも、考えようも無いといったことになってきます。
税金によるお金の持ち出しと売ればいくらお金が入るといったことを、先ずは、知っておく・・・
そのうえで、色々な考えが浮かんでくるものでしょう・・・
まずは、不動産調査、棚卸をして全ての不動産をまず観てみる・・・税金を調べる・・・売却価格を調べてみる(自ずと建築基準法等の制限も調べられることとなります)・・・といったことを、始めてみたらいかがでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
皆さん、相続に対しては非常に興味を示されておりました。
来年からの相続増税に向けて、お客様に有効なアドバイスができるようにならなければと、ひしひしと感じているのが窺えます。
ある相続のセミナーで講師の先生がおしゃっていました。
相続の対策というのは、究極、不動産に関わる税金を知ること、不動産がいくらで売れるかをおさえること、とおしゃっていました。
もと、都市銀行の行員のかたで、相続対策に使える節税商品なども開発してこらえたそうです。
相続対策と言えば、①遺産分割、②納税の準備、③節税対策、といわれています。
遺産分割や納税のことを考えないで、節税対策として土地活用等を進めていくと、結果、円滑な分割が出来ない、納税ができる金融資産がない・・・結果、虎の子の不動産を売却するといったことが起こらないともいえません・・・
本当は、虎の子の不動産を売却しなくても、そのほかの不動産を売却すれば、とりあえず、凌げたのにといった場合でも・・・
不動産業者さんが、とりあえず、こっちの条件のおちる不動産を売却すれば何とか凌げそうですねといってくれればいいですが・・・当然に、条件のいい土地の売却を押しすすめたいというのが、本音でしょう・・・
もっとも、その判断が出来るほどの情報をお客様からいただけないというのが、現実のところとなってきますが・・・
不動産に関わる税金とは・・・何か・・・
まずは、所得税関係・・・
代表的なものは、不動産を売却した時の譲渡所得、土地や建物であれば、分離課税となります。
相続に絡む場合は、ほとんどが長期になるでしょうから、取得費や必要経費控除後に、住民税等を含めて約20%の税金が貸されます。
相続税を払うために相続財産である不動産を売却した場合には、相続税のうち一定額を譲渡所得の取得費に加算されることとなりますので、相続後に売却した方が納税資金の準備としては効率のよいものとなりますが、問題は不動産の売却はいつ売れるか、いくらで売れるかの具体的な予想が困難なことでしょう・・・
相続後の売却で、申告期限10カ月に決済が間に合わないといった時に、税務署に事情を説明して、とりあえず延納の申請をして切り抜けたことがあります。
最終的に、土地の決済が終了した段階で延納分の相続税を利子と一緒に納めて完了しました。
他には、不動産を賃貸に供してれば、不動産所得が生じてきます・・・
不動産所得や将来の相続の対策のために、不動産管理法人をつくって、家族を社員として所得分散をして、給与所得控除の恩恵をうけながら、超過累進税率の税率も下げていくという節税方法もよく取られています。
不動産管理法人を設立するほどでなければ、賃貸物件の建物のみを子どもに売却か贈与をして、所得分散をするといった方法も取られています。
テーマは所得分散と、法人をつくる場合は、給与所得控除の活用というところでしょう・・・
また、不動産所得にからむ消費税の対策も考えられるでしょう・・・
消費税のかかる駐車場や事業貸家の売り上げを家族の中で分散化させることで、1000万円を下回させれば、消費税の納税は回避できることとなります。
もっとも、駐車場の所得分散は土地の譲渡や贈与が前提となってきますので、事業用の倉庫や事務所といった貸家の譲渡や贈与となるでしょう・・・
他には、固定資産税等々・・・ただの更地で稼がない遊休土地をどうするか・・・
土地の活用が難しい立地、周辺に住宅もお店もなく、とにかく、寂しいといった場合、太陽光発電の可能性があるかもしれません・・・
そういった可能性がなければ、納税用に売れるときに売ってしまった方がいいかもしれません。
固定資産税を、ただ払い続けるだけならば・・・その選択はありえるでしょう・・・
そして、相続税、土地の多くも所有していれば、路線価という評価額(若しくは固定資産税評価額の一定の倍率)を、もとに課税されることとなります。
相続税での不動産の注意点は、何といっても、税法上の特例の規定を意識することでしょう・・・
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例
広大地の評価
農地の納税猶予
さらに会社経営をされている場合、非上場株式等の納税猶予
不整形地評価と利用区分
貸家建築による評価減
等々・・・相続税法には、適正に評価を下げられる計算方法が定められています。
まずは、こういった特例を余すことなく利用することが重要です・・・
以上が、大まかな不動産に関連する税金といったところでしょうか・・・
そして、不動産の価値を知ること・・・
それぞれの不動産が、いま、いくらで売れるかを知っておく・・・
これが、分からないと、そもそも、考えようも無いといったことになってきます。
税金によるお金の持ち出しと売ればいくらお金が入るといったことを、先ずは、知っておく・・・
そのうえで、色々な考えが浮かんでくるものでしょう・・・
まずは、不動産調査、棚卸をして全ての不動産をまず観てみる・・・税金を調べる・・・売却価格を調べてみる(自ずと建築基準法等の制限も調べられることとなります)・・・といったことを、始めてみたらいかがでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年03月30日
武富士事件による海外財産と相続税法の変遷・・・
平成23年2月に最高裁の判決が出た武富士事件・・・
この武富士事件とは、簡単に概略をお話すると・・・
武富士の創始者が長男を香港に在住(名前だけの香港支店をつくった)させ、香港在住時に武富士の株式の多数を所有している海外法人の株式を長男に贈与をしました。
当時の相続税法では、海外の居住者が海外の財産を贈与または相続で取得した場合は課税対象外となり、贈与税または相続税は課されないものとなっていました。
当然、贈与をうけた長男も贈与税の申告はしませんでした。
この事実に対し、所轄税務署長は贈与税の決定処分を下し贈与税を課すこととしました。
その決定処分の理由は、住所の考え方でした。
所轄税務署側は、香港の住所は、税務上の住所ではない・・・税務上の住所は国内の家にあるとしたものです・・・
その根拠は、香港の住まいはホテルのような住まいであり、生活のすべてを移転したとはいえない、これは税負担を回避することを目的とした寓居であるといった感じです。
その他の根拠は、年間の日本に滞在している日数等も立証項目にあげていました。
そして、何といっても、この税負担を回避すべきスキーム等を考えた公認会計士等が、長男の日本国内に滞在する日数を一定以上超えないように指導していた事実などをあげていました。
この贈与税は、実に1300億円もの金額にも上るものでした。
この決定処分に対しては、当然ながら、納得するわけもなく、税務訴訟にとなりました。
東京地裁は、香港に住民票も移転してあることから、国内の住所という論拠には無理があるとして、国の敗訴となりました。
東京高裁は、税負担回避の意図的な海外移転であるとして、国の勝訴となりました。
最高裁は、租税法律主義は守られるべきとして、遺憾ながらも住所を国内として課税することには無理があるとして、国の敗訴となりました。
この判決によって、還付加算金も含めて約2000億円が還付されるようになったようです・・・
この一連の訴訟を行っている間にも、同様の租税回避の行為を避けるべく、相続税法の納税義務者の規定についての改正を行いました。
前々から、同様の改正は行っていきたい意向であったようですが、なかなか改正に踏み切れなかったものが、この武富士事件を契機に改正への道を辿ったようです。
この改正で、海外居住者であっても、日本国籍を有する一定の者については、海外財産を贈与や相続で取得した場合、課税されることとなりました。
これで、とにもかくにも、日本国籍を有する者であれば、海外に住所を移転しても、海外財産の贈与や相続の課税を行えることとなってきます。
逆にいえば、日本国籍を有さない海外居住者者の贈与や相続により取得した海外財産は課税されないこととなります。
それで、昨年の税制改正で、さらに、日本国籍を有しない海外居住者であっても、贈与や相続時の海外財産の贈与者もしくは被相続人が国内に住所を有している場合は、課税できることとなりました。
武富士事件を、契機に、海外財産の相続や贈与での課税強化がされることとなってきました・・・
海外に財産を移すことによって、相続税や贈与税を軽減する・・・
これは、日本に限らず、先進諸外国でも、行われています。
また、タックスシェルターと呼ばれる節税用商品も頻繁に販売されています・・・
日本の場合、節税効果の高い金融商品などは、都度、税制改正でその評価方法を見直し、節税の効果をなくさせています。
年金の受給権の評価方法(相続税法旧24条)の改正などが、その代表例でしょう。
その他、たとえば、法定相続人の数に算入する養子の数の制限の改正なども、課税強化の一環です。
もっとも、養子の場合は、不自然すぎるほど、養子縁組をするケースが目立ちましたので、その改正が行われたのでしょう。
相続開始前、3年以内に取得した土地や建物の相続税評価額が、相続発生時の取引相場価格(路線価や固定資産税評価額は使わない)と改正されたのも、税負担を免れるために不動産を直前に購入するケースが続いたことが要因でしょう。
相続税の基礎控除の減額もあることながら、海外への財産移転に対する課税の強化もされてきています。
民主党政権時の税制改正大綱に盛り込まれた生命保険金等の非課税の対象者の制限(同居親族、未成年者、障害者)は、政権交代で見送られてきました。
この流れで、生命保険金等の非課税にも改正は及んでくるのでしょうか・・・
気になるところではあります・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
この武富士事件とは、簡単に概略をお話すると・・・
武富士の創始者が長男を香港に在住(名前だけの香港支店をつくった)させ、香港在住時に武富士の株式の多数を所有している海外法人の株式を長男に贈与をしました。
当時の相続税法では、海外の居住者が海外の財産を贈与または相続で取得した場合は課税対象外となり、贈与税または相続税は課されないものとなっていました。
当然、贈与をうけた長男も贈与税の申告はしませんでした。
この事実に対し、所轄税務署長は贈与税の決定処分を下し贈与税を課すこととしました。
その決定処分の理由は、住所の考え方でした。
所轄税務署側は、香港の住所は、税務上の住所ではない・・・税務上の住所は国内の家にあるとしたものです・・・
その根拠は、香港の住まいはホテルのような住まいであり、生活のすべてを移転したとはいえない、これは税負担を回避することを目的とした寓居であるといった感じです。
その他の根拠は、年間の日本に滞在している日数等も立証項目にあげていました。
そして、何といっても、この税負担を回避すべきスキーム等を考えた公認会計士等が、長男の日本国内に滞在する日数を一定以上超えないように指導していた事実などをあげていました。
この贈与税は、実に1300億円もの金額にも上るものでした。
この決定処分に対しては、当然ながら、納得するわけもなく、税務訴訟にとなりました。
東京地裁は、香港に住民票も移転してあることから、国内の住所という論拠には無理があるとして、国の敗訴となりました。
東京高裁は、税負担回避の意図的な海外移転であるとして、国の勝訴となりました。
最高裁は、租税法律主義は守られるべきとして、遺憾ながらも住所を国内として課税することには無理があるとして、国の敗訴となりました。
この判決によって、還付加算金も含めて約2000億円が還付されるようになったようです・・・
この一連の訴訟を行っている間にも、同様の租税回避の行為を避けるべく、相続税法の納税義務者の規定についての改正を行いました。
前々から、同様の改正は行っていきたい意向であったようですが、なかなか改正に踏み切れなかったものが、この武富士事件を契機に改正への道を辿ったようです。
この改正で、海外居住者であっても、日本国籍を有する一定の者については、海外財産を贈与や相続で取得した場合、課税されることとなりました。
これで、とにもかくにも、日本国籍を有する者であれば、海外に住所を移転しても、海外財産の贈与や相続の課税を行えることとなってきます。
逆にいえば、日本国籍を有さない海外居住者者の贈与や相続により取得した海外財産は課税されないこととなります。
それで、昨年の税制改正で、さらに、日本国籍を有しない海外居住者であっても、贈与や相続時の海外財産の贈与者もしくは被相続人が国内に住所を有している場合は、課税できることとなりました。
武富士事件を、契機に、海外財産の相続や贈与での課税強化がされることとなってきました・・・
海外に財産を移すことによって、相続税や贈与税を軽減する・・・
これは、日本に限らず、先進諸外国でも、行われています。
また、タックスシェルターと呼ばれる節税用商品も頻繁に販売されています・・・
日本の場合、節税効果の高い金融商品などは、都度、税制改正でその評価方法を見直し、節税の効果をなくさせています。
年金の受給権の評価方法(相続税法旧24条)の改正などが、その代表例でしょう。
その他、たとえば、法定相続人の数に算入する養子の数の制限の改正なども、課税強化の一環です。
もっとも、養子の場合は、不自然すぎるほど、養子縁組をするケースが目立ちましたので、その改正が行われたのでしょう。
相続開始前、3年以内に取得した土地や建物の相続税評価額が、相続発生時の取引相場価格(路線価や固定資産税評価額は使わない)と改正されたのも、税負担を免れるために不動産を直前に購入するケースが続いたことが要因でしょう。
相続税の基礎控除の減額もあることながら、海外への財産移転に対する課税の強化もされてきています。
民主党政権時の税制改正大綱に盛り込まれた生命保険金等の非課税の対象者の制限(同居親族、未成年者、障害者)は、政権交代で見送られてきました。
この流れで、生命保険金等の非課税にも改正は及んでくるのでしょうか・・・
気になるところではあります・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年02月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『相続人の確定②』について
本日は、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきます。
1.法定相続分
各相続人の法定相続分は次の通りとなります。
(1)共同相続人が配偶者と子である場合には、配偶者及び子の相続分は各2分の1です。昭和55年の改正前は、配偶者及び子の相続分は、それぞれ3分の1、3分の2とされていましたので注意を要します。
子が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされますが、子のなかに非嫡出子がいれば、その相続分は2分の1とされます。
この非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しないかについては従来より議論があります。過去の判例によりますと最高裁はこの規定は憲法14条に反しないとの判断を繰り返しています。
代襲相続人の相続分は、被相続人の子・・・つまり・・・代襲相続人の親・・・の法定相続分と同じとなります。代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の親が受けるべきであった相続分について、上記の子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。
(2)共同相続人が配偶者と直系兄弟姉妹である場合には、配偶者の相続分は3分の2であり、直系尊属の相続分は3分の1となります。
直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます。
(3)共同相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合には、配偶者の相続分は4分の3であり、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。兄弟姉妹が複数いるときは、その相続分は相等しいとされますが、このなかに父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹があるときは、その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされます。
代襲相続人の相続分は、被相続人の子・・・つまり・・・代襲相続人の親・・・の法定相続分と同じとなります。代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の親が受けるべきであった相続分について、上記の子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。
2.相続放棄
相続放棄がなされると、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
例えば、推定相続人が配偶者と2人の子がある場合に、子のうちの1人が放棄をすれば、配偶者と放棄をしなかった子とが共同相続人となり、それぞれの法定相続分は各2分の1となります。
ところで、放棄によって次順位の者が相続人となる場合があります。例えば、推定相続人が配偶者と一人の子である場合に、その子が放棄をすれば、初めから子がいなかったのと同様となり、相続人は配偶者と直系尊属(直系尊属がいなければ兄弟姉妹)となります。
なお、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理された場合、相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができ、これは登記手続の際の添付書類となります。
3.相続欠格と推定相続人の廃除
民法891条所定の事由(相続人の欠格事由)に該当するものは、相続人となることができません。
なお、相続人欠格事由の一つである遺言書の破棄・隠匿行為については、同条項の趣旨が遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して民事上の制裁を課そうとすることにあるから、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、当該行為をした相続人は相続欠格者に当たらないとする最高裁の判断が示されています。
また、一定の事由(被相続人に対し虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又はその他の著しい非行があったとき)に該当する推定相続人がいる場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することにより推定相続人廃除の審判がなされるときは、被廃除者は相続人となることができません。なお、推定相続人の意思表示は、遺言でなすこともできます。
相続欠格該当者ないし被廃除者に子がいる場合は、その子は代襲相続人となり、相続の当事者となることができます。この点で相続の放棄と効果が異なります。
以上、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
1.法定相続分
各相続人の法定相続分は次の通りとなります。
(1)共同相続人が配偶者と子である場合には、配偶者及び子の相続分は各2分の1です。昭和55年の改正前は、配偶者及び子の相続分は、それぞれ3分の1、3分の2とされていましたので注意を要します。
子が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされますが、子のなかに非嫡出子がいれば、その相続分は2分の1とされます。
この非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しないかについては従来より議論があります。過去の判例によりますと最高裁はこの規定は憲法14条に反しないとの判断を繰り返しています。
代襲相続人の相続分は、被相続人の子・・・つまり・・・代襲相続人の親・・・の法定相続分と同じとなります。代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の親が受けるべきであった相続分について、上記の子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。
(2)共同相続人が配偶者と直系兄弟姉妹である場合には、配偶者の相続分は3分の2であり、直系尊属の相続分は3分の1となります。
直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます。
(3)共同相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合には、配偶者の相続分は4分の3であり、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。兄弟姉妹が複数いるときは、その相続分は相等しいとされますが、このなかに父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹があるときは、その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされます。
代襲相続人の相続分は、被相続人の子・・・つまり・・・代襲相続人の親・・・の法定相続分と同じとなります。代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の親が受けるべきであった相続分について、上記の子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。
2.相続放棄
相続放棄がなされると、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
例えば、推定相続人が配偶者と2人の子がある場合に、子のうちの1人が放棄をすれば、配偶者と放棄をしなかった子とが共同相続人となり、それぞれの法定相続分は各2分の1となります。
ところで、放棄によって次順位の者が相続人となる場合があります。例えば、推定相続人が配偶者と一人の子である場合に、その子が放棄をすれば、初めから子がいなかったのと同様となり、相続人は配偶者と直系尊属(直系尊属がいなければ兄弟姉妹)となります。
なお、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理された場合、相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができ、これは登記手続の際の添付書類となります。
3.相続欠格と推定相続人の廃除
民法891条所定の事由(相続人の欠格事由)に該当するものは、相続人となることができません。
なお、相続人欠格事由の一つである遺言書の破棄・隠匿行為については、同条項の趣旨が遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して民事上の制裁を課そうとすることにあるから、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、当該行為をした相続人は相続欠格者に当たらないとする最高裁の判断が示されています。
また、一定の事由(被相続人に対し虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又はその他の著しい非行があったとき)に該当する推定相続人がいる場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することにより推定相続人廃除の審判がなされるときは、被廃除者は相続人となることができません。なお、推定相続人の意思表示は、遺言でなすこともできます。
相続欠格該当者ないし被廃除者に子がいる場合は、その子は代襲相続人となり、相続の当事者となることができます。この点で相続の放棄と効果が異なります。
以上、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
2014年02月16日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『相続人の確定』について
本日は、『相続人の確定』についてを、お話させていただきます。
1.相続人の順位
相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄・欠格・廃除の場合を含む)に次順位の相続人に相続権が生じます。
(1)第1順位の相続人=子
被相続人に子があれば、その子(胎児を含む)は第1順位の相続人となります。嫡出子であると非嫡出子であるとを問いません。
相続開始以前に相続人たるべき子が死亡しているときは、その者にさらに子があれば、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。
相続開始以前に代襲者が死亡していても、その者にさらに子があればその子が相続人となります。これを再代襲相続といいます。
(2)第2順位の相続人=直系尊属
被相続人に子ないし代襲者がいない場合は、直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります。
(3)第3順位の相続人=兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
相続開始以前に、相続人たるべき兄弟姉妹が死亡していても、その者に子がいれば、その子が代襲して相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続においては、再代襲は認められません。
但し、昭和55年12月31日以前の相続につきましては、兄弟姉妹についても再代襲がありますので注意が必要です。
(4)配偶者=常に相続人
被相続人の配偶者は、前述の(1)~(3)の順位で決まる相続人と常に同順位で相続人となります。
例えば、被相続人に配偶者がいて、さらに子がいれば、その子と配偶者とが共同相続人となります。子はいませんが親が生きている場合には、その親と配偶者とが共同相続人となります。
(5)被相続人と相続人との間に養子縁組関係があった場合
養子縁組により、養子は養親の嫡出子の身分を取得するから養親子相互間及び養子と養方の親族(直系尊属、兄弟姉妹)との間にも相続が発生します。
普通養子縁組の場合には、養子と実方の父母との親族関係は終了しないので、養子が被相続人となった場合には、実方、養方双方の父母及び親族が相続人となります。
これに対して、特別養子縁組の場合は、実方の父母及び親族との親族関係は終了するので、相続は養方の父母及び親族との関係のみ発生することとなります。
以上、『相続人の確定①』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
1.相続人の順位
相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄・欠格・廃除の場合を含む)に次順位の相続人に相続権が生じます。
(1)第1順位の相続人=子
被相続人に子があれば、その子(胎児を含む)は第1順位の相続人となります。嫡出子であると非嫡出子であるとを問いません。
相続開始以前に相続人たるべき子が死亡しているときは、その者にさらに子があれば、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。
相続開始以前に代襲者が死亡していても、その者にさらに子があればその子が相続人となります。これを再代襲相続といいます。
(2)第2順位の相続人=直系尊属
被相続人に子ないし代襲者がいない場合は、直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります。
(3)第3順位の相続人=兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
相続開始以前に、相続人たるべき兄弟姉妹が死亡していても、その者に子がいれば、その子が代襲して相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続においては、再代襲は認められません。
但し、昭和55年12月31日以前の相続につきましては、兄弟姉妹についても再代襲がありますので注意が必要です。
(4)配偶者=常に相続人
被相続人の配偶者は、前述の(1)~(3)の順位で決まる相続人と常に同順位で相続人となります。
例えば、被相続人に配偶者がいて、さらに子がいれば、その子と配偶者とが共同相続人となります。子はいませんが親が生きている場合には、その親と配偶者とが共同相続人となります。
(5)被相続人と相続人との間に養子縁組関係があった場合
養子縁組により、養子は養親の嫡出子の身分を取得するから養親子相互間及び養子と養方の親族(直系尊属、兄弟姉妹)との間にも相続が発生します。
普通養子縁組の場合には、養子と実方の父母との親族関係は終了しないので、養子が被相続人となった場合には、実方、養方双方の父母及び親族が相続人となります。
これに対して、特別養子縁組の場合は、実方の父母及び親族との親族関係は終了するので、相続は養方の父母及び親族との関係のみ発生することとなります。
以上、『相続人の確定①』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
2014年02月12日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『一部分割の可否』について
本日は、『一部分割の可否』についてを、お話させていただきます。
1・遺産の分割は、遺産のすべてを一回で分割することが原則です。
しかし、現実の遺産分割にあっては、遺産の種類や性質、あるいは相続人の状況や感情などによって全遺産を同時に分割することが出来ないケースもあります。
例えば、ある不動産が遺産に属するかについての訴訟が継続中の場合、一方に簡易に分割できる現金がある場合で一部の相続人が早急に現金を欲している場合などが考えられます。
このような場合に、協議あるいは調停により一部分割をなすことは通説及び判例はこれを肯定しており、実務においてもしばしば行われています。
2.しかし、①一部分割が先行した後、残余財産の遺産分割が審判になった場合にどのような影響があるか、②審判において一部分轄がなし得るか、の2点が問題となります。
3.一部分割協議が先行した後、残余財産の遺産分割が審判となった場合に、遺産分割の協議(調停も含む)は、相続人による任意の合意のもとに行われたものであれば法定相続分と異なった分割でも有効となりますから、相続人全員が一部分割であることを認識している限り錯誤等の意思表示の瑕疵のない限り原則として有効と考えるべきであり、一部分割がなされた遺産は審判分割の対象から除外し、残余財産のみを審判の対象とすることとなります。
ただし、一部分割の対象財産と残余財産の分割との関係に独立性がない場合や遺産の大部分を占める物件が一部分割の協議の対象から脱落している場合や、あるいは残余財産の分配のみでは相続人間の公平がはかれない場合などには、一部分割が無効とされる余地があるようです。
また、一部分割の内容が全く審判に影響しないわけではなく、民法906条の分割基準から見て相続人間に不公平感が生じるような場合には、残余財産の分配に当たって一部分割により遺産を取得した相続人の取得分に影響を及ぼすものと考えられます。
以上のような観点から、一部分割をする場合には、残余財産の分割が控えていることを十分に考慮し、分割協議書または調停調書に、一部分割である旨及びその一部分割が残余財産の分割に際してどのような影響があるのか、ないのかを明確にしておくべきです。
4.審判において一部分割がなし得るのか?
前述の通り、遺産分割は一回で全遺産の分割を終えることが望ましく、ことに審判においてはこれを原則とすべきです。
しかしながら、一部の遺産について早い時期に分割審判が出来ない場合や一部分割をなすことによって紛争の解決が早期に実現出来る場合などのように、一部分割をすることによって合理性があって、一部分割によって遺産全体についての適正な分割が不可能とならないような場合には、審判による一部分割も認められるべきと考えます。
審判例では、①遺産の範囲に争いが有り、判決による確定を相当とする場合等やむをえない事情があり、かつ分割基準に従った総合的分割の実現に支障がないときに限るものとして厳格に考えるものもありますが、②一部分割をしても民法906条の分割基準による適正妥当な分割の実現が不可能になるような場合でない限り許されるとした例や、③遺産分割当時一部の遺産の存在自体が相続人全員に知られてなかった場合その他相当の理由がある場合には許されるとするものなど緩やかに解されるものあるようです。
以上、『一部分割の可否』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
1・遺産の分割は、遺産のすべてを一回で分割することが原則です。
しかし、現実の遺産分割にあっては、遺産の種類や性質、あるいは相続人の状況や感情などによって全遺産を同時に分割することが出来ないケースもあります。
例えば、ある不動産が遺産に属するかについての訴訟が継続中の場合、一方に簡易に分割できる現金がある場合で一部の相続人が早急に現金を欲している場合などが考えられます。
このような場合に、協議あるいは調停により一部分割をなすことは通説及び判例はこれを肯定しており、実務においてもしばしば行われています。
2.しかし、①一部分割が先行した後、残余財産の遺産分割が審判になった場合にどのような影響があるか、②審判において一部分轄がなし得るか、の2点が問題となります。
3.一部分割協議が先行した後、残余財産の遺産分割が審判となった場合に、遺産分割の協議(調停も含む)は、相続人による任意の合意のもとに行われたものであれば法定相続分と異なった分割でも有効となりますから、相続人全員が一部分割であることを認識している限り錯誤等の意思表示の瑕疵のない限り原則として有効と考えるべきであり、一部分割がなされた遺産は審判分割の対象から除外し、残余財産のみを審判の対象とすることとなります。
ただし、一部分割の対象財産と残余財産の分割との関係に独立性がない場合や遺産の大部分を占める物件が一部分割の協議の対象から脱落している場合や、あるいは残余財産の分配のみでは相続人間の公平がはかれない場合などには、一部分割が無効とされる余地があるようです。
また、一部分割の内容が全く審判に影響しないわけではなく、民法906条の分割基準から見て相続人間に不公平感が生じるような場合には、残余財産の分配に当たって一部分割により遺産を取得した相続人の取得分に影響を及ぼすものと考えられます。
以上のような観点から、一部分割をする場合には、残余財産の分割が控えていることを十分に考慮し、分割協議書または調停調書に、一部分割である旨及びその一部分割が残余財産の分割に際してどのような影響があるのか、ないのかを明確にしておくべきです。
4.審判において一部分割がなし得るのか?
前述の通り、遺産分割は一回で全遺産の分割を終えることが望ましく、ことに審判においてはこれを原則とすべきです。
しかしながら、一部の遺産について早い時期に分割審判が出来ない場合や一部分割をなすことによって紛争の解決が早期に実現出来る場合などのように、一部分割をすることによって合理性があって、一部分割によって遺産全体についての適正な分割が不可能とならないような場合には、審判による一部分割も認められるべきと考えます。
審判例では、①遺産の範囲に争いが有り、判決による確定を相当とする場合等やむをえない事情があり、かつ分割基準に従った総合的分割の実現に支障がないときに限るものとして厳格に考えるものもありますが、②一部分割をしても民法906条の分割基準による適正妥当な分割の実現が不可能になるような場合でない限り許されるとした例や、③遺産分割当時一部の遺産の存在自体が相続人全員に知られてなかった場合その他相当の理由がある場合には許されるとするものなど緩やかに解されるものあるようです。
以上、『一部分割の可否』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)